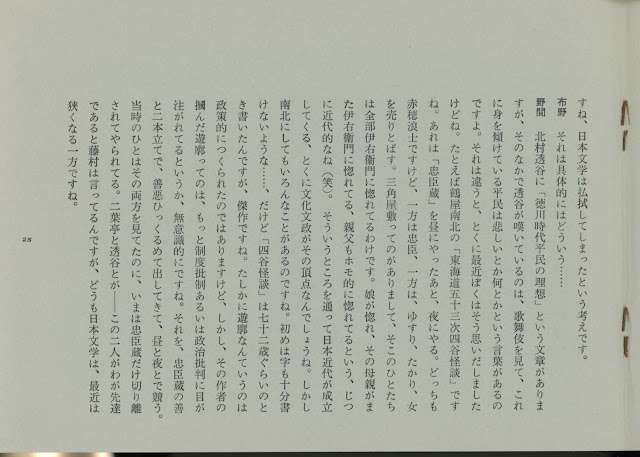都市悪という鏡 対談 野間宏/布野修司、『風声 京洛便り』第六号、197903
このブログを検索
2022年4月11日月曜日
2022年4月10日日曜日
2022年4月9日土曜日
シンポジウム:司会:歴史的街並みの活用とコミュニティ創生に関する東南アジア(ASEAN)専門家会議, 梶山秀一郎 木下龍一 東樋口護,京都市景観・まちづくりセンター・日本建築学会 第三世界歴史都市・住宅特別研究委員会,19991106ー07
シンポジウム:司会:歴史的街並みの活用とコミュニティ創生に関する東南アジア(ASEAN)専門家会議, 梶山秀一郎 木下龍一 東樋口護,京都市景観・まちづくりセンター・日本建築学会 第三世界歴史都市・住宅特別研究委員会,19991106ー07
2022年4月8日金曜日
2022年4月7日木曜日
2022年4月5日火曜日
公開ヒヤリング方式の定着へ,ギャラリー間,コンペ・アンド・コンテストNO49,199611
公開ヒヤリング方式の定着へ,ギャラリー間,コンペ・アンド・コンテストNO49,199611
公開ヒヤリング方式の定着へ
布野修司
「鹿島町立体育館公開コンペ」「建築専門委員 結果に不満」「町側委員に押し切られた」「運営方法に問題 在り方に疑問の声」という見出しが山陰中央新報の一面を飾った(1996年8月9日)。リード文には、「決定した島根県鹿島町の町立総合体育館の設計案をめぐって、審査した建築専門委員がそろって「町側委員に押し切られた」とし、審査結果に不満を評している。決定案は町側委員が強く支持、建築専門委員は「管理しやすい以外、何の評価もない。他案とのレベルの差は歴然」と主張したが、聞き入れられなかった。」
建築専門委員のひとりが筆者である。審査委員長を務めた。恥ずかしい限りである。審査については、報告書に述べる通りである(興味を持たれる向きは鹿島町に問い合わせられたい)。審査委員長として報告書以外に言うべきことはない。
ただ、冒頭のような記事が載ることになったのは、報告書の以下のような付記が公開されなかったからである(現在では公開されている)。
「付記(審査委員長の個人的見解):審査内容、経過についての報告は上記する通りである。審査が慎重かつ公正に行われたことはいうまでもない。しかし、審査結果は、委員長個人の評価判断とは異なったものとなった。審査結果と個人的評価の違いを説明することは、設計競技への参加者、公開ヒヤリングへの参加者、また町民への委員長としての責務と考えて以下に付記する次第である。
選定された案は、コンパクトにまとめられていること、従って管理がしやすいこと、また、メンテナンスにかかる費用等が他案に比べてかからない(と思われる)こと等、専ら、管理者側の評価を重視して選定されたものであって、他の点についてはとりたてて見るべきものがない。他案にはるかにすぐれた提案が多かったことは、審査評に示す通りである。最終的には、「夢を取る」か「無難な案」を取るかが争点となったが、長時間の議論の末、町側委員、町長以下事務当局の意向および能力として、選定案以外を受け入れることができない、と判断して多数決に従うことにしたのが経緯である。
選定案は、以下のような欠点がある。実施に当たっては、可能な限り良い施設となるよう、選定された設計者は、当局、町民と協力し合って努力されたい。・・・(以下、箇条書きの要望事項)・・・以上を検討する中で再度慎重な検討をされたい。」
実に恥ずかしい話である。こう書かざるを得ない案を選ぶ羽目に陥ったのである。そもそも審査委員構成が問題であった。助役、教育長、議長と専門委員2人の構成である。町側委員に建築関係者を入れるように要請したのであるが、「小さな町で建築の専門家はいない、県庁OBの技術者を嘱託として(投票権無し)事務局につけるから」ということであった。町はじめてのコンペであり、しかも公開ヒヤリングをやることを了解してもらっており、とにかくコンペを行うことの意義を優先した判断であった。結果として墓穴を掘った。自らの非力を感じるばかりである。建築専門家としての判断に徹底して執着すべきだという気も全くないわけではなかったが、多数決には従わざるを得なかったのが経緯である。
つくづく感じたのは、建築の世界が全く一般に理解されていないということである。教育長にしろ、助役にしろ、議長にしろ、町の中ではすぐれた見識の持ち主である。そうした見識者に、建築のもつ全体として意義がなかなか通じないのである。素朴機能主義的な評価、デザインより機能といった二元論的理解を抜けれないのである。
もっと問題なのは、行政当局、事務局の管理者的態度、小官僚的発想である。自分たちの仕事が煩雑でないことのみがチェックリストにあげられる。
さらに痛切に感じたのは、「建築」アレルギーである。スター建築家が、メンテナンスを考えずに「やり逃げ」する。苦労するのは自治体で、「建築家」は責任をとらない。「見てくれだけの建築は要注意!」というのが、常識になっているのである。
「何のための公開ヒヤリングか」(山陰中央新報 9月5日)脇田祥尚島根女子短大講師がフォローしてくれている。公開ヒヤリングの意義がまさに問われていると、さらなる議論の必要性を訴えている、のである。「島根方式」と呼ばれ出そうとしている公開ヒヤリング方式は、これまで比較的うまく行った例が多かった。今回はそれ以前に問題があった。しかし、それでも建築の世界を外へ開くきっかけにはなったと思う。公開ヒヤリング方式の定着を願うばかりである。
2022年4月3日日曜日
住まいの輸出に答えなし 押しつけよりもアジアモデルを探れ,対談:布野修司vs恵藤英郎),NNA『カンパサールKanpasar』, 第3号,201104
住まいの輸出に答えなし 押しつけよりもアジアモデルを探れ,対談:布野修司vs恵藤英郎),NNA『カンパサールKanpasar』, 第3号,201104
――住宅関連メーカー各社のトップの発言などをみていると、多くはアジアを中心とした海外市場への進出を目指す、あるいは強化するという論調が目立ちます。
恵藤:当社は米国で1万戸を販売した実績や経験もありますし、中国でも80年代から事業を展開しています。あまり海外市場に抵抗はなかったですし、日本で作り上げてきたノウハウを活用し、各地で住まい方の提案をして底上げをしようという使命感を持っています。日本の市場が縮小しているから海外に出ようという姿勢だとしたらもったいないですね。
布野:日本の住宅がそのまま輸出できるものなのか、考える必要がありますね。私は70年代にインドネシアに行って以来、アセアン諸国やインドなどの住宅を見てきました。インドネシア第2の都市スラバヤのカンポン(都市集落)には30年以上通っています。アジアは急速な経済発展を遂げているとはいえ、依然として貧困層が多い。都心に行けば高層住宅もありますが、まだまだ平屋や二階建ての住宅が中心という印象です。
恵藤:当社もすでに事業を進めている中国だけでなく、マレーシアやタイ、インドネシア、ベトナムなどの市場調査を行っていますが、今のところはビジネスとして成り立たせるのは難しいという印象です。都市部ではコンドミニアムが多いですが、われわれの本業である戸建てを何とか展開したいと考えています。
布野:大和ハウスさんが昭和30年代半ば?(1959年)に「ミゼットハウス」を発売したことを考えれば、東南アジアにプレハブを投入するというのは、自然な流れですよね。
恵藤:おっしゃる通りです。そもそも当社の創業者がミゼットハウスを考え出したのは、当時の子どもたちに帰る部屋がなく、夕方遅くまで外で遊んでいたのを見て「帰る部屋を作ればいい」と思ったことがきっかけです。住宅が不足している地域に供給するのは、当社の本来的なポリシーですから。
ただ、特に戸建て事業に関しては採算を取るのが難しいのが現状です。東南アジアで比較的戸建てが高いクアラルンプールやバンコク、ジャカルタあたりでうまく行けば、商機もあるかもしれないと考えてはいますが。
布野:タイやマレーシアでは、リタイアした日本人向けに畳を使った部屋などの需要はありませんか。
恵藤:中国の集合住宅は1プロジェクト当たり1,000戸単位でやっていることを考えると、絶対数が少ないですね。
■日本の住宅は北欧モデル
布野:ある国際シンポジウムに出席したとき、環境共生住宅(エコハウス:環境に良い住宅???)のモデルについて議論をしました。そこで出る話と言えば、寒い国の住宅モデルばかりです。
恵藤:高気密、高断熱ですね。
布野:そう。それは日本も同じですね。その席で私は、熱帯や赤道付近の人口は30億人で、これからも増え続けると思うが、そういった地域向けの住宅モデルは考えなくていいのかと問いかけました。そうしたら「あなたが考えてみてください」と言われた。それで1998年に、スラバヤ・エコハウスという実験集合住宅を建てました(写真●)。現地で調達したヤシの繊維を断熱材に使い、井戸水を太陽電池のポンプでくみ上げてパイプで水を循環させ、室温を下げるといった構造にしました。
恵藤:確かに、暑い国では家の機密性を高めてエアコンかけて涼しくする、という方向性だけが正しい選択ではないと思います。自然を活用したパッシブクーリングの発想は、今後も重要になってくると思います。当社も越谷レークタウンというプロジェクトで川の水と空気を街の中に流し、家の中を涼しくする仕組みを作りました。
布野:スラバヤ・エコハウスは、現在も大学の寮で使われています。ただ、地元の人は「日本は冷房を使っているのに、なぜ私たちにだけ、こんなモデルを押しつけるんだ」と怒られました(笑)。「モデルを考える必要はあるでしょう」と説得しましたが。
日本のやり方ではコストがかさみ、東南アジアではお金が足りないことが多い。ただ、バナキュラー(その土地固有の)建築など、昔からの知恵があるので、そういった装置を現代的に活用すればいいと思う。非政府組織(NGO)などと協力して、自治体や政府を説得する必要がありますね。大和ハウスさんも、是非お金を出してください(笑)
恵藤:(笑)。そういった方面での事業も、必要ですね。
布野:国によっては、技術供与を行ってもろくに活用されないこともある。日本はノウハウを持っているのに、政府の関係機関が積極的でないところもあるんです。最近の援助は人権方面が主で、モノの援助がしにくくなっている。ベーシック・ヒューマン・ニーズとして住宅の援助は必要ではないかと思うけれども、そのあたりは韓国などの方が積極的にやっている。
恵藤:住む場所のない人に住宅を援助しても、まったく問題はないと思いますがね。
■駐在員向けから始まった
布野:大和ハウスさんは、他の企業と比べてもかなり早い時期に中国に進出されていますね。
恵藤:1983年に大連、85年に上海に進出しました。日系のハウスメーカーとしては早いほうだと思います。ただ、そのころは中国人向けのビジネスではなく、日本人の駐在員向けでした。中国の住宅事情が良くなかったので、過酷な地に赴任される方に日本の環境をそのまま作って提供しようという考えでした。日本語が通じる環境で、日本食を買えるコンビニやタクシーのサービスなども用意しました。中国で5カ所に建設しましたが、中国の住宅環境も整ってきましたし、現在は使命を終えたと思っています。合弁の期間が終了したら、順次撤退していく予定です。
布野:建材などは、中国の工場で生産されたのですか。
恵藤:全て輸入でした。ただ、特に上海市政府は外資を誘致したいという思いが強かったので、それでも非常に優遇されました。当時の市長は江沢民でしたが、建設現場に視察に来ました。
布野:江沢民は街中の伝統的な部分さえ守れば、あとは開発に非常に積極的だったと聞いています。それもあって中国も様変わりし、蘇州は歴史的なすばらしい街ですが、一歩郊外に出るとアメリカの郊外のようですね。中国が住宅バブルになっているという印象はありますか。
恵藤:北京や上海など、一部ですね。中国は都市部の人口が約6億人で、世帯数は2億世帯。日本のバブルがはじけた時は、持ち家のストックが世帯数を完全に上回っていましたが、中国では家を持っていない世帯も多い。中国の住宅市場は、紆余(うよ)曲折はあっても中期的に見ればまだまだ伸びると思っています。2006年には大連で、09年には蘇州でも中国人向けの分譲マンションの開発に着手しています。昨年11月には無錫市で不動産開発用地を落札し、中国で4番目となる不動産開発「無錫呉博園プロジェクト」を開始することになりました。
■求ム「外向きの人材」
布野:中国ではサブコンがまだまだ育っていないですから、施工や管理でも日本に一日の長があるでしょう。職人の質や材料の問題など、地元ならではの問題もある。
恵藤:実際に動くのは地元の方々なので、日本からは工程や品質の管理のノウハウなど、ソフトの部分を輸出するしかないですね。人の育成には当然時間がかかります。ある地場の業者と仕事をしたとき、当社が日本でやっているように手直しを繰り返していたら「話が違う。こんなことまでするなら、次回からは大和ハウスとは仕事をしたくない」と言われたこともあります。
布野:日本で研修はしたのですか。
恵藤:いいえ。ただ、地場のデベロッパーにとっては、日本の業者と仕事ができたなら、同じ水準の仕事がまたできるだろうと。それで「新たな仕事の依頼が来るんだからいいじゃないか」となだめましたが(笑)。中国の市政府が日系企業に期待しているのは、地場企業の技術水準の底上げなので、誘致をしてくれる地域ではやりやすい。
布野:政治状況も難しいなかで、よくやってらっしゃいますね。今後も中国事業を拡大する方針ですか。
恵藤:人材の数も限られているので、長江デルタや、当社が関わった歴史が長い大連でも拡大していきたいと考えています。バブルを免れている天津なども検討しています。
布野:人材ということですが、日本の学生は内向きですね。アジアでなら、日本でできないような、すごいものを作ることもできるのに。外国に出て行けと言っても、出て行かない。就職活動で1年くらい費やしてますからね。
恵藤:バブルがはじけてから、便利で清潔でモノが安い日本の生活をエンジョイしたいという人が増えている気がします。
布野:入社したころの恵藤さんはどうだったんですか。
恵藤:私は入社のときに「3年たって海外に行かせてもらえなければ、会社を辞めます」と言ったんです。それで無理やり米国に赴任させてもらった(笑)。その後はオーストラリアと中国で、会社人生は海外のほうが長いくらいです。海外に行きたがらない人を見ると、会社がお金を出してくれて、異文化を体験させてくれるのにと不思議ですね。
■ニーズは手探り
布野:コアハウスの部分だけを大量生産するというシステムの普及を検討しているのですが、そういった事業の可能性はいかがですか。
恵藤:どこまでこちらが割り切れるか難しいですね。売りっぱなしでは、何かあったときの責任が取れず、企業イメージを維持できませんから。当社製のコアハウスが丈夫で劣化しないというイメージを確固たるものにできれば、そこから広げていける可能性もありますが。
布野:マレーシアやインドネシアではスケルトン売りが多いですね。多様な民族と風習があり、例えばバリ人はヒンズー教に基づいたバリ風のインテリアにしたりするので、内装まで仕上げてしまうと売れない。基本的には仕上げない売り方ですよね。
恵藤:中国も似たような所があります。富裕層の中には、建築屋は信用できないので内装は自分たちでやると言う人も多い。当社の蘇州のプロジェクトは内装付きですが、スケルトンだけだと差別化が難しい。
布野:1995年からインドネシアで、共有部分を最大にした集合住宅を設計しました。キッチンは共有で、シャワーは2戸にひとつ。2階と3階のフロアには店舗も入れられる。もともと共同生活をしている人が多いので、個々の施設の所有関係がはっきりしていなくても、すんなり受け入れられる。国によってはこういった住宅もありうるという提案でした。コレクティブ・ハウスといっていいのですが、子供が多いのでなかなか活気がある集合住宅になりました。ただ、シンガポールでは理解できなかったようで、「共有部分をだれが所有して、だれが管理するのか」と質問攻めに合いました。
恵藤:なるほど。
布野:高齢化が進むと、ひとつの家に単身で住む居住者が増え、核家族を前提としたモデルの住居が合わなくなっていく。中国は急速に高齢化していくので、近い将来シェア型の集合住宅の普及もありえるかもしれません。
恵藤:シルバー産業には中国でも地元のデベロッパーは目を向けています。まずは富裕層を狙っていて、高級老人ホームが出てきていますね。バリアフリーも知識としては入っているようです。
布野:私は51C型という、日本の公団のプロトタイプを作った研究室の出身なんです。インドネシアやフィリピンに最初に行ったときに、日本はアジアにどんな住宅が提案できるのかと考えさせられました。材料が日本と違うし、収入の階層も違う、気候の問題もあります。家族の形なども含めて、本腰を入れて調査をした上で臨まないといけないと思いました。
恵藤:そうですね。ビジネスとしても、相手が求めているものを、しっかりと探して作らなければと思います。例えば、インドネシアで耐震構造付きの住宅を提案しても「ジャカルタではそんなに地震がないからいらない」と言われ、セールスポイントにならなかった。また、耐震構造はお金がかかるので、コストとの兼ね合いの問題もある。相手が何を求めているのか、手探りの状態です。まして、住宅はずっと住むものですから。
布野:自動車や家電を輸出するのとは違う。
恵藤:ええ。ただ、日本発の便利なものを提案すれば、アジアでも受け入れられる素地はあります。中国ではバスタブに入る習慣はありませんが、温泉も好きですし、風呂に入れば、それなりに好評です。トイレとバスも一緒の住宅がほとんどですが、トイレを独立させたら「気に入った」という中国人も多い。蘇州のプロジェクトでは、全戸にウォシュレットをつけました。家電などでもそうですが、不要な部分をそぎ落として売る必要があるでしょうね。
2022年4月2日土曜日
災害に強いまちづくりのための社会システムの構築(主査 岡田憲夫 分担執筆),京都大学防災研究所,1997年3月
災害に強いまちづくりのための社会システムの構築(主査 岡田憲夫 分担執筆),京都大学防災研究所,1997年3月
災害に強い町づくりのための社会システムの構築に関するメモ
布野修司
世紀末建築の行方:戦後50年と阪神・淡路大震災
敗戦から阪神・淡路大震災への戦後50年
戦後50年の節目に当たる1995年は、日本の戦後50年のなかでも敗戦の1945年とともにとりわけ記憶される年になった。阪神・淡路大震災とオウム事件。この二つの大事件によって、日本の戦後50年の様々な問題が根底的に問い直されることになったのである。加えて、年末からは「住専問題」が明るみに出た。日本の都市と建築を支えてきたものが大きく揺さぶられ続けたのが1995年であった。
建築界は、阪神・淡路大震災で明け暮れた。この間の日本建築学会の対応は以下にまとめられる通りである。またこの一年『建築雑誌』等でも一貫して取り上げられてきた通りである。今手元にたまたま、大部の報告書『兵庫県南部地震の被害調査に基づいた実証的分析による被害の検証』(研究代表者 藤原悌三 1996年3月)があるのであるが、この一冊だけからも、大変な災害であったことが再確認できると同時に、多くの研究者・建築家が大震災をそれぞれ自らの大きな課題として取り組んできたことがうかがえる。
一方、大震災から一年半を経て、時間の経過に伴う感慨もある。最早、大震災は遠い過去のものとなりつつあるように思えてしまうのである。既に3月20日の地下鉄サリン事件以降、オウムの事件が日本列島を席巻し、被災地は置き去られた感はあった。
大震災の最大の教訓は、実は、人々は容易に震災を忘れてしまうことではないか。
しかし、大震災の投げかけた意味が一年を通して問い続けられたことは疑いはない。また、これからも問い続けられていくであろう。この50年の建築や都市のあり方を根底的に考え直させる、それほど大きな事件であったことは論をまたないところだ。阪神・淡路大震災をめぐっては、個人的にもこの一年、様々な議論の場に関わり、何度か思うところを記録する機会があった*1。また、戦後50年ということで、戦後建築の歴史を振り返り、まとめ直す機会があった*2。それを基礎に、建築の戦後50年を振り返ってみたい。
人工環境化・・・自然の力・・・地域の生態バランス
阪神・淡路大震災に関してまず確認すべきは自然の力である。いくつものビルが横転し、高速道路が捻り倒された。そんなことがあっていいのか、というのは別の感慨として、とにかく地震の力は強大であった。また、避難所生活を通じての不自由さは自然に依拠した生活基盤の大事さを思い知らせてくれた。
水道の蛇口をひねればすぐ水が出る。スイッチをひねれば明かりが灯る。エアコンディショニングで室内気候は自由に制御できる。人工的に全ての環境をコントロールできる、あるいはコントロールしているとつい考えがちなのであるが、とんでもない。災害が起こる度に思い知らされるのは、自然の力を読みそこなっていることである。自然の力を忘れてしまっていることである。山を削って土地をつくり、湿地に土を盛って宅地にする。そして、海を埋め立てる。本来人が住まなかった場所だ。災害を恐れるからそういう場所には住んでこなかった。その歴史の智恵を忘れて、開発が進められてきたのである。
それにしても、関西には地震はこない、というのはどんな根拠に基づいていたのか。軟弱地盤や活断層、液状化の問題についていかに無知であったことか。また、知っていても、結果的にいかに甘く見ていたか。
一方、自然のもつ力のすばらしさも再認識させられた。例えば、家の前の樹木が火を止めた例がある。緑の役割は大きいのである。自然の河川や井戸の意味も大きくクローズアップされたのであった。
人工環境化、あるいは人工都市化が戦後一貫した建築界の趨勢である。自然は都市から追放されてきた。果たして、その行き着く先がどうなるのか、阪神・淡路大震災は示したのではないか。「地球環境」という大きな枠組みが明らかになるなかで、また、日本列島から開発フロンティアが失われるなかで、自然の生態バランスに基礎を置いた都市、建築のあり方が模索されるべきではないのか。
フロンティア拡大の論理・・・「文化住宅」の悲劇・・・開発の社会経済バランス
阪神・淡路大震災の発生、避難所生活、応急仮設住宅居住、そして復旧・復興へという過程を見てつくづく感じるのは、日本社会の階層性である。すぐさまホテル住まいに移行した層がいる一方で、避難所が閉鎖されて猶、避難生活を続けざるを得ない人たちがいる。間もなく出入りの業者や関連企業の社員に倒壊建物を片づけさせる邸宅がある一方で、長い間手つかずの建物がある。びくともしなかった高級住宅街のすぐ隣で数多くの死者を出した地区がある。これほどまでに日本社会は階層的であったのか。
最もダメージを受けたのは、高齢者であり、障害者であり、住宅困窮者であり、外国人であり、要するに社会的弱者であった。結果として、浮き彫りになったのは、都市計画の論理や都市開発戦略がそうした社会的弱者を切り捨てる階層性の上に組み立てられてきたことだ。
ひたすらフロンティアを求める都市拡大政策の影で、都心が見捨てられてきた。開発の投資効果のみが求められ、居住環境整備や防災対策など都心への投資は常に後回しにされてきた。
例えば、最も大きな打撃を受けたのが「文化」である。関西で「ブンカ」というと「文化住宅」という一つの住居形式を意味する。その「文化住宅」が大きな被害にあった。木造だったからということではない。木造住宅であっても、震災に耐えた住宅は数しれない。木造住宅が潰れて亡くなった方もいるけれど家具が倒れて(飛んで)亡くなった方が数多い。大震災の教訓は数多いけれど、しっかり設計した建物は総じて問題はなかった。「文化住宅」は、築後年数が長く、白蟻や腐食で老朽化したものが多かったため大きな被害を受けたのである。戦後の住宅政策や都市政策の貧困の裏で、「文化住宅」は、日本の社会を支えてきた。それが最もダメージを受けたのである。それにしても「文化住宅」とは皮肉な命名である。阪神・淡路大震災によって、「文化住宅」の存在という日本の住宅文化の一断面が浮き彫りになったのである。
都市計画の問題として、まず、指摘されるのは、戦後に一貫する開発戦略の問題点である。企業経営の論理を取り入れた都市経営の展開は、自治体の模範とされた。しかし、その裏で、また、結果として、都心の整備を遅らせてきた。都心に投資するのは効率が悪い。時間がかかる。また、防災にはコストがかかる。経済論理が全てを支配する中で、都市生活者の論理、都市の論理が見失われてきた。都市経営のポリシー、都市計画の基本論理が根底的に問われたのである。
一極集中システム・・・重層的な都市構造・・・地区の自律性
日本の大都市はひたすら肥大化してきた。移動時間を短縮させるメディアを発達させひたすら集積度を高めてきた。郊外へのスプロールが限界に達するや、空へ、地下へ、海へ、さらにフロンティアを求め、巨大化してきた。都市や街区の適正な規模について、われわれはあまりに無頓着ではなかったか。
都市構造の問題として露呈したのが、一極集中型のネットワークの問題点である。大震災が首都圏で起きていたら、一体どうなっていたのか。東京一極集中の日本の国土構造の弱点がより致命的に問われたのは確実である。遷都問題がかってないほどの関心を集めはじめたのは当然と言えば当然のことである。
阪神間の都市構造が大きな問題をもっていることはすぐさま明らかになった。インフラストラクチャーの多くが機能停止に陥ったのである。それぞれに代替システム、重層システムがなかったのである。交通機関について、鉄道が幅一キロメートルに四つの路線が平行に走るけれど迂回する線が無い。道路にしてもそうである。多重性のあるネットワークは、交通に限らず、上下水道などライフラインのシステム全体に必要なのである。
エネルギー供給の単位、システムについても、多核・分散型のネットワーク・システム、地区の自律性が必要である。ガス・ディーゼル・電気の併用、井戸の分散配置など、多様な系がつくられる必要がある。また、情報システムとしても地区の間に多重のネットワークが必要であった。
また、公共空間の貧困が大きな問題となった。公共建築の建築としての弱さは、致命的である。特に、病院がダメージを受けたのは大きかった。危機管理の問題ともつながるけれど、消防署など防災のネットワークが十分に機能しなかったことも大きい。想像を超えた震災だったということもあるが、システム上の問題も指摘される。避難生活、応急生活を支えたのは、小中学校とコンビニエンスストアであった。公共施設のあり方は、非日常時を想定した性能が要求されるのである。
また、クローズアップされたのは、オープンスペースの少なさである。公園空地が少なくて、火災が止まらなかった。また、仮設住宅を建てるスペースがない。地区における公共空間の他に代え難い意味を教えてくれたのが今回の大震災である。
産業社会の論理・・・地域コミュニティのネットワーク・・・ヴォランティアの役割
目の前で自宅が燃えているのを呆然と見ているだけでなす術がないというのは、どうみてもおかしい。同時多発型の火災の場合にどういうシステムが必要なのか。防火にしろ、人命救助にしろ、うまく機能したのはコミュニティがしっかりしている地区であった。救急車や消防車が来るのをただ待つだけという地区は結果として被害を拡大することにつながったのである。
今回の大震災における最大の教訓は、行政が役に立たないことが明らかになった、という自虐的な声を聞いた。一理はある。自治体職員もまた被災者である。行政のみに依存する体質が有効に機能しないのは明かである。問題は、自治の仕組みであり、地区の自律性である。行政システムにしろ、産業的な諸システムにしろ、他への依存度が高い程問題は大きかったのである。
産業化の論理こそ、戦後社会を導いてきたものである。その方向性が容易に揺らぐとは思えないけれど、その高度化、もしくは多重化が追求されることになろう。ひとつの焦点になるのがヴォランティア活動である。あるいはNPO(非営利組織)の役割である。
今回の震災によって、一般的にヴォランティアの役割が大きくクローズアップされた。まちづくりにおけるヴォランティアの意味の確認は重要である。しかし、ヴォランティアの問題点も既に意識される。行政との間で、また、被災者との間で様々な軋轢も生まれたのである。多くは、システムとしてヴォランティア活動が位置づけられていないことに起因する。
建築の分野でも被災度調査から始まって復興計画に至る過程で、ヴォランティアの果たした役割は少なくない。しかし、その持続的なシステムについては必ずしも十分とは言えない。ある地区のみ関心が集中し、建築、都市計画の専門家の支援が必要とされる大半の地区が見捨てられたままである。また、行政当局も、専門家、ヴォランティアの派遣について、必ずしも積極的ではない。粘り強い取り組みの中で、日常的なまちづくりにおける専門ヴォランティアの役割を実質化しながら状況を変えて行くことになるであろう。
最適設計の思想・・・建築技術の社会的基盤・・・ストック再生の技術
何故、多くのビルや橋、高速道路が倒壊したのか。何故、多くの人命が失われることになったのか。建築界に関わるわれわれ全てが深く掘り下げる必要がある。最悪なのは、専門外だから自分とは無縁であるという態度である。問題なのは社会システムであると、自らの依って立つ基盤を問わない態度である。問題は基準法なのか、施工技術なのか、検査システムなのか、重層下請構造なのか、という個別的な問いの立て方ではなくて、建築を支える思想(設計思想)の全体、建築界を支える全構造(社会的基盤)がまずは問われるべきである。建造物の倒壊によって人命が失われるという事態はあってはならないことである。しかし、それが起こった。だからこそ、建築界の構造の致命的な欠陥によるのではないかと第一に疑ってみる必要があるのである。
要するに、安全率の見方が甘かった。予想を超える地震力だった。といった次元の問題ではないのではないか、ということである。経済的合理性とは何か。技術的合理性とは何か。経済性と安全性の考え方、最適設計という平面がどこで成立するのかがもっと深く問われるべきなのである。
建築技術の問題として、被災した建造物を無償ということで廃棄したのは決定的なことであった。都市を再生する手がかりを失うことにつながったからである。特に、木造住宅の場合、再生可能であるという、その最大の特性を生かす機会を奪われてしまった。廃材を使ってでも住み続ける意欲の中に再生の最初のきっかけもあったのである。
何故、鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物の再生利用が試みられなかったのも不思議である。技術的には様々な復旧方法が可能ではないか。そして、関東大震災以降、新潟地震の場合など、かなりの復旧事例もある。阪神・淡路大震災の場合、少なくとも、再生技術の様々な方法が蓄積されるべきではなかったか。
仮設都市・・・スクラップ・アンド・ビルド・・・サテイアン
阪神・淡路大震災は、人々の生活構造を根底から揺るがし、都市そのものを廃棄物と化した。しかし、それ以前に、われわれの都市は廃棄物として建てられているのではないか、という気もしてくる。建てては壊し、壊しては建てる、阪神・淡路大震災は、スクラップ・アンド・ビルドの日本の都市の体質を浮かび上がらせただけではないか。
阪神・淡路大震災の前には全ての建築の問題が霞むのであるが、1995年の建築界を振り返って次に挙げるべき事件は都市博の中止である。近代日本の百年、都市計画は博覧会を都市開発の有力な手段にしてきた。仮設の博覧会のためにインフラストラクチャーを公共団体が整備し、博覧会が終わると民間企業が進出して都市開発を行う。戦後も大阪万博以降、各自治体が様々なテーマで繰り広げる博覧会にその手法は踏襲されてきた。博覧会型都市計画は、果たして、その命脈を断たれることになるであろうか。いずれにせよ、建築界にとって戦後50年が大きな区切りの年になったことは間違いない。
戦災復興から高度成長期へ、日本の建築界はひたすら建てることのみを目指してきたように見える。住宅の総戸数が世帯数を超え、オイルショックにみまわれた70年代前半を経ても、そのスクラップ・アンド・ビルドの趨勢は揺るがなかった。都市計画も成長拡大政策が基調であった。また、巨大プロジェクト主義が支配的であった。
都市博が「東京フロンティア」と名づけられていたことは象徴的である。フロンティアの消滅が意識されるからこそ、フロンティアが求められたのである。
しかしそれにしても、オウム真理教のサティアンと呼ばれる建築物も戦後建築の50年の原点と到達点を示しているようで無気味であった。そこにあるのは経済的合理性のみの表現である。あるいは何の美学もない間に合わせのバラック主義である。そこでは建築や街並み、周辺の景観など一切顧慮されていないのである。仮設の建物のなかで、全く我侭に、自らの魂の救済のみが求められている。
変わらぬ構造
大震災によって何が変わったのか、というと、今のところ、何も変わらなかったのではないか、という気がしないでもない。震災があったからといって、そう簡単にものごとの仕組みが変わるわけはないのである。そのインパクトが現れてくるまでには時間がかかるだろう。しかしそうは思っても、果たして何かが変わっていくのかどうか疑問が湧いてくる。
建築家、都市計画プランナーたちはヴォランティアとして、それぞれ復旧、震災復興の課題に取り組んできた。コンテナ住宅の提案、紙の教会の建設、ユニークで想像力豊かな試みもなされてきた。この新しいまちづくりへの模索は実に貴重な蓄積となるであろう。
しかし、そうした試みによって新しい動きが見えてきたかというと必ずしもそうでもない。復興計画は行政と住民の間に様々な葛藤を生み、容易にまとまりそうにないのである。そして、大震災の教訓が復興計画に如何に生かされようとしているのか、というと心許ない限りである。都市計画を支える制度的な枠組みは揺らいではいないし、立案された復興計画をみると、大復興計画というべき巨大プロジェクト主義が見えかくれしている。フロンテイア主義は変わらないのであろうか。
関東大震災後も、戦災復興の時にも、そして、今度の大震災の後も、日本の都市計画は同じようなことを繰り返すだけではないのか。要するに、何も変わらないのではないか、と思えてくる。復興過程の袋小路を見ていると、震災が来ようと来まいと、基本的な問題点が露呈しただけであるように見える。問題は、被災地であろうと被災地でなかろうと関係ない。どこにも遍在する問題を地震の一揺れが一瞬のうちに露呈させたのではないか。だとすると、ずっと問われているのは戦後50年の都市と建築のあり方なのである。
バブルが弾けて、ポストモダンの建築は完全にその勢いを失った。デコン(破壊)派と呼ばれた殊更に傾いた壁やファサード(正面)を弄んできた建築表現の動向も大震災の破壊の前で児戯と化した。建築表現は世紀末へ向けてどう変化していくのか。
このところCAD表現主義とも言うべき、コンピューターを駆使することによって可能になった形態表現が目立つ。新しいメディアによって新たな建築表現が試みられるのは当然である。しかし、CADによる形態操作の生み出す多様な表現はすぐさま飽和状態に達する予感がないでもない。建築はヴァーチャルな世界で完結はしないからである。
都市(建築)の死と再生
今度の大震災がわれわれにつきつけたのは都市(建築)の死というテーマである。そして、その再生というテーマである。被災直後の街の光景にわれわれがみたのは滅亡する都市(建築)のイメージと逞しく再生しようとする都市(建築)のイメージの二つである。都市(建築)が死ぬことがあるという発見、というにはあまりにも圧倒的な事実は、より原理的に受けとめられなければならないだろう。
現代都市の死、廃墟を見てしまったからには、これまでとは異なった都市(建築)の姿が見えたのでなければならない。復興計画は、当然、これまでにない都市(建築)のあり方へと結びついていかねばならない。
そこで、都市の歴史、都市の記憶をどう考えるのかは、復興計画の大きなテーマである。何を復旧すべきか、何を復興すべきか、何を再生すべきか、必然的には都市の固有性、歴史性をどう考えるかが問われるのである。
建造物の再生、復旧が、まず建築家にとって大きな問題となる。同じものを復元すればいいのか、という問いを前にして、建築家は基本的な解答を求められる。それはしかし、震災があろうとなかろうと常に問われている問題である。都市の歴史的、文化的コンテクストをどう読むか、それをどう表現するかは、日常的テーマといっていいのである。
戦災復興でヨーロッパの都市がそう試みたように、全く元通りに復旧すればいいというのであれば簡単である。しかし、そうした復旧の理念は、日本においてどう考えても共有されそうにない。都市が復旧に値する価値を持っているかどうか、ということに関して疑問は多いのである。すなわち、日本の都市は社会的なストックとして意識されてきていないのである。戦後50年で、日本の都市はすぐさま復興を遂げ、驚くほどの変貌を遂げた。しかし、この半世紀が造り上げた後世に残すべき町や建築は何かというと実に心許ないのである。
スクラップ・アンド・ビルド型の都市でいいということであれば、震災による都市の破壊もスクラップの一つの形態ということでいい。必ずしも、まちづくりについてのパラダイムの変更は必要ないだろう。しかし、バブル崩壊後、スクラップ・ビルドの体制は必然的に変わって行かざるを得ないのではないか。
そして、都市が本来人々の生活の歴史を刻み、しかも、共有化されたイメージや記憶をもつものだとすれば、物理的にもその手がかりをもつのでなければならない。都市のシンボル的建造物のみならず、ここそこの場所に記憶の種が埋め込まれている必要がある。極めて具体的に、ストック型の都市が目指されるとしたら、復興の理念に再生の理念、建造物の再生利用の概念が含まれていなければならない。否、建築の理念そのものに再生の理念が含まれていなければならない。
果たして、日本の都市はストックー再生型の都市に転換していくことができるのであろうか。
表現の問題として、都市の骨格、すなわち、アイデンティティーをどうつくりだすことができるか。単に、建造物を凍結的に復元保存すればいいのか、歴史的、地域的な建築様式のステレオタイプをただ用いればいいのか、地域で産する建築材料をただ使えばいいのか、・・・・議論は大震災以前からのものである。
阪神・淡路大震災は、こうして、日本の建築界の抱えている基本的問題を抉り出した。しかし、その解答への何らかの方向性を見い出す契機になるのかどうかはわからない。半世紀後の被災地の姿にその答えは明確となる筈だ。しかし、それ以前に、半世紀前から同じ問いの答えが求められているのである。
(日本建築学会 建築雑誌
1996年 研究年報7月17日 記)
*1 拙稿、「阪神大震災とまちづくり……地区に自律のシステムを」共同通信配信、一九九五年一月二九日『神戸新聞』、「阪神・淡路大震災と戦後建築の五〇年」、『建築思潮』4号、1996年、「日本の都市の死と再生」、『THIS IS 読売』、1996年2月号など
*2 拙著、『戦後建築の終焉』、れんが書房新社、1995年、『戦後建築の来た道 行く道』、東京建築設計厚生年金基金、1995年
-
traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...