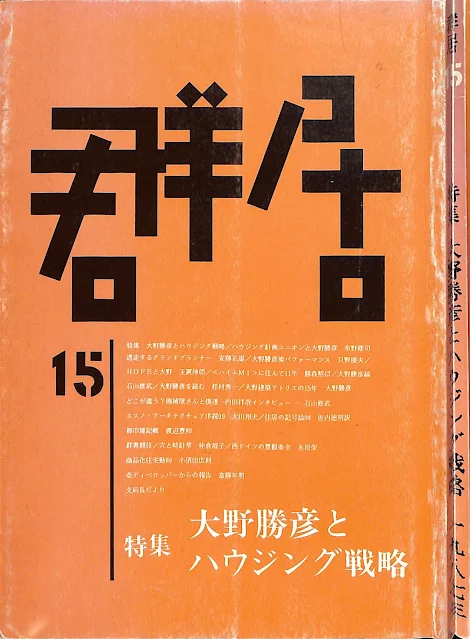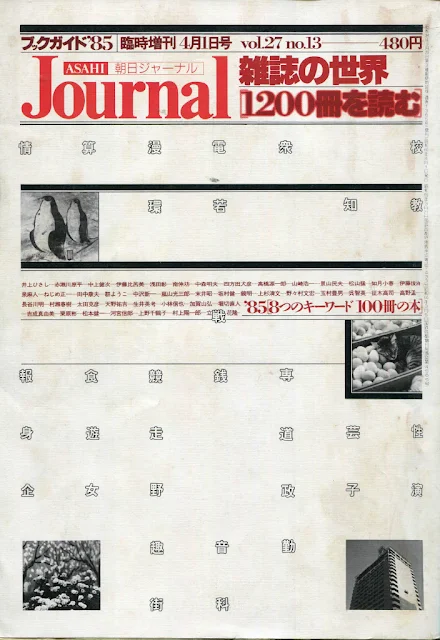平良敬一という建築メディア-『住宅建築』500号に寄せて
布野修司
「対抗者の視座がある。抑圧されている側によりそって,運動を起こしている。事件の渦中に好んで入っている。/ユートピアが死んで,マニフェストが無効になった時代の近代建築を新しい媒体としての建築雑誌(メディア)をつくりだすことによって活性化する。/宮古島生まれのオキナンチュウヒララが記しつづけたのは,中心にある権力に対して,これを足元からゆすぶりながら崩していこうとする南島の風土に根づいた記憶にある。/いつも控えめではにかんでいる。だが編集の手つきは過激である。/ゼネコンのつくった編集部にいながら,町の工務店の手仕事をつくりはじめる。/テクノクラートがつくる都市を批判して,エコがつくりだすすまいをとさがす。/91歳のいまも,平良(ヒララ)敬一は対抗者でありつづける。」(磯崎新「対抗者 平良敬一」『平良敬一建築論集 機能主義を超えるもの』帯)
平良敬一とは何者か?
戦後日本の建築界を代表する建築ジャーナリストであり,編集者である。
しかし,それ以上の何者かである。磯崎新が,見事にその核心を言い当てている。
建築ジャーナリストとは何者か?あるいは編集者とは何者か?SNSがコミュニケーション手段となり,WEBマガジンが一般化するなかで,改めてその役割を問い直したいと思う。
そう思うのなら,ひとりでもやれ!
平良敬一さんが亡くなったのは2020年4月29日である。Covid-19の感染が大都市圏から地方にも広がり全都道府県に4月16日に緊急事態宣言が出されてまもなくのことである。遡ること3年前,2017年5月11日に東京竹橋の学士会館で開かれた平良さんの唯一の建築論集『機能主義を超えるもの』(風土社,2017)の出版をお祝いする会(平良敬一さん「建築論集」の出版を祝う会)でお会いしたのが最後となった。そろそろ終わりかける頃,平良さんは近くにいた何人かをひとりずつ呼んで短い時間個別に話をされた。紙媒体雑誌の衰退と平良さんのような編集者の不在を嘆いた筆者に対して,平良さんは言われた。「そう思うのなら,ひとりでもやれ!」。筆者への遺言である。
平良さんの「お別れの会」が開かれないままに,その時のシンポジウムに登壇された内田祥哉先生(1925~2021),長谷川堯さん(1937~2019),そして磯崎新さん(1931~2022)も相次いで逝ってしまわれた。訃報を聞いてまもなく,新たなメディアの立ち上げも視野に「平良敬一と戦後建築ジャーナリズム」について改めて考えてみようと,田尻裕彦,神子久忠,中谷正人,川床優などにインタビューを始めた。また,A-Forumで斎藤公男先生と「建築とジャーナリズム研究会(AJ研)」を立ち上げた[1]。しかし,かたちにする作業は遅々としてすすまない。そうしているうちに『住宅建築』は500号になるという。筆者は,創刊200号記念特大号の「座談会:200号まで来た」(布野修司・益子義弘+平良敬一・立桧久昌・植久哲男:1991年11月)に呼ばれている。また,400号記念に「そして,『住宅建築』が残った…ヴァナキュラー建築の地水脈」」(2008年8月)という文章を寄稿している。それから15年,平良さんの遺伝子である『住宅建築』(小泉淳子編集長)の驚異的な持続力に心から敬意を表したい。
戦後建築と平良敬一
平良敬一の軌跡については,『機能主義を超えるもの』のあとがき「戦後建築ジャーナリズムとともに歩む」がある。筆者がインタビューをもとにまとめた「戦後建築ジャーナリズム秘史」(『建築思潮』Ⅰ「未踏の世紀末」,学芸出版社,
19930320)を増補したものである[2]。
敗戦後,建築家が大同団結した新日本建築家集団NAU(New Architects Union)(1947~1951)の事務局に入って,機関紙『NAUM』の編集に携わって以降,『国際建築』(1950入社)『新建築』(1953入社~1957)『建築知識』(全日本建築士会出版局,1963創刊・編集長)『建築』(槙書店,青銅社,1960創刊・編集長)鹿島研究所出版会移籍(1962~1974)『SD』(1965創刊・編集長)『都市住宅』(1968創刊)建築思潮研究所設立(代表取締役1974)『住宅建築』(建築資料研究社,1975創刊・編集長)『造景』(建築資料研究社,1996創刊・編集長)と編集活動は一貫している。さらに『住宅建築』別冊『店舗と建築』『建築設計資料』があるし,『チルチンびと』(風土社)の創刊(1997)にも関わっている。戦後日本の建築雑誌のほとんどすべてに関わってきたのが平良敬一である。こうした戦後建築ジャーナリズムの歴史については,さらに「建築ジャーナリズムの戦後50年」(対談 平良敬一・布野修司,GA,1995 SPRING)がある。
「昭和戦後」生まれの建築家たち,少なくともICT革命以前に建築を学んだ建築少年たちは,平良敬一に代表される編集者によって編まれた建築雑誌を読んで育った。平良敬一そのものが戦後建築のメディアであった。
戦後建築ジャーナリズムの場には模索すべき共通のテーマがあった。誤解を恐れずに言えば,それは「近代建築批判」[3]であり,平良さんのいう「機能主義を超えるもの」である。建築メディアが果たすべき役割の第一は建築をめぐる様々なプロブレマティークを議論する場を用意することである。川添登・宮島圀夫・平良敬一・宮内嘉久の4人体制の『新建築』を黄金時代と平良さんは振り返るが,伝統建築論争など建築界の議論をリードしたのが『新建築』であった。ただ,この黄金時代は村野藤吾の有楽町「そごう」の評価をめぐって4人全員解雇に終わる(「新建築問題」)。
自立メディアと商業メディア,そして運動としてのメディア
平良さんと最初に会ったのは「同時代建築研究会」[4]においてである。同時代建築研究会は,第一期連続シンポジウム(戦後史をいかに書くか,稲垣栄三,19780114:建築における近代化,あるいは近代主義について,大谷幸夫,19780128:戦後建築ジャーナリズム,宮内嘉久,19780210:伝統論からメタボリズムへ,川添登,19780225:建築の危機と建築家,藤井庄一郎,19780311:『建築文化』197808ー11)に続いて「空白の一九四〇年代ー戦争と建築」[5](浜口隆一・神代雄一郎・平良敬一,1983年12月9日),「近代と近代建築の終焉ー一九五〇年代の建築と文化」(神代雄一郎・鬼頭梓・平良敬一,1984年12月8日)を開催する。今日であれば,YouTubeで発信,録画記録するだけで,興味があればご覧くださいで終わってしまうのだけれど,現場での議論を文章にして活字化する作業が編集の基礎作業である。そして,シンポジウムは饗宴であって,お酒を酌み交わしながら学んだことは多大である。
筆者は,並行して『群居』というワープロ雑誌の創刊(創刊準備号1982年12月,創刊号1983年4月)に関わり,終刊50号(2000年12月)まで編集長を務めることになる。そのひとつのきっかけとなったのが,筆者自身が参加を求められた宮内嘉久さんの新しい建築雑誌『地平線』創刊をめぐる「事件」―編集方針をめぐる意見の対立で筆者が離脱,結果として創刊を潰したとされる―である。
平良さんと嘉久さんはNAUの事務局時代からの言わば同志で,『新建築』でも一緒であったし,『新建築』退職後には「宮内平良編集事務所」を設立している。また,1970年代初頭のAF(建築戦線)の活動も共にしている。しかし,建築メディアについての考え方は異なっていったように思われる。平良敬一も宮内嘉久も既に建築ジャーナリズムのレジェンドであり。若い世代にとっては歴史上の人物である。二人については,楠田博子『戦後建築雑誌における編集者・平良敬一の研究̶ "
機能主義を超えるもの" の変遷と実践 ̶』(東北大学大学院工学研究科,2015年度修士論文),福井駿『編集者宮内嘉久の思想と実践について』(京都工芸繊維大学大学院,2020年度修士論文)という修士論文が書かれている。幻の雑誌『地平線』をめぐる「事件」の詳細は,福井論文に資料として収められた筆者へのインタビューに委ねるが,要は,特定のパトロンに依存する雑誌の財政基盤,特定の建築家,特定の建築作品傾向を排除する編集方針に対する違和感である。建築メディアの基本原則の第二は,あらゆる批判を議論の場に挙げることであろう。
嘉久さんは「建築ジャーナリズム研究所」の解体以後,『廃墟から』という個人誌に依拠することになる。現在であれば,個人誌はブログというかたちで展開可能である。そして,『風声』『燎火』という著名な建築家の同人誌の編集に向かう。その頃,筆者は「自立メディア幻想の彼方へ」(螺旋工房クロニクル,建築文化,197809)を書いた。嘉久さんとしてみたら,再び開かれた場としての『地平線』の構想であったと思う。嘉久さんは,後に『建築ジャーナル』の編集に関わっている。編集者として自立して生きていくことは容易ではない。嘉久さんは何冊もの建築論集をまとめるが,編集者というより評論家であったと思う。
『群居』という会員制のメディアの立ち上げに参加したのは,自分なりの答えを模索したいと思ったからである。「編集の神様」に思えていた平良さんには,折に触れてアドヴァイスも受けたが,会員制の部数が2000人になった時「あとは減るだけだ」と言われてその通りになったことは別のところにも書いた。また,渡辺豊和さんと始めたAF(建築フォーラム)『建築思潮』(創刊号1992~5号1998)の命名については平良さんに許可を得た。『群居』以降,『traverse』(2000~)『京都げのむ』(京都コミュニティ・デザイン・リーグCD)2001年~2006年)『雑口罵乱』(談話室,滋賀県立大学,2007年~)の立ち上げに関わってきた。『建築雑誌』(日本建築学会)には3度編集委員会に加わり,最後は 編集長(2002年1月号~2003年12月号)を務めた。そして,WEB版『建築討論』(日本建築学会)を立ち上げ,編集長を務めた(2014年~2017年 No.01~13)[6]。
建築メディアの第三の役割は,編集によってその時々の状況を記録することである。平良さんは運動としてのメディアという。メディアは,編集という行為の運動の記録である。
共同環境形成論―機能主義を超えるもの
同時代建築研究会の議論で今でも覚えているのは,何を評価するのか,建築家(人)か建築(物)かという議論である。平良さんは建築派であった。ただ,平良さんの編集方針の基幹にあったのは「建築家」の「デザイン」,その「作品」ではない。建築がいかにあるべきか,都市がいかにあるべきかが問題であった。次々にメディアを立ち上げたのは,われわれを取り巻く全環境のあり方が関心の中心であったからである。平良さんのいう建築は,社会システムの建築と切り離せないものと考えられていた。
建築論集の冒頭(はじめに)に「これだけはぶれていないという一貫した筋はあった。それは“機能主義を超えるもの”を見出したいということである。」と書いている。評価基準は,「機能主義を超えるもの」である。
「機能主義を超えるもの」というのは,実は,平良さんの処女論文のタイトルである(葉山一夫名,『美術批評』,1954年3月号)。建築論集の中心に置かれる「機能主義を超える論理と倫理を求めて-「言語モデル的空間論」」という長大な論文[7]に採録されるが,機能主義の評価とその批判,社会主義リアリズムと呼ばれる伝統様式の再評価,それをどう統合化しうるかという問いは,平良さんの編集活動において反芻され続けるのである。1969年に書かれた論文は最早歴史的論文というべきかもしれないけれど,戦後建築の初心を確認するうえで繰り返し読まれるべき考察を含んでいる。また,未完の論考して,完成されるべき論点を今猶提起し続けている。
第一に主張されるのは「機能主義」を単純に経済合理主義あるいは効用主義的にのみ解するのは誤りである,ということである。平良さんには「機能主義」の原点についての否定しがたいシンパシーがある。だから,「機能主義」の否定ではなくて,再生であり,それを超えるものを目指すという問題設定である。平良さんは,古くは用美の二元論,ファンクショナリズムvsフォルマリズム,「形態は機能に従う」(H.グリーノウ)vs「美しきもののみ機能的である」(丹下健三)という単純なディコトミーを排して,機械的機能主義と有機的機能主義を区別して,前者を変数とする関数によって後者が構成される,すなわち機能的なものは有機的な全体へ発展しうると議論を整理する[8]。続いて,ルイス・カーン,ル・コルビュジェ,F.L.ライト,F.ジョンソンらの作品に即して,劇的構成,モンタージュ,様式,内部空間の演出といった概念に触れながら,表現機能すなわち象徴機能が不可欠であるとする。そして,形式だけでは象徴機能は果たせず,形式の様式化が必要であるとする。ここまでは,今では共通認識といっていいのではないか?
それを前提に「言語モデル的空間論」が<アイデア>の段階として考察される。そして,それに技術論が重ね合わせられる。言語モデルへの関心は,空間の意味と価値,建築の象徴機能についての理論を突詰める,環境を記号(象徴)体系として把握しようとする必要に基づいている。そして,技術論については,平良さんが戦後まもなくから依拠してきた武谷三男の「人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意識的適用」という技術概念を見直し,また,L.マンフォードの技術と芸術の分離を前提としてその総合をめざすという立場も否定し,技術を人間の作るという一貫する価値選択の行動であるとする山田慶児(1932~)(土法の思想)[9]の規定を検討している。そして,記号論(言語理論)と技術論を二大支柱にして構築しようとする建築・都市理論の総体を「共同環境形成論」と呼ぶ。残念ながら,その具体的な展開は未完である。論考の全体を通じて,随所にマルクスが引用される。この間の物質循環,共同所有(コモンズ)に着目したマルクスの再評価,再読解を知れば,平良さんは,我が意を得たり,とその全体理論を確信をもって完成させると思う。
竣工写真をレイアウトし設計者の設計者の設計意図を付すだけの建築雑誌,スタイルブックと化した建築雑誌のレヴェルとは次元が違う。まして,今日でInstagramの一枚の写真と140字のツィッターで建築情報を得るだけというのは論外である。
建築メディアの第四の条件は,建築,都市のあり方について一定の理論を前提にすることである。平良さんの編集の根底には,建築の方法,都市計画の方法をめぐる理論が置かれてきたのである。平良さんは、編集者以前に建築理論家であった。
『住宅建築』
1975年に創刊された『住宅建築』は,1~100号まで平良さんが編集長を務めた後,101~193号を立松久昌が,194~373号を植久哲男が編集長引き継ぐ。そして「もう一度俺の雑誌をつくる」と言って,平良さんが編集長に復帰(2006年5月),374~426号を出した後,現小泉淳子編集長が引き継いで500号に至る。小泉さんには、『裸の建築家-タウンアーキテクト論序説』(2000)の編集でお世話になった。
『住宅建築』の創刊のことば(1975年5月号)には,「住宅建築はだれか特定の個人の制作品では断じてありません。それをその建設のために結集された人びとの共有の制作品であり,ことばを変えていえば,人びとが相互に生活の場を作り上げていく活動が生み出す集団の共同作品であり,集団の生きざまや心のありようを人びとが意識すると市内に関わりなく表現しているものなのです。」という。これは建築メディアの第五の条件である,というより,全てに優先する前提である。建築メディアは,予め,建築家界や建築業界の内に閉じたものではありえないのである。
300号(2000年3月号)の巻頭言「戦後史の記憶から浮かび上がるキーワードは,技能の復権である」には,雑誌『住宅建築』の思想(こころざし)が再確認されている。1960年代以降,つくり手の過度の自己表出の恣意性が見られるようになる,これはまずい,もっと地道なアプローチを激励するメディアが必要ではないか,と考えたのが『住宅建築』である。「問題は,設計者というつくり手・表現者の実感の表出はよいとして,ではそこに住まう人の実感に届き得ているか,問いたい」のである。さらに,平良さんは,そこで,木造に寄せる想い,技能の復権,グローバリズムという「超近代主義」への対抗について綴った後,前川國男のリアズムに触れて「あの「自邸」の見せるふてぶてしさよ,それが『住宅建築』にほしいものなのだ。言葉を変えてそっと,それこそWildernessと呼びたい。」と結んでいる。これが復帰の理由なのであろうか。Wildernessすなわち荒野,否,野生である。『住宅建築』で扱うべき住宅建築には野生が欲しい,というメッセージである。
『住宅建築』は毎号送ってもらっているけれど,お世辞ではなく,『住宅建築』の初心を貫いていると思う。丁寧に建築家たちのいい仕事を紹介してくれている。かつて研究室や「木匠塾」などで議論した若い建築家の仕事が取り上げられているのを見るのが楽しみである。
問題は,『住宅建築』に呼応する建築メディアの不在である。
反芻されるのは,「そう思うのなら,ひとりでもやれ」という平良さんの遺言である。
[1] A-Forum(建築フォーーラム)建築とジャーナリズム(AJ)研究会 幹事:斎藤公男,和田章,神子久忠,布野修司,磯達雄,今村創平,青井哲人/第1回 建築ジャーナリズムの来し方行く末 神子久忠 コーディネーター:布野修司 コメンテーター:斎藤公男,和田章,磯達雄,今村創平 2021年7月3日/第2回 建築メディアの新たな潮流 加藤純(TECTURE MAG 編集長)・富井雄太郎(株式会社ミルグラフ代表取締役) コーディネーター:磯達雄(建築ジャーナリスト Office Bunga)日時:2022年6月4日/第3回 建築メディアと一般メディアー建築界の「界」を問う 「マイパブリックとグランドレベル」をめぐって(仮)・・田中元子+大西正紀 建築界を拓くー出版界と建築界 真壁智治 コーディネーター:布野修司 日時:2022年11月26日(土)。
[2] これを踏まえたインタビューに「平良敬一[1926-] 運動の媒体としてのジャーナリズム」(聞き手:青井哲人・橋本純・石榑督和 シリーズ 建築と戦後70年,建築討論010号,2016年冬)がある。
[3] 『新建築』臨時増刊『日本建築史再考-虚構の崩壊』(1974年10月)」や『建築文化』誌の「近代の呪縛に放て」シリーズ(1975~77)がその象徴である。
[4] 1976年12月,宮内康,堀川勉,布野修司の三人で結成。当初「昭和建築研究会」と称し,「同時代建築研究会」に改称。もっとも詳細な記録は『怨恨のユートピア』刊行委員会編『怨恨のユートピア・・・宮内康の居る場所』(れんが書房新社,2000年)。
[5] 「国家と様式 1940年代の建築と文化,浜口隆一・神代雄一郎・平良敬一・同時代建築研究会 司会 堀川勉・岡利実(『建築文化』,198409)。
[6] 筆者の建築メディアとの関りについては,「布野修司インタビュー メディアとコミュニティ,聞き手;市川紘司,『建築討論』,2022年1月」がある。
[7] 加藤秀俊監修『現代デザイン講座』(風土社,1969年)第二巻「デザインの環境」所収。原タイトルは「言語モデル的空間論」。
[8] イタリアの建築史家B.ゼヴィ(1918~2000)のように,近代建築の歴史の流れの中に有機的機能主義と機械的機能主義を区別する視点は既にあったが,形式論理の問題として,あるいは構造-関数-要素の問題とするのである。