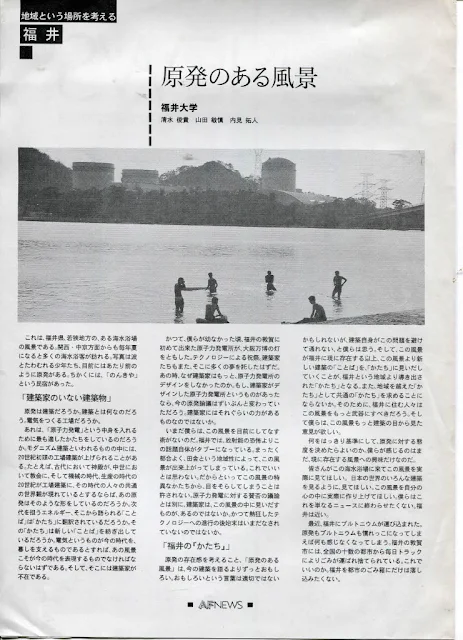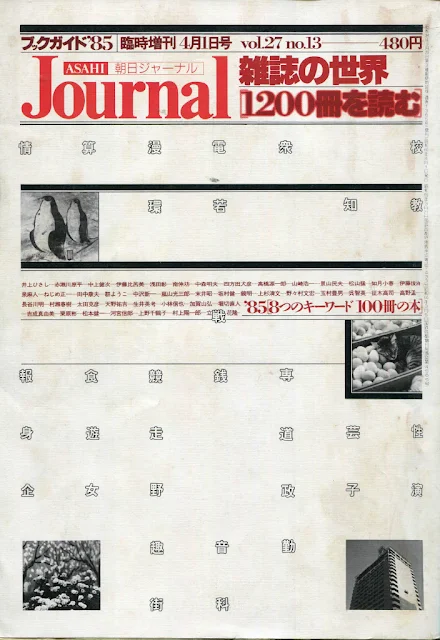布野修司インタビュー メディアとコミュニティ,聞き手;市川紘司,『建築討論』,2021年1月メディアとコミュニティ - 建築討論 - Medium
メディアとコミュニティ
インタビュー:布野修司(滋賀県立大学・日本大学)|063|202201 特集:建築メディアは楽し
い
左手と右手──アカデミズムとジャーナリズムの分断?
──布野修司さんは、大学に所属する研究者として膨大な数の論文を書かれる一方で、評論活動も活発に行われてきました。さらにときには、ご自身でメディアそのものを立ち上げる。アカデミズムにとどまならないこうした活動スタイルはどのように生まれたのでしょうか。
布野修司:すべて成り行きみたいなものです。「アカデミズム」と言うけど、いまの建築学会の状況を前提にしていると分からないかもね。「黄表紙」(建築学会の査読論文の通称)といっても、誤解を恐れずに言うけど、いまのように細々したものじゃなかった。そ
もそも僕が東京大学に入った年(1968年)は「東大闘争」ですぐに全学ストライキで、ほとんど授業がなかった。いろんな問題があったけれど、学問そのもの、大学そのもの、学会そのものが問われた、そんな時代です。授業がないから初めて出会ったクラスメートと自主ゼミを始めたけど、大学というのはそういうもので、自分で勉強するところだといまでも思ってる。
東大では医学部のインターン制度の問題があったし、工学部では産学癒着の問題が指摘されていた。現在は、産学融合が当たり前のように言われていて、学術会議に内閣府が介入するそんな時代になっている、問題は変わってないよね。それ以前に、その場所にいない学生を処分する、大学組織の体質そのものの問題があった。これも変わってない。そういう諸「問題」を追求するということを、ほぼ学生全員が課題として共有したんだと思う。大学の体制批判にはじまり、ちょっとスコープを広げれば「戦後民主主義」の裏で何が起こっているのかということが、そもそも最初から問題意識として共有されていた。だから基礎的な勉強はしながら、それをもとに諸問題を問い詰めた。実際、都市工学科の大学院生が、公害問題をめぐって追求して、答えられない先生を辞めさせたりした。大学院生が教授に議論で勝っちゃうわけ。公害の問題や日照権の問題など、戦後日本の高度経済成長にさまざまな「負の部分」がある、それを追求すること、これが、まず僕らの前提にある。
布野:そう。その構えが一番先にある。「アカデミズム」の基本も同じでしょう。だから、「アカデミズム」と「ジャーナリズム」の区分けは、あまり意味がないと思う。僕からすれば、「問題を追求する」という根幹は同じで、日々の出来事の中に問題を追及するのがジャーナリズムで、それをより大きな歴史的なパースペクティブに位置付けるのがアカデミズム。アカデミズムは科学に依拠するといってもいいけど、アカデミズムといっても、T.クーンが明らかにしたように、それを支えてきた科学「界」(仲間内)のパラダイムがある。現実から逃避し「象牙の塔」に立て籠っている、というアカデミズム批判はいまでもあるでしょう。特に、社会科学、人文科学の分野では区別はできないと思う。まして、建築学や都市計画学の実践的分野で「アカデミズム」と「ジャーナリズム」の分断はほとんど意味がない。
──例えば、戦後建築ジャーナリズムで活躍した編集者の宮内嘉久さんは、建築における「アカデミズム」と「ジャーナリズム」の違いを強調していました。彼自身は在野の評論家、編集者であり、アカデミズムを建築の主流だとすれば、そのオルタナティヴを作ろうと著述活動やメディアの立ち上げをした。『建築ジャーナリズム無頼』や『少数派建築論』などの書名などにそのスタンスはよく現れています。布野さんの考えとは対照的と言えそうです。
布野:「象牙の塔」批判が根っこにはずっとあるから、スタンスとしては同じと思うけど、逆に、宮内嘉久さんの建築ジャーナリズムについての考え方に違和感があった。最近、福井駿さんが『編集者宮内嘉久の思想と実践について』という修士論文(京都工業繊維大学、2021年3月)を書いたんだけど、そのなかに、宮内嘉久さんが構想して、結局は僕が潰してしまったということになっている『地平線』という雑誌についての僕の証言が収録されています。ジャーナリズムはある意味ではその日暮らしのジャーニーで、そのための身過ぎ世過ぎの問題がある。編集者に徹した平良敬一さんと嘉久さんとはスタンスが少し違ったと思います。嘉久さんのアカデミズム批判というのは、ひとり自分は少数派であるという意識を特権化した建築業界全体についての批判で、編集者というより批評家だったと思う。後でも詳しく言うけど、僕が『群居』を始めたのは、この『地平線』というメディアの構想に対抗する意識もあったんです。
──ともあれ、研究者と評論家・編集者の双方で膨大な成果を出してきた布野さんのキャリアは、かなり異質に見えます。
布野:どこから見て異質なの?
──少なくとも、同じような活動をされている方は見当たらない、という意味で。
布野: その都度考えて動いてきた成り行きなんだけどね。東大では、定年前に筑波大に異動した吉武先生の指令(?)で博士課程に進学して、2年目の1976年には、鈴木成文先生に助手にしてもらった。かたちとしては公募で応募したんだけどね。でも、それまでいわゆる「論文」なんて一本も書いてなかった。助手になったんだから、建築学会でなにか発表しなきゃまずいぞ、くらいの意識。それで、助手になった当時の学部4年生には土居義岳、村松伸、宇野求、横山俊祐などがいたので、彼らと一緒に、建売住宅のファサード分析や公団住宅の増改築調査をやった。「51C型」を設計した建築計画研究室の助手になったから、北海道から沖縄まで同じ2DKを建てた「標準設計」の問題を考えようと思った。当時、建売住宅がバンバン建ったし、公共住宅では違反増築が大きな問題になっていたからね。
それでも、東大助手時代は学会大会発表用の梗概を書いたくらいで、いわゆる査読論文は書いていない。1978年には東洋大学に移るんだけど、助教授になるときに『週刊ポスト』に書いた記事を教授リストに入れたら、教授会で問題になったらしい。博士論文(「インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究 ハウジング・システムに関する方法論的考察」1987年)をまとめたのは助教授になった後で、鈴木先生から定年になるので出しなさいと声をかけていただいたことが大きい。「黄表紙」は、1991年に京都大学に移るまでは1本も書かなかったね。論文が一気に多くなるのは、京大に異動してから。
──それはどのような理由で?
布野:単純な話で、京大では研究業績が求められたから。博士論文は書いていたけど、京大では研究業績を積み上げることに対するプレッシャーが相当あった。だから、研究室の弟子たちにも「論文は書いておきなさい」と指導し続けた。それと並行して、建築メィアで文章を書かせたりもしたけど。結果的に、布野研究室出身で教授になった人間はいっぱい出た。それは全部指導教員のおかげなんだよ(笑)。
そのときに言っていたのが、「論文は左手で書け、命を懸けて書く必要はない」。利き手(右手)では設計をしたり、まちづくりにかかわったり、より広い読者向けの文章を書くために残しておけ、だから論文は左手で書けと。本当の論文というのは一生に一本かけるかどうかでしょう。しかしそうは言っても、学生はなかなか査読論文を書き切れないわけ。修士論文をまとめる段階で終わっちゃう。それでは勿体ないから、僕が内容をさらに発展させて、連名で査読論文にするようにした。だから論文数が多いわけ。建築構造の和田章先生が建築学会会長になった時、僕は一緒に副会長になったんだけど、理事を決めるときに、和田さんが査読論文の数をバーっと出した。建築計画分野では、僕が論文数が一番多かった。いまでも博士課程の学生を指導しているから書くけどね。今年(2021年)亡くなった内田祥哉先生に言われて、日本学士院の紀要に論文(ShujiFuno: Ancient Chinese Capital ModelsーMeasurement System in UrbanPlanningー, Proceedings of the Japan Academy Series B Physical andBiological Sciences November 2017 Vol.93 №9, 721ー745.)書いたんだけど、これは和田先生より早かったんだよ。
メディエイター──建築と社会をつなぐ
──「アカデミズム」と「ジャーナリズム」を分裂させず、左手と右手でアウトプットを使い分ける、という布野さんのスタンスがよく分かりました。しかし、それでは、この左右両手を統合する布野さんのアイデンティティは一体どのあたりにあるのでしょうか。
布野:エディターとかメディエイター、という感じかな。建築と社会をつなぐ、その中間にいようと、考えたことはあります。前川國男が「今は、建てない建築家こそが最も優れた建築家である」と言ってたんですよ、当時。建築を建てると、日照権の問題が起こったりする。要するに建築することは自然に対する暴力なわけです。長谷川堯さんの『神殿か獄舎か』(1972年)はそんなタイミングで出た著作で、僕らの世代は大いに刺激されました。あと、実際のところ、僕はそんなに設計の手が動くタイプではなかった。だから、先輩の建築家たちには「そばにいて口は出すぞ」と言ったことがある(笑)。でも、村野・森事務所に行った「雛芥子」の千葉政継、ツバメアーキテクツの千葉元生くんのお父さんと一緒に5軒ぐらい住宅を設計したし、宮内康さんの山谷労働者福祉会館のセルフビルドには東洋大学の布野研究室全体が参加したよ。京大の布野研究室では鳥取の智頭町の町営住宅とかお寺の庫裏、それにスラバヤ・エコハウスを設計した。
設計にはものすごいエネルギーがかかる。それに比べれば論文のほうがずっと簡単、というと怒られるかもしれないけど、実際そうでしょう。だから、それは「左手」でやり、メディエイターとしての仕事を「右手」でやろうと決めたようなところがある。
──それで建築メディアのなかでの活動を始められたと。
布野:『建築文化』の「近代の呪縛に放て」シリーズ(1975〜1976年)に呼ばれたのが、具体的には最初の建築メディアでの仕事だと思う。正確には、その以前に三宅理一や杉本俊多らと「雛芥子」というグループで批評活動をしていた(1971年〜)。安田講堂前での「黒テント」の芝居を手伝った縁で麿赤兒と知り合って、大駱駝艦の旗揚げ公演前に東大の製図室で芝居をしてもらったり、ドイツ表現派の映画会を、ドイツインスティチュートからフィルムを借りてきて、原広司さん呼んで上映会をしたり。そういう活動をしていたら、真壁智治さん、大竹誠さんの遺留品研究所の面々、コンペイトウの松山巖さん、井出さんなどから、雑誌『TAU』(編集長石川喬司、坂手健剛、商店建築社)への執筆の声がかかり、『同時代演劇』や『芸術俱楽部』に書く機会があり、そのうちに建築専門誌からも呼ばれるようになった、というのが経緯。
『建築文化』1975年4月号(「近代の呪縛に放て」シリーズ第3回掲載号)
そういえば東洋大学に在籍していたとき、『建築文化』の編集長をやってくれないかという依頼があったな。「冗談だろ」って思ったけど(笑)。相手はいたって真面目で本気だったらしい。引き受けてたらどうなっていただろうね。
──布野編集体制による『建築文化』の誌面を想像するのは興味深いです(笑)。ともあれ、1980年代の布野さんは、明確に「ジャーナリズムの人」だったんですね。アカデミーのなかでの研究者としてバリバリ論文を書くのは、その後。明確に順番がある。
布野:そう。当時よく議論していたのは、「建築社会学」か「社会建築学」か、ということ。建築を社会学的に考えることもできる一方で、「社会を建築する」という、社会建築学という立場もあるはずだと。建築は空間を扱うわけだから、その空間をどう配分するのかということを考えれば、それはもう社会をどうつくるかという、そのものだよね。大きな言い方をすれば。建築計画学をやっていると、この問題はとくにリアリティがある。標準的な2DKの住戸をただ積んでいけばいいのか、そうではないでしょう。
こういう問いは、本来は建築の問題でもあり、社会そのものの問題でもある。建築という「モノ」だけに視座を置いていると、それが見えなくなってくる。とはいえ、「モノ」を作ることができるのは建築という領域の最大の武器だからね。そのときに、作られる空間の社会的な意味を明らかにしたい、それによって建築することを応援したい、という考えがある。
『群居』へ
──布野さんの特異性は、単に建築メディアに評論を寄稿することに留まらず、メディアそのものを立ち上げてきたことです。実際、じつに多くの建築メディアの立ち上げに関わっています。宮内康氏と組織された同時代建築研究会の『同時代建築通信』(1983年〜)、大野勝彦・石山修武・渡辺豊和三氏と組織されたハウジング計画ユニオン(HPU)の『群居』(1982年〜)、あるいは磯崎新氏や原広司氏らとの連続シンポジウムなどを収録した『建築思潮』(1992年〜)。他方で、建築学会では『建築雑誌』の編集長を務められ(2002〜2003年)、ウェブ媒体として本誌『建築討論』も2014年に創刊させている。
『建築思潮03 アジア夢幻』
なかでも、編集長だった『群居』は、2000年までに計50号も刊行されており、突出した仕事だと思います。このあたりのことを聞きたいのですが。
布野:『建築雑誌』は全部で3期6年関わっている。学会内だけど、分野を超えた議論の場は貴重だった。『群居』はたまたま僕がいちばん若かったので編集長を任されたけど、仕掛け人は建築家の大野勝彦さん。そこに石山、渡辺、布野が集まった。
『群居』創刊号
『群居』では、片方には池辺陽さんや難波和彦さんのようにナンバリングされた住宅をつくる考えかたがあり、もう一方にはオープン部品を住宅に取り入れてシステム化する考えかたがあった。実は、建売住宅を最初に作品として発表したのは、渡辺豊和さんなんだよね。1978年頃の「テラス・ロマネスク桃山台」とか、「標準住宅001」とかね。渡辺さんも「住居のプロトタイプ」を考えていた。戦後まもなく住宅問題があって、最小限住居のいろいろな試みがあり、その後プレハブメーカーが台頭する。1960年代末〜1970年代になると、建築家に住宅設計を依頼できる層が形成されて、住宅メーカーのほうでも、現場小屋的なプレハブ住宅は売れないから商品化住宅へと切り替わる。そうした流れのなかで、本気でもういっぺん建築家が住宅の問題に取り組むべきだ、というのが『群居』の初心です。そういう思想を引っ張ったのは大野さんです。
──50号も続いた『群居』のサスティナビリティに注目しています。どのように制作、運営されていたのですか。
『群居』1982年〜2000年[写真提供=秋吉浩気]
布野:基本は会費制です。1冊1,500円が販売価格だったから、年間4冊の刊行予定で、計6,000円。それを会費として前払いで銀行口座に振り込んでもらっていた。会員は最大で2,000人までいった。平良敬一さんが「それはすごい」と評価してくれたな。この会費を制作費にできたから、そこから執筆者への原稿料も出せていた。微々たるものではありましたけどね。
最初は16ドットのプリンターで出力して、みんなで集まって切り貼りして刊行していましたよ。ちょうどワープロが出だした頃で、これを使えば新しいメディアができそうだと、嬉しかった。その前はガリ版だからね。当時は椎名誠とイラストレーター沢野ひとしの『本の雑誌』というのがあって、そこは学生を集めて、刷り上がったら書店に持参するわけ。それで我々も、大手取次を通さないで直に書店に持って行ったし、学生にも制作作業に関わってもらった。さまざまな建築活動、そして研究と教育は一緒です。
──2,000人という会員数は、建築の同人誌的なメディアではそう簡単に集められるボリュームではないように思いますが、どのような方々が読者・会員だったのでしょうか。
布野:あまり詳しく分析してないけど、メーカーや工務店の関係者は多かったと思う。編集のときには、4号単位で特集テーマを分けることを意識していた。つまり、住宅を購入したい一般の人向けの特集、メーカーや工務店など住宅生産組織向けの特集、建築家やデザインに興味のある建築学生向けの特集、行政や都市計画に携わる人向けの特集。だから少なくとも、建築専門誌とはちょっと違う読者がついていたとは思う。
あとは年間購読する会員のほかに、当然ながら地道に販売努力はしてましたよ(笑)。たとえば大野勝彦さんが講演をするときに、そこで手渡しで売る。対面で思いを伝える、というのはメディアの原則だと思う。広告入れて売れたら楽だけど、ちょっと違うんだな。
──自前のメディアを持つと、現実的な作業が求められますよね。コンテンツを考えるだけではなく、会費を管理したり、注文を受けたら梱包して発送したり、実際に汗をかかないといけない。要するに事務作業。『群居』ではそのあたりはどのようにされていたのですか。
布野:実を言うと、事務作業は企業コンサルをしていた野部公一さんのオプコード研究所がおもに請け負っていた。大野勝彦さんのネットワークだったと思う。ただ、発送作業なんかはその事務所に我々も集まって汗かいてましたよ。石山だって来て作業した(笑)。創刊号準備号が完成したときは「出来たー!」と言って、ものすごく喜んでいましたね。会員の管理実務もオプコードがしていました。
──オプコード研究所の野部さんのお名前は、『群居』の編集後記などに見られますね。単なる事務作業の請負ということを超えて、制作同人の一人、という関係性であるように見えます。
布野:そうです。一種の同志かな。オプコードは、たとえば瓦屋のアドバイザーなんかをしていて、その頃は「ゼミ屋」と我々は言っていた。人を集めていろいろ情報交換したり、研修したり。あるいは住宅メーカーに販売促進やユーザー獲得のための仕事をしてい
た。
「スポンサーありき」という問題
──ところで、『群居』が建築専門家内に留まらない読者・会員を想定したという先程のお話が興味深いです。『群居』の創刊は1983年(創刊準備号は1982年12月)。直前の1970年代は野武士に代表される実験的な住宅作品がメディアを賑わせていて、それに対して、日建設計の林昌二氏が建築ジャーナリズムの偏向であると、厳しく批判したりもしていました(「歪められた建築の時代」『新建築』1979年11月号)。要するに、現実の社会や都市の問題とデタッチした建築作品をもてはやすだけでいいのか、と。『群居』の読者想定は、オルタナティヴな建築メディアとして、そのあたりの問題意識が背景にあるように見えるのですが、いかがですか。
布野:正直言って、そのあたりを意識した記憶はない。さっきも言ったように、『群居』の主たるテーマは戦後まもなくから続く住宅問題だったから。住宅問題を扱う以上、建築業界に閉じた議論にはならないから、なんらかの時代的な繋がりはあるのかもしれない。
むしろ、『群居』を始める前のことで覚えているのは、さっき話したけど、編集者の宮内嘉久さんのこと。彼は1960年代末に建築ジャーナリズム研究所(1967〜1969年)をつくったもののすぐに解体することになり、その後は個人誌や同人誌を始めますよね。『廃墟から』(1970〜1979年)、『風声』(1976〜1987年)、『燎』(1987〜1995年)。じつはその間、もういちど組織的に勝負しようということで、『地平線』というメディアの創刊を構想していた(1980年)。
でも、嘉久さんはもういっぺん勝負しようと言うわけなんだけど、結局スポンサーありきなんですね。『風声』は岡澤で、『燎』は伊奈製陶(INAX)。それだとメディアとしてはぜんぜん自立できていないわけ。
──「ジャーナリズム無頼」と謳いながも、実態としてはスポンサーありきだった。
布野:うん。彼はエディターというより評論家だったと思うから、そういうスタンスはわからないでもない。スポンサーありきという問題は、嘉久さんに限らず、建築メディアの根本的な問題なんだよね。平良さんも『SD』や『都市住宅』を仕掛けたわけだけど、それも鹿島建設の出版事業部のなかでのことだからね。
ただ、僕はそのことに問題を感じていたから、ちゃんと実売によって出版を成立させるべきだと嘉久さんに主張したわけです。さらに言うと、嘉久さんは個人的な人間関係によって、掲載する建築家の選別なんかもしていた。そういう選別は、どこかの党の機関紙ならあり得るかもしれないけど、僕としてはジャーナリズムではありえない。それで対立した。結局『地平線』はうまくいかず、そういう経緯もあって、僕が潰したことになってる(笑)。この時のことは「自立メディア幻想の彼方へ」(『建築文化』1978年10月号)にも書いています。
そんなときに会費制の『群居』の話が持ち上がったから、「これはいい」と思ったのね。
──宮内さんや平良さんは、いわば戦後建築ジャーナリズムを代表する伝説的な編集者であるわけですが、会費制の『群居』にはそうした世代への批判的意識が投影されていたのは、とても興味深いです。
運動と議論の場を求めて
──『群居』のもうひとつの特徴は、情報を取りまとめるスタティックなメディアというよりも、HPUでの住居やまちづくりの実務的実践と密接に絡み合っている点。現実を変えようとする「運動」としての側面があった点です。
布野:たしかに『群居』はHPUという運動体の機関誌的な側面はあった。HPUは地域の工務店と連帯していこうという意識もあったし、大野勝彦さんが仕掛けていた国交省の住宅計画(HOPE計画)も並走していた。ただ、大野さんが早くに亡くなって、そういう国とのつなぎ役がいなくなってしまった。そういう人材がいま必要なんだろうと思う。
建築メディアの現状に引きつけて言うと、僕はいまでも運動体的な建築メディアの動きがあったほうがよいと思うし、見てみたいと思う。でも、なかなか出てこない。みんな忙しすぎるんだよね。あとは『群居』にとってのオプコードのような、一緒に並走してくれるパートナーが必要。
──最初はガリ版、『群居』ではワープロと、布野さんのこれまでのメディア活動でもツールは変遷してきたわけですが、情報媒体の性質については、どうお考えですか。近年、メディウムはとても多様化しています。インターネットではテクストとは別に映像や音声などが自由に使われ、それによって届く層も変わってきている。
布野:市川さんも五十嵐太郎さんと「シラス」で建築系の動画をやっていますよね。そういう流れに抵抗するわけではないけど、個人的には文章化するプロセスが大事、という感じがある。放送だと、どうしても時間がかかるじゃない。最近は、映画評論家も見るものが多すぎるから何倍速かでみるらしい。しかし、映画批評は文章として必要でしょう。建築批評も文章として定着しておかないと、参照するのに困るんじゃない?酒飲みながらだらだらしゃべるのは大好きで批評のポイントは大体そんなときに浮かぶんだけど、それを録画で全部見せられてもね?編集が必要だよね。しかし、映像だと引用ができない。それとTwitterの140字では掘り下げられない。このインタビューにしても、テープ起こして、双方で手を入れていく作業があって一つの記事になるわけで、このプロセスが大事だと思う。この時間感覚とか一覧性は文章独特のものなんじゃないかと思う。
紙媒体で定期的な間隔で議論を積み重ねる、というのが、僕の世代ではやはり基本的な考えかたかな。昨年、平良敬一さんが亡くなりましたね(2020年4月29日)。著作集の『平良敬一建築論集──機能主義を超えるもの』(2017年)の出版記念会でお会いしたときに、最後の紙媒体の建築雑誌をやれ!と発破をかけられたんですよ。紙媒体はお金もかかるから、まだ考え中なんだけど。ただ、年寄りだけでやってもダメだから、若い人間と一緒にやれるような枠組みがあるべきで、それをいま模索中です。
──布野さん自身いまなおプレイヤーとして動こうとしているわけですね。振り返ってみると、アカデミズムとジャーナリズムを自由に横断する布野さんの活動には、ある種の「コミュニティ」をつくろうとするモチベーションが通底しているように見えます。同人的な組織をつくってメディアを立ち上げたり、あるいはアカデミックな研究活動のほうでも学生を巻き込みながら論文成果を出したり、横断的な専門家と「アジア都市建築研究会」などを組織したり。
布野:そうかもね。やっぱり議論がないといけない、そうでないと建築家たちの仕事のチェックや刺激にならない。だからメディアは必要だし、建築批評は必要。そのあたりは素朴にそう思います。若い学生なんかに聞くと、情報はいっぱいある、という。だけど批評はない。ああだこうだと議論をしないと、何をつくっていくかは考えられないわけで、そういう場所が一定程度維持されるべきだと思う。ただ、本音を言えば、要するに居心地のいい議論の場がほしいんですよ(笑)。そういうところにいて、議論をしたい、という思いが先。それは研究のほうでも変わらない。
──人を集めて議論することが純粋に楽しい、というのがまず先立つ。
布野:そう。自分が一方的に発信するだけだったら、Twitterやブログでできるしね。それを仲間と共有するために場所が必要。それで、その成果を発信して、一過性で消すことなく残していく。そこでメディエイターの役割が求められる。『建築討論』の3代目編集長になった市川さんにも大いに期待しています。■
2021年11月20日、A-Forumにて
文=和田隆介+市川紘司+齊藤光/写真(ポートレート)=和田隆介
布野修司| Shuji Funo
建築計画、建築批評。滋賀県立大学名誉教授、日本大学客員教授/
1949年生まれ。著作に『戦後建築論ノート』『カンポンの世界:ジ
ャワの庶民住居史』『布野修司建築論集』(全3巻)『大元都市 中
国都城の理念と空間構造』など。