
中高層ハウジングの「かたち」と供給システム
布野修司
中高層ハウジング=積層集合住宅(地)の多様な形式
中高層ハウジングのめざすもの、その基本理念、指針、基本モデルのための5つの柱から、具体的にはどのような「かたち」が導かれるのか。
中高層ハウジングというと、日本では「マンション」「公団住宅」などの中高層集合住宅がイメージされる。しかし、ここでいう中高層ハウジングは、現在日本に見られる中高層住宅を前提にしているわけではない。むしろ、日本のこれまでの中高層住宅と異なる「かたち」を目指したい。また、その基本理念は別の「かたち」を要求しているはずである。
日本の集合住宅は必ずしも多様でもない。というより、画一的だと指摘されることが多い。住戸形式もnLDKという記号で表現されるほど定型化され、その定型化された住戸をただ並べ、積み重ねるだけの「かたち」が一般的である。そして、そうした集合住宅によって形成されるまちの景観もそう豊かではない。同じような集合住宅が建ち並ぶ日本の団地の景観は、日本のまちの象徴である。
中高層ハウジングの解答はひとつではない、立地により、建設・維持のしくみにより、またそこに暮らす人びとの生活により、さまざまな「かたち」をとる、中高層ハウジングは多様である、というのが第一の基本理念である。
中高層ハウジングといっても、必ずしも階(層)数が問題なのではない。2~3層が低層、エレベーターを用いない5層までが中層、エレベーターの必要なのが高層というのが一般的分類であるが、高齢者やハンディキャップトのために2~3階建ての戸建住宅にもリフトが使用されるとするとその区別は本質的ではない。接地性(地面への近さ)による区別も、庭園や立体街路を各層に取り込む形になると必ずしも本質的ではない。テーマとなるのは、積層する住居の集合の「かたち」であり、立体的に住む住み方である。
都市型住宅のかたち=共用空間の多様な形式
中高層ハウジングは都市型のハウジングである。一戸一戸が独立するかたちの戸建住宅とは違って、集まって住む「かたち」が問題となる。廊下階段、壁など躯体のみを共有する区分所有の形式が一般的であるが、「所有」から「利用」へ、住居に対する価値観が転換して行くとすれば、何を「共有」し「共用」するかが問題になる。中高層ハウジングの「かたち」、集まって住むかたちを決めるのは、ある意味では「共用空間」の「かたち」である。そして、その「かたち」は住戸の形式とも関わる。
・厨房、食堂、居間などの空間を含めてほとんど全てのサーヴィス機能を共有する形式(例えば、「ホテル型マンション」)。
・厨房、バス、トイレなど設備のいくつかを共用する形式(コレクティブ・ハウス、設備共用アパート)
・部屋を共用する形式(例えば、倉庫、ピアノ室、書斎・勉強部屋などを一定期間賃貸する)
・廊下・通路空間を共用居間として利用する形式。
すなわち、住機能をどのように配分するかによって多様な「かたち」がつくられる。さらに、集まって住むために必要な施設、店舗や集会所などのコミュニティ施設が有機的に組み込まれて多様な中高層ハウジングの「かたち」がつくり出されるのである。
中高層ハウジングの骨格=スケルトンの3つの型
中高層ハウジングが以上のように多様な「かたち」をとることを前提にした上で、具体的な「かたち」を考えよう。積み重なって住むことを可能にし、しかも多様な住戸形式、集合形式を可能にする手法が「スケルトン(躯体)分離」である。スケルトンとインフィル(内装)を分離することによって、居住者自ら住環境をつくりだす手掛かりを与えることができ、維持管理に関わる耐用年限の違いにも対応できる。
多様といっても、それを物理的に実現するシステムが問題となる。技術的には無限の方法があるわけではない。その基本は建設システム、中でもスケルトン(躯体)のシステムである。スケルトンは、原理的に以下のO、A、Bの三つに分けられる。
O 柱列型スケルトン
A 壁型スケルトン
B 地盤型スケルトン
もちろん、このO、A、Bのそれぞれにも構造技術的にヴァリエーションがある。しかし、めざすべき中高層ハウジングの「かたち」について大きな整理ができ、最初の出発点になる。O、A、Bは、それぞれ大きく集合形式を規定し、住戸形式にも制約を与える。例えば、A型は、O型、B型に比べて、住戸単位の「かたち」や大きさを規定する。また、「共用空間」のシステムなど集合のためのサブ・システムがさらに必要となる。
いずれにせよ、スケルトンの3つの型によって、中高層ハウジングの骨格を得ることが出来る。
中高層ハウジングの供給モデル=土地・建物の所有(権移転)のモデル
中高層ハウジングの「かたち」は、その立地によって異なる。従って、具体的な場所を設定しなければその「かたち」を議論することが出来ない。ここで具体的な敷地を設定する前提として、供給モデルを設定する必要がある。手掛かりは現実性である。また、中高層ハウジングの基本理念である。土地・建物の所有権の移転、供給主体に着目して供給システムを分析すると以下のような三つの供給(事業)モデルを設定できる。
供給O型:個人の土地所有者による供給モデル(賃貸マンション、定期借地権付きマンション)。
供給A型:供給後、居住者が土地・建物を共有するモデル(分譲マンション)。
供給B型:供給後、法人・公共団体が土地・建物を所有する供給モデル(公団賃貸住宅、社宅・会員制マンション)。
すなわち、供給後の土地・建物の所有形態によってわけるのである。ストック社会における住居形態を考える上で、ストックをどう維持管理するかが極めて重要なのである。
中高層ハウジングの立地と開発モデル
供給主体、そして供給後の土地・建物の所有関係のイメージを、ある程度以上のように区別した上で、中高層ハウジングの立地を考えてみると、その供給(開発)規模によって供給形態を区別することができる。
開発O型ー1(One
apartment)住棟規模:
開発A型ー団地(an Apartment
complex)規模:
開発B型ー街区(Block)レヴェル:
O型の開発が隣接すれば、複数棟の開発になり、あらかじめ計画されるとするとA型の開発になる。また、さらに複数棟の開発が連続すれば街区単位の開発につながり、B型につながる。そうした意味でO型は基本である。しかし、規模によって「共有空間」のとり方に差異がある。
中高層ハウジングの敷地を具体的に設定するには、当然、協調建替え、換地など都市計画的手法が必要である。また、敷地の形状に応じて、何段階かの開発プロセスが必要となる。まちづくりのプロセスとリンクすることにおいて、中高層ハウジングは都市型ハウジングとなりうるのである。
中高層ハウジングの三つの型 98O、98A、98B
スケルトンのOAB、供給モデルのoab、開発OABの区分において、原理的には3×3×3=27(OoO)(OoA)・・・・(BbB)のパターンが設定できる。しかし、現実に最も可能性が高い組み合わせが(OoO)(AaA)(BbB)の三つである。紛らわしが、OABという同じ記号を用いた理由である。特にスケルトンの型と開発(供給)規模には対応関係がある。スケルトンO型はどんな規模にも対応できるけれど、スケルトンA、B型はそれぞれ開発A、B型が最も適している。そこでスケルトンの型と供給規模の型を合わせてAOBの三つの型を考える。供給oabとの組み合わせが9パターン考えられるが(oB)(bA)の組み合わせは考えにくい。最も可能性高いケースが(Oo)(Aa)(Bb)である。そこで基本設計モデルのために単純化して三つの分類視点を会わせて、OABの三つの型を区別する。戦後日本の住宅のモデルとなった51cにならえば、98OABである。(Oa)(Ob)(Ao)(Ba)もその応用としてかんがえることができるだろう。
以上において、中高層ハウジングのおよその「かたち」(スケルトン、敷地規模)が設定できた。それでは、具体的な住戸、住棟、団地、街区のイメージはどのような「かたち」をとるのか。居住者によっては具体的な「かたち」こそ問題である。
しかし、ここではnLDKといった住戸モデル、階段室型といった住棟モデルは提出されない。すべて、立地、維持管理の仕組み、居住者の参加に仕方等によって「かたち」は変わりうる。中高層ハウジングが目指すのものが、居住者自らの居住環境形成であり、集まって住む多様な「かたち」であるが故に、後は個々の実例を積み重ねる必要がある。具体的な「かたち」が積み重ねられることによって、いくつかの型が生み出されるとすれば、中高層ハウジングという中性的な名称ではなく、また、「マンション」「アパート」「公団住宅」といったネーミングとは違う名前が定着することになるであろう。「つくば方式」「保谷Ⅰ、Ⅱ」といった地域名が冠されることになるかもしれない。
日本の「まち」に相応しい都市型住宅が成立するかどうか、はもちろん、日本における家族や社会のあり方がどうなるか、また、それを支える様々な制度がどうなっていくかが問題である。高齢化が進行し、高齢の単身者が増えて行くとすれば、厨房や居間を共用するかたちのコレクティブ・ハウスの形式やケア付き住宅は不可欠である。女性の社会進出も、住宅の形式を変える可能性がある。外国人など文化的な背景を異にする人が集まって住むとすれば、当然これまでと異なる形式が必要になる。nLDKモデルだけでは対応できないことは明らかであろう。
それに中高層ハウジングがひとつのまちであるとすると、住居以外の機能を持った空間が様々に挿入された新しい形式が必要になる。その「かたち」が日本の集合住宅を大きく変えることになろう。













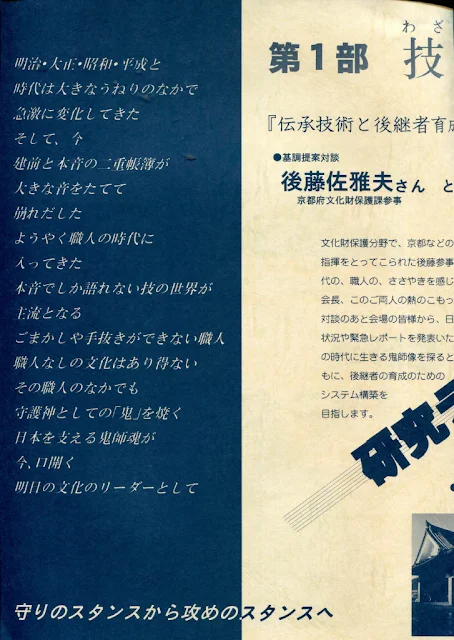

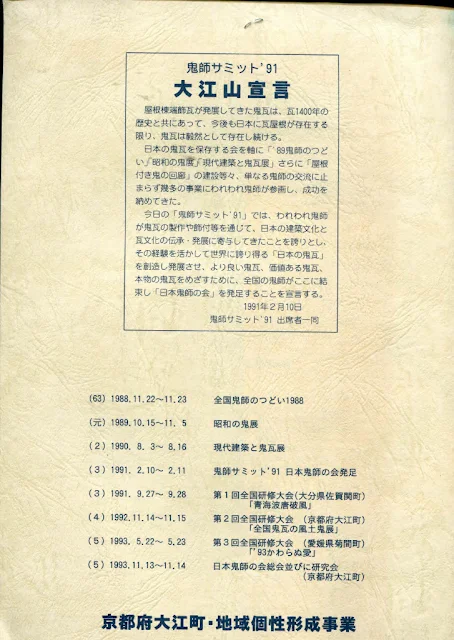



















%EF%BC%8C%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E7%9C%81%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%B1%80%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%AA%B2%EF%BC%8C1993%E5%B9%B4063.jpg)
%EF%BC%8C%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E7%9C%81%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%B1%80%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%AA%B2%EF%BC%8C1993%E5%B9%B4063.jpg)

























