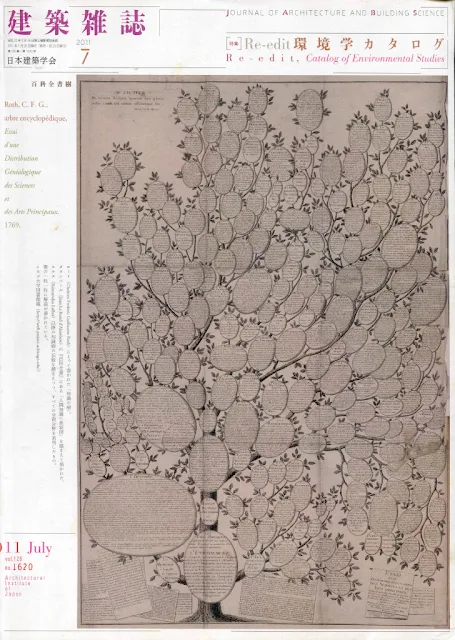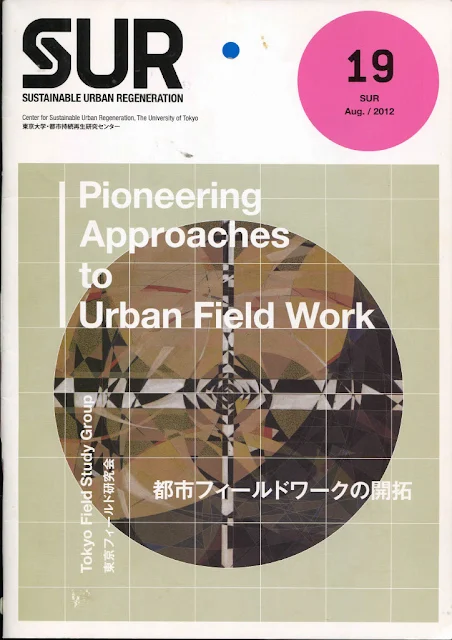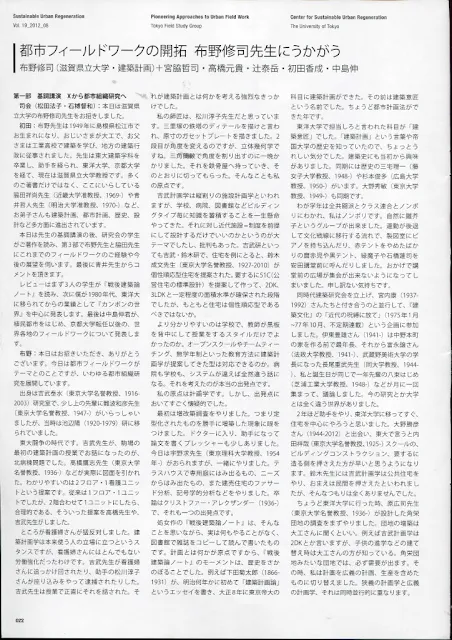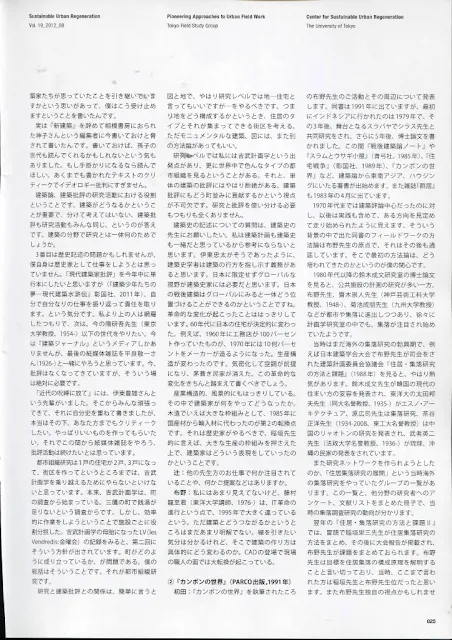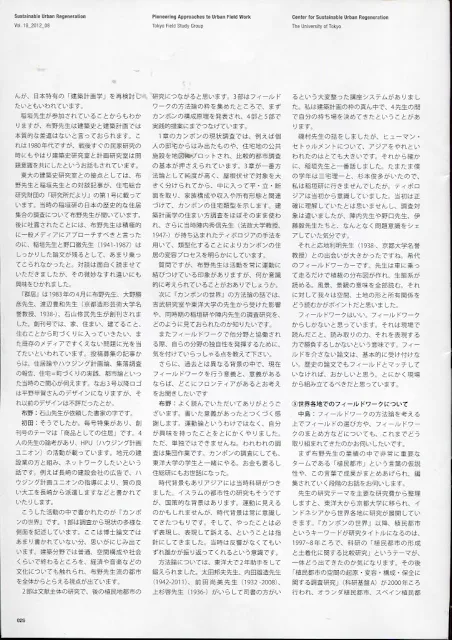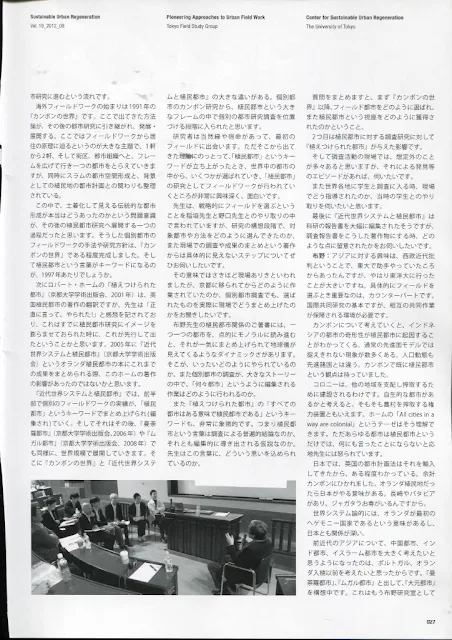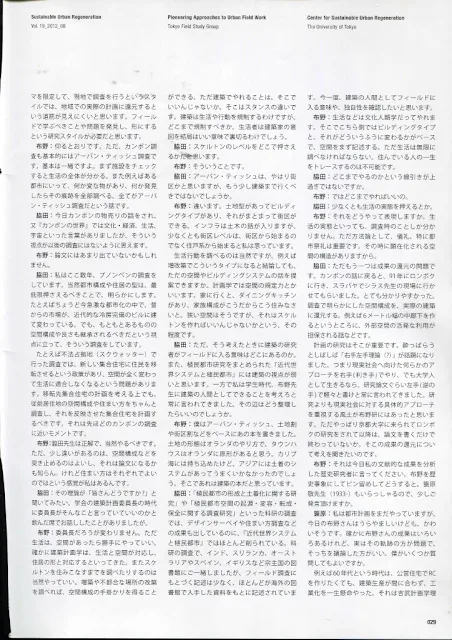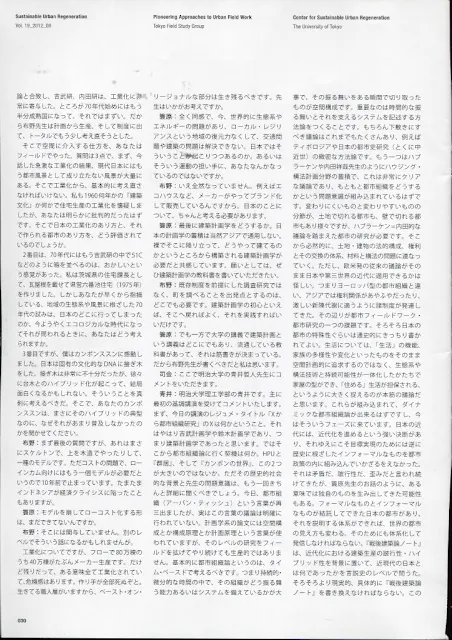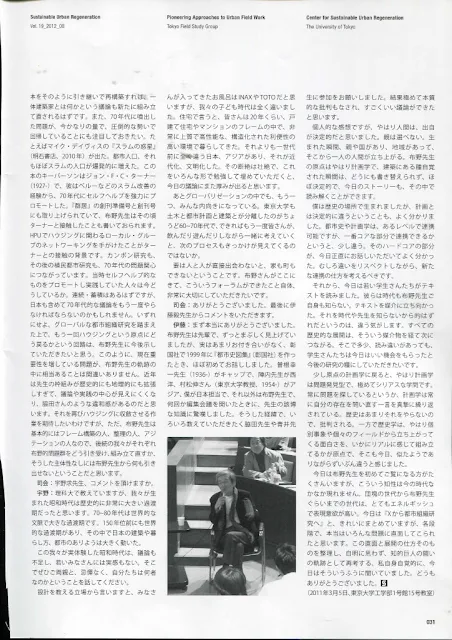東西の交流刻む土地の名はスレイブランドにシナモンガーデン
二〇〇四年一二月二十日 コロンボージャフナ
インド洋遥かに円い地平線くっきり浮かぶ麗しの島
降り立つと見渡す限りの草の原検問ばかりのまるで戦場
ココヤシの樹々の間に点々と民家が見える焼け落ちた屋根
にぎやかな通りの中にエアポケット迷彩服が抱える銃
在りし日の栄華を偲ぶ城塞が近代兵器に見るも無惨
荒れ果てて草むす古城に兵士の影戦い続ける人の定めか
美しき海岸線を遠ざける鉄条網の棘や悲しき
ジャフナ城地雷注意の立て札に古の思い後ずさりする
整然と区画割られた旧市街無数の弾痕廃屋の壁
二〇〇四年一二月二一日 マンナール
一本のビール取り持つ縁かな軍事施設も平気で入る
君知るや自ずと滲む我が臭い見知らぬ人が酒場へ誘う
まれびとを鋭く捉える悲しい眼一期一会を飲んで語らん
二〇〇四年一二月二二日 アヌラーダプラ
耳慣れぬ鳥の囀り木霊する植民住居の庭の深さよ
傘竿を空に突き刺す大覆鉢仏の教え今も変わらず
樹々の間に岩の連なり息を飲むここに棲みしか穴を穿ちて
時を超え生きながらえるボーディー・ツリー祈りを捧ぐ信者は絶えず
森の中ひっそり眠る精舎址深い思索に思いを馳せる
久々に蚊に襲われて思い出す熱く楽しい調査三昧
二〇〇四年一二月二三日 アヌラーダプラーコロンボ
スリランカ 二〇〇四年一二月一八日―二九日
マヒンドラティッサと問答山の上見下ろす先に大覆鉢
シーギリア天上の館何故につぶやきながら階段登る
ダンブッラ何故おわす仏たち窮屈すぎはしませんか
シーギリア比丘尼の姿はトップレス誰に見せんとこの崖の上
天上の館が仮にありとせばああそはここかああシーギリア
ナーランダヒンドゥー仏教ナーランダ二つの神々親戚同士
キャンディーの王につかまり二十年数奇の体験歴史に残る
二〇〇四年一二月二四日 コロンボーゴール
由緒あるコロニアルホテルで式挙げる新郎新婦の晴れがましき顔
道問えば笑って答える子どもたちトライリンガルアンビリーバブル
たそがれに紳士淑女が群れ集うゴールフェイスに夕日が沈む
シンプルに自然にデザイン力まずに心豊かなジェフリーバウア
列柱と椰子の林のその向こう見通す海はああインド洋
荒波がゴールロードにふりそそぐ船乗り運ぶ南西モンスーン
二〇〇四年一二月二五日 ゴール
ゴール・フォート二本のマストが海に浮くライトハウスにクロックタワー
着飾った西洋人が群れ集うクリスマス・イブのニュー・オリエンタル
あれはゴムブトゥル・ナッツにビンロウ樹お茶の畑にココナツ林
二〇〇四年一二月二六日 ゴール 大津波
高波が襲ったという人の声あるわけないよこの晴天に
道端に座り込んでる母子の眼宙を彷徨い震えるのみ
一瞬に召された命数知れずああ大津波神のみが知る
気がつけばクリケット場に舟浮かぶフェンス破ってバスもろともに
シュルシュルと獲物を狙う蛇のよう運河を登る津波の早さよ
気がつくと昨日撮った橋がない津波に飲まれ跡形も無し
海岸線全てズタズタ引き裂かれ大型バスが山道塞ぐ
救急車サイレン鳴らし向かい来る命を思って皆道を空ける
二〇〇四年一二月二七日 コロンボ 大津波
転がった列車の中から幼児が生還名前名乗るも住所を知らず
二〇〇四年一二月二七日 コロンボ空港
怪我人でごった返しの飛行場痛々しげにその時を語る
パスポート荷物もろとも流されて出国できない空港ロビー
傷ついて緊急帰国安堵の顔全員揃ってチケット獲れて