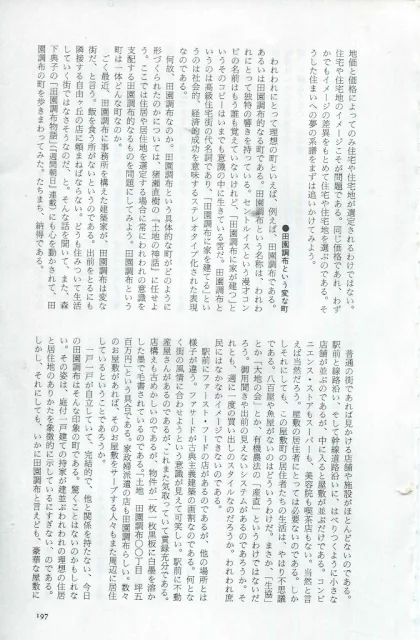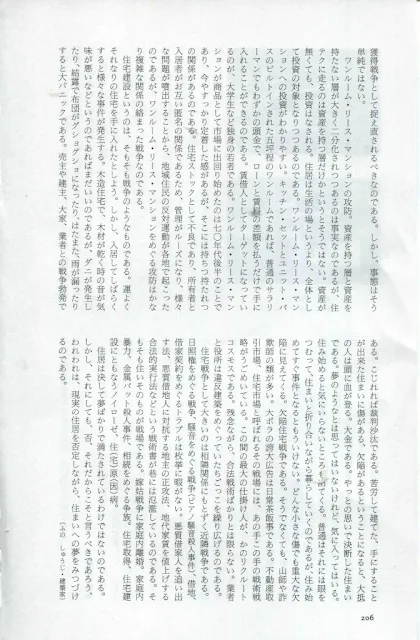投機的所有を考える手掛かり,丹羽邦男『土地問題の起源』,共同通信,198909,
このブログを検索
2025年5月10日土曜日
2024年11月9日土曜日
2024年10月17日木曜日
都市に寄生せよ 設計演習Ⅱ、東洋大学、住宅戦争,彰国社,1989年12月10日
住宅戦争,彰国社,1989年12月10日
都市に寄生せよ
「ある日あなたは突然家族と家を失った。
身よりも何もない。あなたは誰にも頼らずたった独りで生きていくことを決意する。いわゆるフーテンである。家を建てたり借りたりする気は最早無く、またその余裕もない。都市そのものに住もうと考える。しかし、そのためにも生活上最低限の装置は必要である。時には地下鉄の入口で、あるいは橋の下で、またあるいは路上で寝なければならない。
都市に寄生して生きる。」
課題はこれだけである。ヴァリエーションとして、以下のような条件をつける場合もあっていい。
「以下の条件を最低限満足する装置をデザインせよ。」
1.寝られること
2 食事ができること
3 人を招待できること
要求図面
①装置の平面図
②装置の立面図
③使用状況のスケッチまたはアクソメ、その他必要と思われる図面
すべての材料を明確に、着色の上提出すること。
要するに、住宅の設計課題である。住宅の設計は、建築家の基本であるという。
しかし、住宅の設計といっても、すぐさまできるわけではない。まずは、コピーから入るのが順当であろう。近代建築史のなかで傑作とされる住宅をあるいは評価の高い現代住宅を数多くコピーする。できたら模型をつくってみる。
いきなり、「理想の住宅」を設計せよ、といっても、うまくいくわけはない。まず、住宅は極めて身近であり、その具体的なイメージから離れられないということがある。「理想の住宅」といっても、どこかしら、今住んでいる、また育ってきた住宅の痕跡が表現されるものである。困るのは、固定した住宅イメージから全く逃れられない場合である。まずは固定観念をぬぐい去って、頭を柔らかくする必要がある。
いずれにしても体験しない空間を具体化するのは難しい。だから、とにかく、実際に様々な空間を体験すること、古今東西のすぐれた建築を見て歩くのが建築家となる第一歩であり、基本である。
住宅といっても実に様々である。世界中を見渡して見て欲しい。地域によって、民族によって、様々な形態がある。
こうしたヴァナキュラーな住居に、基本的な架構原理など多くを学ぶことができる。また、その多様性によって固定観念は揺らいでくるはずである。
しかし、結局自分にとっての「理想の住宅」である。自分がよければいいのである。
また、そもそも住宅の設計が複雑であるはそのものが
2024年9月12日木曜日
2024年8月9日金曜日
ラディカリズムの行方,見えなくなった構図,建築文化,彰国社,198910
ラディカリズムの行方・・・見えなくなった構図
磯崎 ラディカリズムのレヴェルにおいては、彼はもはや、ぼくが七〇年代の初めにつつましくやったものをはるかに超えているし、どこまで行くか、というのにかけている人たちだと思うんですね。それは、連中ももう腰を据えているはずだと思うから、やはり七〇年代は頑張ってもらわないといけないのだ。
原 彼らのやっている手法とか全体的な文脈を見てみると、微妙な差異があるんだね。
布野 個々にですね。
原 そう。……あと五年もすると距離がだんだん出てくると思うんです。それで、ある立体的な構造というのが出てくればすごくおもしろい。だれが正統なのか、アウトの中の正統なのか、ということもわからなくなってしまって、みんなそれぞれに存在理由をもつようなかたちで、建築家が分布する……、というような像が初めて出てくるのじゃないか、彼らが頑張れば。……
……七〇年代では磯崎さんがある意味でヘゲモニーをもっていたと思う。この次には、センターみたいなものがなくなるような状態が出てきてほしいと思うんです。……低いレヴェルで拡散しているのはやさしいけれども。……
………
磯崎 布野さんはちょっと下のジェネレーションですね。だから、その下のジェネレーションから彼らがどう見えているか聞きたいところです。
布野 世代が近いから、ぼくの場合はシンパシーはもつわけですよ、当然。だけど、全面的に乗れるかというと、ちょっと違う面があるんですね。……もうちょっと下になると、彼らを見ていて、つぶされるか、ビチッと立体的な場を広げてくれるかを見て表現し出すのじゃないかという……(笑)。わりとそういう感じなわけですよね。
鼎談「建築・そのプログレマティーク」 磯崎新、原広司、布野修司*[i]
ニュー・アンダー・フォーティー
編集長「突然なんですけど、最近の若い人たちをどう思ってらっしゃいますか? 」………「建築を勉強する若い建築少年が、少なくなったという話ですか。それなら『室内』*[ii]にちょっと書いたんですけどね」
編集長「いや、ほんとに、本誌(『建築文化』)連載の『戦後、建築家の足跡』に登場する大先生ですら知らない、という若い人が多いんですよね。でも、その話じゃなくて、布野さんたちの世代の下、アンダー・フォーティーの建築家たちなんですけど、どうなんでしょう。いろいろ出てきたんですが」………「どんな建築家がいて、どんなもんつくってるんだか、よく知らないんだけど。雑誌を見てると随分器用な人たちが多いね。上の世代が、下手に見える。でも、そんなに印象に残る人が思い浮かばないんだけど、面白い人がいるんですか」
編集長「竹山聖とか、小林克弘とか、宇野求とか、團紀彦とか、高崎正治とか、やたら威勢がいいんですよ。全共闘世代の、布野さんたちの世代は、三宅理一さんにしても、八東はじめさんにしても、杉本俊多さんにしても、藤森照信さんにしても、陣内秀信さんにしても、松山巌さんにしても、みんな評論家とか、歴史家になっちゃったでしょう。だから、建築家がいない。下の世代は、楽でいい、もう俺たちの時代だって、言ってるんですよ………「竹山、小林、宇野なんてのは、よく知ってるけど、そんなこと言ってんですか。團くんも、昔、エスキスみたことあるし、高崎くんには、智頭のコンペで縁があったし、その後の活躍を期待してるんですけどね。しかし、全共闘世代に建築家がいないなんていったら、怒られるんじゃないの。なんせ、数は沢山いるんだから。でも、卒業時に、オイルショックにかかって、なかなか、自立する条件がなかったということはあるかもね。それに、当時、前川國男大先生が「いま最もラディカルな建築家は、つくらない建築家である」なんていった時代だったから、建築を捨てた(あきらめた)という学生も多かったということもある。評論や歴史へ向かったというのも、それなりの理由があるんだけど、社会が建築についての評論を要請するから、目立つということであって、建築家がいないなんてことは、言えないんじゃないの。どういう意味で言ってるんだろう。今は、全く別の理由で建築についてのこだわりがなくなってるよね。「リクルート・コスモス」なんかに行くの多いもんね。銀行とか証券会社とか、ね。一方、いまは仕事が多すぎて、若い人たちが、どんどん独立する条件が出来てる。上の世代が、一〇年苦労したのに比べると、デビューしやすいかもね。しかし、忙しすぎて潰れなきゃいいけどね」
編集長「その辺のことでいいんですけど、ちょっとお願いできませんかね。建築家の世代論について。全共闘以後とか、ニュー・アンダー・フォーティーとかいうことで」………「そんな、無理だよ。だいたい、建築家の世代論というのは、五期会あたりで終わらせていいんじゃないの。世代論というのはうさんくさいからね。下手すると、世代論の背後には、エリート意識がのぞくでしょう。建築ジャーナリズムのイニシアティブをめぐる。一般的にも、権力闘争のにおいがする。それに、実際問題なのは、実年齢じゃなくて、精神年齢なんだよね。だいたい、先行世代だって、磯崎、原から、山本理顕、高松伸まで、世代的には幅があるでしょう。渡辺豊和さんのように、年のわりに信じられないぐらい若いのもいるしね。世代というより、状況に対するスタンスの問題じゃないの。それにね.世代が問題になるときには、世代を規定して枠にはめてやろう、そして、大抵は批判してやろう、という意思や主張が明快にあるもんでしょう。上からでも、下からでも。若い世代の誰だったか、われわれの戦略目標とはなにか、とかなんとか書いていたような気がするんだけど、戦略目標を問うようじゃ駄目なんじゃないの。すでに共有されていて、具体的に先行する世代にぶつけるというかたちじゃなくては。彼らには、明快な主張と理論の展開の用意があるのかしら。どうも、建築はうまいんだけど、内に向かって、自分の世界に、閉じこもってるって感じがあるんだけど。それに、何か、みんなヴァリエーションに見えちゃう……」
編集長「いや、その辺りでけっこうなんですけど」………「いや、そんな無責任な。これ以上言うことないんだけどなあ」
個室に封じ込められた人類?
この夏、多摩ニュータウンで開かれた「ニュータウン再考・・浮遊する快適空間」と題するシンポジウム*[iii]に参加する機会があった。パネラーは、ほかに三浦展(パルコ出版『アクロス』編集部)、山崎哲(劇作家、犯罪評論)、吉田真由美(映画評論)の諸氏である。テーマは、ニュータウン再考。サブタイトルには「高度成長・団塊の世代そして新しい街づくり」とある。随分と拡散的である。結果として議論の中心となったのは、団地という家族の空間であった。連続幼女誘拐殺害事件が、世間の耳目を集めている真っ最中であり、その事件の舞台が近接していることもあって当然のように大きな話題になったのであった。
議論に参加しながら思ったのは、日本社会の閉鎖化の深度のようなことである。地域共同体からの家族の自立へ、家父長制的な家族から核家族へ、そして個の自立へ、と戦後の過程において日本社会が開かれてきたように見える一方で、実際に進行してきたのは、個をひとつの閉じた空間に押し込めていく過程ではなかったか。
器としての住まいを見ると、その推移は比較的わかりやすい。食べるスペースと寝るスペースの分離(食寝分離DK誕生), 公的なスペースと私的なスペースの分離(公私室分離、モダンリビングの誕生、プライバシーの確保)、個室の自立、といったことが次々に主張され、そして具体的なものとなっていったのである。家族の自立(核家族化、マイホーム主義)、個の自立というスローガンのもとに展開された建築家の論理は、住戸の広さを獲得していく以上の論理ではなかったのだけれど、結果として、日本中に蔓延したのはnLDKという住戸形式であった。nLDKの空間がほとんどつながりなく積層するのが、ニュータウンの空間である。
しかし、いまnLDKという住戸形式によって象徴される家族像(nLDK家族モデル)が揺らいでいる。バラバラの個の単なる集合へと変容しつつある。住居が、単に、個室の集合へと還元されつつある、と言えば、わかりやすいであろうか。個室に封じ込められた個をオルガナイズするのが、さまざまな情報メディアである。各個室には、それぞれに、電話、TV、AV機器など(個電製品)があふれかえる。世界のあらゆる情報に開かれ、しかし、物理的には閉じた個室が浮遊し始めている。
連続幼女誘拐殺害事件については、決してフィジカルな空間の問題ではない。金属バット殺人事件も、コンクリート詰め殺人事件も、すべて、建築家のせいにされたんじゃかなわない、と思わず口にしてはみた。しかし、考えてみれば、建築家も危ういのではないか。デザインの差異を競いながら、閉じた世界へとますます内向しながら、「浮遊する個室」をつくり続けているのが、結局は建築家の現在なのではないか。モダンリビングを解体すること、nLDKを解体すること、近代建築批判の課題は、若い建築家たちには、どのように引き受けられつつあるのであろうか、などと思ったのであった。
大いなる迷走:団塊の世代って何?
主催者の狙いの中心は、実は、多摩ニュータウンの居住者の一割余りを占める「団塊の世代」を問う、ということであった。しかし、ひとりの若者によるショッキングな事件のせいで、むしろクローズアップされたのは、若者論の方であった。『大いなる迷走・・団塊世代さまよいの歴史と現在』*[iv]をまとめた三浦展の提起も, いささか遠慮がちであった。他のパネラーが、すべて団塊の世代ということもあったが、何となく、高度成長=団塊世代=ニュータウン=幼女誘拐といった議論の構図が出来てしまいそうだったからである。
三浦展がひとつ話題にしたのは、団塊世代は全国各地で同じように生まれながら、移動が多く、現在、例えば、多摩ニュータウンのような大都市の周辺に住む割合が多いのは何故か、ということであった。それに対しては、そうでない人もいるでしょう、というのがひとつの答えであり、そう言うと、それ以上に議論のしようがない。それに、年齢によって、すなわち、年齢によって居住地の選定が限定されるということであれば、世代によらず、時代によらず、そうだったはずなのである。
『大いなる迷走』をのぞいてみよう。
「終戦直後の一九四七~四九に生まれた約八〇〇万人は、これまで実にさまざまな呼び名で呼ばれてきた。「ベビーブーム世代」、「フォーク世代」、「全共闘世代」、「ニューファミリー世代」、「団塊世代」、「ニューサーティ」……。戦後四四年の日本社会の変化と歩みをともにしてきた彼らは、おそらくは純粋に世代論の対象として語られた最初の世代であろう。消費のマーケットとして、新ライフスタイルのリーダーとして、あるいは社会の変革者として、常に分析され、期待され、恐れられてきた。彼らは終生、注目され論じられるべく運命づけられているかのようだ。団塊世代がついに四〇歳となった今、彼らが再び世代論の俎上にのせられようとしているのも無理はない。」
冒頭の一節である。何となく違和感の残る書出しである。「純粋に世代論の対象として語られた最初の世代」というのはどういうことか。世代論というのは、「戦中派」とか「昭和ひとけた」とかなんとか、もうすこし、一般的に語られ続けてきたのではないのか。純粋な世代論の対象とは何だろう。誰が対象にし、語ったのだろう。誰が、団塊の世代を、分析し、期待し、恐れてきたのであろう。誰が、終生、注目し、論ずるのであろう。誰が、再び世代論の俎上に載せ、誰が、そのことを無理ない、と思うのであろう。あるコンテクストが前提とされているようでいて、それが曖昧にぼかされた言い方をされるので、気味が悪いのである。
前提される視線とは何か。あらかじめはっきり言ってしまえば、それは、マーケティングの視線ということになろう。あるいは、資本が量をとらえる視線といってもいい。『大いなる迷走』のあとがきは「団塊世代を一つの理論的枠組みの中に押し込めること」は、非常に困難であり、「個人個人の現在置かれている状況は極めて多様であり、安易な単純化・図式化を許さない」というのであるが、結果としてそこで取られているのは、統計的手法のようなものである。「団塊世代を、過去においては政治的かつ風俗的存在として、現在においては経済的存在としてのみとらえる視点では、この世代の本質はみえてこない」と言いながら、一定のフレームに収めようとする。そこには、無意識であれ、ある意思が感じられるのである。でもまあ、世代論とはそういうものである。
団塊の世代とは、戦後日本の「ユダヤ人」である。集団就職の金の卵世代である。団塊世代は、共和国の夢を追い続けている。団塊世代女性はクロワッサン主婦である。団塊世代は、郊外で市民運動を展開し始めている。団塊世代の父はアウトドア志向である。等々、団塊の世代に対してさまざまなレッテルが張られるが、むしろ興味深いのは、下の世代との差異が強調される次のような指摘である。
「団塊世代より一〇歳若い昭和三〇年代生まれは、物心がついた時にはすでに高度経済成長が始まっていた。この世代は、物の豊かさやテレビの面白さや広告の魅力を否定することが生来的にできない。もちろん、物質的豊かさやコマーシャリズムの虚偽性も理解できるが、それを全否定すれば、彼らの生活基盤そのものを切り崩すことになることを彼らはよく知っている。……日本のどこに住んでいても、テレビが彼らの意識を近代的な未来社会へ向かわせた。まさにその点に、団塊世代と昭和三〇年代生まれの本質的な違いがある。彼らは、マスメディアと商品がつくりだす疑似環境・記号環境としての消費社会に、ごく自然に接することができる。彼らにとってそれはすでにひとつの自然だからである。」「一般に団塊世代は、感性の世代ではあるが、感性を論理化できる世代ではない。彼らの中では、感性と論理は常に矛盾・対立している。感性は、論理によって抑圧されるものであり、また、論理からの解放のためにあるのだ、というのが彼らの認識である。が、論理化されない非合理な感性はファナティックな政治運動の推進力にはなりうるが、経済活動(コマーシャリズム)に乗ることはできない。言い換えれば、経済の論理の支配する企業社会・官僚制の中では、感性は抑圧されるばかりである。しかし、一九八〇年代は、まさにこの感性の論理化・商品化を目指して、多くの企業がしのぎを削った時代であった。感性は、抑圧されるどころか、新製品のように次々と大量に生み出され、宣伝され、流通され、販売され、もてはやされ、消費され、消えていった。……団塊世代にはまだ、個人の感性を商品化することに対する抵抗が強いが、昭和三〇年代生まれにはそれがなかったのである。」
見えなくなった構図:リーディング・アーキテクトの消失
マスメディアとコマーシャリズムがつくり出す疑似環境・記号環境としての消費社会を自然のものとするか、違和感をもつか、あるいは、感性の論理化・商品化に対して抵抗感をもつかどうか、というのは、決して世代の問題ではないだろう。『大いなる迷走』は、YMOの細野晴臣や、糸井重里や川崎徹に代表される広告文化人、都市の中の廃墟をトレンドスポットに変えてしまった建築家・松井雅美、日産の開発に携わったコンセプター坂井直樹のように、感性時代の先端を走るトレンドリーダーとしての団塊世代も存在するけど、少数派だという。しかし、僕に言わせれば、むしろ、感性の商品化を戦略化する一線で活躍してきたのは、全共闘世代のような気がしないでもない。建築の分野でも、感性の論理化を盛んに主張し、若い建築家をリードするのは、三宅理一のような全共闘世代の評論家なのである。
しかし、感性を商品化することを戦術化できるかどうかは、建築家を区別する大きなポイントとなろう。問題なのは、マスディアやコマーシャリズムを所与のものとして前提し出発するかどうか、である。ア・ブリオリに、「建築」とか、「建築家」という理念を前提とするのではなく、消費社会の現実の中から、幾人もの「建築家」が生まれ始めているとすれば、大きな状況の変化なのである。果して、若いそうした建築家たちが陸続と生まれつつあるのであろうか。
冒頭の鼎談は、ちょうど一〇年前のものである。そこでは、ある見取り図が何となく、語られようとしている。そこで、「彼ら」ということで具体的にイメージされていたのは、伊東豊雄から、高松伸まで、いまでは四〇代の何人かの建築家たちである。当時、アンダー・フォーティー、その鼎談で、落胤の世代と呼ばれている連中である。「彼ら」は、その後、どのように状況と渡り合ってきたのか。ある意味では、予想どうり「立体的な場」を広げてきたのであろうか。
しかし、そうだとすれば、いま、アンダーフォーティーと呼ばれる世代は、どのような場を広げつつあり、一〇年後に、どのような場を広げると予想されるのか。いま、それを具体的に語りうるであろうか。いささか、こころもとない。建築家の役割が全く変わっていく、そういう予想があるのである。
「彼ら」は、八〇年代を通じて、エスタブリッシュされていく。言ってみれば、彼らのラディカリズムは、建築界において次第に認知されていった。建築界でもっとも権威があるとされる日本建築学会賞のような賞が「彼ら」に次々に与えられたことが、それを示している。「彼ら」が社会的に認知されていくのに、大きな力をもったのがマスメディアである。建築ジャーナリズムの枠を超えたメディアに「彼ら」は、戦線を拡大することにおいて、それぞれの存在基盤を獲得してきたのである。原広司が予言したように、センターみたいなものがなくなるような状態が、出現してきたように見える。
しかし、興味深いのは、「彼ら」の微妙な差異である。近代建築に対する根源的批判を出発点とする「彼ら」の方向性については、これまで折にふれて書いてきた*[v]のであるが、当初からその方向性を巡っては、微妙なというより大きな差異があった。それゆえ、建築ジャーナリズムの上のみならず、連夜のように激しい議論が闘わされていたのである。
しかし、現在、その方向性を巡る差異は、逆に見えなくなりつつあるような気がしないでもない。近代建築の方向性をめぐる差異が、デザインの差異に還元されて、併置されてしまうのである。とても、「立体的な構造」とはいえないのではないか、と思えるのである。まさに「低いレブェルで拡散している」状況が訪れつつあるのである。こうなると、すぐさま群雄割拠である。八東はじめが、疑似アヴァンギャルドとか言って、歯ぎしりするのであるが、差異の主張はそこでは等価である。デザインの差異、感性の商品化のロジックのみがそこで問われる。単にデザインのみではない。ファッションすらもそこでは問われる。歌って、踊れて、しゃべれる、そんなタレントが、そこでは要請されつつあるのである。
ラディカリズムの死:「大文字の『建築』と「建築批判」
思うに磯崎新が、あからさまに「転向」を口にしながら、「大文字の建築」などということを言い出さざるをえなかったのは、以上のような状況を特権的に差異化したかったからではないか、と思う。「大きな物語」の崩壊と不可能性のみが論じられねる中で、無数の「小さな物語」が蔓延する状況に対して、そう言ってみたい気分は、わからないでもないけれど、ついに最後の言葉を吐いたな、という感じである。
その磯崎に対して、『建築雑誌』で質問を投げかける機会があった*[vi](。その回答によると、建築家の仕事も、すべて、この「大文字の『建築雑誌』というメタ概念を把握しているかどうかで、評価できるという。「大文字の『建築』」というメタ概念こそが、建築的言説を成立させる論理と枠組みのすべてをしばりあげている制度である」というのだ。その制度としての「建築」の解体こそが問題ではなかったか、と問えば「それへの違反、免脱、破壊、解体、そして脱構築の作業がなされながら、おそらく、いま、明らかにされつつあるのは、『建築』とは、そのすべを成立させている論理を根底において支えている、名付けようのなかった何ものかを指すのだ」という。
そこでは、近代建築批判も建築批判も無化される。世代も、時代も、状況も、問題とはならない。あまりに超越論的な地平へと到達してしまったものである。
磯崎については、これまで幾度か論ずる機会があった*[vii]のであるが、その過剰な言説よりも、そのラディカリズムの行方にのみ興味があった。その行き着く先が、言説の上で明らかになったということであろう。
そうした、磯崎の「大文字の『建築』」を鈴木隆之が執ように問うている*[viii]。彼が繰り返し主張するのは、「建築」なんて、ないのだ。すべてが「建築」でしかない、という認識だけがありうる、ということだ。あるいは、すれちがった思い入れかもしれないけれど、その指摘の多くに共感を覚えながら読んだ。
制度としての建築をいかに解体するのか、「建築」から、いかに逃亡するか、という矛盾に満ちた問いを出発点にするとき、とりあえずの解答はそう言うしかない。少なくとも、僕の場合、磯崎の「建築の解体」とハンス・ホラインの「あらゆるものが建築である」というスローガンを同じものとして受け止めながら、原広司のいう「建築に何が可能か」を指針としてきたのである。「大文字の『建築』」というメタ概念は、一切の問いを停止させてしまう。
ところで、鈴木隆之の、こうした「建築批判」の視座は、彼に属する世代に固有なものなのだろうか。そうではあるまい。状況とのスタンスとして、常に要求されてきたものであろう。むしろ、重要なのは、「建築」なんてない、すべてが「建築」である、という状況が具体的に現れ始めていることだ。そして、それを認識することである。デザインの差異が次から次へと消費される、消費社会の神話と論理が支配する中で、「大文字の『建築』」というメタ概念を知っているかどうかが決定的なのだ、と言おうが言うまいが、どうでもいいことである。
「建築」なんてない、すべてが「建築」でしかない、という言説は、もちろん両義的である。マスメディアとコマーシャリズムがつくり出す疑似環境・記号環境としての消費社会そのものが、そうした言説を成立させるからである。「大文字の『建築』」などという概念とは無縁にこの状況を突破する筋道に、少なくとも、僕は関心があるのである。などと、言えば、やはり「団塊の世代」に特有なものいいということになろうか。
『大いなる迷走』は、次のように締めくくられている。
「戦後日本の社会と文化の中で、常に“アウトサイダー”的な役割を演じてきた彼ら(ユダヤ人! )が、「大いなる迷走」の果てに、ついに何ものかを見いだし、創造する日は来るのであろうか? 」
果たしてどうか?
2024年6月13日木曜日
2024年6月11日火曜日
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
鳩おどし,都市(東京)のディテール(9),春秋,春秋社,198907
生産緑地,都市(東京)のディテール(10),春秋,春秋社,198909
2024年6月10日月曜日
ゴミ箱,都市(東京)のディテール(7),春秋,春秋社,198905
ゴミ箱,都市(東京)のディテール(7),春秋,春秋社,198905
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
鳩おどし,都市(東京)のディテール(9),春秋,春秋社,198907
生産緑地,都市(東京)のディテール(10),春秋,春秋社,198909,
2024年6月9日日曜日
井戸,都市(東京)のディテール(6),春秋,春秋社,198904
都市(東京)のディテール 『春秋』 春秋社 1988年10月~1989年9月
井戸,都市(東京)のディテール(6),春秋,春秋社,198904
ゴミ箱,都市(東京)のディテール(7),春秋,春秋社,198905
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
鳩おどし,都市(東京)のディテール(9),春秋,春秋社,198907
生産緑地,都市(東京)のディテール(10),春秋,春秋社,198909,
2024年6月8日土曜日
納骨堂,都市(東京)のディテール(5),春秋,春秋社,198903
都市(東京)のディテール 『春秋』 春秋社 1988年10月~1989年9月
納骨堂,都市(東京)のディテール(5),春秋,春秋社,198903
井戸,都市(東京)のディテール(6),春秋,春秋社,198904
ゴミ箱,都市(東京)のディテール(7),春秋,春秋社,198905
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
鳩おどし,都市(東京)のディテール(9),春秋,春秋社,198907
生産緑地,都市(東京)のディテール(10),春秋,春秋社,198909,
2024年6月7日金曜日
山,都市(東京)のディテール(4),春秋,春秋社,198902
都市(東京)のディテール 『春秋』 春秋社 1988年10月~1989年9月
山,都市(東京)のディテール(4),春秋,春秋社,198902
納骨堂,都市(東京)のディテール(5),春秋,春秋社,198903
井戸,都市(東京)のディテール(6),春秋,春秋社,198904
ゴミ箱,都市(東京)のディテール(7),春秋,春秋社,198905
小屋,都市(東京)のディテール(8),春秋,春秋社,198906
鳩おどし,都市(東京)のディテール(9),春秋,春秋社,198907
生産緑地,都市(東京)のディテール(10),春秋,春秋社,198909,
2024年6月2日日曜日
2024年3月24日日曜日
2024年3月8日金曜日
2023年12月31日日曜日
建築における一九三〇年代,KB Freeway,『建築文化』,198001
建築における一九三〇年代
七〇年代の幕が閉じ、八〇年代が幕を開ける。一〇年を一区切りとして、時の流れをとらえていくことは、もとより便宜的でしかないとは思いつつも、過ぎ去った一〇年を振り返り、来るべき一〇年を展望する問いに,多くはとらわれる。いくつかの雑誌が七〇年代の総括を試みる特集を組み、また、八〇年代を展望する特集を組んでいる。目に触れる多くの文章が一つの区切りを意識している。一〇年は一昔である。
しかし、明確な形に集約される問いが、そこにあるわけではない。便宜的な区切り以上の何ものかがそこにあるわけではない。問えば問うほどむしろ、八〇年という時間的な閾が単に経過点にすぎないという意識のみが浮かび上がってくるようにみえるはずである。「七〇年代から八〇年代へという時間的な推移が七〇年代の対自化ということを要請しているとしても、七〇年代がいかなる時代であったと問うことは、基本的には空しい営みに終わるほかない」、「七〇年代においては実際に何ごとか起こってはいる、と言いうるだろう。それが何であるかということは明確に指摘できはしないし、あるいはこれからやって来るであろう八〇年代という時代においてそれが明瞭な像を結ぶということでもないかもしれない」「だからここではもはや七〇年代から八〇年代へといった方向性を問うことはやめて、そのような問いを曖昧さの中に差し向けてやることしかできないのである」といった言い方こそが、そこでは支配的なのである。
問題は、そうした問い方自体にすでに存在していると言ってもよい。しかし、そうした問い方によって明らかにされる地平は、すぐれて状況的であると言える。おそらく、七〇年代的パラダイムと呼びうるものによって、その時代を振り返へることは可能であろう。解体の時代、空白の時代、不在の時代、引用の時代、周縁の時代。知の戯れの風景において、頻繁に発せられた言葉たちによって、七〇年代という時代を特徴づけることができる。しかし、われわれはその時代の終焉を確認することができない。やがて八〇年代のパラダイムと呼ばれるものが明確な差異をもって現れてくるかどうか、その予感はないのである。六〇年、七〇年という時点と比べてみれば、それは一層明らかなように思える。一九六〇年代という時代区分が単なる便宜的な区切り以上の意味をもっているのは、六〇年安保、七〇年安保といった政治的課題のメルクマールがわれわれの時代意識に大きな影を落としているからであり、しかも、それが戦後復興・・戦後の終焉・離陸・・高度成長・・破錠という戦後過程に対応しているように思えるからである。そして、それぞれの時点ですでに、ある一つの先行する時代の終焉が意識され、少なくとも具体的な課題がそれなりに共有されていたように思われるからである。しかし、われわれは必ずしも、七〇年代を一つの区切られた時代として意識化しえない。八〇年代へ向けて具体的な課題が共有されているわけでもないのである。七〇年代は、その時代を特徴づける求心的な何ものかを生み出しえなかった。拡散的な経験のみがそこには存在している。七〇年代の総括の試みが、個別の作家や作品、出来事についての記述の羅列という形をとるのはそれ故にでもある。ある意味では、六〇年代末から七〇年代初頭にかけて確認された一つの時代の終焉を、確認し続けたのが七〇年代であったと言ってもよいのである。
「私たちは七〇年代の思想状況を二重の解体のコンテクストとして読むことができる。ひとつは幻想的な普遍性のエクリチュールの解体過程であり、もうひとつは、知的な普遍性のエクリチュールの解体過程である。そしてこの解体が多様な現実を私たちに見せると同時に、思想的な求心性の解体であることによって、人々は根拠と希望を求めてさまよったのである」と小阪修平は言う*[ii]。そのさまよいは今なお続いているし、ここしばらく続くであろう。七〇年代の経験に、確実な何かを見いだしえないが故に、そう言わざるをえないのである。
「観念的ラジカリズムの終焉」という、小阪が七〇年代に対して与える総括は、ある意味で七〇年代という時代をくっきり浮かび上がらせると言ってもよい。しかし、「私はこの小論で、観念的ラジカリズムをひとつの自然過程としてあつかってきた。したがって、私が七〇年代に読んだ、観念的ラジカリズムの終焉というコンテクストに、正の価値を与えるか、負の価値を与えるかは読者の自由である。」と、あえて注記するように、その終焉の確認において、八〇年代がくっきりと見えてくるわけではない。むしろ逆である。確かに、観念的ラジカリズムは、七〇年代において、市民社会の外部=周縁ーー第三世界、土着、辺境、日本的なるもの、差別、身体……ーーへ向かい、それを一つの希望としてとらえようとしてきた。ある意味では、その希望が拡散的な状況を生み出してきた。しかし、それぞれの希望が裏切られ続けてきたのが七〇年代なのではないか。自然過程としてとらえる限りにおいて、そうした意味で観念的ラジカリズムは終焉したのだ、と小阪修平は言うのである。こうした認識の地平から何を展望しうるのか。少なくとも、その終焉を負の価値ととらえるものにとってそれは厳しい。安易に希望を語りえない状況の困難性が、根底的なレベルで意識されるはずである。確かに、周縁的なるものへの希望は知の表層で語られ続けたのであるが、周縁的なるものへの具体的な回路を見いだしえなかったと言いうるからである。
建築における七〇年代は、近代建築の解体と建築そのものの解体(商品化)という二重の解体のコンテクストにおいて、多様な表現を生み出してきた過程であった。ポスト・モダニズムとかポスト・メタボリズムとか呼ばれる状況がそれである。しかし、それはまた、その時代を特徴づける求心的な何ものをも生み出しはしなかった。拡散的な七〇年代の経験のみがそこに同じように浮遊したのである。
そうした状況を最も的確にとらえ、体現してきたのが磯崎新である。彼は、中心性の解体を逸早く予感し、主題の不在、空洞の時代がかなりの深さと長さで進行していくことを予想しえていた。それ故、彼は、そうした状況に対して有効な戦略を展開しえたのであり、広範な影響を及ぼしえたと言ってよいの。「建築の解体」、「主題の不在」、「引用」、「手法」、「修辞」、「記号論」………。彼の発した言葉、論の展開などすべてそのまま建築の七〇年代におけるパラダイムを形成したのである。
しかし、彼は七〇年代を通して、「建築の解体」状況を、そしてそれによる拡散状況を突破する確実な方向を提示しえなかった。「空洞の中心への吸引を常に感じながら」「中心の空洞にむかい合うことを避けられなくなりつつある」ことを予感しながら、「建築の地層」をさぐり当てねばという意識に駆り立てられながら、次なるステップは必ずしも彼のうちで収斂していかないのである。ある意味では、きわどいバランスの上に位置してきた彼にとって、そうだとすれば状況は次第に困難となりつつあると言える。例えば、次第に大きくなりつつある概念建築に対する否定的な声は、状況が次第に困難となりつつあることを彼に意識させているはずなのである。
日本における建築のそうした状況は、とりわけ、若い世代の建築家たちの評価をめぐる議論において確認することができる。石山修武の「新傾向の一部について」*[iii]と林昌二*[iv]の「歪められた建築の時代ーー一九七〇年代を顧みて」*[v]をひき比べることによって、あるいは槙文彦の「平和な時代の野武士達」*[vi]と鈴木博之*[vii]の「貧乏くじは君が引く」*[viii]を読み比べることにおいて、建築の小状況における対立の構図の一端を手に入れることができる。
ある規模意識、使命感、秩序意識に照らせば、建築の七〇年代は「平和な時代」であり、「実りの少ない時代」であり「歪められた建築の時代」でしかない。そうした規範意識を強烈に提示するのが林昌二である。それは、観念的ラジカリズムの終焉を建築において、まさに正の価値として確認しようとするものと言ってよいであろう。
市民社会の外へ向かった暴力(反日武装戦線による三菱重工ビル爆破事件、間組、鹿島建設など海外進出企業に対する一連の爆破事件)が建築とその環境を閉鎖的なものに変えたこと(暴力による歪み)、建築ジャーナリズムの演出によって、高度成長、学園紛争の落とし子たちによる、「虚しくも華麗な、実物大小住宅のあだ花が咲いたこと」(情報による歪み)、日照権をめぐる紛争が法律化までゆきついた事件に象徴されるように、ほしいままの権利主張が建築の自由を奪ったこと(権利主張による歪み)、さらに、エネルギー・ショックが、建設から維持、撤去まで含めた全過程をとらえて資源の節減・再利用を図るためには、どのような取組み方が必要かという形では論じられず、省エネルギーのための代替装置の開発にすり換えられていることを指摘しながら、林昌二は過去への復帰(保存、伝統的様式)は何ものも生み出さない。今ようやく、高度に発展した工業を背景として現代にふさわしい建築が生まれる条件が成熟したのだ、と言うのである。
そこには、テクノロジー、テクノクラシーを基盤にする建築家の極めて正統的な価値意識が示されていると言えるであろう。そこで示されている規範意識は、依然として支配的である。それは、ある意味では近代建築を支えた規範意識である。また、「建築が健康さを取り戻すよい機会」とか「変転を越えて生き続ける建築の生命」という言い方に示されるような、「建築」に対する限りない信頼において書かれる価値意識である。
しかし、建築あるいは建築家のアイデンティティそのものが問われていると考え、近代建築の解体を見据えようとするものにとって、そうした支配的な意識こそが問題であった。工業的なるものがもたらしたものが、商品と交換の世界の一般化にほかならないのであり、工業社会そのものに対する根底的な懐疑から出発するものにとって、決して「高度に発展した工業を背景として、現代にふさわしい建築が生まれる条件が成熟した」と見ることによって、新たな展望を語ることはできないのである。若い建築家たちや、保存や日本の伝統的様式への関心に対する林昌二の評価は,極めて厳しくポレミカルである。しかし、問題の構図は停止したままであることに変わりはない。テクノロジーあるとは工業的なものに対する評価の決定的差異がそこにあり、それを前提とするものが支配的な現実に対峙し得、それを否定的媒介とするものが、「社会性を欠いた小世界」に閉じ込もり、あるいは芸術や文化や知の領域へ平面をずらしていくという構図がそれである。七〇年代において、若い建築家たちに大きな影響を及ぼした磯崎新にとって、少なくとも、それは出発点において見えていた構図である。「テクノクラートに味方するか、あるいはデザインを放棄するか、この二者択一しか残されないとしたら、建築の思考は,当然のこととして不毛に陥らざるを得ない」のであり、それに陥らない新たな地平の模索こそが、彼の七〇年代の作業であったと言いうるのである。それが「アートとしての建築」、「小世界への自由」として現れざるを得なかったとすれば、またその限界すらも見えてきたとすれば、その新たな地平の模索がますます困難な状況を迎えつつあることが意識されるだけなのである。
もとより、そうしたアポリアは、若い建築家たちにおいてより意識されている。「まさに千載一遇の大世紀末へと雪崩れ込んでゆく時の巡り合わせに遭遇した」ことをあえて「僥倖」と言いながら、「現在を大世紀末の洞穴への入口であるとするならば、その漆黒の大迷路をくぐり抜けるためには、よほどの身構え、気構えが必要なことは明白で、そのための準備、修練をおさおさおこたってはなるまい」「千載一遇の大世紀末洞穴へくぐってゆくのには余りに軽装備、灯りも小さく、ほとんど丸腰,無防備なものの多さばかりが目につく」と石山修武が言うとき、それは明らかであろう。石山修武自身がいかなる根拠と希望に基づいて「漆黒の大迷路」をくぐり抜けようとし、いかなる準備、修練をつんでいるのかそれ自体は興味深いことである。しかし、そこには、極めて鋭く状況の困難性が予感されており、したたかな覚悟が示されているのを見ることができるはずである。単に、建築ジャーナリズムにおいて、「高度成長の、あるいは学園紛争の落とし子たち」が「虚しくも華麗なあだ花を繰り広げて見せた」「幕間の寸劇にしては長すぎる舞台」の幕が下り、「本舞台」の幕が開くといったレヴェルでのみとらえられてはならないものが、そこにはあるはずである。状況は、若い層においてはるかに厳しいと言えるのである。七〇年代の疾走を雑誌の特集という形で振り返る機会を得た原広司もまた、繰り返し状況の厳しさを語っているはずである。固化しつつある状況を逆手にとり、いかに活性化、流動化しうるか、それこそが問われているのである。
建築界がますます分断化されていく状況の中で、共有化された場はますます待ちえなくなりつつある。そうした状況において八〇年代を展望することは気が重い。われわれの日常のさまざまな局面につきまとうどうしようもなさは、漠然と暗鬱なる世紀末を予感させる。そうした漠然とした危機感がやがてとてつもない方向へ組織されるのではないかという不安が先に立つ。そうした中で、中心の空洞へ向き合うことがいかに可能か。共通の地層,地下水脈を果たして探り当てることができるのか。われわれは、ここしばらくは、さらに、希望と根拠を求めてさまよわねばならないのである。
七〇年代における建築の拡散的状況は、いくつかの関心を浮上させてきた。それらは、「市民社会」、工業、テクノロジー、近代といった中心が排除してきた、周縁的なるものへ眼を向けてきたものであると言ってもよい。第三世界、亜細亜、東洋、ヴァナキュラーなもの、様式・装飾・折衷主義、沖縄、被差別部落、和風・数寄屋・日本的なるもの、地域、共同体………。しかし、それらは、いくつかの例外を除いて、単に眼差しとして対置されたにすぎない。単に眼差しとして対置する限りにおいて、それが現実をつき動かす支配的趨勢に対して力を持ちえないことは明らかであった。
いま、われわれはおそらく磯崎新の『建築の一九三〇年代』がいち早く提起したように、少なくとも建築における一九三〇年代を想記すべきであろう。そうした関心をめぐるプロブレマティークのほとんどを見いだすことができるからである。そうしたさまざまな関心が、やがて、産業合理化、生産力増強、節約、建築の統制、建築新体制といった過程でなしくずしにされていったことを見ることができるからである。それを支えたのが、テクノロジーを基盤とする実務の思想であったからである。
布野修司 履歴 2025年1月1日
布野修司 20241101 履歴 住所 東京都小平市上水本町 6 ー 5 - 7 ー 103 本籍 島根県松江市東朝日町 236 ー 14 1949 年 8 月 10 日 島根県出雲市知井宮生まれ 学歴 196...
-
traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...
-
進撃の建築家 開拓者たち 第 11 回 開拓者 13 藤村龍至 建築まちづくりの最前線ー運動としての建築 「 OM TERRACE 」『建築ジャーナル』 2017 年7月(『進撃の建築家たち』所収) 開拓者たち第 12 回 開拓者 14 藤村龍至 ...