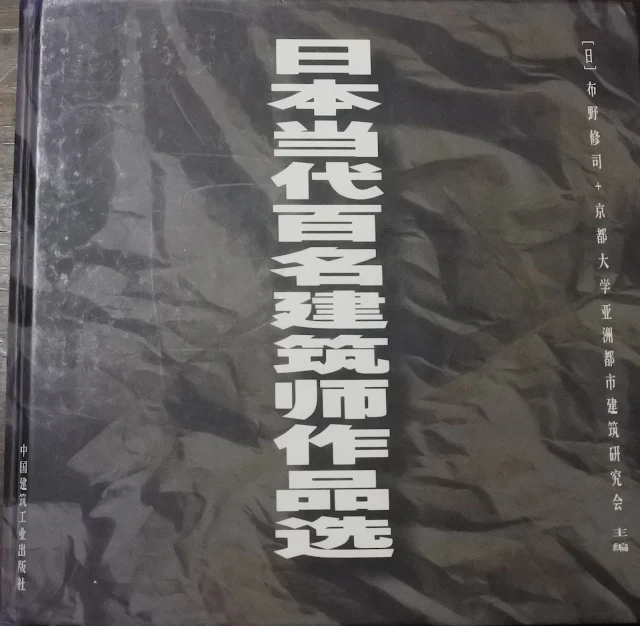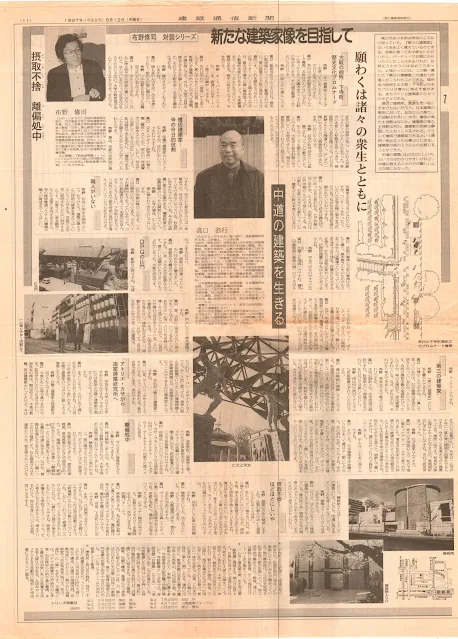当代日本城市設計精選
近代日本の建築家と都市計画
布野修司
はじめに
日本の都市計画の伝統は古代に中国からもたらされた。藤原京、平城京(奈良)、長岡京、平安京(京都)と続いて建設された「都城」は中国の都城の理念に基づいて建設されたとされる。もちろん、『周礼』考工記が記述する中国の都城理念がそのまま持ち込まれたということではない。例えば、日本の古代都城は「中央宮闕」にはなっていない。平安京が左京は洛陽、右京は長安と名付けられたように、一般的には唐の長安を真似たとされる。しかし、長安と京都は東西南北のプロポーションも規模も異なっている。最大の違いは日本の都城が城壁をもたないことである。また、社稷、宗廟などが配置されないのも特徴である。
一方、日本の都城も平城京、長岡京、平安京と時代を経るに連れて進化している。街区の寸法についてみると、平城京では、心々(芯々、真々)制ー道路の中心を寸法の基準にするーが採られている。平城京では内法制ー道路の端(内側)と端を基準とするーである。すなわち、平城京では街路の幅の違いによって街区の大きさは異なるのに対して、平安京では街路の幅に関わらず街区の大きさは一定である。藤原京については、最近の発掘成果からこれまでよりはるかに大きい「大藤原京」説が有力になりつつある。そうすると宮廷は都城の中心に位置することになり、『周礼』考工記に近いことになる。平安京の配置についても、風水説や道教の影響を指摘する論考もあり、興味深いテーマが残されている。
日本の都市はその後独自の展開を開始する。理念は理念としてそのまま実現されるとは限らないのである。また、人々の実際の生活によって変容していく。平安京も左京はいち早くさびれ、重心は左京に移る。中国からもたらされた都市の理念は次第に日本化していくのである。外来の概念が土着化していく過程も興味深いところである。
政治的中心としての都市は鎌倉、江戸に移るが、天皇の所在地としての京都は1867年まで日本の中心であり続ける。1994年に建都1200年を迎えた京都は世界的に見ても珍しい歴史都市である。1996年には,27の社寺などが世界遺産に登録された。今日に至るまで、様々な変化を経験してきたのが京都である。
日本の歴史的大都市ということでは、江戸、大阪を加えて、三都市が挙げられる。18世紀初頭日本全国の人口は約3000万人と見積もられるが、江戸が50.1万人(1721年)、大阪38.2満員万人(1721年)、京都が34.1万人(1719年)であった。江戸は螺旋状の構造をしており、明らかに京都のグリッド・パターンとは異なっている。城下町は日本のもうひとつの都市の伝統である。
中世から近世にかけて、産業の発達とともに都市が発達する。日本の伝統的都市はいくつかに分類される。社寺を中心とする門前町(宇治山田、長野、奈良など)、なかでも浄土真宗本願寺派を中核とする寺内町(越前吉崎、石山(大阪)、山科、今井など)、港町(尾道、敦賀、小浜、大湊など)、宿場町(掛川、沼津、三島など)、自由都市(堺、博多)、そして城下町(一乗谷、小田原、山口、甲府など)である。
江戸時代の幕藩体制において、各地域(藩)に城下町が築かれた。京都も秀吉によってお土居が築かれ、城下町化が計られる。今日の日本の都市は、基本的には江戸時代の城下町を受け継いで発展してきたといっていい。
19世紀半ば、新たな都市計画の伝統が移植される。きっかけとなったのは、長崎、神戸、大阪、横浜、新潟、築地(東京)など、開国に伴う開港場の建設である。西欧世界へ開かれた港町の建設を通じて西欧の都市建設技術がもたらされるのである。
以降、一世紀半の歴史が流れた。この間の日本の近代都市計画の歴史を簡単に振り返り、その問題点について考えてみたい。
近代日本の都市計画
一般的には、1888(明治21)年の東京市区改正条例の公布と翌年の同条例施行および市区改正設計の告示をもって日本の近代都市計画の始まりとされる。「市区改正」とは今日の「都市計画」のことである。
その歴史はいくつかの段階にわけることができる。石田頼房による時代区分がわかりやすい*1。
第1期 欧風化都市改造期(1868~1887年)
第2期 市区改正期(1880~1918年)
第3期 都市計画制度確立期(1910~1935年)
第4期 戦時下都市計画期(1931~1945年)
第5期 戦後復興都市計画期(1945~1954年)
第6期 基本法不在・都市開発期(1955~1968年)
第7期 新基本法期(1968~1985年)
第8期 反計画期(1982~)
第1期の欧風化都市改造期は、銀座煉瓦街建設(1972年)、日比谷官庁集中計画(1886年)などヨーロッパ風の都市計画が行われる時期だ。開港場が建設されてから、東京市区改正条例が制定されるまで日本都市計画の前史である。この過程については、藤森照信の『明治の東京計画』*2などが詳しく光を当てるところだ。この時期は、上海で活躍した英国人ウォートルス兄弟が銀座煉瓦街の計画、ドイツから招かれたエンデとベックマンが日比谷官庁集中計画に携わるなど、「お雇い外国人」としての建築家、都市計画が活躍した時期である。若干25才で日本を訪れた英国人建築家J.コンドルが日本の建築家の先生である。
第2期が1880年からの区分とされるのは、既にその動きが始まっていたからである。こうした時代区分はある年を閾として截然と区切れるものではない。
第3期において、東京市区改正土地建物処分規則(1889年)などを踏まえて、都市計画法、市街地建築物法(今日の建築基準法)が制定(1919年)される。戦前期における都市計画制度が1応確立された。1919年は日本の近代都市計画史にとって記憶すべき年である。この時期の関東大震災後(1923年)の震災復興都市計画事業は、日本の都市計画にとって極めて大きな経験であったといっていい。同潤会による不良住宅地区改良事業、住宅供給事業、また、土地区画整理事業の即成市街地への適用など、具体的な事業展開がなされ出すのである。同潤会は、震災復興のために各国から贈られた義捐金によってつくられた日本で最初の公的住宅供給機関である。1940年に日本住宅営団に改組される。
「15年戦争」(1931~45)下の第4期は、ある意味では特殊である。国土計画設定用綱(1940年)にみられるように、国土計画、防災都市計画などが全面的に主題となった時期である。しかし、都市計画史の上では、決して空白期でも停滞期でもない。数多くの実験的な試みがなされた時期であり、戦後へ直接つながるものを残している。極めて大きな経験となったのは、植民地における都市計画の実践であった。
戦後については、戦後復興期の経験の後は、1968年の建築基準法改正が画期になる。
第5期は戦後復興が全面的な課題であった。戦後復興は経済復興という意味では予想外の成功をみせた。1955年には「戦後は終わった」と宣言され、高度成長期を迎える。第6期、1960年代は、盛んに都市開発が行われた時期である。そして、都市計画法が整備される第7期を迎える。オイルショックを経験し、成長の限界が意識される。
そして、既成緩和策が取られた第8期は、バブル経済期にあたる。その崩壊後は、今日につながる時期である。従って、石田の区分にもう1期加えておこう。
第8期 反計画期(1982~95年)
第9期 バブル崩壊期(1991~)
具体的な展開は他の書物に譲るとして、まず、以上のような日本の都市計画の歴史を貫いている課題を指摘しよう。建築家が都市問題に目覚めて以降、具体的なアプローチがさまざまに展開されてきたのであるが、残されている課題は依然として大きいと考えられるのである。すなわち、日本の建築家は西欧の都市計画技術の移入に追われて、独自の行動原理を現実の都市のフィールドから引き出してきたかどうかは大いに疑問なのである。
①西欧都市計画技術の移入
日本の都市計画の第一の特徴は西欧の近代都市計画技術の多大な影響である。
明治期の「お雇い外国人」による都市計画技術や建築技術の直接導入以降、常にモデルは欧米にあった。オースマン*3のパリ改造と「市区改正」、ナチスの国土計画理論*4と戦時体制下の国土計画理論、グレーター・ロンドン・プラン*5と首都圏整備計画、戦後でもドイツのB(ベー)-プラン*6(地区詳細計画)と地区計画制度(1980年)など、基本的には欧米の制度を輸入してきた。日本の現実の中から独自の手法や施策が生み出されるということは必ずしもなかったのである。
②都市計画の主体の未確立
都市計画の主体は誰なのか。誰が都市計画を行うのか。国なのか地方自治体なのか、行政なのか住民なのか。日本の場合極めて曖昧である。その点中国と日本では相当事情が異なっている。
日本の場合、基本的には国が都市計画を主導してきた。三割自治体と言われるように国がイニシアティブをもっており、国の補助金事業によって全国画一的に都市計画が行われてきた。そうしたなかで、地方分権の主張とともに、都市計画は地方自治体が主体となるべきだという意見が次第に大きくなりつつある。また、住民参加論がさまざまに展開されてきている。すなわち、まちづくりの主体は地域社会(コミュニティ)であることが次第に認識されつつあるのである。
③都市計画の財源の問題
都市計画の財源はどこに求められるか。何でまかなうのか。受益と負担の問題は日本の都市計画における一貫する問題である。これまでの日本の都市計画は、インフラストラクチャーの建設を主体とする公共事業を主体としてきた。あるいは一般的には民間の都市開発を行政がコントロールするかたちをとってきた。道路や鉄道などの建設を公共団体が行い、後の開発は民間の開発業者に委ねられるのである。特に巨大開発をめぐって、都市計画事業が生み出す開発利益の帰属をめぐっては、政、財、官をめぐって癒着の構造が成立してきたことがしばしば指摘される。また、公共事業誘致の地域間競争が繰り広げられるのが常であった。
一般的な手法としてよく使われるのが博覧会である。博覧会の建設によってインフラ整備が終わった土地をイヴェント終了後に開発する手法である。大阪万国博(1970年)、沖縄海洋博(1975)、筑波科学技術博(1985年)、また、1980年代後半に自治体設立百周年を記念して各自治体で行われた地方博覧会など、地域開発のための重要な手法とされてきた。
日本には都市計画税という税があるが、都市計画に用いる仕組みがない。経済状況に関わらず、まちづくりに用いる財源を確保するのが課題であり続けているのである。
④土地問題、所有権と土地利用規制の問題
土地問題、あるいは土地所有権と利用権、土地の公共性と私有権、所有権と土地利用規制の問題は、都市計画の基本的問題であり続けている。土地私有制は資本主義社会の基本である。この点中国と前提が全く異なる。
日本においては土地の売買、建設は基本的には自由である。しかし、都市計画が都市計画として成立するためには、土地の利用についての何らかのコントロールが可能でなければならない。
そのためにはある理念が必要である。例えばその前提となる公共性の概念は日本において極めて未成熟であり、曖昧である。そうした状況に西欧の都市計画モデルを導入するところにまず混乱の源があった。ある意味で、日本の都市のあり方を規定してきたのは、土地への投機行動である。そして、それを規制する法制度である。
極端にいうと、規制と規制逃れのいたちごっこがあるだけで、結果として無秩序なまことに日本的な都市が出来上がってきたのである。
⑤都市計画の組織の問題
都市計画のための組織も以上からうかがえるように日本では未確立である。その根底には日本の地方自治体の問題がある。また、都市計画の決定にさまざまな主体が絡み合い、その決定プロセスを不透明にする構造が一貫して存在してきた。いま、日本では非営利組織(NPO:Non Profit Organization)によるまちづくりが展望されようとしている。地方自治体と地域社会をつなぐ仕組みの確立が大きな問題なのである。
以上を念頭に置きながら、戦後復興から今日に至る過程を振り返ってみよう。建築家にとっての都市と建築をめぐる課題は、いっこうに解かれていないことがわかる。しかし、その前に中国との関係において触れざるを得ない課題がある。「15年戦争」期(第4期)の植民地における都市計画の問題である。
都市計画と国家・・・・植民地の都市計画
「15年戦争」期において、大連、奉天、新京(長春)、ハルビン、撫順、牡丹峰、北京、上海、青島、京城、釜山、台北、高雄など、満州、中国、朝鮮、台湾の主だった都市で都市計画が実施される。大同都市計画、新京都市計画、など建築家も数多く参加したのであった。また、日本の都市計画法や市街地建築物法にならった法制度も施行されている。朝鮮市街地計画令が1934年6月に、台湾都市計画令が1936年8月に、関東州計画令が1938年2月にそれぞれ公布されたのであった。
なぜ、植民地における都市計画が振り返って着目されるかというと、理念がストレートに実現されようとしたかに見えるからである。それまでに蓄積されてきた都市計画の技術や理念を初めて本格的に実践する一大実験場となったように思えるからである。
越沢明は、なかでも新京の都市計画を近代日本の都市計画史のなかで看過できない重要な意味をもつとする*7。近代都市計画の理念、制度、事業手法、技術は、日本では1930年代にほぼ確立しており、新京における実践においてそれが明らかにできるというのである。新京の都市計画については、越沢によっても明らかにされていないことも多い。ただ、理念の実現という観点からみて、その計画の意義が全体として評価されるのである。
理念をある程度「理想的に」実現させたものは、植民地という体制である。強力な植民地権力の存在があって、初めて、理念の実現が可能となった。都市計画は、その本質において、あるいはその背後に、強力な権力の存在を必要とする。植民地の場合、その都市計画の目的ははっきりしている。先の植民地の都市計画法も、それぞれ似ているけれども、日本の都市計画法とは全く異なる。その目的とするのは植民地支配のための「市街地や農地の創設と改良」であって、公共の福利や生活空間の創造ではないのである。また、さまざまな規定の強制力は比較にならないものであった。土地の収用権は、台湾でも朝鮮でも総督が握っていた。区画整理事業にしても強制施行がほとんどである。
植民地期の都市計画の実験を理想化することは、こうして、都市計画に付随する暴力的側面を覆い隠すことにおいて大きな問題がある。しかし、都市計画の理念の実現に強力なリーダーシップが必要であること、私権を制限する強力な強制力が必要であること、都市計画が国家権力と不可避的に結びつくものであることを確認する上で、植民地における都市計画を振り返っておくことは無駄ではない。
日本の場合、象徴的なのは後藤新平*8であろう。近代日本の都市計画の生みの親ともいわれ、東京市長として帝都復興計画を実現しようとした後藤新平にとって、一方で、「機関銃でパリの街を櫛(くし)削る」といわれたオースマンが理想であった。しかし、植民地台湾、植民地満州における経験もまた決定的であった。都市計画のひとつの理想をそこで見たに違いないのである。しかし結局は、彼の関東大震災後の帝都復興計画は挫折するのであった。
白紙の上に都市計画を展開するという経験は、北海道のいくつかの都市を除くと、植民地においてしか日本はもたない。日本の植民地における都市計画が何を遺産として残したのかは注意深く検証されるべきであろう。
第二次世界大戦の敗戦によって日本のほとんどの都市は灰燼に帰した。極わずかの爆撃でダメージを受けなかったのは京都などごくわずかしかない。東京は焼け野原であった。建築家にとってはまさに白紙である。その白紙の上にどのような都市が築かれていったのか。
戦後の建築家と都市
戦後まもなく日本の建築家にとって全面的な主題となったのは戦後復興である。具体的な課題として、早急な都市建設、住宅建設が焦眉の課題となった。戦災復興都市計画には数多くの都市計画家が参加している。
戦災復興院は、典型的な13の都市について、建築家に委嘱して調査計画立案作業を行った。1946年の秋から夏にかけてのことである。高山栄華が長岡市、丹下健三が広島市、前橋市、武基雄が長崎市、呉市などの計画立案に当たった。また、東京都は、1946年2月に東京都復興都市計画コンペを銀座、新宿、浅草、渋谷、品川。深川といった地区をとりあげて行っている。新宿復興コンペで1等当選したのが内田祥文・祥哉兄弟などのグループである。この新宿地区計画は淀橋上水場を含んでいたのであるが、東京都庁舎を含むオフィス街を計画しており、今日の新宿新都心の姿を先取りしているのが興味深い。また、早稲田、本郷、池袋、三田の4地区において文教地区計画が立案されている。
戦後まもなくの東京における復興計画についてこうしたコンペの企画を行ったのは石川栄耀*9(1893~1955年)である。彼は、1933年以来、東京都の都市計画を手掛けてきたのであるが、知られるように戦前戦後を通じた都市計画界の最大のイデオローグである。驚くことに、1945年8月27日には、石川が課長をしていた都市計画課は「帝都再建方策」を発表している。東京戦災復興の公式の計画である「東京戦災復興計画」は、1946年4月に街路計画、区画整理が、9月に用途地域が、1948年7月に緑地地域が計画決定されていくのであるが、それと並行して、いわば復興機運を盛り上げるために復興コンペが企画されたのであった。
この復興コンペを含む「東京戦災復興都市計画」は、ある理想の表現であった。結果として、実施されなかった計画であり、そうした意味では未完である。否、現実の過程は、その計画とは大きく異なった方向に展開してきたのであった。紙の上にある理想の図式を描くスタイルがここでも踏襲された。そのモデルは、しかも、ヨーロッパのものであった。都市計画制度も都市計画技術もむしろ戦前との連続線上に前提されていた。欧米諸国が新しい都市計画制度を模索する取組みを見せたのに対して、日本の場合、あまりにも余裕がなかったのであった。
1950年代初頭、朝鮮戦争の特需によってビル建設ブームが始まり、戦災復興が軌道に乗ると建築家の都市計画への関心は相対的に薄れていく。理想の計画案より、高度経済成長へむかうエネルギーが都市建設の方向を支配していくのである。
こうして、関東大震災直後に続いて、日本の建築家・都市計画家は、理想の都市計画を実践する機会をまたしても失ったのだ、といわれることになる。
東京オリンピックが開かれるのが1964年、大阪万国博が1970年、日本の1960年代は黄金の60年代と呼ばれる。日本の国土はこの十年でがらっと変わるのである。
建築家が都市への関心を集中的に示すのは、1960年前後のことである。盛んに都市のプロジェクトが建築家によって描かれるのである。菊竹清訓*10の「海上都市」、「搭状都市」、黒川紀章*11の「空間都市」、「農村都市」、「垂直壁都市」、槙文彦*12・大高正人*13の「新宿副都心計画」、磯崎新*14の「空中都市」、そして丹下健三*15の「東京計画1960」などがそうだ。また、メタボリズムをはじめに都市構成論が展開される。アーバン・デザインという領域の確立、都市デザインの方法および発展段階についての整理、建築への時間性の導入とその技術化、槙文彦の「群造形論」、大谷幸夫*16の「Urbanics試論」、磯崎新の「プロセス・プランニング」、原広司*17の「有孔体理論」、西澤文隆*18の「コートハウス論」などがそうだ。60年代に至って、建築家が一斉に「都市づいて」いった過程とその帰結については拙著『戦後建築論ノート』*19で詳述している。要するに結論は以下のようだ。
「西山夘三*20は、『60年代は日本の建築家が都市に対して眼を開き、かつて戦災のあとの絶好(?)の機会に能力不足で果たせなかった責任の償いをし、〈所得倍増計画〉という華やかな建設のかけ声にのって、大きな成果をかちとる時代である・・といった期待が語り合われ、少なからぬ人々が意気にもえている』と書いていた。おそらくそうであった。戦時中の中国大陸での経験を別とすれば、建築家は絶好の都市(都市計画)への実践の機会を戦後まもなくに続いて再びもったといえるであろう。」と書いた。
しかし、帰結はどうか。
「アーバン・デザインという1つの領域を仮構し、建築家の構想力による都市のフィジカルな配列を提案することによって、その社会的、経済的、技術的実現可能性を問うというスタイルは、近代建築の英雄時代の巨匠のスタイルである。……しかし、都市へのコミットの回路として、こうしたスタイルが衝撃をもち得たのは、60年代初頭のほんのわずかな幸福な時期に過ぎなかった。未来都市のプロジェクトは、ほぼこの時期に集中して提出されたのみで、急速に色あせていくのである。一面から見れば、60年代の過程は、彼等の構想力が現実化されていく過程であったといえよう。彼らのプロジェクトが色あせて見え出したのは、現実の過程がそれを囲い込み、疑似的な形であれ現実のコンテクストのなかでそれなりの形態をあたえることによって、追い越し始めたからである。それをものの見事に示したのが、日本万国博・Expo'70であり、沖縄海洋博であった。……」
ポストモダンの都市論
オイルショック(1973年)とともに建築家の「都市からの撤退」が始まる。若い建築家たちの表現の場は、ほとんど住宅の設計という小さな自閉的な回路に限定されていく。そうした状況を原広司が「最後の砦としての住居」と比喩的に呼んだことは1970年代の雰囲気をよく現している*21。
大規模なニュータウンの基本設計など具体的な仕事が日本住宅公団など当該機関に委ねられ、実践の機会が失われたということもある。しかし、建築家が自ら都市への回路を閉ざした点が大きい。自らの方法論やプロジェクトの提示によって引き起こされる現実のさまざまなコンフリクトを引き受けようとする意欲も余裕もなくなるのである。そういう意味では、建築家たちは二重に都市への回路を閉ざされ、また自ら閉ざしていったのであった。
ところが再び、都市の時代がやってくる。バブル経済の波が日本列島を襲うなか、東京をはじめとする日本の都市はさらに大きく変容することになるのである。建築家は、またしても都市へと駆り立てられていくことになった。民間活力導入のかけ声のもと規制緩和による「反計画」の時代が始まる。建築家の無防備さも、無手勝流も「反計画」の時代に再び受け入れられたように見えたのであった。
80年代から90年代にかけて都市への関心は次第に大きくなっていく。大都市東京をはじめとして、都市をめぐる様々な書物が洪水のように出版された。東京論、都市論の隆盛は都市への関心の大きさを示していた。その背景にあったのが、膨大な金余り現象からのさまざまな都市改造計画への蠢きであった。
バブル経済期の都市論は、およそ3つに分けることができる。ひとつはストレートな都市改造論であり、都市再開発論である。
なぜ、都市改造なのか、特に東京をめぐってははっきりしている。一言でいえば、「フロンティアの消滅」である。
17世紀の初頭には東国の寒村にすぎなかった江戸が世界都市・東京へ至ったその歴史を振り返る余裕はここではないが、単純にその平面的広がりを考えても過飽和状態に達しつつあることは明らかである。東京一極集中がますます加速されるなかで、首都圏において都市発展のフロンティアが消滅しつつある。
そこで、開発のためにまず求められたのがウォーターフロントである。また、未利用の公有地である。そして、ジオ・フロント(地下空間)であり、空中である。空へ、地下へ、海へ、フロンティアが求められた。そして、それが全国へと波及していったのである。
もうひとつの都市論の流れは、レトロスペクティブ(回顧趣味的)な都市論である。都市化の進展によって失われた古きよき都市の伝統や記憶が次々に掘り起こされていった。都市の中の過去が、自然が現代都市への批判として対置されたのである。もちろん、そうした素朴な回顧趣味は都市改造のうねりに巻き込まれてしまう。水への郷愁がストレートにウォーターフロント開発へ結び付けられたことがそれを示していた。
さらにもうひとつの都市論の流れは、いわゆるポストモダンの都市論である。すなわち、いまあるがままの現代都市、とりわけ、国際化し、ますます人工環境化し、スクラップ・アンド・ビルドを繰り返す仮設都市をそのまま肯定し、愛であげる都市論である。ただただ、今都市が面白い、東京が面白いという都市論である。このポストモダンの都市論の系譜は、レトロスペクティブな都市論をすぐさま取り込む。ポストモダン・ヒストリシズム(歴史主義)といわれた皮相な歴史主義的なポストモダン・デザインが都市の表層を飾り出したのである。
こうしてあえて3つの都市論の流れを区別してみてわかることは、全体としてそれぞれがつながっていることである。レトロスペクティブな都市論は一見都市改造への悲鳴であるようでいて、ポストモダンの都市論を介して過去の都市を疑似的に再現する回路に送り込まれたし、ポストモダンの都市論は、都市改造のさまざまな蠢きをその華やかさのうちに包み込むものであった。
そうしてバブルがはじけた。そして阪神・淡路大震災がやってきた。
阪神・淡路大震災の教訓*22
戦後50年の節目に当たる1995年は、日本の戦後50年のなかでも敗戦の1945年とともにとりわけ記憶される年になった。日本の都市と建築を支えてきたものが大きく揺さぶられ続けたのが1995年であった。
阪神・淡路大震災の教訓を列挙してみよう。
a 人工環境化・・・自然の力・・・地域の生態バランス
阪神・淡路大震災に関してまず確認すべきは自然の力である。いくつものビルが横転し、高速道路が捻り倒された。地震の力は強大であった。また、避難所生活を通じての不自由さは自然に依拠した生活基盤の大事さを思い知らせてくれた。水道の蛇口をひねればすぐ水が出る。スイッチをひねれば明かりが灯る。エアコンディショニングで室内気候は自由に制御できる。人工的に全ての環境をコントロールできる、というのは不遜な考えである。災害が起こる度に思い知らされるのは、自然の力を読みそこなっていることである。山を削って土地をつくり、湿地に土を盛って宅地にする。そして、海を埋め立てるという形で都市開発を行ってきたのであるが、そうしてできた居住地は本来人が住まなかった場所だ。災害を恐れるから人々はそういう場所には住んでこなかった。その歴史の智恵を忘れて、開発が進められてきたのである。
まず第一に自然の力に対する認識の問題がある。関西には地震がない、というのは全くの無根拠であった。軟弱地盤や活断層、液状化の問題についていかに無知であったかは大いに反省されなければならない。一方、自然のもつ力のすばらしさも再認識させられた。例えば、家の前の樹木が火を止めた例がある。緑の役割は大きい。自然の河川や井戸の意味も大きくクローズアップされた。
人工環境化、あるいは人工都市化が戦後一貫した都市計画の趨勢である。自然は都市から追放されてきた。果たして、その行き着く先がどうなるのか、阪神・淡路大震災は示したといえるのではないか。「地球環境」という大きな枠組みが明らかになるなかで、また、日本列島から開発フロンティアが失われるなかで、自然の生態バランスに基礎を置いた都市、建築のあり方が模索されるべきことが大きく示唆される。
b フロンティア拡大の論理・・・開発の社会経済バランス
阪神・淡路大震災の発生、避難所生活、応急仮設住宅居住、そして復旧・復興へという過程において明らかになったのは、日本社会の階層性である。すぐさまホテル住まいに移行した層がいる一方で、避難所が閉鎖されて猶、避難生活を続けざるを得ない人たちが存在した。間もなく出入りの業者や関連企業の社員に倒壊建物を片づけさせる邸宅がある一方で、長い間手つかずの建物がある。びくともしなかった高級住宅街のすぐ隣で数多くの死者を出した地区がある。
最もダメージを受けたのは、高齢者であり、障害者であり、住宅困窮者であり、外国人であり、要するに社会的弱者であった。結果として、浮き彫りになったのは、都市計画の論理や都市開発戦略がそうした社会的弱者を切り捨てる階層性の上に組み立てられてきたことである。
ひたすらフロンティアを求める都市拡大政策の影で、都心地区が見捨てられてきた。開発の投資効果のみが求められ、居住環境整備や防災対策など都心への投資は常に後回しにされてきた。
例えば、最も大きな打撃を受けたのが「文化」である。関西で「ブンカ」というと「文化住宅」というひとつの住居形式を意味する。その「文化住宅」が大きな被害にあった。木造だったからということではない。木造住宅であっても、震災に耐えた住宅は数しれない。木造住宅が潰れて亡くなった方もいるけれど家具が倒れて(飛んで)亡くなった方が数多い。大震災の教訓は数多いけれど、しっかり設計した建物は総じて問題はなかった。「文化住宅」は、築後年数が長く、白蟻や腐食で老朽化したものが多かったため大きな被害を受けたのである。戦後の住宅政策や都市政策の貧困の裏で、「文化住宅」は、日本の社会を支えてきた。それが最もダメージを受けたのである。それにしても「文化住宅」とは皮肉な命名である。阪神・淡路大震災によって、「文化住宅」の存在という日本の住宅文化の一断面が浮き彫りになったといえる。
都市計画の問題として、まず、指摘されるのは、戦後に一貫する開発戦略の問題点である。拡大成長政策、新規開発政策が常に優先されてきた。都心に投資するのは効率が悪い。時間がかかる。また、防災にはコストがかかる。経済論理が全てを支配するなかで、都市生活者の論理、都市の論理が見失われてきた。都市経営のポリシー、都市計画の基本論理が根底的に問われたといっていい。
c 一極集中システム・・・重層的な都市構造・・・地区の自律性
日本の大都市は、移動時間を短縮させるメディアを発達させひたすら集積度を高めてきた。郊外へのスプロールが限界に達するや、空へ、地下へ、海へ、さらにフロンティアを求め、巨大化してきた。その一方で都市や街区の適正な規模について、われわれはあまりに無頓着であったことが反省される。
都市構造の問題として露呈したのが、一極集中型のネットワークの問題点である。大震災が首都圏で起きていたら、東京一極集中の日本の国土構造の弱点がより致命的に問われたのは確実である。阪神間の都市構造が大きな問題をもっていることは、インフラストラクチャーの多くが機能停止に陥ったことによって、すぐさま明らかになった。それぞれに代替システム、重層システムがなかったのである。交通機関について、鉄道が幅一キロメートルに四つの路線が平行に走るけれど迂回する線がない。道路にしてもそうである。多重性のあるネットワークは、交通インフラに限らず、上下水道などライフラインのシステム全体に必要である。
エネルギー供給の単位、システムについても、多核・分散型のネットワーク・システム、地区の自律性が必要である。ガス・ディーゼル・電気の併用、井戸の分散配置など、多様な系がつくられる必要がある。また、情報システムとしても地区の間に多重のネットワークが必要であった。
d 公的空間の貧困
また、公共空間の貧困が大きな問題となった。公共建築の建築としての弱さは、致命的である。特に、病院がダメージを受けたのは大きかった。危機管理の問題ともつながるけれど、消防署など防災のネットワークが十分に機能しなかったことも大きい。想像をこえた震災だったということもあるが、システム上の問題も指摘される。避難生活、応急生活を支えたのは、小中学校とコンビニエンスストアであった。地域施設としての公共施設のあり方は、非日常時を想定した性能が要求されるのである。
また、クローズアップされたのは、オープンスペースの少なさである。公園空地が少なくて、火災が止まらなかったケースがある。また、仮設住宅を建てるスペースがない。地区における公共空間の、他に代え難い意味を教えてくれたのが今回の大震災である。
e 地域コミュニティのネットワーク・・・ヴォランティアの役割
目の前で自宅が燃えているのを呆然とみているだけでなす術がないというのは、どうみてもおかしい。同時多発型の火災の場合にどういうシステムが必要なのか。防火にしろ、人命救助にしろ、うまく機能したのはコミュニティがしっかりしている地区であった。救急車や消防車が来るのをただ待つだけという地区は結果として被害を拡大することにつながった。
阪神淡路大震災において最大の教訓は、行政が役に立たないことが明らかになったことだ、という自虐的な声がある。一理はある。自治体職員もまた被災者である。行政のみに依存する体質が有効に機能しないのは明らかである。問題は、自治の仕組みであり、地区の自律性である。行政システムにしろ、産業的な諸システムにしろ、他への依存度が高いほど問題は大きかった。教訓として、その高度化、もしくは多重化が追求されることになろう。ひとつの焦点になるのがヴォランティア活動である。あるいはNPO(非営利組織)の役割である。
f 技術の社会的基盤の認識・・・ストック再生の技術の必要
何故、多くのビルや橋、高速道路が倒壊したのか。何故、多くの人命が失われることになったのか。問題なのは、社会システムの欠陥のせいにして、自らのよって立つ基盤を問わない態度である。問題は基準法なのか、施工技術なのか、検査システムなのか、重層下請構造なのか、という個別的な問いの立て方ではなくて、建築を支える思想(設計思想)の全体、建築界を支える全構造(社会的基盤)がまずは問われるべきである。建造物の倒壊によって人命が失われるという事態はあってはならないことである。しかし、それが起こった。だからこそ、建築界の構造の致命的な欠陥によるのではないかと第一に疑ってみる必要がある。
要するに、安全率の見方が甘かった。予想をこえる地震力だった。といった次元の問題ではないのではないか、ということである。経済的合理性とは何か。技術的合理性とは何か。経済性と安全性の考え方、最適設計という平面がどこで成立するのかがもっと深く問われるべきである。
建築技術の問題として、被災した建造物を無償ということで廃棄したのは決定的なことであった。都市を再生する手がかりを失うことにつながったからである。特に、木造住宅の場合、再生可能であるという、その最大の特性を生かす機会を奪われてしまった。廃材を使ってでも住み続ける意欲のなかに再生の最初のきっかけもあったといっていい。
何故、鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物の再生利用が試みられなかったのも問題である。技術的には様々な復旧方法が可能ではないか。そして、関東大震災以降、新潟地震の場合など、かなりの復旧事例もある。阪神・淡路大震災の場合、少なくとも、再生技術の様々な方法が蓄積されるべきであった。
g 都市(建築)の死と再生
今度の大震災がわれわれにつきつけたのは都市(建築)の死というテーマである。そして、その再生というテーマである。被災直後の街の光景にわれわれがみたのは滅亡する都市(建築)のイメージと逞しく再生しようとする都市(建築)のイメージの二つである。都市(建築)が死ぬことがあるという発見、というにはあまりにも圧倒的な事実は、より原理的に受けとめられなければならないだろう。
現代都市の死、廃墟を見てしまったからには、これまでとは異なった都市(建築)の姿が見えたのでなければならない。復興計画は、当然、これまでにない都市(建築)のあり方へと結びついていかねばならない。
そこで、都市の歴史、都市の記憶をどう考えるのかは、復興計画の大きなテーマである。何を復旧すべきか、何を復興すべきか、何を再生すべきか、必然的には都市の固有性、歴史性をどう考えるかが問われるのである。
建造物の再生、復旧が、まず建築家にとって大きな問題となる。同じものを復元すればいいのか、という問いを前にして、建築家は基本的な解答を求められる。それはしかし、震災があろうとなかろうと常に問われている問題である。都市の歴史的、文化的コンテクストをどう読むか、それをどう表現するかは、日常的テーマといっていいのである。
戦災復興でヨーロッパの都市がそう試みたように、全く元通りに復旧すればいいというのであれば簡単である。しかし、そうした復旧の理念は、日本においてどう考えても共有されそうにない。都市が復旧に値する価値をもっているかどうか、ということに関して疑問は多いのである。すなわち、日本の都市は社会的なストックとして意識されてきていないのである。戦後五〇年で、日本の都市はすぐさま復興を遂げ、驚くほどの変貌を遂げた。しかし、この半世紀が造り上げた後世に残すべき町や建築は何かというと実に心許ないのである。
スクラップ・アンド・ビルド型の都市でいいということであれば、震災による都市の破壊もスクラップのひとつの形態ということでいい。しかし、バブル崩壊後、スクラップ・アンド・ビルドの体制は必然的に変わっていかざるを得ないのではないか。
そして、都市が本来人々の生活の歴史を刻み、しかも、共有化されたイメージや記憶をもつものだとすれば、物理的にもその手がかりをもつのでなければならない。都市のシンボル的建造物のみならず、ここそこの場所に記憶の種が埋め込まれている必要がある。極めて具体的に、ストック型の都市が目指されるとしたら、復興の理念に再生の理念、建造物の再生利用の概念が含まれていなければならない。否、建築の理念そのものに再生の理念が含まれていなければならない。
果たして、日本の都市はストックー再生型の都市に転換していくことができるのであろうか。表現の問題として、都市の骨格、すなわち、アイデンティティーをどうつくりだすことができるか。単に、建造物を凍結的に復元保存すればいいのか、歴史的、地域的な建築様式のステレオタイプをただ用いればいいのか、地域で産する建築材料をただ使えばいいのか、・・・・議論は大震災以前からのものである。
阪神・淡路大震災は、こうして、日本の都市と建築界の抱えている基本的問題を抉り出した。しかし、それ以前に、半世紀前から同じ問いの答えが求められているのである。
現代日本の都市計画
以上に振り返ったように、建築家と都市のかかわりは、震災、戦災、高度成長経済、バブル経済による建設と破壊の歴史とともにあった。いま再び、建築家は都市から撤退する時代を迎えつつある。日本の都市計画は何処へ向かうのか。それが今われわれの問題である。
①新規開発プロジェクト
日本のいわゆるニュータウン開発は1960年代初頭に始まる。千里ニュータウン(大阪)、高蔵寺ニュータウン(名古屋)、多摩ニュータウン(東京)など大規模な住宅地建設が長い年月をかけて行われてきた。
日本のニュータウンは、ベッド(ドーミトリー)・タウンといわれる。ただ、睡眠をとるだけ、住宅機能だけしかない町という意味である。すなわち、工場や事務所など雇用を吸収する施設は十分に設置されず、居住者は仕事を得るために都心に通うかたちとなった。多くの国で田園都市の理念はそのまま実現することなく、田園郊外にとどまったように、日本のニュータウンも自立的で自己完結的な住宅地とならなかった。
今日本のニュータウンの問題は高齢化である。ある時期に同じ世代が入居し、人口の大多数が高齢化しつつある。都市は老若男女バランスがとれていなければならない。人口構成の面では大きな失敗であったけれど、現実の問題として高齢者に向けてどう産業を起こすかは極めて重要な課題である。
②再開発プロジェクト
新規開発プロジェクトに代わって、主流になりつつあるのが再開発である。都心のブライト(空洞)化、都心問題(インナー・シティ問題)は世界の先進諸国に共通の問題である。
先進諸国の場合、産業構造の転換が再開発を必然的にしてきた。その一環がウォーターフロント開発である。産業構造が第二次産業からサーヴィス産業に移行することによって港湾部に立地した工場などの跡地が機能転換を余儀なくされるのである。1980年代から90年代にかけてニューヨーク、パリ、ロンドンなどと同様日本でも大規模な都市再開発がなされたのであった。
大川端リバーシティを皮切りに、東京湾沿岸部の開発がなされた。横浜のMM(みなと未来)21開発も日本一の高さを誇るランドマークタワーが評判になった。千葉の幕張ベイタウン開発ではこれまでと異なった西欧的な町並みが目指された。天王州アイル、りんくうタウンなど大阪の臨海部、シーサイド百地、福岡の臨海部もすっかり面目を一新することになった。この間注目を浴びた大規模プロジェクトの多くが太平洋沿岸部に集中しているのである。ただ、都市博を梃子に計画された東京都の湾岸開発がバブルに乗り遅れ、都市博の中止とともにスローダウンしたのは上述したとおりである。
既成市街地の再開発は、権利者の調整がネックになることから、時間がかかる。東京の都心部ではアークヒルズが先駆的である。鉄道用地、大規模な公有地、工場跡地がターゲットとなる。恵比寿ガーデンプレイスなど新しい東京のスポットとなった。
③歴史的環境の保存修景計画
大規模な再開発によってこれまでにない町が建設される一方、歴史的な町並みの保存も日本各地で行われてきている。70年代の妻籠(岐阜県)を先駆として、様々な取り組みがある。大きな力になったのは文化財保護法の重要伝統建造物群保存地区の指定制度である。要するに、単体ではなく面として歴史的環境を保存する仕組みがつくられたのである。
④景観計画
歴史的な地区に限らず、既成市街地の景観をどうデザインするかは極めて重要なテーマである。1980年から90年代にかけて、多くの自治体で景観審議会がつくられ、景観条例がつくられた。この景観条例は、法的な強制力はないけれど、地域の景観をつくりあげる一定のガイドラインになりつつある。
景観の問題で、大きな問題は狭量や高架道路など土木スケールの構築物のデザインである。これまであまりデザインは問題にされなかったけれど、それらにもデザイナー、建築家が登用されだしている。
治水のための河川工事や山崩れ防止の工事などにおいても、親自然型工法といった自然景観を考慮した工法が採用され始めている。
⑤地域住宅計画
建設省住宅局は1980年代半ばにひとつの画期的な施策を打ち出した。HOPE計画(HOusing with Proper Environment)と呼ばれる。要するに地域に根ざした形の住宅供給が方針とされるのである。具体的には地域産材を用いるなど地域の住宅の伝統を生かした住宅の型の創出が目指された。戦後の日本では、北海道から沖縄まで、画一的な標準住居が公共住宅として供給されてきた。しかし、地域毎に固有のやり方が目指されるようになった。一大転換である。
HOPE計画の主体は市町村である。これまで中央政府で全て決めてきた供給戸数なども地方自治体が決定する。画期的である。さらに興味深いのは、計画の内容も自治体毎に独自に決定できることである。喜多方(福島)の倉を利用するまちづくりなどユニークな取り組みがなされてきた。日本には3000を超える自治体があるが、10年でおよそ300近い自治体が建設省の補助を受け、独自の施策を競い合っている。
阪神・淡路大震災がひとつのきっかけとなって、住民参加型のまちづくりが様々に展開されはじめている。ワークショップ方式と呼ばれる、自分たちの住んでいる町を調査し、問題点を話し合う集会やディスカッションを続けながらまちづくりを進めるやり方である。こうしたボトムアップのやり方は、これまでとは比較にならないほど手間暇がかかる。そこで期待されるのが、ヴォランタリーな活動である。上述したように、日本ではNPO(非営利組織)に法人格を認める法案が整備された。NPOが自治体と住民をつなぐ形のまちづくりがこれからの方向性として期待されている。そのモデルと考えられるのが世田谷(東京)のまちづくりである。小さな公園を整備したり、看板をそろえたり、植樹をしたり、身近にできることからやっていくのが特徴である。
都市計画に関わる仕組み、法制度を変えていく試みも重要であるが、一方で事例を積み重ねていくことも必要である。試行錯誤の中から日本の独自の方法が生み出されることを大いに期待したい。
21世紀へ向けて・・・集団の作品としての生きられた都市
都市計画において基本的なのは部分と全体をめぐる問題である。全体から部分へか、部分から全体へか、部分の中の全体か、全体の中の部分か、都市と建築をめぐる、あるいは都市と住居をめぐる基本的問いがある。
都市計画の起源というヒッポダモス風の都市計画がまず挙げられる。このグリッド・パターンの都市計画は古今東西実に広範にみることができるのであるが、知られるようにギリシャ・ローマの都市計画には別の伝統がある。都市を壮麗化し大規模な景観のなかに都市を構想する流れである。1方がグリッドという形で部分と全体にあらかじめ枠組みを与えるのに対して、他方は、自然の地形や景観を前提として、都市全体を記念碑化しようとする。もちろん、単純ではない。植民都市における実験としてヒッポダモス風都市計画が実践される場合、絶えず、危険性があった。都市の立地によっては、大規模な造成が必要となるからである。
全体をあらかじめ想定した都市計画の伝統として、宇宙論的な都市の系譜がある。都市を宇宙の反映として考える伝統である。宇宙の構造を都市の構造として表現しようとするのが、例えば、中国や日本、朝鮮の都城であり、インドのヒンドゥー都市である。しかし、そうした理念型がそのまま実現されることはまずない。また、理念型に基づいて計画されても、大きく変容していくのが普通である。平安京や長安の変遷をみてもそれは明らかであろう。
王権の所在地としての「都」そして城郭をもった都市、その2つの性格を併せ持つ都市、すなわち都城について、その都城を支えるコスモロジーと具体的な都市形態との関係をグローバルに見てみると、王権を根拠づける思想、コスモロジーが具体的都市のプランに極めて明快に投影されるケースとそうでないケースがある。すなわち、都市の理念型として超越的なモデルが存在し、そのメタファーとして現実の都市形態が考えられる場合と、実践的、機能的な論理が支配的な場合がある。前者の場合も理念型がそのまま実現する場合は少ないのである。また、都市構造と理念との関係は時代とともに変化していくし、理念型と生きられた都市は常に重層的なのである。
西アジア、イスラーム圏には、都城の思想を表す書はない。イスラームの都市計画の伝統はそうした意味で興味深い。イスラーム都市は全く非科学的で、迷路のような細かい街路が特徴的である。しかし、都市構成の原理がないからというと決してそうではない。全体が部分を律するのではなく、部分を積み重ねることによって全体が構成されるそんな原理がイスラーム都市にはある。イスラーム都市を律しているのはイスラーム法である。道路の幅や隣家同士の関係など細かいディテールに関する規則の集積が都市計画を律しているのである。街区を構成していく場合に予め全体像は必ずしも必要とされないのである。
以上のような前近代におけるいくつかの都市計画の伝統から示唆されることは何か。少なくとも言えることは、都市というのは計画されるものであると同時に生きられるものだということである。そのダイナミックな過程を組み込まないあらゆる都市計画理論はそれだけでは無効であるということである。近代日本の都市計画の歴史が教える最大なものも、都市が無数の集団の作品であり、建築家の構想力や空間の創造も生きられてはじめて意味を持つということである。
*1 石田頼房、『日本近代都市計画の百年』、自治体研究社、一九八七年。
*2 岩波書店、一九八二年。
*3 Georges Eugene Haussman。一八〇九~一八九一年。パリ生まれの行政官、都市計画家。ナポレオン三世の下でセーヌ県の知事となり(五三~七〇)、パリ市の都市計画を大胆に実施した。
*4 G.フェーダーの都市計画理論がその典型であるとされる。
*5 1949年、P.アーバークロンビーが中心になって作成した。半径30マイルを計画域とし、同心円状に都心、郊外、緑地帯、周辺地帯の四つの環帯を区分した。
*6 地区詳細計画。特定の地区について遵守すべき建物の高さ、形態、色彩などを決める制度。
*7 越沢明、『満州国の首都計画』、日本経済評論社、一九八八年。
*8 一八五七岩手県~一九二九年。官僚,政治家。須賀川医学校卒。愛知県病院長,愛知医学校校長を経て一八八三年内務省衛生局に入る。九八年台湾総督・児玉源太郎の求めで台湾総督府民政局長となる。一九〇三年貴族院勅選議員。一九〇六~〇八年満鉄初代総裁に就任。児玉源太郎の死後、桂太郎に接近、第二次・第三次桂内閣に逓相として入閣。寺内内閣の内相、のち外相となりシベリア出兵を推進。二〇~二三年東京市長。帝都復輿院総裁となり、震災後の東京の大復興計画の立案を行う。
*9 一八九三山形県~一九五五年。都市計画者。一九一八年東京帝大卒。米国貿易会社に就職したが、二〇年内務省都市計画地方委員会技師となり、名古屋勤務となる。その後、東京都道路・都市計画課長を歴任し、五一年東京都建設局長で退職。早大工学部教授。名古屋では都市計画原案の作成に従事、土地区画整理事業を導入した。東京では戦災復興のため、駅前広場の建設とこれを中心とする盛り場計画を推進した。新宿歌舞伎町は彼の命名であり、組合施行方式の都市計画事業として完成させた。地方計画にも関心を抱き、「生活圏」の考え方を提唱、今日の国土計画の基礎を築いた。
*10 菊竹清訓▼きくたけ・きよのり▼《1928久留米~.》◇建築家。早稲田大学理工学部建築学科卒業(50)。竹中工務店、村野・森建築事務所を経て、53年菊竹建築研究所設立。川添登・黒川紀章・槙文彦・大高正人らと共にメタボリズム・グループを結成。「か・かた・かたち」論、「代謝建築論」など独自の建築論を展開した。「出雲大社庁の舎」(61)で日本建築学会賞受賞。「スカイハウス」(57)、「ホテル東光園」(63)など多くの作品がある。また、「塔状都市」(59)、「海上都市」(60)といった都市プロジェクトも多く、沖縄海洋博覧会(75)において、アクアポリスを実現させた。
*11 黒川紀章▼くろかわ・きしょう▼《1934~.名古屋》◇建築家。京都大学工学部建築学科卒(57)。東京大学大学院で丹下健三に師事し、62年より黒川紀章建築都市設計事務所を主催。60年代の日本の建築界をリードしたメタボリズム・グループの旗手として知られる。後に「中銀カプセルタワービル」(72)に実現されるようなカプセル住宅によって構成される未来都市のイメージをいち早く提示した。「広島市現代美術館」(88)で日本建築学会賞受賞。「国立民族学博物館」、「国立文楽劇場」など作品多数。海外の作品も多い。多彩な活動で知られ、『共生の思想』など著書も多数ある。
*12 槙文彦 まき・ふみひこ。一九二八東京~。建築家。東京大学建築学科卒(五二)。ハーバード大学等で学ぶ。SOM建築事務所、ジャクソン建築事務所に勤務の後、ワシントン大学、ハーバード大学助教授を経て、槙総合計画事務所設立(六五)。東京大学工学部建築学科教授(七九~八九)。59年メタボリズム・グループ結成に参画。群造形理論で知られる。「名古屋大学豊田講堂」(62)、「藤沢市秋葉台文化体育館」(84)で日本建築学会賞。「代官山集合住居」(67)、「幕張メッセ」(88)、「SPIRAL」(84)、「京都国立近代美術館」(86)など作品多数。著書に『記憶の継承』(92)などがある。
*13 大高正人 おおたかまさと。一九二三福島県三春町~。東京大学大学院卒業、(四九)。前川国男建築設計事務所を経て大高建築設計事務所。
*14 磯崎新 いそざき・あらた。一九三一大分~。建築家。東京大学建築学科卒業。丹下健三に師事する。磯崎新アトリエ設立(六三)。「大分県医師会館」(六三)以降、「群馬県立近代美術館」(七四)「筑波センタービル」(八三)「バルセロナ・スポーツ・パレス」(九〇)など多くの話題作がある。一九七〇年代から八〇年代にかけて、一貫して近代建築批判を展開し、「建築の解体」「見えない都市」「大文字の建築」など様々なキーワードを提示するとともに日本の建築界をリードした。著書も『空間へ』、『建築の解体』、『建築の修辞』、『建築という形式』など極めて多い。
*15 丹下健三。一九一三大阪~。日本を代表する建築家。東京帝国大学を卒業(三八)後、前川国男の事務所に勤務。同大学院卒業(四五)。一九四六年東京大学工学部建築学科助教授(四六)、東京大学工学部都市工学科教授に就任(六三)、東京大学名誉教授(七四)。その間、丹下健三都市建築設計研究所を設立。日本の近代建築は彼によってつくられたといっても過言ではなかろう。広島平和会館(五五)、東京都庁舎(五七)、香川県庁舎(五八)、国立屋内総合競技場(六四)、山梨文化会館(六七)、赤坂プリンスホテル(八三)、新東京都庁舎(八七)。その他、海外二〇数カ国にプロジェクトをもっている。日本建築学会賞、国際オリンピック委員会功労賞、イギリス王立建築家協会ローヤルゴールドメダル、朝日新聞朝日賞、アメリカ建築家協会ゴールドメダル、フランス建築アカデミー・ゴールドメダル、文化勲章等、受賞多数。
*16 大谷幸夫▼おおたにさちお▼《1924東京~.》◇建築家、都市計画家。1946年に東京大学建築学科入学、以後60年まで丹下研究室に在籍する。56年、建築家の運動体である五期会の設立に参加、その中心的な存在として活躍する。その後も一貫して、建築、都市のあり方をめぐって発言を続けている。61年、株式会社・設計連合を設立。64年~84年東京大学都市工学科で教鞭をとる。「国立京都国際会館競技設計」において最優秀賞を受賞(63)。「金沢工業大学」(66)「川崎市河原町高層公営住宅団地」(68)、「沖縄コンベンションセンター」など作品多数。
*17 原広司▼はら・ひろし▼《1936長野県~》◇建築家。東京大学生産技術研究所教授。東京大学建築学科卒業。「田崎美術館」で日本建築学会賞(86)。「ヤマトインターナショナル」(87)で村野藤吾賞。91年「JR京都駅ビル再開発設計競技」において一等入選。「飯田市美術博物館」(88)「新梅田シティー・スカイタワー」(92)「内子町立大瀬中学校」(92)など作品多数。また、世界の住居集落についての研究を展開してきた。主な著書に「建築に何が可能か」(67)「空間<機能から様相へ>」(87)などがあり、建築理論家としても知られる。
*18 西沢文隆 一九一五滋賀~八六。建築家。東京帝国大学建築学科卒業(四〇)。坂倉準三建築研究所入所。坂倉建築研究所設立(六九)代表取締役(~八五)。日本芸術院賞(五九)。日本建築学会賞(六六)。『西沢文隆小論集』全4(七四~七六)。『伝統の合理主義』(八一)など。
*19 拙著、相模書房、一九八一年。増補改訂『戦後建築の終焉』、れんが書房新社、一九九五年。
*20 西山卯三▼にしやま・うぞう▼《1911~一九九四。》◇建築学者、建築家。京都大学名誉教授。京都大学建築学科卒業(33)後、石本喜久治事務所、住宅営団研究部を経て、京大講師、営繕課長。戦後同大学助教授、教授を歴任。学生時代にDEZAMというグループを組織して以降、青年建築家連盟を始め、戦後の新日本建築家集団(NAU)など、一貫して建築運動に関わる。食寝分離論に代表される住宅計画理論を確立するなど、日本における住宅研究、住宅問題の理論的研究の権威としての位置を占めてきた。『国民住居論攷』(43)、『これからのすまい』(47)を始めとする住居論の他、地域空間論、建築論、建築家論などに関する著作も多い。
*21 拙稿、「世紀末建築論ノートⅤ デミウルゴスとゲニウス・ロキ」、『建築思潮』01、一九九二年一二月。
*22 拙稿、「阪神大震災とまちづくり……地区に自律のシステムを」共同通信配信、一九九五年一月二九日『神戸新聞』、「阪神・淡路大震災と戦後建築の五〇年」、『建築思潮』4号、1996年、「日本の都市の死と再生」、『THIS IS 読売』、1996年2月号など。