高口恭行 願わくは諸々の衆生とともに,新たな建築家像を目指して 布野修司対談シリーズ7,日刊建設通信新聞社,19970512
13*400-450 5850字 14.625枚
布野修司対談シリーズ
新たな建築家像を目指して
高口恭行
願わくは諸々の衆生とともに
中道の建築を目指して
摂取不捨 理偏処中
高口先生の名前は学生の頃から知っていた。『第三の建築家』という本をよく覚えているのである。京都に移って御手紙を頂いたり、パーティーでお眼にかかったりしたことはあるけれど、お話をうかがうのは初めてであった。心強かったのは、この間一貫して「第三の建築家」の道をつき進んでこられたことである。現在全力投球する大阪・下寺町のまちづくりは豊かに実る予感がある。まちづくりと建築家のひとつのモデルである。
僧侶で建築家。重源を思い起こすまでもないだろう。日本建築の歴史においてお坊さんの果たした役割は大きい。今日、僧侶の果たす役割はなにか。建築家の果たす役割は何か。建築家の世界は解脱したとおっしゃるけれど、どうして僧侶で建築家であるという渾然一体となった仕事ぶりにある建築家の気のようなものを感じることができた。
中道の建築、ほどほどにしいや、というのはわかりやすいけれど、中道に耐えることの方が難しいような気にもなった。
大阪の個性・・・茶臼山下寺町歴史文化プロムナード構想
布野: 今一番興味とエネルギーを使っていることというと、やはりお寺のことですか。
高口: 茶臼山下寺町歴史文化プロムナード構想。名前はどんくさいけどね。この一心寺から北へ大蓮寺まで二五軒の寺がある。それを整備しようというわけです。
布野: 行政との仕事なんですか。
高口: 風致地区なんですけどね。歴史の散歩道になってるけど何もしてない。僕の認識だと大阪の個性のような場所だ。まず、それを顕在化させたい。一心寺シアターというぼろ小屋があるんですが、文楽劇場まで、いくつか劇場をつないでいく構想もある。勝手に始めたんです。かかりっきりなんです。
布野: オートバイタウンですか。いま、表通りにはオートバイやさんが集中してますね。
高口: 前は自転車やさんが多かった。しかし、下寺町の真ん中には昔は藤原家高の夕陽庵というのがあったんです。夕陽を拝んでた。大阪で自然を語るとすると夕陽しかないんじゃないか。だから、まず上町大地へ至る坂を顕在化させる。
布野: 緑のスタディーもされていますね。
高口: 緑も多いんだけどみな寺の中だから一般の人の眼に触れない。
布野: 二五軒のお寺さんは賛同されているんですか。
高口: キー・ポイントをつくね。ここはみな浄土宗だから宗派の違いはないけれど、並んでいるからって足並みが揃う分けじゃない。似たようなことをやってるけど同じことをやってるわけじゃない。大学の教官室が並んでいるようなもんです。それでも、今年の春の彼岸の時に、難波人形劇フェスティバルというのをやった。各寺の本堂に人形劇団を呼んできて、普段閉じているのを開こうと。テレビや新聞とかにも報道されて少しづつ一緒にやろうという雰囲気が出てきた。まあ、じわじわとです。
布野: お寺の町内会みたいな組織ですね。ソフトが動き出した。
高口: そこでハードも動かそうということになる。大阪市も総合計画の中で重視している地区ですから、案を出してくれという話がある。それならと、たたき台をつくろうとしてるところなんです。
僧侶建築家・・・寺の今日的役割
布野: 住職で建築家ということなんですが、他にもいらっしゃるわけですよね。
高口: GKの栄久庵さんとか、京大の一年後輩だけど知恩院の坂本さんとか少なくない。しかし、坊主だと公言しているのは少ないでしょうな。師匠である先代に、僧侶であることを隠すとためにならんぞといわれたんです。
布野: 最近、京都の法然院の梶田貫首とお近づきになれたんですが、コンサートをやったり、色々お寺を開く努力をされている。もともとお寺は社会に開かれていたわけですね。
高口: なにかにつけて坊主は葬式ばっかりやっとると言われる。ただ弁解がましい意見はあるんだ。大阪の人口は、江戸の末の頃の一〇倍になってる。寺の数も、本堂の大きさも変わっていない。檀家さんの数は本堂の大きさに比例します。坊さんの方は一生懸命でも、一〇人にひとりしかサービスできなくなっている。キャパシティがたりないから、今日的に組織を変える必要がある。檀家制度が会員組織なら公開制にしていく。
布野: 一心寺の場合、むしろ大衆に開かれてきたんじゃないですか。
高口: それも江戸末以降のことです。ソフトは解放。でもハードの建物が限定されている。二万人の参詣者があって、本堂が五〇〇人。どうしようもない。だから、下寺町のまちづくりもご奉仕じゃないんです。空間が足りない。寺にとっては死活問題だと思っているんです。
職人がいない
布野: お寺に対する期待として、もうひとつ、建築の職人さんの技術の継承を考えて欲しいということがある。京都だとお寺に期待するしかない気がするんです。お東さんなんか全国に末寺があるから寺の維持管理システムの構築や職人の育成をやってほしい。
高口: そう思うけど、職人文化の維持継承に賭けようという状況ではない。京都の事情と大阪の事情は全く違う。植木屋さんそのものがおりません。公園屋さんになっている。僕の方が知っている。石を積むのにモルタルを使う。かなり技術は落ちてる。苦労しているんです。
布野: 守るべきものがすでにない。
高口: 瓦も凋落一方ですね。けらばのところがきちっとそろわない。
布野: 淡路の山田脩二さんところへ行かれたと聞いたんですが。
高口: いま、瓦は岐阜なんです。堺にいい瓦屋がいたけどつぶれてしまった。大変な状況です。
DPGの山門
布野: 斬新な山門ですね。立体トラスとDPG(ドット・ポインティッド・ガラス)の屋根は日本で唯一でしょう。働いている職人さんが自慢してました。
高口: 何故、木造でないかというと法規の問題ですね。基壇のところは、もともと茶所と駐車場だった。その間に山門があった。伝統的なものであるとそのサイズものしか建たない。上のところは境内野外ステージになっている。二万人のための建築なんです。
布野: 門というより複合建築ですね
高口: 建築家というより住職としての意向が強いかもしれません。昔、大阪に小西頼山という俳人がおったんです。今宮のほうから読んだ「しぐるるやしぐれのなかの一心寺」という歌がある。一心寺の上だけが晴れている、といった意味ですが、いま、向こうの方から見えない。建物も目立たない、活動も目立たない。とにかく、目立たなあかんわけですこの建築は。
布野: ランドマークですね。
第三の建築家
布野: 『第三の建築家』という本をかかれてますね。
高口: 万博の頃ですかね。一貫して思っているのは、何故、建築というのは浮き上がっているのか、ということです。機能主義の全盛時代だったんですが、裸の王様的だ。庶民感覚からづれている。何故、づれるのか、僕の考えてきたことはそれしかない。
布野: 奈良女子大で教えられるわけですが。
高口: 住宅の設計とか、住宅団地の設計ですね。計画学の理論があるけれど、あれはあれでひどく美しくないし。
布野: 西山夘三流のリアリズムも庶民感覚とづれていたわけですか。
高口: 僕は単純に理解してたんですよ。計画学というのは五〇〇分の一とか、一〇〇〇〇分の一の世界でしょう。所詮基本計画のレヴェルです。さわったり、階段を歩いたりという話にはなりにくい。勾配とか踏面の話はするかもしれないけれど手摺のさわり具合は飛ばしてしまう。材料も触れない。その辺をつなぐ人間がいる。今日ではすっかり言わなくなったけれどアーバン・デザイナーなんです。センス的に言っても、美学の話と庶民感覚でいうところの環境問題とか身障者問題であるとか、伝統的な和の様式とかをつなげるのは建築家なんです。
布野: それが「第三の建築家」ですね。
高口: いま、アーバン・デザイナーですというと、え、と言われる。昔の名前で出ています、あれですわ。
アトリエ・カサから造家建築研究所へ
布野: 奈良女には一七年半おられたんですね。やめられたのは教師と住職と建築家が鼎立しがたくなったということですね。
高口: まさしくそう。それに五〇歳になるということもありますね。振り返って中途半端だという思いがあった。住職で建築家に徹しようと覚悟したんです。
布野: 住職と建築家と時間配分はどうなんですか。
高口: 三食ともこの辺で食べるわけです。区別がないといったほうがいい。奈良女の時は、朝は坊さん、午後は教員、夜は建築家といってたけど、今はそういう必要がない。来年は骨仏をつくるんですが、そのことを考えながら建築やってる。渾然一体です。奈良女は居心地はよかったんですけど、実施設計ができないんですね。それで研究所をつくった。
布野: なぜ造家なんですか。
高口: 京大の大学院のころ、下宿に集まったのがグループ・カサなんです。増田先生のとこの仲間とか川崎先生のとこの笹田とか上田先生のところの学生とか。いま大阪芸術大学の田端修とかね。何をしてたかゆうと酒飲んで騒いでただけ。建たなかったけれど設計料もらったりしてた。
布野: そんなことあり得たんですね。
高口: その頃、日本学生会議というのがあって僕は少し動いてたから、その流れもあったんですね。その後、北白川の方にそれらしい空間をつくったんですが、その頃『第三の建築家』を書いたんですけど、少し出世してアトリエ・カサ。外に組織をつくる時にカタカナの名前は日本ではあんまり信用されないということをちらっと聞いて、日本語に直しただけです。思いとしては住宅をやっていこうということです。
布野: 造家学科、造家学と言っていたのを伊東忠太がアーキテクチャーの本義ということで建築といいだす。庶民感覚ということで先祖帰りなわけですね。
高口: 由緒正しいということもあるし、カサ・ブランカというのは地中海の白い「アーキテクチャー・ウイズアウト・アーキテクト」の家々の原イメージもある。
理偏処中
布野: 今の日本の建築界をどうご覧になってますか。
高口: 僕は解脱しましたね。全くというと語弊があるけれど、大学を辞めた段階で関心がなくなりましたね。
布野: 解脱されたと言われると、話の継ぎようがないんですが。ポストモダンはどう評価されてたんですか。
高口: 共感を覚えてました。歴史的連続感、庶民感覚からみて可能性があった。ただ、極端に行くんですね。釈迦が生きていた頃の言葉に「理偏処中」という言葉があります。「偏りを離れて中道に処する」。何故か、建築は中道にとどまらない。いい線いってたけど挫折した。石山さんは大道芸というか、芸を売らないといけないという。磯崎さんはアートとしての建築という。どうも、中位に処するということを成り立たなくしている。
布野: 建築ジャーナリズムは芸人好きですから。
高口: だけど、ほんとにそういう職業はいるんだろうかと僕はずっと思っている。僕は知り合い関係、お寺の関係のネットワークの中で生きているから余計そう思うのかもしれない。
摂取不捨・・・ほどほどにしいや
布野: 建築の方法も関係しますよね。仏教の教えの中にも建築に関わることは多い。
高口: 一番大きいのは、切り捨てられないということです。摂取不捨。例えば安藤忠雄さんはあらゆるものを摂取せず捨てまくりますよね。僕は何も捨てられない。そこに木があるでしょう。工事に邪魔になるけど伐れない。移すことはあってもどっかに使います。そうしますと、出来上がったものは確かにシャープにならないですね。
布野: 共生(ぐしょう)という仏教の自然観ですね。
高口: 関西弁でいうと、ほどほどにしいや、ということにつきる。
布野: 仏教建築で何か、惹かれるものがありますか。
高口: ヴェニスの小さな島に中道のいい礼拝堂がありましてね。京都の寺町にお寺を真似してつくったんですよ。
布野: ビザンチン様式の寺ですか。仏教のコスモロジーを表現するという一派がいますね。曼陀羅パターンで。
高口: 密教系ですね。ヒンドゥー教なんかもそうですが、釈迦仏教は少し違う。非常に多様な価値観が共存するけれど曼陀羅は神々の場所が決まってるんですね。摩訶不思議の世界なんです。
布野: 当面、下寺町にかかり切りですね。
高口: まあ、この界隈で生きていくんですから、ちびちびしたことを続けていきますよ。この場所が安定したら、コンペなんかもどんどんやりたいんですけどね。これは活動ですから、『新建築』なんか載らないでしょうね。扱いにくいでしょうね。しかし、これは普通のことなんですよ。格好よすぎりかもしれないけれど、「願わくば諸々の衆生とともに」ということですね。なんで俺だけがやらないといけないんだ、という思いもある。みんなでやっていきたいんです。
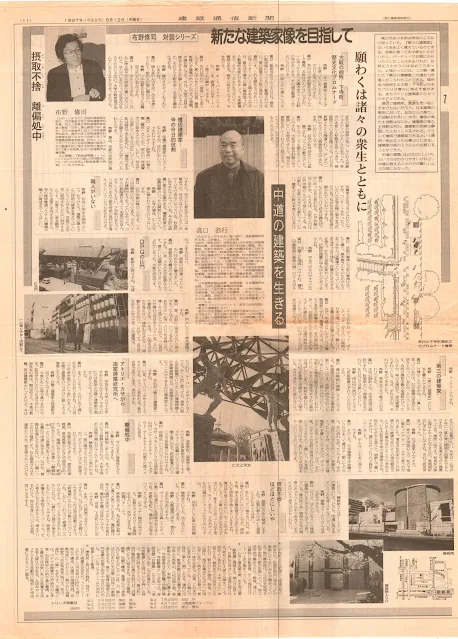



0 件のコメント:
コメントを投稿