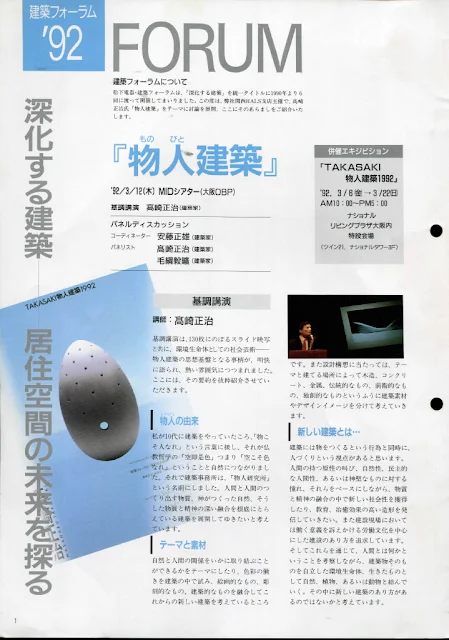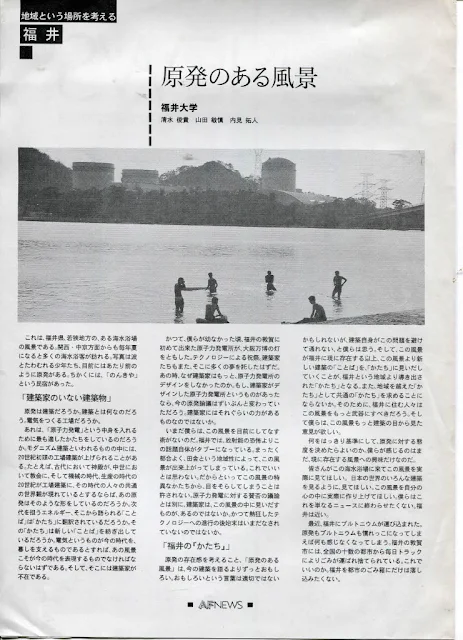地球の行方--東南アジア学フォ-ラム,雑木林の世界32,住宅と木材,(財)日本住宅・木材技術センター,199204
雑木林の世界31
地球の行方
東南アジア学フォーラム
布野修司
京都大学に東南アジア研究センターという研究機関がある。設立は一九六六年で昨年二五周年を迎えた。この東南アジア研究センターには印象深い思い出がある。東洋大学で東南アジア研究を始めた頃、東南アジアについて右も左もわからず手がかりを得たくて何度か通ったのである。その頃、一九七九年から八一年にかけてだったと思う、センターでは学生や若い研究者を対象とした夏期セミナーを開講しており、それを受講するのが主目的であった。今振り返ると、渡部忠世、高谷好一、前田成文、矢野暢といったそうそうたる諸先生から東南アジア学の手ほどきを受けたことになる。実に幸運なことであった。
その東南アジア研究センターで昨年「東南アジア学フォーラム」が開始された。これまでのプログラムは以下のようである。
●第一回 一九九一年九月一八日・・国民国家の政治文化 土屋健治 ディスカッサント 山室信一/世界単位概念の設定 高谷好一 ディスカッサント 応地利明
●第二回 一九九一年一一月一六日・・アダットと人間関係 前田成文 ディスカッサント 宮本 勝/マレー世界の自然と文化 古川久雄 ディスカッサント 田中二郎
●第三回 一九九二年二月一五日・・東南アジア的人口史観 坪内良博 ディスカッサント 足立明/地球資源・環境問題と南北問題 福井捷朗 ディスカッサント 森田学
最初の二回は、ばたばたしていて出席できず、三回目にようやく参加できたのであるが、全国から百人もの研究者が出席する、なかなかに刺激的な会であった。鶴見良行氏、中村尚史氏の顔も見えた。東南アジア学フォーラムは、単なる研究会ではない。東南アジアに関する知識を深めるというのではなく、現代世界の問題を如何に解くかをめぐって、思い切って発言し、議論する場として設定されている。実に魅力的なのである。
とりわけポレミカルであったのは、福井捷朗氏(東南アジア研究センター)の報告である。またそれに対する森田学氏(京都文化短期大学)のコメントである。福井氏の報告は、地球環境問題に関する基本的考えの変遷をレビューし、とりわけ南北問題に焦点を当てながら資源問題を展望しようというものであった。
環境問題に関わる主な出来事と見解の展開をざっと振り返った上で、検討に足るものとして、福井氏が取り上げたのは、ローマクラブの「成長の限界」(一九七二年)と国連のまとめた「持続的発展」(ブルントラント報告 一九八七年)である。ローマクラブの「成長の限界」における世界認識はいささか古いのではないかというコメントがディスカッションの時に出されたのであるが、氏の問題にしたのは理論構成であって、地球がそもそも存続し得るかどうかという大テーマなのであった。
ローマクラブの結論は、現在の成長率が不変のまま続くならば、「破局」に達するだろうということであった。そして、その提言は、「破局」に至ることなく持続可能な生態学的ならびに経済的な安定性を打ち立てることは可能であるということであった。その安定化の条件は人口に関しては出生率と死亡率が等しく一定であること、資本についても、投資率と減耗率が等しいこと、資源消費、生産および公害の汚染量は一九七〇年の四分の一となること、消費選好は物財からサービスへ向かうことなどである。
それに対して、十五年後に出された「持続的発展」論はどうか。その結論は、悲観的将来予測に基づくゼロ成長に代わって、環境資源を持続、拡大させる政策によって、従来とは異なった成長が可能であるというものである。発展の限界はある。しかし、それらは環境資源利用の技術および社会組織の限界と、生物界の許容限界とであって、前二者が絶対的でない限り、限界も絶対的ではないというのが「持続的発展」論である。
二つは一見異なる。一方が悲観的であるのに対して、他方は希望的である。十五年の間に状況は果たして変わったのであろうか。福井氏は、二つの立論を詳細に検討して見せたのであるが、将来展望に関する限り、実は二つの論にそう差はないのである。そして、環境問題において、南北問題こそが決定的であるというのが福井氏の主張である。
「成長の限界」も「持続的発展」も、世界全体を平均化した指標によって問題にしているのであるが、例えば発展途上国だけを対象としてシミュレーションを行ったらどうか。破局は異なった時期に異なった形で現れる筈だ。既に南の国の一部には破局の前兆が現れているのではないかと福井氏は言う。南の国の破局によって、北の国の破局が先延ばしが可能になっている。南の貧困は、地球資源・環境問題の先取りの結果であると考えるのである。
下手な要約でホットな提起を伝えていないのであるが、森口学氏のコメントは、森林資源の問題に即して、以上を補足するものであった。
森口氏は、焼き畑農業などアグロフォレストリーの研究で知られる。これまで二回ほど研究報告を聞いたことがある。農業と林業の共存こそが生態学的に意味があるという指摘が記憶に残っていた。当日のコメントの骨子は、森林保全に関して、「持続的発展」のための三つの方向がこれまで出されてきているというものであった。
ひとつは今日の林学の基礎をつくった一八世紀ドイツにおける森林経営、ひとつは、イギリスがインド、ビルマといった植民地で展開した森林経営、そしてもうひとつがインドネシアのタウンヤ法と呼ばれる森林経営である。いずれもよく理解するところではないのであるが、ドイツの場合は市場価値の高い樹種を毎年一定生産するところ、農業と林業を有機的に関連づけ、共同体の植林労働をベースにするところに特徴があるという。それに対して、イギリスの場合、多種多様の樹種を熱帯林に近い形で植林するのが特徴だ。インドネシアの場合、多少理解できた。過剰人口を背景として労働集約的な焼き畑移動耕作をベースとするのである。また、森口氏が森林の農民的活用として推奨するのがジャワのプカランガンと呼ばれる屋敷林である。プカランガンとは、野菜、一年生の樹種、バナナ、ヤシ、用材といった形で多様な樹種が植えられる、生活に合わせた利用が可能な農地林である。
福井氏の結論とは何であったか。
「熱帯林の破壊は、南の持続的発展にとってマイナスであろう。しかし、南にとってだけの問題ならば、これほど声高には言わない。北をも含んだ地球全体にとってマイナスであるからこそ(温暖化、遺伝資源)、問題とする。しかし、同じく温暖化の原因となる化石燃料の使用に関しては、自らの成長を犠牲にしてまで規制はしない。ゴルフ場造成のために木を伐る国の人が、子供の学資をうるため焼き畑をする農民を非難するのは不道徳的である。」と氏はいう。それでは希望はあるのか。「できるところから始める」は、有効か。あるいは、全く異なった社会、経済、国家のあり方が要求されているのか。結論は、重く聴衆に開かれ、預けられたままであった。