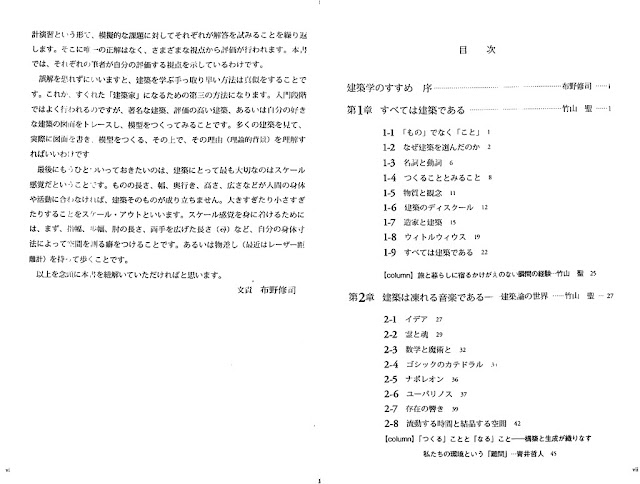traverse編:建築学のすすめ,昭和堂,2015年5月
このブログを検索
2022年7月18日月曜日
2022年6月5日日曜日
布野修司、西山良平、高取愛子 町家de春の京大トーク 京都「歴史」に住まう 『読売新聞』 2015年4月30日

▼西山先生講演
今回の町家トークでは「住まう」ということがテーマになっていますが、「住人」という言葉が初めて史料に出てくるのは985年です。つまり、人が「どこに住んでいるか」ということに重きを置くようになるのが西暦1000年頃ですが、実は平安京の町家も大体、同じ頃に成立したのではないか、と私は考えています。その頃、それまでの平安京とは断絶した、現在の京都の原型を生む非常に大きな転換があった。一言で言えば古代都城が衰滅して、道路と住人の結びつきが強くなったことが、町家が成立した要因なのではないか、ということです。
その前の時代、平安京では、1町すなわち120㍍四方の大きな空間(町)が細かく分けられ一般庶民に分け与えられました。そこに小屋あるいは小家と言われた町家(当時は町家という言葉は無く、町家の語が使われるようになるのは鎌倉時代)が作られるわけですが、それらは基本的には道路に沿って並ぶわけですし、それぞれの奥行きは小さいですから、必然的に奥に空閑地ができます。これはいわば多目的共用空間というべきもので、井戸やトイレ、洗濯物の干し物といったような空間になる。つまり四面が道に面した区画の内側に共用空間がある、今日私たちが「四面町」と呼ぶものが誕生する。その四面それぞれが自立して「片側町」として地縁を結び、さらに向かいの片側町と合体していわゆる両側町が誕生する。両側町の誕生はずっと後、応仁の乱の頃と言われますが、いずれにしても、西暦1000年頃に、町家の成立とともに「随近」「近辺」と呼ばれた地縁集団が誕生するわけです。
これが現在の町内会などと違うのは、刑事事件に対応して自分達で制裁を加えることもある、つまりは現在と比べて広範な権限をもった集団だったということです。時代が下るにつれ、裁判権などは国家の側に移っていきますが、それでも江戸の中頃までは、町家を売買するときには町の了解が要りました。つまり家屋敷の保全が両側町の役割だったわけですね。空間としての町家の特性やその今日的な意味については、高取先生、布野先生にお任せするとして、そうした暮らしをどう保全し、改善し、継承していくかということを考えるとき、町家の成立とともに誕生した地縁、今日の言葉で言えば町内会の持つ役割について、平安時代、中世、近世とは自ずと違った形にはなりますが、しっかり考えて行く必要があるのではないでしょうか。
▼高取先生講演
私は大学で研究活動をする傍ら、京都はもとより全国で実際の住宅設計をしています。言うまでもなく、生活や文化は地域によって異なるわけですが、そうした差異を個別性や特異性として強調しつつ、それらを包み込むことのできる器としての住まいには、日本中あるいは世界中、不思議なほど共通点があります。中でも京都の町家には、人が心地よく住まうための普遍的な技術が数多く見られます。
一般に京都の町家では、いわゆる「ウナギの寝床」と言われるような間口に対して、深い奥行きが目立っています。これは間口にかけられた税制度によるものと言われますが、こうした敷地形状の制約が、空間を豊かに見せるための様々な工夫や知恵を生み出しています。例えば、複数の庭を用いた伝統的平面計画は、都市化した街中集合居住への最適解を示しています。また、京町家に入るときは、少し頭を下げるような形で木戸をくぐった瞬間、一気に吹き抜けの垂直空間に投げ出されますが、京町家では、水平、垂直といった対比的な空間を並置することで、空間に抑揚がもたらされているのです。こうしたことは、現代的な課題のひとつでもある極小住宅の設計にも展開可能な事柄と言えます。
さらに言えば、そもそも時代時代の厳しい要請に応じる形で発展してきたこと、その発展が、住まい手と作り手双方を主体にして行なわれてきたという町家の発展過程そのものにも、今日私たちが質的に豊かな人間生活に立ち返るための、一つの大きな解が示されているように思います。売り手から一方的に供給されるマンションや建て売り住宅のそれとは対局にある、住む事に実直に向き合うことの重要性が示されているのです。
このような「暮らすための技術」は、空間や関係性に濃度というか、質的な湿り気(あるいはグラデーション)を与えるものであり、このような間(あわい)もまた、様式や形式をこえて、時代を超えた力強さを持っていると考えています。これからも残していくべき「京都らしさ」として、私はこうした点を強調したいと思います。
▼布野先生コメント
碁盤目状の都市、すなわちグリッド都市というのは、古今東西に見られます。アジア全体を見ますと、伝統的な都市は、大きく中国とインドの二つの都市形式に分かれますが、中国の形式は、日本、韓国、ベトナム、台湾に影響を与えました。京都は、その中でも大変精密な寸法体系を持っています。世界中を見渡しても、1000年以上の長きにわたってこの規模と繁栄を維持した都市は、京都の他にはほとんどありません。その秘密の一つは、この強いグリッドにあることは間違いありません。もう一つ、世界の住居をおおざっぱに2種類に分類すると、中庭型と外庭型というようなものに分かれます。西山先生のお話しにもありましたが、都市に住むためにはどうしても道路に面して並ばなければならない。そうすると、どうしても風と光をとる空間が必要になる。そこを作業スペースにする。そういうことで必ず中庭が出来ます。大きくいうと京町家もその系列ですが、高取先生が指摘されたように、京都の町家は、都市における狭小な住宅のあり方としては最適な解と言えます。
私は2004年まで京都大学にいて、京町家再生の活動にも取り組みましたが、そのときびっくりしたのは、巨大な合筆が起こったことです。土地というのは細分化されていくのが歴史だと思うのですが、小学校校区をまたがるような巨大なマンションが建つというような現象が起こった。もう一つ、京町家を今のまま建て替えようと思うとできない。消防法とかもろもろの問題があってそのまま再現するのは相当な壁がある。つまり、グリッドにしても町家に住まう技術しても、京都を今日まで持続させてきた普遍的な力というものが失われかねない。持続的な都市、持続的な都市生活というものを考えるとき、このことは、京都だけの問題ではありません。お二人がおっしゃるように、私たちが、都市に住まうと言うことに主体的に実直に向き合うことが大切になっているのではないでしょうか。
実は今日の会場になっているこの建物(西村家住宅)は、戦後日本における近世町家建築研究の嚆矢となった、故野口徹先生の研究対象となった建物です。偶然とはいえ、こうした場所で、私たちの住まいと暮らしの未来を考えることが出来たことは、まさしく京都ならではの、貴重な機会だったと思います。
プロフィール
西山良平(にしやま・りょうへい)
1951年、大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。著書に『都市平安京』など。
高取愛子(たかとり・あいこ)
1975年、岡山県生まれ。京都大学工学研究科付属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センター講師。1級建築士。
布野修司(ふの・しゅうじ)
1949年、島根県生まれ。前滋賀県立大学副学長・理事。『韓国近代都市景観の形成』『グリッド都市』で二度の日本建築学会著作賞を受賞するなど、多数の受賞歴を持つ。
2022年6月3日金曜日
2022年4月12日火曜日
戦後建築の70年「世界資本主義と地球のデザイン」『建築ジャーナル』2015年12月
戦後建築の70年「世界資本主義と地球のデザイン」『建築ジャーナル』2015年12月
戦後建築の70年
世界資本主義と地球のデザインー求められる大建築理論ー
布野修司
2015(平成27)年、戦後70年目のこの1年は、間違いなく歴史を画する年になる。
「安保法案」の成立(2015.09.19)が決定的な閾(メルクマール)である。戦後日本を支えてきたもの(「平和憲法(第九条)」に象徴されるこの国のかたち)、その存立根拠が否定されることで、その歴史を戦後の零地点にまで遡行し、改めて、戦前・戦後の連続・非連続を問わざるを得なくなる。
永続敗戦
戦後政治史の脈絡においてはっきりしたのは、白井聡の『永続敗戦論』(2013年)他が指摘するように、「戦後」が終わったということ、「戦後」という歴史の枠組みの終焉が宣言されたということである。「戦後政治の総決算」「戦後レジームからの脱却」は、既に1982年の中曽根政権以降唱えられ続けられてきたのであるが、「新体制」が目指すのは、「戦争を終わらせる」国制ではなく、「戦争ができる」国制である。フクシマ(2011.03.11)を受けて改正された原子力委員会設置法(2012.06)は、「我が国の安全保障に資すること」という条件を付されて、核技術の軍事利用に道を開くものでもある。沖縄の基地の固定化は全く顧みられることはなく、「非核三原則」もなし崩しにされつつある。浮かび上がるのは、戦前・戦後の連続性である。フクシマ(2011.3.11)で、また、新国立競技場をめぐる問題で露わになったのは「無責任の体系」(丸山眞男)である。戦時下に総力戦に突き進んでいったファシズム体制と同相である。実に奇妙なのは、原子力爆弾の投下(広島1945.0806、長崎1945.0809)による敗戦(1945.08.15)によって出発した日本が,徹頭徹尾アメリカ追従、アメリカ依存であり続けてきたことである。何故、保守でナショナリストを自認する勢力がアメリカに追従するのか(「親米右翼」「親米保守」)、その奇妙な捻じれについては、日本社会の基層に戦前に遡る分厚い闇があることを指摘すべきであろう。
戦前・戦後の連続・非連続
戦後建築の歴史を遡ることによって確認されるのは戦前・戦後が截然と分離されるわけではないことである。確かに、明治以降、西欧から日本に移植された様式建築、折衷主義建築は、戦後に全く設計されなくなる。しかし、稲垣栄三の『日本の近代建築』(1959年)がつとに指摘するように、また実際、その歴史叙述を戦前期で終えているように、日本の近代建築が育ってきた歴史は明治に遡る。そして、およそ1930年代前半には近代建築の理念と方法は共有され、それを実現する体制は成立していたというのが一般的な理解である。建築における近代化、産業化の流れは戦前期から一貫するのである。この近代化、産業化の流れについては、戦後大きく疑問視されることになるが、一方で、克服すべき課題と意識された建設業界をはじめとする重層的下請構造についても温存されたように思われる。「姉歯事件」(構造計算書偽造)そして現在大きくマスコミにとりあげられる「杭打ち偽装問題」など、日本の建設業界の体質はどうしようもなく思われるほどである。
決定的なのは、戦中期(15年戦争期)である。日本ファシズム体制が形成される中で、日本趣味や東洋趣味の建築様式、あるいは、大東亜建築様式などの概念によって建築様式の統制が行われる。いわゆる「帝冠(併合)様式」がその象徴である。この「帝冠様式」の評価をめぐって、戦前・戦後の連続・非連続の評価も分かれることになる。例えば、長谷川堯は、「帝冠様式」は、近代建築がそれぞれの地域に定着していく過程で出現する「盲腸」のようなものだとし、昭和期の建築を「昭和建築」=近代合理主義の建築と一括して規定し、全否定した上で、「大正建築」あるいは「中世の建築」を評価する構えを採った。
しかし、屋根のシンボリズムは単にキッチュとして切捨てることのできない建築の方法の問題に関わるし、ポストモダン建築の跋扈において、また、景観規制の問題として、戦後も問われ続けることになる。また、建築における日本的なるもの、あるいは建築と地域性をめぐる議論は、1950年代の伝統論争以降も繰り返し行われることになる。そしてさらに大きな問題は、「建築新体制」(1940年)によって、建築界の全体が総動員体制、翼賛体制に巻き込まれたことである。
建築の1960年代
戦後建築は、「戦後民主主義」「平和憲法」の下で、戦争責任の問題を深く問い詰めることはなく、日本ファシズム体制下の建築のあり方、そして、建築家のあり方を否定することによって出発することになる。そして、「帝冠様式」に象徴される様式建築、折衷主義建築を否定することがその前提であった。すなわち、「旧体制」(日本ファシズム体制)に対して、近代建築の理念を実現することがその目標とされた。しかしやがて、近代建築の理念が目指したものと建築(生産)を支える産業化システム(経済合理主義)の関係そのものが問われ始める。こうして、日本建築における連続・非連続の問題はいささか錯綜することになる。
『戦後建築論ノート』を上梓したのは1981年である。「1960年代(高度成長時代)の建築」をどう批判的に乗り越えるかを大きく問うた。すなわち、「鉄とガラスとコンクリート」による「四角い箱型(フラットルーフのラーメン構造)」(国際様式)の建築が世界中至る所に蔓延していく情勢とそれを支える近代建築の理念と方法への疑問(近代建築批判)が執筆のモメントである。そして、1973年と1978年の2度のオイルショックが背景にあった。拡大成長から縮小(低成長)へ、高エネルギー消費から省エネルギーへ、高層から低層へ、量から質へ、・・・建築をめぐるパラダイムが大きく転換する中で、新たな建築の方向を見出したいという思いがあった。
「ポスト・モダニズムの建築」(C.ジェンクス)と一括される建築の新たな多様な表現が産み出されつつあった。わかりやすいのはポストモダン・ヒストリシズム(脱近代歴史主義)と呼ばれる動向である。モダニズムの建築は単調で退屈だから、様式や装飾を復活しようという。しかし、問題は、単なるデザインの問題ではない。建築のあり方を全体として規定している産業化のシステムである。
1960年代の10年間は、日本建築の、戦後のみならず日本の歴史の一大転換期である。この10年の間に草葺屋根が消えた。アルミサッシュの普及率が0%から100%になった(空間の気密性が高まり空気調和設備が急速に普及した)。工業化(プレファブ)の割合が年間新築住宅の15%を占めるに至った。日本列島の風景は1960年代に一変したのである。
『戦後建築論ノート』は、1960年代初頭に一斉に「都市づいていった(数多くの都市プロジェクトを提案した)」建築家たちが、次第に「都市からの撤退」を迫られ、1970年代に入って住宅の設計という小宇宙に封じ込められるなかで、住宅の設計を「最初の砦」として、何が構想できるかを問い、地域の生態系に基づく建築システム、産業社会から廃棄されていくものの再生などを展望したのであった。
戦後建築の終焉
しかし、事態はその展望の方向へは動かなかった。1980年代から1990年代にかけて日本を襲ったのはバブル経済の大波であった。世界資本主義のグローバル展開の過程で、東京は国際金融都市となる。1980年代半ばの東京論の隆盛は、東京が決定的に変質したことによる悲鳴のようなものであったと思う。おそらく、戦後日本が最も「豊かさ」の幻影に酔った時代である。海外から有名建築家が次々に日本を訪れ、ポスト・モダニズム建築の徒花が跋扈することになった。
そして、バブルが弾けた。さらに、阪神淡路大震災(1995.01.17)が起こった。
『戦後建築論ノート』を増補(第四章 Ⅱ、Ⅲ)して『戦後建築の終焉―世紀末建築論ノート―』を出したのは1995年である。戦後建築界が積み重ねてきたものは一体何だったのか?という阪神淡路大震災の衝撃が大きい。1995年も、日本の都市計画、建築の歴史におけるひとつの閾である。ヴォランティアが出現したのは阪神淡路大震災によってであり、以降、住民参加、ワークショップ型のまちづくりが一般化していくのである。タウンアーキテクト(コミュニティ・アーキテクト)論をまとめた『裸の建築家』を出版したのは2000年である。
増補版では、1970年代、1980年代の日本の建築家の作品と活動をトレースし、その評価を試みた、拡大成長、格差拡大を駆動力とする産業資本主義のオールタナティブをさらに求めたいという問いは同じである。
1980年代半ば前川國男が亡くなった(1986.06.26)。そして、丹下健三が日本に帰還し、東京新都庁舎を設計し、「ポストモダンに出口はない」と発言したのは1980年代末である。戦後建築を担った建築家たちが次々に亡くなっていくことで、戦後建築の終焉が強く、意識されたことがそのタイトルに示されている。
建築のグローバリゼーション
そして、振り返れば、戦後建築の基盤は、1990年代初頭に大きく転換していたといっていい。日本では、昭和から平成への移行がある(1989.01.08)が、ひとつの閾となるのは1985年(昭和60年)である。この年、新築住宅戸数のうち木造住宅が5割を下回り、集合住宅が5割を超えた。1980年代は、1960年代に続く、日本建築の転換期である。しかし大きいのは、東欧革命(1989)、そしてソ連邦の崩壊(1991.12.25)という世界史の転換である。「歴史の終焉」が喧伝され、東西冷戦構造が収束した。
以降、世界資本主義の流れが加速化していくことになる。そして、1990年代に入って携帯電話が一気に普及し、ICT技術が世界のインフラストラクチャーになっていく。
増補部分の最期に主要に論じたのは、磯崎新の「デミウルゴス論」「大文字の建築」論、原広司の「均質空間論」「様相論」である。である。建築(生産、体制)の産業化に対する磯崎の「建築の解体」論、主題不在論、手法論、引用論…は、近代建築批判の大きな力になった。しかし、その批判は、一瞬の切断、仮構された平面での「建築」の自律性の主張に過ぎなかった。「大文字の建築」を殊更言い立てても、最早、どんな建築家であれ、特権的ではありえない。あらゆるデザインは、グローバリゼーションの波に飲み込まれることになるのである。
巨大な資本の流れが、世界中のタレント建築家を集め、CAD,CAM,BIMといったコンピューター技術が可能にした「アイコン」建築と呼ばれるようになる新奇な形の超高層建築や大規模建築が世界中に蔓延していくことになった。建築家そのものがブランド化し、作品ともども消費されていく状況の出現である。北京オリンピック(2002年)から上海万博(2010年)にかけての中国、リーマンショック(2008.09.15)以前のドバイがその象徴である。
地球のデザイン
21世紀の初頭、アメリカ合衆国の一人勝ちの状況が現れる。世界の警察を任じ、アメリカ合衆国が世界を制覇したかに見えた。そうしたなかでセプテンバー・イレブン(2001.09.11)起こった。イラク戦争が仕掛けられ、イスラーム勢力の抵抗も拡大していくことになり、世界各地でナショナリズムが抬頭することになった。中国が経済大国となり、アメリカの相対的地位が低下、世界秩序は機軸を失いつつあるように見える。そうした中で、どういう建築が構想できるのか。
フクシマ3.11の年、『現代建築水滸伝 建築少年たちの夢』(2011年)という本を書いた。僕より年上の建築家たち9人(集団)(安藤忠雄、藤森照信、伊東豊雄、山本理顕、石山修武、渡辺豊和、象設計集団、原広司、磯崎新)についての建築家論である。建築は楽しい、楽しかった、もっと楽しい筈だ、という思いに駆られて書いた本だ。本当は、若い世代についてももう一冊書いて、その可能性をエンカレッジしたいのだけど、未だ果たせていない。
アメリカ合衆国、中国、ロシア、EUが角突合せ、イスラーム国(IS)の伸長が大量の難民を生み出すなど、世界が蕩けていく中で、世界資本主義は自己運動を続けていくだろう。各国はそれをそれぞれに制御しようとするだろう。その過程で、ナショナリズム間の対立は激化していくだろう。そうした中で、我々に必要なのは、世界の枠組みであり、世界史の理論、そしてそれに基づいた大建築理論である。
『戦後建築の終焉―世紀末建築論ノート―』では、「地球」という枠組みについて触れて締め括った。今のところ、それを繰り返すしかない。戦後、石炭から石油にエネルギー資源が変わったのは1960年代初頭である。そして、1970年代のオイルショックを通じて、地球が有限の「宇宙船地球号」であることが共通の認識になった。そして、温室効果ガスによる地球温暖化の問題が具体的な問題を引き起こしつつある。さらに、人類が制御不可能な原子力発電の放棄が絶対である。いずれも、「地球」の存続という枠組みに関わっている。
「これからの建築の展開を枠づけるのは「世界」であり、「地球」であり、「宇宙」である。…具体的に振出しに戻って、「住宅の設計を最初の砦」としたとして、そこから「地球」のシステムを問うことなど容易なことではない。だがしかし、「より豊かな部分からなる<全体>へ向かうための、地域的、場所的部分を表現してゆこうという方法」を求めるにあたって、当然問題になるのは「全体」なのである。…いずれにせよ、「日本」というフレームが失効したことは確認した方がいい。あらゆる建築的営為において、遺伝子として、「地球」のデザインというプログラムが組み込まれているかどうかが問われる、そんな時代が今始まりつつあるのである。」
2022年3月21日月曜日
『図書新聞』読書アンケート 2015上半期 下半期
『図書新聞』読書アンケート 2015上半期 下半期
2015年度上半期
① 山本理顕、権力の空間/空間の権力、講談社新書メチエ
②黒石いずみ、東北の震災復興と今和次郎、平凡社
③渡辺真弓、イタリア建築紀行、平凡社。
①は、この間最も建築のありかたを根源的に問い続けてきた建築家の渾身の建築論。個人と国家の<あいだ>を設計せよ、が副題。雑誌『思想』における同題5回の連載がもとになっている。建築の社会的あり方を公私の空間のあり方、その境界<閾>のあり方に即して追求する。ハンナ・アーレントの一連の著作が読み解かれる。②は、東日本大震災後の被災地支援に取り組む筆者のグループが昭和戦前期の「東北地方農村漁村住宅改善調査」を中心に今和次郎の仕事の意味を問い直す。復興計画の現在と重ね合わせられることによって、その問題点が浮彫にされる。③はゲーテの『イタリア紀行』を下敷きにしたイタリア建築案内。イタリア旅行に必携の書。他に、絵本のなかまみちづくりの発想を読み解く④延藤安弘、こんなまちに住みたいナ、晶文社、など
布野修司(建築批評・アジア都市研究・環境問題)
2015年度下半期
① 藤本隆宏・野城智也・安藤正雄・吉田敏、建築ものづくり論 Architecture as “Architecture、有斐閣
②陣内秀信、イタリア都市の空間人類学、弦書房
③鈴木哲也・高瀬桃子、学術書を書く、京都大学学術出版会。
①は、「アーキテクチャー」概念を媒介とする経営学・経済学と建築学の共同研究の成果をもとにした新たな建築産業論。新国立競技場問題、杭打ちデータ偽装問題など建設業の抱える構造的問題が世情を賑わすが、日本型建築生産システムの成立を跡づけ、その強みと弱みを分析した上で、新たな「建築ものづくり」の方向を示唆する。②は、イタリア都市の建築類型学研究を出発点とし「空間人類学」の手法を確立、イタリアから地中海、イスラーム圏、さらに中国、東京・日本での膨大な調査研究を展開してきた著者の論集。③は、大学出版会において長年学術出版に携わってきた著者たちによる学術論。ノウハウ本の趣をとっているが、学術論文のあり方、専門分野のあり方、そして学のあり方そのものが問われる。評者は、『近代世界システムと植民都市』『大元都市』なだ何冊もお世話になり、鍛えられた。
布野修司(建築批評・アジア都市研究・環境問題)
2022年3月11日金曜日
「建築家は自分なりの武器を持とう」,特集 ネクスト:建築家のこれから⑬『JIA MAGAZINE』⑧,2015年6月
インタビュー:布野修司氏に聞く 聞き手:今村創平:「建築家は自分なりの武器を持とう」,特集 ネクスト:建築家のこれから⑬『JIA MAGAZINE』⑧,2015年6月
建築家は自分なりの武器を持とう
今回は長くアジアの建築・都市について調査・研究されている布野修司さんをお迎えしました。最近は、オープンな設計者選定のために、滋賀でいくつかのコンペに携わっておられます。今日は大きくその2点についてうかがいます。_ (『JIA_MAGAZINE』編集長 今村創平)
アジア調査・研究のきっかけ
今村 まずアジアについてのお話からうかがいます。最初に布野先生はどのようなきっかけでアジアを調査・研究されるようになったのでしょうか。
布野 僕の出自というか原点は建築計画学なんです。東大の建築計画研究室(吉武泰水・鈴木成文研究室)の出身ですが、1970年代初頭、研究室に入った頃、その歴史、方法をめぐって先輩たちが熾烈な議論をしていました。建築計画学批判ですね。その施設(インスティチューション=制度)を前提にした縦割り研究の限界についての認識が出発点です。住宅計画についていうと、太平洋戦争で東京が廃墟になって圧倒的に住宅が足りない状況で、日本の建築家は解答を求められたわけですが、建築計画学の解答は「51C」という公営住宅の型だったわけです。ダイニングキッチンDKという独特の空間はその後日本中に蔓延することになるわけです。大量供給のために住戸のプランを標準化したわけです。学校でも、図書館でも、病院でも、みんな似たような問題があって、戦後復興の際に基本の型を提案していった。「果たして同じ解答でいいの?」「標準設計でいいの?」というのが、1970年代初頭の研究室の議論です。
東大で2年助手をしたあと、1978年に東洋大に呼ばれたんですが、当時の学長は、前都立大学長で都市社会学の大家の磯村英一先生で、その磯村先生からうちの大学は「東洋大学」という名前だから、アジアのことをやるように言われたんです。冗談じゃなく本当の話です。当時、中国、韓国はとても調査する環境にはなかった。ソウルの地下鉄で写真を撮っただけで「フイルムを抜け」と言われるような時代でした。研究費の額の問題もあったので、とりあえず東南アジア、ASEAN諸国をターゲットにしたんです。
三宅理一とか杉本俊多とか、僕の東大の同級生は、東大闘争、全共闘運動の収束期にヨーロッパへ行くんです。僕は、同じことをやってもしょうがないから、アジアから問題を立てようと思った、個人的にはそういういくつかの動機がありました。
振り返って整理すると、同じ圧倒的に住宅が足りない状況で日本が出した答えとは別の答えがあるのではないか、それを探りたいということだったと思います。東南アジアにおいても日本と同じ組み立て方をするのか、2DKとか51C型が解答なのか、というテーマですね。
今村 それが70年代の終わりなのでしょうか。
布野 最初にインドネシアに行ったのは、 1979年でしたから、もう東洋大の講師になっていましたね。きっかけは磯村英一先生です。ただ、その前からずっと、ヨーロッパ、アメリカよりも、アジアをやるべきだとは思っていました。
今村 建築家がどんどんアジアに行くようになったのはその頃なのでしょうか。
布野 鈴木研究室には、アジアからは、韓国から 1人、台湾から 1人とかという程度で、日本からどんどんアジアに行くような状況ではありませんでした。アジアの都市建築研究が活性化するのは、アジアからの留学生が日本に来だした1980年代末くらいからですね。
今村 ということは、布野先生が行かれた頃は、ほとんどまだ誰もアジアに行っていなかったのでしょうか。
布野 原広司研究室の世界集落調査が建築界では早いんですが、東南アジア、東アジアはあんまり行っていない。戦後、賠償問題があって、ゼネコンなどをはじめ、日本の建築の分野がアジアに出かけたのは意外に早いんですけどね。建設産業としては、1950年代の末くらいから 60年代にかけて、例えば、インドネシアで大きな建築を建てています。アジアに行くには、従軍慰安婦問題もそうですが、触れてはならないタブーがありました。
今村 それは戦争の影響ということですね。
布野 そうです。フィリピンは反日感情が強かったですね。インドネシアはそうでもなかった。山の中へ調査に行くと、ラジオ体操をやってみせてくれたり、ベチャ(人力車)に乗ったら車夫が「海行かば」といった軍歌を歌う。スハルトが独立宣言文の草稿を練ったのが前田将軍のジャカルタの邸宅だったこともあって、インドネシアは割とウェルカムだったんです。それでも、 1972年の田中角栄のジャカルタ訪問の時には暴動があった。韓国とは今また険悪ですが、調査が本格的に可能になったのは韓流ブームくらいからです。
今村 確かに最近ですよね。文化交流で、 1990年代まであまり関係が良くなかったですね。
布野 そう、20世紀の末くらいからです。ただ、留学生はたくさんいました。中国は、ようやく留学生が来だしてから一緒に調べましょうという感じになりましたが、現在、また悪い。昨年、北京の町を調査していて、若い女性に「日本人は嫌い」と言われてショックでした。
現地の建築家や住民と協同
今村 具体的には、現地でどのような調査・研究をされたのでしょうか。
布野 都市組織(urban fabric, urban tissues)研究といっています。僕らの世代の言葉でいえば、デザイン・サーヴェイです。集落や都市の街区を対象として一戸一戸採寸して図面を起こし、インタビューを重ねます。一戸の住宅ではなくて、それが集合して構成される街区や集落の構成原理を明らかにします。1982年くらいからですが、科研費やトヨタ財団や清水建設の住宅総合研究所など研究財団から研究費をもらえました。学会というか、仲間の研究者たちから文化侵略だ、アジアを経済戦略する先兵だと批判も受けました。ただ、日本でやることとアジアをやることの区別は僕の中にはなかったですね。当初から「地域の生態系に基づく居住システムに関する研究」を掲げていたんですが、先見の明はあったと思っています。日本では1960年代の10年で、茅葺きが消えてアルミサッシの普及が 100%になった、都市、建築、住宅のあり方はすっかり変わってしまった。日本では民家というと民家園みたいなところにしか残っていないけれど、東南アジアではまだ生きていた、という感じでしたね。最初の数年は、ASEANを順に回りながら、大都市では都市問題、居住問題を、農村では住居集落のエコシステムを、二本立てで研究してきたんです。
今村 その頃はまだ、いわゆる現地での先行研究はなかったのでしょうか。
布野 ほとんどなかったですね。
今村 それでは何もストックがないところに行って調べたのですね。
布野 そうですね。当初は、情報収集いってみれば観光していたわけですが、インテンシブな共同研究をやらないと信用されないわけで、調査は一種のスパイですが、情報を持って帰るだけではなくて、カウンターパートと共同して、問題意識を共有する構えでやったのがインドネシアのスラバヤの臨地調査です。J.シラスという師匠に出会ったことが大きいです。
今村 それはインドネシアの大学と協同で調査研究をしたということですか。
布野 タイやフィリピンでも、インドネシアでも、当初は、住宅や都市の問題について、地元で一所懸命に頑張っている建築家や日本でいうと国交省や自治体、政府機関の政策担当者と会って情報収集をしたんです。そうしたなかで、J.シラスに会った。スラバヤ工科大学ITSの先生だったんですが、建築事務所も構えていました。歳は一回り上ですが僕の先生になりました。この夏もスラバヤに行って会います。カンポン(都市集落)調査が僕の原点です。学位論文もカンポンについて書きました(写真①abc 全部使えという意味ではありません。以下同様。写真①a難しければ、一枚トリミングしてください。あるいは、写真①書影がいいかも?)。
今村 他の国の建築家は、アジアにいたのでしょうか。
布野 1976年に国際連合人間居住会議が行われ、 78年に国際連合人間居住計画(国連ハビタット)が設立されるのでます。国連ハビタットの本部は今ナイロビにありますが、76年に設立に先行してマニラで面白いコンペをやりました。吉阪研など、日本からも相当応募しました。今日いうエコ・シティ、エコ・ヴィレッジをコンセプトとするオーストラリアの建築家グループが最優秀賞を獲るんですが、残念ながら実施に至りませんでした。1970年代末からアジアを歩きだすと、既にエコ・ヴィレッジなどのプロジェクトが実際ありました。日本はオイルショック後、そんなに新たな動きがなかったから、「えーっ」というくらい新鮮でした。また、コアハウス・プロジェクト(写真②ab)とか、セルフ・ヘルプハウジングが実際展開されているのも興味深かったですね。スケルトン・インフィル・クラディングのシステムが既に実践されているわけです。要するに、スケルトンだけ供給して、あとは勝手にやりなさいというシステムですね。そうした試みをするグループもたくさんいました。
今村 アジア各地にいたのでしょうか。
布野 タイのビルディング・トゲザー(写真③ab)、フィリピンのフリーダム・トゥ・ビルド(写真④ab)、インドネシアのディアン・デサなどですね。理論家はイギリスのJ.F.ターナー。会ったこともあります。それこそ“Freedom to Build”とか”Housing by people”といった本を書いています。
今村 いわゆる欧米のインテリがアジアに理想的なものをつくろうというような感じだったのでしょうか。
布野 それはあったかもしれません。例えば、バンコクのアジア工科大学AITに大学院大学がありますが、そこにはクリストファー・アレグザンダーの協働者だったシュロモ・エンジェルがいて、コアハウス・プロジェクトを主導していました(写真⑤)。それ以前に、C.アレグザンダーはリマのコンペで同様のアイディアを示していました。S.エンジェルは、一緒にやったんだと思います。『パタン・ランゲージ』も一緒に描いています。これは、2DKを提案するのとは異なる組立で面白かったですね。
今村 通算するとアジアに関わられて40年くらいになるわけですね。
布野 最初はいいカウンターパートに会って、当面、スラバヤに絞ろうということでした。その後、インドにまでフィールドは広がっていきます。様々な縁や状況の中で選択してきたような気がします。例えばジャカルタとかマニラなどの首都は、中央政府に近くて調査がすごくやりにくく、結構難しい。やはり距離を置いたほうがいいということがありました。
今村 ちょっと田舎の方が調査しやすいのですね。
布野 田舎の方が厳しい場合もあります。カウンターパートのJ.シラスの力が大きかったですね。彼は、インドネシア国家のハウジング部門のアドバイザーをやるようになります。アガ・カーン賞をはじめ日本の国際居住年賞、国連Habitat賞インターナショナルにいっぱい賞をもらうんです。いい人にめぐり会えたと思います。僕も、その後京大へ行って、論文を書く学生が増えて行ったので、インドくらいまで、範囲を広げていきました。
もうひとつは1980年代末にイスラーム研究が出てきました。これからイスラームが世界を握るだろうと日本の文部省も学者を集めたんです。僕もインドネシアを研究していたので呼ばれたわけですが、インドネシアはムスリムが9割なんですね。それでいっぱい仲間ができました。最後の締め括りの総括シンポジウムで「僕はスラムのことは多少わかりますがイスラームはわかりません」って言って、大受けしたことを覚えています。
今村 東洋大学だから東洋研究だとおっしゃいましたが、京都大学の中にもアジアの有名な研究所がありますよね。
布野 当時はセンターと言っていましたが東南アジア研究所があります。今はアジア・アフリカ地域研究研究科ASAFASがあります。 東洋大で研究を始める時に、東南アジア研究センターのサマースクールに参加して、一夏、東南アジア学の手ほどきを受けたんです。いろんな先生方と知り合いました。そういうこともあって、のちに京大に行くことになったような気がします。
今村 世界でアジア研究というのは3ヵ所あって、 1つはロンドン大学の
SOAS、アメリカに 1ヵ所、それでもう1ヵ所が京大なんですよね。軍事戦略と同じでアジアに対しての研究の先端をつくるのだということで。
布野 SOASにも行きましたが、戦前の満鉄調査部、東洋文化研究所にしても国策ですよね。東南アジア研究センターも日本にとってこれから東南アジアが重要だということでつくられました。そうした背景は当然意識化している必要があります。現在は、国家戦略としては、アフリカ研究が遅れているのではないかと思います。本当はアフリカ・スタディやインド・スタディももっとやらないといけない。必要な研究には研究費が付きますが、そうなると当然、それで何をやるのか、どういうポジションでどういうことを言うのか、何かやってみせないといけないことになります。僕もインドネシアのスラバヤでエコハウスモデルをつくりましたが、それもやはり ODA(政府開発援助)が付いたという背景があります。
スラバヤ・エコハウスは日本とは違う集合住宅モデルです。2DKを積み重ねるのとは違う。日本でもコレクティブハウスのモデルとなると思っています(写真⑥)。プルムナスPerumunasという日本の住宅公団に当たる機関に売込みにいったんですが、20世紀末に経済クライシスがあって、うまくいかなかった。少しオーヴァー・スペックで高かったんです。その後JICAも全部撤収したんですが、インドネシアは今景気がいいから、ちゃんとやったらいいと思います。
今村 そのスラバヤ・エコハウスはどういったものなのでしょうか。
布野 床に埋め込んだパイプに井戸水をソーラーバッテリーによるポンプで循環させる輻射冷房、ヤシの繊維を断熱材に使う、小玉祐一郎さんの指導ですが、一言で言えばパッシブ・エコハウス、考えられる要素をいろいろ盛り込んだものです(写真⑦abcd)。スラバヤは大阪と同じくらいの気温なのです。だから、そのモデルは日本でも使えると思っています。何度もいいますが、日本とアジアを区別しているつもりはなくて、最初からアジアなのです。
急激に変化を遂げたアジア
今村 ここ10~20年、アジアの国々がものすごい勢いで成長している状態があって、そこに建築家もある程度目が向いていると思うのですが、既にグローバルシティみたいなものをイメージして、ここにビジネスがあるように見ている場合もあると思います。それぞれの国や地域にずっとあったモダナイゼーションの歴史を見ようともせずに、グローバルなビルを現地でつくればいいとなってしまうことに対して、どのように考えていらっしゃいますか。
布野 発展途上国の第二次世界大戦後、あるいは20世紀に入ってからの歴史を見るとどこも似てきていますね。プライメイト・シティと言われる圧倒的に巨大化した大都市には同じような超高層が林立していますね。世界資本主義の表現といっていいかもしれません。一方、超高層ビル群の足下に、全く別の世界がある。資本主義は差異化のシステムですから、日本でも、東京と地方は全く違う世界に差異化されつつあるわけですが、アジアではどうか、グローバリゼーションが差異化していく世界を見てきている。
僕らは都市組織研究と言っていますが、住戸計画だけでは駄目じゃないか、住戸が集合する形、あるいは街区をみようとしてきています。最初に言いましたが、僕なりの建築計画学批判の視点です。住戸の平面だけ考えて、それを階段室の両側に積めばいい、という解答だけではない。場所、地域、国によって様々な都市組織の形、住居集合の形式があることをいろいろ見て、それを面白がっているのです。モダニズムの建築といっても、例えば、フラットルーフのガラス張りはやはり熱帯に合わないので、いろんなことをやり出す。それを「こういうのもあるんじゃないの」と一緒に考えているんです。
僕が一番親しいのはインドネシアですが、見ていると、
西欧化、植民地化の400年の歴史を積み重ねてきたものと全然違うものが現在出来てきている。それがグローバリゼーションの共通の問題ですね。それと建築学会で八束はじめさんとも議論しているんですが、コミュニケーション手段ICTが発達することで、拡張大都市圏(エクステンディッド・メトロポリタン・リージョンEMR)といいますが、大都市圏が農村部までだらだら繋がってしまうような新しい現象が起こってきている。スマホとバイクで都市の形ががらっと変わるわけです。これは次元を分けていったほうがいい。僕が現地を歩き出したのは、バイク以前で、インドネシアではベチャといいますが、リキシャー(人力車)が大都市を走っている時代でした。
I.イリイチだった思いますが「社会主義は自転車でやってくる」といって、人が余っているんだから自転車でドア・トゥ・ドアで行き来する、そのほうが地球にやさしい、オイルショックが強烈だったこともあって、ガソリンを使うよりも自転車で、というようなことを結構本気で議論していました。今でもやりたいけど、「何言っているの」という話になってしまうでしょうね。
今村 アジアの都市は、もちろん戦後から発展していくためにずっといろいろと変化してきたのでしょうが、やはり何か刹那的なものを感じます。
布野 赤道間近のシンガポールには、スラバヤもですが、ショッピングセンターにアイスリンクがあります。これから30億人もの人口が増えるのは熱帯地域です。そこで全てがエアコンを使い出すとするとエネルギー問題一体どうなるのか深刻な問題ですね。しかし、それを止められない。こちらは「エコハウスがいいでしょう」といって提案したら、「お前は、日本でエアコンを使っていないのか、なんで押し付けるんだ」と言われるわけです。
アジアには、地域の生態系で昔ながらの素朴でエコロジカルな仕組みが残っていたし、それに日本ももういっぺん学ぶべきだというのが問題意識だったのですが、今はそれが通用しない。正直言って、どう持っていけばいいかという事態が出現していると思います。
今村 日本では経済がずっとあまり良くないこともありますし、もう成長ではないと多くの人が感じて農業などに人々が目を向けるようになり、まさに地方の時代だという回帰があります。ただ日本の場合は、昔地域に根ざした農業などが、ある程度疲弊したところに今もう一回入ってつくろうとしているわけです。それで参考にアジアに見に行こうとすると、じつは、アジアも全然違った状況になっているということですね。
布野 日本と同じだと思ったほうがいいです。それがグローバリゼーションです。同時代的になっているから、ともに連携するとか協働するというように違う仕掛けじゃないといけないと思います。
歴史的、政治的な背景
今村 台湾では割と日本がつくった近代遺産を大事にしているという話がありますが、一方韓国では、日本がつくったものをかなり嫌って、存在を消そうとしているところがあります。アジア全般では、ヨーロッパ人が残した産業遺産や近代遺産みたいなものを受け入れているのでしょうか。
布野 それはケース・バイ・ケースですね。ジャカルタにオランダがつくったバタヴィア城がありました。東京と同じぐらい歴史のあるジャカルタは面白いし、素晴らしい景観もあります。そのバタヴィア城をオランダの研究者が「復元したい」と言ったら、インドネシアの建築家やジャカルタ市長たちは嫌だと言う。決めるのはインドネシアの人たちですね。僕らは、まず「運河をきれいにしましょう、昔を再生して環境を戻しましょう」、オランダ風の跳ね橋が残っているので、それは残したらいいのではないかといった議論には加わりました。長崎とバタヴィアは関係が深いし、「じゃがたらお春」の存在もあります。バタヴィア城の復元は面白いと思うんですが、オランダの植民地支配の象徴にはすごく抵抗感がある。
日本もそうですよね。各地にある城も封建制度の象徴だといって、明治維新以後つぶしてきました。姫路城でも二束三文だった。
今村 去年学生と韓国に行って、帰ってきてから気がついたのですが、ソウルの街に 20世紀の建築があまり見られないのです。やはり 20世紀前半は彼らにとっては日本の時代だから、その遺産を残したくない。そのあと戦後30年くらいは独裁期間だから、その頃のものも残したくない。彼らにとっては 20世紀の大半は振り返りたくない過去なのでしょう。ただ、今後を考える中では、その頃の研究がないことは大変ですし、韓国の人にとって20世紀の 8割が歴史から欠落していることは、なかなか厳しいことなのではないかと思いました。
布野 韓国には、日帝時代以前から、秀吉が朝鮮の建築を全部焼いてしまったというような歴史があります。ただ、それなりに建築家は育ってきています。キム・ジュコン(金壽根)は東京藝大にいて、その後韓国で空間社を設立します。そのお弟子さんたちがいて、僕と同い年だったチャン・セヤン(張世洋)という建築家、張世洋の後輩のショウ(承孝相)さんという建築家は空間社を継がなかったけれども、今結構いろいろな建築をつくっています。確かに日帝時代は日本がつくっていて、日本も近代化しながら韓国に持っていっていますから、だから日本化が近代化のようなところがあります。ただ、戦後ル・コルビュジエの事務所に行っていた人や、日本に来ていた人、そのあたりが僕と同じ世代で、そこから若いお弟子さんたちが出てきています。
今村 布野先生は韓国の本を出されていて(『韓国近代都市景観の形成日本人移住漁村と鉄道町』布野修司・韓三建・朴重信・趙聖民共著、京都大学学術出版会、 2010年)、日本化について触れられていますが、あのような研究は現地で抵抗がなかったのでしょうか。
布野 僕が東大の研究室にいた頃、先輩に朴勇喚先生が、漢陽大学で偉くなるんですが、同じような研究をしています。日式住宅についてですが、本国で発表できずに日本で出版しました。そのあとは都市計画制度を日本が持ち込んで制度史が先行したのです。ところが制度史だとソウルや釜山など大都市の話になりますから、我々は鉄道町や日本人の移住漁村を研究し、その頃は、もちろん韓国からの留学生がいましたし、韓流ブームもありましたから、調査もそれほどきつくなかったですね。
今村 それこそ、この数年だったら難しかったかもしれませんね。
布野 そうかもしれません。でも大学などアカデミックなところでは全然問題がなくて、そういうレベルでもいろんな話ができますね。
日本の建築家がアジアでできること
今村 アジアのお話の最後に、建築家はアジアで何をすべきか、また JIAの建築家はアジアでもっとこういうことをやればいいのではないか、ということはありますか。
布野 日本は今空き家がいっぱいあってストックの時代だし、メンテの時代ですね。身近な仕事だとリノベーションとかリニューアルしかありません。今の若手建築家は、デビューのチャンスがない。おそらく JIAの会員の若い建築家もまずはリノベーションから出発することになる。学生には、これから日本で仕事をしていこうと思ったら、まずメンテナンスでしょうと言ってきました。だから環境工学、設備工学を一所懸命に勉強しなさいと、絶対にそのほうが仕事がある。それと一方で「新築の建築をつくりたければアジアでしょ」とずっと言ってきました。建物が建つところでないと仕事ができないですからね。だから「まず中国、次はインドですよ」と言ってきた。アフリカや中東はいまのところいろいろ危険もある。中国には、僕が言わなくても、結構多くの若い建築家が出ていきましたね。ポリティカルな問題がいろいろあって、今は撤収気味ですが、一時期はみんな行った。ただ、海外でやる場合、どういう方法論、どういう理論をもとに何やるかが問われると思います。
インドネシアに行ったときには、現地で何ができるかを考えました。日本の戦後まもなく、建築計画学は、51Cという平面型を解答としたわけですが、材料も構法も考えないといけないと思いました。どこから材料を持ってくるか、現地で何が取れるか、次に、人々がどういう生活や暮らしをしていて、どういう空間を欲しがっているかを当然調べます。それは日本にいても一緒ですね。沖縄で設計する場合と北海道で設計する場合を考えても違うでしょう。気候を考えて、どんな建材屋さんがあるのか、どんな工務店の職人がいるのか調べるわけでしょう。それはアジアでも一緒です。
あとひとつはまちづくりです。少子高齢化で地域社会が衰退しているから、そのお世話をする。建築家はクライアントに対して仕事をしてきたわけですが、コミュニティを代弁して自治体とつなぐ役割がある。コミュニティ・アーキテクトですね。すでに JIAもそういうことを主張していると思うし、国際委員会もあるわけですから、アジアでやることは山ほどあると思います。日本の建築家は、アジアで様々な建築モデルをつくったりすることを、もっとやるべきだと思います。やる仕事はたくさんあるんではないでしょうか。
今村 日本でも建築家という定義が曖昧ではありますが、建築家といってアジアに乗り込んでも、それこそ、向こうの人は理解してくれないのではないかという危惧があります。例えば、ゼネコンが入ってアジアで仕事をするのと、いわゆるヨーロッパ的な概念の建築家がアジアに行った場合とどのような違いがあるのでしょうか。
布野 アジアといってもいろいろありますが、コモンウエルスのスリランカのモラトゥワ大、シンガポール大などはRIBAに準じてディプロマを取得すれば建築家の資格を与えます。マレーシアなども、留学する場合はみんなイギリスに行って、帰ると結構ヨーロッパ並みの待遇になる。東南アジアについては宗主国がヨーロッパだから、ヨーロッパへ留学するのが少し前までは主流でしたね。
今村 以前、いわゆるアトリエ系のような建築家がハノイにどれくらいいるのかと聞いたとき、 5人くらいだと言われたことがありました。
布野 ベトナムは、今は建築技術者が足りない。だから大学で建築学科の設立ブームです。そういうところに日本の建築家が教えに行ったらいいと思います。マクロに見たらそういうことで、建築系の技術者はどのくらいの層がいて、どのくらい必要で、どこで育てるかという問題ですね。
今村 一緒につくろうとか、技術を教えようというと分かりますが、クライアントから普通に住宅の設計を依頼されるつもりでアジアに行ったとしても、仕事にならないのではないでしょうか。
布野 何を持っていくかによるでしょう。つまり、腕と技術を持っているかどうかです。現地の職人のレベルとか、そういうものを全部受け入れたうえで、表現を組み立てられる能力を持った人が行くべきですね。
今村 スター建築家が招聘されるのとは全然違うわけですから、単にビジネスチャンスがあるからといってブラッと行って仕事になるわけではないということですね。
布野 大建築家が呼ばれて現地の建築家と JVでやったとしても結局みんな苦労しますよね。それは建築家と建築の関係はやはり「地」のものだということがあると思います。「地」をどう読んで、「地」からどう組み立てていくかについてはトレーニングが必要だし、 JIAからもそういう経験を積んだ建築家がたくさん出ていいと思います。
オープンなコンペを実施するために
今村 それではここからは、布野先生がいくつか続けて関わられているコンペについてうかがいます。
布野 1970年代に、家協会で公取問題がありましたね。会員の建築家が倫理規定違反を問われたわけですが、逆に業務独占について訴えられた。独占禁止法に引っかかるということで公正取引委員会が問題にすることになったわけです。僕は、家協会に所属する建築家が特権的に設計料率を決めているのは、実態としてダンピングがあるし、問題だと思っていました。また、倫理というのは団体の名において守るものではない、と思っていました。公取問題以降、国に業務報酬規定をつくってほしいということになっていきました。建築家は、いくらでも時間を使うし、知恵も使うし、もちろん建築家にも能力の差もありますが、それはそれとして、家協会は、一方で、公共建築の設計者選定のルールのようなものを主張していた筈です。けれども、首長さんとか自治体などが公共建築を発注するときには、どうもそうなっていかない。大学にいて、これまでいろんな設計者選定委員会に関係してきたんですが、なかなかすっきりしない。
デザインビルドと設計施工分離の問題、組織事務所対アトリエ派建築家、建築界に様々な対立構造があって、住民のための公共建築を選ぶ仕組みになっていない、と思うことがしばしばありました。世間では、コンペは談合システムと思われている場合もある。そうした中で、相談を受けると必ず提案してきたのが「公開ヒヤリング」方式です。これは一石三鳥くらいの仕組みだと今でも思っています。
可能な限り建築家に負担をかけずにアイディアを出してもらう、可能な限り若い世代に機会を与える、そして、もうひとつ、地域の建築家を基本に考える。その仕事の機会をむやみに奪わない。規模によって、技術レベルによって応募者の範囲を考慮する。大規模な新しい文化センターやオペラハウスなどと地域の小規模な施設の設計のランクを分ける。国際的な知恵を借りるもの、日本全国の知恵を借りるもの、地域の知恵でいいといったように分けた上で、可能な限りオープンにして進めていく、といったことが原則です。たまたま縁があって、滋賀県守山市の宮本和宏市長が建築学科出身だというので、「こうやってやればいいじゃない」と提案すると、「それは面白い、やってみましょう」ということになったのです。
今村 1つ目はどれですか。
布野 守山中学校で石原健也さんが最優秀賞を取りました(写真⑧)。次が守山市立浮気(ふけ)保育園で藤本壮介さんが取りました。最初守山中学校の案を募集したら、いかにコンペがなかったのか、応募が 100近かった。次の浮気保育園ではもっと増えました。
3つ目は、今度は市ではなく滋賀県で滋賀県近代美術館を増築する(滋賀県新生美術館)というので、知事に説明したら実施することになりました。プログラムが問題で、参加資格のハードルについてちょっとレベルが高くて頑張りきれなかったかもしれません。SANAAがとりました(写真⑨)。新国立競技場の場合も、技術的なプログラムの詰めが甘いから、今これだけ問題になっているのだと思います。
小学校や保育園というのは地元だけでもできます。市民、住民にもプログラムを分かってもらえて、こういう中学校をつくること、省エネはこういうことを考えていると知らせる機会にもなるんです。三日月知事もこれ以後、「公開ヒヤリング」方式でやれと言っていると聞きました。
その間に千葉の鋸南町(きょなんまち)で同じ方式でコンペをしました。鋸南町立中央公民館です。日大の広田直行先生、斎藤公男先生の仕掛けなんじゃないかと思いますが、「布野が面白いことをやっているから委員長にしろ」ということになって。 N.A.S.A設計共同体(NASCA+設計組織ADH+architecture WORKSHOP+空間研究所)が取りました。
今村 最近は、単に建設量も減っているからだとは思いますが、それを差し引いても 20年くらい前に比べてコンペが極端に減りましたので、このコンペのことは結構建築界で話題になりました。
布野 僕がやったのは島根方式といって、島根で 6つくらいやっているもので結構評価を受けていると思っています(写真⑩abcd)。新居千秋さんが取った「悠邑ふるさと会館」(1996)。それから、渡辺豊和さんが取った「加茂町文化ホール」(1994)などもあります。あとは高松伸さんが取った七類の「メテオプラザ」(1994)もそうです。あんまりやると、どうしても力量的に県外の建築家が取ってしまいますので地元としてはおもしろくありません。ですから、いろいろ仕組みをつくって、地元のこともちゃんと考えて JVを組むなどきちんとケアしないといけない。本当はそれぞれ県単位とかで、タウンアーキテクトのような存在をつくっていくことをJIAがやるべきだと思いますし、 JIAもそのようなことは、ずっと言っているはずです。
今村 各自治体の長の方がコンペをやりたい、でも、どこに頼んだらいいか分からないし、特定の人に頼むと問題がある。そんな時に JIAに頼めば、適切な運営の仕方をサポートし、そのときに審査員の推薦をしたりすることがもっと浸透すればいいのですね。
布野方式では、審査はオープンなのでしょうか。
布野 審査は公開で行い、1段階目はハードルを下げたオープンコンペです。お金は一切出さなくて、自発的に応募してもらいます。
今村 1段階目は完全に誰でも応募できるのでしょうか。それとも、一級建築士というだけではなくて、ある程度キャリアを持つ人なのでしょうか。
布野 それは場合によりますね。規模にもよりますし、例えば、 JIAとか建築士会などが主催する場合は、やはり資格を持っているという条件になるのはしょうがないことです。守山中学校のとき、竹山聖さんは「誰でもいいじゃない。中学生でもいいじゃない」と言ったけれど、さすがに地元のことを考えるとそれは難しいですよね。一定の資格をもっている人で、その資格用件はプログラムの内容や難しさで決めます。できるだけ広い知恵を借りるのが第1段階です。
今村 第2段階の審査も公開で行うのでしょうか。
布野 はい。その際には応募者にお金を出します。ですから何人選ぶかは予算によります。設計者はそのくらいの労力を使うわけだし知恵を借りるのだから、無償はおかしいと言います。
それと同時に、審査員も全員壇上で顔を見せます。ライバルが言うことも聞いている。下手なシンポジウムよりもよっぽど面白いですよ。緊張感があります。
通常は、一社ずつ密室に呼び込んでヒヤリングするわけですよね。時間もかかる。僕は菊竹清訓先生が最優秀を取った島根県立美術館のコンペの委員をしましたが、委員長だった大髙正人先生から「嫌なことは全部お前が聞け」と言われて、岡田新一先生とか、応募者の大先生に「ここが問題なのですけれど」と尋ねる嫌な役を全部引き受けたことがあります。
今村 それはクローズドなのでしょうか。
布野 クローズでワン・トゥ・ワンでした。
今村 周りは何を聞かれているか分からないのですね。
布野 周りにライバルがいたらウソや調子がいいことを言えないですから。
今村 布野方式だと、応募者同士お互いに意見を言い合ってもいいのでしょうか。
布野 僕が主催すると、振りします。コーディネートに力量が要るとは思います。
滋賀県新生美術館のときは、応募者の建築家が別の建築家に「これは費用がかかりますよ」と主張したんです。すぐ反論してもらいました。建築に詳しくない委員は、そういう意見を聞くと左右されてしまうこともあります。特に行政側の審査員は、「ああ、そうか。安いほうがいい」と思って票を入れるから、必ず反論してもらうようにします。滋賀県新生美術館の時は、それどころか、プログラムがおかしい、われわれの案しかない、という主張がありました。他の応募者の全員に意見を求めました。応募案が大きく分類できて、審査員にとっては、プログラムの当否も見直したうえで判断する材料になったと思います。
専門家が責任を持って設計者を選ぶ
今村 結果発表まで壇上で出すのですか。
布野 それはやりません。あくまでも審査委員会で専門家がやることを原則にしています。住民投票でもいいと言う人もいますが、様々な問題があります。すごくもめている敷地などでは当然反対派がいたりしますから、議論の場が成立しないのです。また、全ての住民に投票してもらえるわけでもありません。あくまでも、情報は全てオープンにしますけれど、決めるのは専門家の委員会です。説明責任は当然あります。その経緯は、委員長名で、全部文書で出します。クレームが出て、それが妥当であれば、審査委員会の責任となります。審査員が悪いということになるかもしれません。次はその人たちに審査員をさせないということになるでしょう。
今村 確かに全部オープンというのはフェアなようですが、逆にいうと、建築家もお互いに知っていますから、審査員は候補者を決めづらいですよね。どうしても気を使うというのが絶対にありますから。
布野 審査員の問題ですね。建築家が審査委員になると、次に逆の立場になるから、いろいろ勘ぐられてしまう。磯崎さんが熊本アートポリスでやったように、その地域では仕事をしない、という原則が成り立てばいいのですが。各県にいっぱい大学があるから、設計実務には直接関わらない研究者が審査委員をつとめるのが、一番現実的かもしれません。それこそ、JIAとか、AIJが支援すべきなんです。でも、仕組みとしてはそれほどお金がかからないし、すごくいいと思いますよ。設計者選定の仕組みを説明すると意欲のある首長さんはだいたい「おっ、やってみよう」となります。オープンにしたほうが議会を通りやすい。「こうやって決めましたよ」といえば、説明責任を果たしやすいはずです。
今村 役所も手間をかけずにやりたいわけですね。
布野 大きい組織のほうが安心なのです。事務局として、担当部署としてはやりやすい。また、安く簡単に審査したいから「実績」重視になっていくわけです。
今村 コンペのプロセスでも、いくつもの応募作を見てやりとりするより、あらかじめ決めて 5名くらいでやっていくほうが早い。おそらく、デザインビルドの問題もそうですが、自治体の力がなくなっているのかもしれません。あと、役所に建築の分かる人が減っていることは明らかなようです。
布野 JIAが頑張ってくれないと楽しくならない。昔は、特権性が気になっていたけど、今は応援しますよ。
今村 応援ではなくて、はっきり「 JIAは何をやっているんだ、 JIAがやらないから自分がやっているんだ」と布野先生に言っていただく方がいいのかもしれません。
布野 とにかく、特に若い人が建築家デビューできるようにしないといけない。
今村 若い世代に継続するシステムが、ちょっと今は壊れていると思います。ヨーロッパのある国では、コンペで候補者を 5名とすると、 1名は必ず経験がない設計者を入れなくてはならないという仕組みがあるそうです。コンペに落ちても若手に必ず経験させる。それを何回かやっていると取れるようになるというように、若い人を入れる決まりがあるようです。規模が小さいとか、経験がないから応募できるというようなコンペがあると良いですよね。
布野 それはいいですね。しかし日本の社会では難しいかもしれない。ないものねだりしてもしょうがないから、まず、トイレから始める。行政は手間がかかってもトイレをコンペに出す。小規模な公共建築をまず経験して、 1,000万円のコンペを取ったら、次は 5倍までの規模のものまでいい、その次は・・・という仕組みにすればいいと思います。結構有名な建築家だって入札不調とかいっぱい起こすわけで、批判も多いですからね。
今村 役所も継続して発注していないとノウハウがなくなってきて、そもそも 20年も建築家に頼んでいないから、面倒くさいからゼネコンに頼もうというように、デザインビルドは楽だという方向に行ってしまいます。
布野 規模によりますが、それこそヨーロッパでもかなりデザインビルドが増えているのではないでしょうか。
今村 アメリカが選択したことが大きいみたいですね。 AIAはデザインビルドを先行して認めたのです。
布野 建築学会にも発注者制度について研究している先生がいます。建築家も設計だけで勝負しようとしたって負けてしまう。小さな住宅スケールの仕事だけだと、設計料だけで食えないのははっきりしています。だから、C.アレグザンダーのいうアーキテクトビルダーがひとつの方向だと思ってきました。大谷幸夫先生も大工・工務店と連帯せよ、とおっしゃっていました。施工もやるし、材料調達や、それから物品の仕入れも、CMも PMだってあるわけだから、いろんなやり方をしていかなければならないと思います。建築家もそこが嫌いだと言っていたり、ふんぞり返って「アーキテクトでございます」と言っていたりでは、なかなか仕事は獲得できません。だから、僕は 2000年に『裸の建築家』(建築資料研究社)という本を書いたのです。建築家も自分なりの武器をちゃんと持っていてください、そういう意味です。
今村 今日は2つのテーマで、貴重なお話をいただきました。ありがとうございました。
(2015年6月2日 JIAにて収録)
布野修司(ふの しゅうじ)略歴
日本大学特任教授。1949年,松江市生まれ。工学博士(東京大学)。建築計画学,地域生活空間計画学専攻。東京大学工学研究科博士課程中途退学。東京大学助手,東洋大学講師・助教授,京都大学助教授,滋賀県立大学教授、副学長・理事を経て現職。『インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究』で日本建築学会賞受賞(1991年),『近代世界システムと植民都市』(編著,2005年)で日本都市計画学会賞論文賞受賞(2006年),『韓国近代都市景観の形成』(共著、2010年)と『グリッド都市:スペイン植民都市の起源,形成,変容,転生』(共著、2013年)で日本建築学会著作賞受賞(2013年、2015年)。
-
traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...