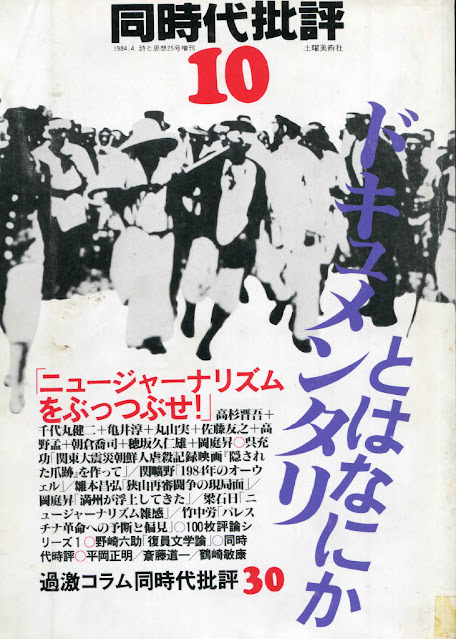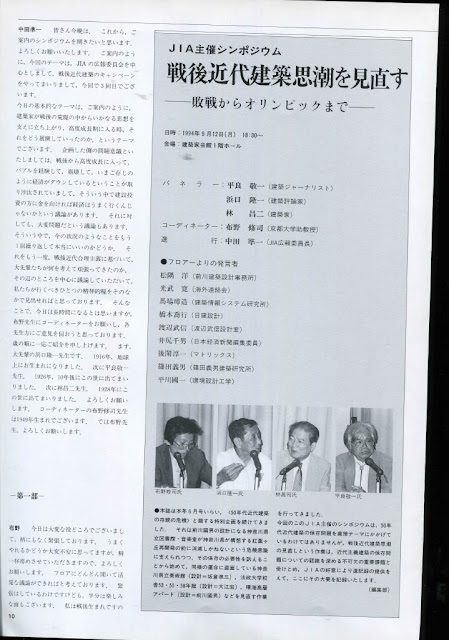このブログを検索
2024年3月6日水曜日
2024年2月18日日曜日
2024年2月17日土曜日
2024年2月15日木曜日
2024年1月26日金曜日
日本建築学会建築歴史・意匠委員会 戦後空間シンポジウム04 バブル・震災・オウム教 戦後空間の変質司会)中谷礼仁・山形浩生 バブル経済について・牧紀男「震災」とその後の都市行政・古賀義章(「オウム教」における経済活動システム コメンテーター)・石山修武(建築家・早稲田大学名誉教授)・布野修司(建築史家・日本大学特任教授) 建築会館会議室,2019年11月22日
戦後空間シンポジウム04
バブル・震災・オウム教 戦後空間の変質
中谷礼仁記 2019/03/11,3/28,
08/19改訂
趣旨)戦後空間とは戦後に展開する様々な史的シークエンス(クブラー)の束である。その束は流れつつ、時たま伏線が現れ、現象の質を変えていく。第4回目のシンポジウムは戦後空間の変質に目を向け、80年代後半から90年代を扱う。
バブルは戦後空間を駆動させた高度経済資本の成長が、イメージゲームにまで展開した。これは直近の政権が意図的に再現しようとしている方法である。
震災は公共福祉を目的とし邁進してきた建築・都市の法的精神を温存させつつも、安全と従来の生活文化に矛盾(例えば当時の坂本功の二者択一論)を生じせしめ、その後の建築行政のあり方(姉歯事件などにも飛び火)の方向性を決定した。
オウム教は「ユートピア」を目指す組織が、その実現にあたって政治権力のみならず一般市民までをも敵とした事件であった。これは戦後空間が保証してきた自由な表現活動一般に対しての大きな挫折となった。
重要なことは、それらが連動していたことである。
バブルは高度経済成長を基にしたイメージゲームと、その崩壊後の経済活性化政策両方を含む。双方は21世紀の特に大都市・建築の構想から実現までのシステムを大きく作り変える発端となった。
オウムは布教活動をその特権的経済活動と連動させ、コンピューター制作会社、巷のラーメン屋など様々な分野で暗躍し、社会活動のシミュラクルとして深く溶け込んだ。この影にはバブル経済のイメージゲームの手法が効果的に用いられていた。私は当時の秋葉原での彼らの暗躍の様子をよく覚えている。
震災は、その後の長田地区の再開発事例のようにボトムアップのまちづくりを実現させた。同時にその活動を法制的に受け止めるために、合意形成をむしろ官主導内部に展開し、手法化された。この方向のもとに、経済活性化のためにその後REIT、特区制度が導入され、設計手法は客観化、定量化、組織化され、現在の「実体」的イメージゲームのような高層商業施設が屹立し(イメージをサポートするかのように都市実体が作られ)ているが、それがどのように具体的に使われるかの検討は画一化し、希薄化している。またインディビデュアルな建築家による自発的立場は傍流へと追いやられている。
この三つの要素とその余波が絡み合うことで、戦後空間の変質が確固とした流れとして現れてきたと言えるのではないか。第4回目のシンポジウムは以上のような要素の出現がその後、現在までの戦後に与えた空間の特質を導きたいのである。
方法)シンポジウム形式、三要素それぞれに報告者を設定し、そのからまり合いが生み出した事象を再確認する。
司会)中谷礼仁
登壇者)
・山形浩生(バブル経済について、https://ja.wikipedia.org/wiki/山形浩生、1964-、翻訳・評論家、元野村総研開発コンサルタント、東大都市工学卒)
・牧紀男(「震災」とその後の都市行政報告者、京都大学防災研究所)
・古賀義章(「オウム教」における経済活動システムについての報告、1964-、講談社入社後『フライデー』在籍時に長期にわたりオウムを取材。2005年から『クーリエ・ジャポン』創刊編集長。記録写真を集めた『アット・オウム』出版)
コメンテーター)
・石山修武(建築家・早稲田大学名誉教授)
・布野修司(建築史家・日本大学特任教授)
以上
2023年12月15日金曜日
変わるものと変わらぬもの、布野修司編:日本の住宅 戦後50年, 彰国社,1995年3月
布野修司編:日本の住宅 戦後50年, 彰国社,1995年3月
布野修司
プロセスとしての住居
戦後50年、日本の住宅はどう変わったのか。身近に振り返ってみよう。この半世紀に日本の住宅は歴史的大転換を遂げたといっていい。それぞれの住宅遍歴の足跡にもその変化の歴史をうかがうことができる筈である。
1949(昭和24)年に生まれた筆者がどのような住宅遍歴を経てきたかについては実は既に書いたことがある。『住宅戦争』の「F氏の住宅遍歴」*1がそうだ。その都度場当たり的に住宅選択を積み重ねて来たように思っていたのであるが、それぞれの住居は時代の断面を浮かび上がらせて我ながら興味深いと思ったのである。
生まれたのは藁葺きの民家、祖父の家である。出雲地方(島根県)に典型的な田の字型プラン(四ツ間取り)である。向かいに納屋があり、奥に続く畑の入り口に牛舎があった。出雲地方の民家といえば、築地松の散居村が有名である。棟が緩やかに反っており、他の地域とは明らかに違う。こうして地域毎に特色を残してきた民家は、戦後50年を通じてほぼ失われるに至った。茅葺き、藁葺き屋根がみるみる消えたのは1960年代の10年であった。
生後8ケ月で移り住んだのが公営住宅である。1950年のことだから、ダイニング・キッチンを生んだ公営住宅の標準住宅51C型以前のタイプである。建築面積10坪。四畳半と六畳の二間に三畳の板の間と台所。戦後知られるようになった記号を使えば2D・Kだ。戦後日本の原住居といっていい住居である。床の間はなく、風呂もない。
この戦後日本の原住居に結局18歳まで暮らすことになるのだが、妹ができ、弟が出来て、親子五人ではいかにも狭い。増改築が行われるのは当然であった。住居(ハウジング)はプロセスなのである。
最初に風呂場を建てた。庭先に別棟で小さな小屋を建てた。自力建設である。近くの川原から小石を大量に運んできて割栗石にした。懸命に手伝った記憶がある。セルフビルド体験であった。大都市でも壕舎やバラックに1960頃まで住んだのだから、自力建設は何も珍しいことではなかった。最近では、余程余裕のある環境でなければ自力建設などできないだろう。
中学に入る頃、大規模な増改築が行われる。公営住宅が払い下げられることが明らかになり、持家になる頃である。所有意識とセルフエイド行為は明らかに関係している。また、小学校入学、中学校入学が増改築のきっかけになるのも一般的なパターンである。「成長する家」という概念は、公共住宅に取り入れられることはなかったのであるが、実にリアルな概念である。
しかし、よく住めたと思う。三年ほど前、京都の公務員宿舎に移り住んで3Kの空間を追体験するにおよんで、つくづく思う。住宅は広さなのだ。そして、環境なのだ、と。記憶の中の原住居の周辺には自然にみちていた。魚釣り水浴び、とんぼとりにメダカすくい、三角ベースやビー玉、メンコ、かくれんぼ・・・ありとあらゆる遊びの場所はそこら中にあった。兎も飼い、鶏も飼った。狭苦しかったという記憶はほとんどないのである。
上京して、民間の学生寮に住んだ。鉄筋コンクリートの5階建て80室。ワンルーム、作りつけのベッド。今なら、大規模なワンルーム・マンションといった方がわかりやすいかもしれないが、寮は寮であり、食堂と共同浴場、洗濯場、トイレ等は共用である。集団生活の最初のトレーニングの場となった(向かいの部屋に佐伯啓思がいた)。こうした集団生活の場も少なくなりつつある。集まって住む経験というのは一旦故郷を離れるとそう一般的ではない。
続いて、賄い付き下宿、木賃アパートと下宿遍歴を経て、庭先鉄賃、民間分譲マンション、そして、公団分譲住宅へ至る。「方荘号字」住み替え双六を辿った。一戸建てを建てる経験のみがまだない。
親が土地を所有するかどうかで住宅遍歴は全く異なる。職業によっても異なる。また、住んだ場所によっても異なる。二世帯住宅やコーポラティブ・ハウス、建売住宅、プレファブ住宅、入母屋御殿、・・・様々な住居形態は見られるけれど、およそ想像がつくのではないか。首都圏でここ1、2年で供給されるマンション住戸の平均的イメージは、3LDK、20坪である。面積的にはむしろ後退している。驚くべき画一化である。地域性を喪失し、画一化の度合いを強めてきたのが戦後50年の日本の住まいである。
戦後家族とnLDK
現代日本の家族と住居を象徴するのは、nLDKという単純な記号である。日本の現代住居のモデルとしてnLDKが成立し、定着したたことこそ戦後最大の出来事である。
このnLDKという住居形式とnLDK家族モデルはどのようにして成立したのか。誕生年がわかる。一九五一年である。51Cがその暗号だ。
51Cについてはよく知られていよう。51Cとは公営住宅の標準プラン(間取り)につけられた符号で、一九五一年のC型という意味である。何故、この51Cという符号が記憶されるかと言えば、この51C型において、日本の戦後住居を象徴するDK(ダイニング・キッチン)が生み出され、2DKが誕生したからである。
2DKはどのように生み出されたか、その原理とは何か。極めて単純な原理といっていい。食べる場所と寝る場所を区別することを第一原則とする、また、隔離就寝、すなわち、夫婦の寝室と子どもの寝室を分けることを優先する、そのために限られたスペースのなかで台所と食堂を一緒にする(ダイニング・キッチン)のもやむを得ない、というよく知られた食寝分離論*2がその基本原理である。公共住宅の住戸形式として考案されたこのDKという空間は、一戸建ての住居形式にも取り入れられ、近代住居のシンボルとしてあっという間に日本中に広まることになったのであった。
建築的原理としてのその後の日本の公共住宅の住戸形式の展開もわかりやすい。食寝分離→公私室の分離→個室の確保という分離の論理と規模拡大の論理がその基本にある。実際、モダンリビングと呼ばれる居間空間が住居の中心に置かれ、2DKから3LDKへ、日本の標準住居が移行していったのは1960年代のことである。因みに、日本住宅公団が「全国統一標準設計」を確立するのは63型である。すなわち、1963年のことであった。
日本の近代家族の成立をめぐって、戦前家族と戦後家族の連続、不連続の問題が議論される。日本の「家」制度は、決して封建遺制などではなく、近代において成立したものであることが主張され、戦前戦後の一貫性がむしろ強調される。家父長制の存続、一般的に言えば、近代家族に固有の抑圧性の存続がそこでの焦点である。また、核家族を近代家族の要件とするかどうかが問題となる。
しかし、住居形式をみる限りにおいて、戦前戦後の転換は明らかである。床の間をもった和室や玄関は戦後の過程を通じて決してなくなりはしなかったけれど、その床の間の空間はある意味でプラス・アルファのスペースで家長の場所ではなくなって行く。戦前において、明治末から大正のはじめにかけて、武家住宅を基礎にして成立しつつあった中廊下式住宅に対して、「居間中心型住宅」が提案されるけれど、必ずしも一般化したわけではない。銘々膳からチャブ台へという変化も明治中頃からはじまっているが*3、一家団らんがすぐさま実現したわけではない。「食卓の民主化」の契機になったのはやはりダイニング・キッチンにおける椅子とテーブルの食事形式の一般化によってである。ダイニング・キッチンそしてnLDKという明快な形で家族の形が規定されるのはやはり戦後になってからである。
このnLDKという住戸型がモデルとするのは核家族である。夫婦とその子ども、n人によってLDKを共有する形は、逆に、日本の戦後家族を規定していったということもできる。大家族制から核家族の自立、そして、核家族における個の自立という住み手の主体性の獲得を物質的に裏付けると同時に、戦後復興から高度成長期にかけて、都市化という社会変動を裏打ちしながら、労働力再生産の単位を一元的に核家族へと編成していく装置がnLDKでもあった。
戦後住居と建築家
戦後住居と建築家をめぐって振り返ってみよう*4。戦後まもなく、建築家にとって住宅の問題は最大の課題であった。住宅に対して、戦後50年、建築家がどう関わってきたのかは戦後建築史の大きなテーマである。
①戦後まもなくの、「住宅近代化」の指針は、浜口ミホの『日本住宅の封建制』(1950年)の「床の間」追放論、あるいは玄関廃止(玄関という名前をやめよう)論に典型的に示されている。また、最も包括的な指針となったのが、西山夘三の『これからのすまい』(1948年)の「新日本の住宅建設に必要な十原則」である。
②住宅問題に対するアプローチには、いくつかのレヴェルが想定されたが、「建築家」は、まず第一に、新たな住宅像の提示という役割を担うことになった。小住宅コンペにおけるモデル住宅の提案、最小限住宅のプロトタイプの創出に多くのエネルギーが注がれた。
③具体的な住居モデルの提示は、a.公的な住宅供給を前提とした回路、およびb.住宅の工業生産化を前提とした回路、そして、c.個別住宅設計の回路の三つにおいてなされた。三つの方向は、決して最初から分離していたわけではないが、やがて、その役割分担は明らかになっていく。a.は、集合住宅を対象とし、その住戸型、標準型をテーマとした。西山夘三とそのシューレ、吉武泰水とシューレなどが主体となる。b.は、戸建て住宅を対象とし、工業化手法そのものをテーマとした。前川国男(MID)、池辺陽、広瀬鎌二、増沢殉、内田祥哉などとそのシューレが先導的に担うことになる。
④「建築家」の住宅への関心は、しかし、1950年代に入って次第に薄れていく。ビルブームとともに、民間のオフィスビルや公共建築が主題となっていくのである。より具体的に、③のa.b.c.のそれぞれの方向をそれぞれ現実化する体制が用意されていったということがある。住宅金融公庫法の成立(1950年)、日本住宅公団の設立(1955年)、そして、ミゼットハウスの登場(1959年)である。
⑤基本的には、住宅の設計を原点とする建築家の真摯な活動は続けられるのであるが、近代住宅の現実化の過程で、日本住宅の伝統が問い直される。清家清らの「新日本調」、「ジャポニカ」の登場と伝統論争が1950年代半ばの状況を象徴する。近代住宅の理念を啓蒙していくモダニズムの立場と民衆の生活レヴェルからの変革を考えるリアリズムの対立がそこには既にあった。一般的には、小住宅作家として活動することが民衆の現実にアプローチする回路として重要視されていた。
⑥1960年代初頭、「建築家」の住宅との関わりは質的転換を遂げる。篠原一男の「住宅は芸術である」と八田利也の「小住宅作家ばんざい」が時代の転換を象徴する。1960年、年間新築住宅戸数60万戸。今日の水準からすれば、三分の一の数字であるけれど、高度成長期を迎え、圧倒的な量の建設が行われ始めたという背景がある。第一、1960年代を通じて、住宅産業が成立する。第二、日本住宅公団を中心とする公共住宅の供給が軌道に乗り出す。第三、建築家にとってアーバン・デザイン、都市計画が主題となる。ニュータウン計画も具体化されていく。日本の住宅のあり方をリードするのは住宅公団であり、1970年代以降、住宅メーカーがイメージ・メーカーとなって行く。そうした中で建築家は何をなしうるのか。作品としての住宅、芸術としての住宅がそこで仮構されたのである。
⑦1960年代を通じて建築家の関心は都市構成論に向けられる。そうした中で都市住居のあり方がテーマとなる。西沢文隆のコートハウス論、大谷幸夫のUrbanics試論がその代表である。しかし、その具体的な展開は大きな流れとはならなかった。建築家による住宅へのアプローチの次のステップのメルクマールとなるのが東孝光の「塔の家」である。理念のみでなく、都市に住むというしたたかな意志を建築化する象徴的な表現となった。1960年代末から1970年代始めにかけて、『都市住宅』誌が建築家と住宅の関わり合いのある断面を示している。プレファブ住宅が日本の社会に位置づく一方、建築家に住宅設計を依頼するクライアントが層として成立してきたことを示している。
⑧1970年代の前半に時代の転換点がある。それを象徴するのが毛綱毅曠の「反住器」であり、石山修武の「幻庵」である。それ以降、建築のポストモダンの流れが住宅において明らかになって行く。また、原広司の「最後の砦としての住宅設計」という意識、あるいは「住居に都市を埋蔵する」という方法意識が状況を表している。即ち、第一次、第二次のオイルショックを経験した1970年代は、一般の「建築家」にとって住宅の設計が限定された表現の場であるという意識があった。そこで、近代住宅、モダンリビング、nLDKを超える試みが住宅設計における課題とされた。そして、1980年代になって、バブル期をピークに、歴史的様式や装飾の復活、地域主義、ヴァナキュラリズム、コンセプチャリズム、・・・・百花繚乱のポストモダン状況が訪れる。
⑨高度成長期の終焉は、一見、住宅に関わるパラダイムの転換をもたらす。高層から低層へ、新規開発から再開発へ、画一性から多様性へ、・・・そして、量から質へ。こうした中で、低層高密度型の集合住宅が定着しはじめる。「六番池」、「桜台コートビレッジ」などがその先駆けである。また、槙文彦の数期にわたる「代官山集合住宅」は、都市型集合住宅創出の数少ないモデル・ケースとなっている。公共住宅の設計に建築家が関わる形が一般化し始める。
⑩住宅生産の変革は戦後建築家の大きな課題であったが、大野勝彦の「セキスイハイムM1」を先駆的仕事として、1980年代に入ると、住宅メーカーやディベロッパーを指導したり、企画型住宅を設計したり、建築家が住宅産業に積極的に関与する形態がみられるようになる。住宅生産の全体の中で大きなウエイトをしめるに至った住宅メーカーにインボルブされる形で仕事をするパターンも定着していく。
⑪1980年代後半、公共住宅の分野で新たな展開が開始される。「ベルコリーヌ南大沢」のマスター・アーキテクト制や熊本アートポリスにおけるコミッショナー・システムなど、新たなプロジェクトのシステムが導入されるとともに、景観形成、脱nLDKがテーマとなる。プロジェクト・システムとしては、磯崎新プロデュースのネクサス・ワールドもインパクトが大きい。外国人建築家によるハウジングの試みも、新たな位相である。
⑫1980年代初頭から展開された「地域住宅(HOPE)計画」は、地域型住宅のモデルを生んだ。また、地域に根ざした一群の建築家を生み出しつつある。また、その運動とも平行しながら、木造住宅の再評価の動きが展開されつつある。古民家再生の試み、古材のリサイクルなどの動きもある。また、雨水利用、太陽熱利用、ビオトープなど環境共生住宅(エコハウス)が主題とされつつある。
これからのすまい:日本の課題
戦後50年において、殊に、1960年代以降において、日本の住宅は決定的に変化したとみていい。決定的なのは、日本の住居全体がnLDKの単なる集合と化したことである。このnLDKという住居形式が理念化したnLDK家族モデルは、社会集団の単位をnLDKという単位に切り分けることにおいてラディカルであった。日本において1960年前後に登場した工業化住宅(プレファブ住宅)は、今や、年間の住宅生産の二割近くを占めるに至るのであるが、その前提としてnLDKという単位の成立が不可欠であった。住宅の工業化=商品化のためには、住居を計量可能な容器へと還元することが必要であり、具体的土地と一旦切り放す必要があった。nLDKという住居の記号化は、空間の商品化の趨勢と軌を一にするものでもあった。家族(核家族)の自立のために、住居を容器に還元する大きな役割を果たしたのがnLDK家族モデルなのである。
核家族モデルが日本においてこうまで一般化したことは、ある意味で日本社会の均質性を示している。北海道から沖縄まで、同じnLDK住居モデルというのは、グローバルにみて極めて特異である。オイルショック以降、住宅の地域的なあり方が様々な形で提唱されるのであるが、それは日本の住宅から地域性が失われていったことの裏返しであった。また、住居の画一化が批判され、個性に基ずく多様性が主張され、様々なスタイルの住宅が現れ始めるのであるが、ポストモダン・デザインの百花繚乱にも関わらず、nLDKというパターンが揺らいだわけではない。それほど生活そのものが画一化されているのである。
核家族モデルをnLDKという住居形式として定着させてきた日本のあり方に対して既に大きな疑問が提出されつつある。社会全体の高齢化や女性の社会進出による少子化といった現象に見られるように家族の形態が実態として多様化し、核家族の理念が揺らぎだしたことがその背景にある。また、身近な生活レヴェルでの国際化が進行し、文化的背景を異にする外国人と共住していく状況が生まれつつあることもある。そうした新たな状況を迎えて、コレクティブ・ハウジングなど多様な家族のあり方、住まい方が求められつつあるのに、決定的なのことは、そうした多様な家族のあり方をnLDKという空間モデルが原理的に許容しないことである。アルファルームとかフレックスルーム、キャラクタープランやフリープラン、ペア住宅、シニア住宅等々・・・新たな住戸形式が模索されつつあるようでnLDKという枠は揺らいではいない。問題は、どのような家族形態を規範モデルとするかである。住宅メーカーが極めて保守的に平均的モデルにターゲットを当て続けるとすれば、新たなモデルを提示する役割は建築家のものとなろう。
家族関係がどうなっていくのかは、住居形式のみの問題では勿論無い。社会全体の編成の問題である。所有と使用の関係、社会的な規範、制度の問題が大きい。ただ、住居形式のモデルとしては、多様な家族関係をどう空間的に保証するか、nLDKを超える空間形式が原理的に問われているのである。
多様な家族関係を考える場合に同時に問われているのが、所有の問題と共に、集合の問題である。戦後日本に定着し、日本の都市景観を変えた団地計画において、必ずしも、集合の論理は突き詰められてこなかったようにみえる。住宅・都市整備公団が1994年12月に出した「先導的な事業・技術開発」というパンフ*5に年表があるけれど、まちづくりの手法としては、「4時間日照」、「近隣住区理論」、「平行配置」、「連続プレイロット」、「歩車分離」といった概念から必ずしも豊富化されているようには見えない。「囲み配置」、「準接地」、・・・「マスター・アーキテクト制」と集合の論理そのものへの切り込みは希薄なのである。外部空間に関わる概念は比較的豊富化してきたのであるが、問題は内部と外部の関係である。そして鍵となるのは、共有空間である。多様な家族関係、集団関係をどのような共有・共用空間によって媒介していくか、様々な実験がもとめられているといえるであろう。
課題は、積層形式における共有空間である。要するに、都市型住宅としてどのような集合住宅をプロトタイプとするかというテーマである。街路型住宅、景観形成型住宅がテーマとされるけれど、問題は型であって、ファサード・デザインではないことは明らかであろう。山本理顕の「雑居ビルの上の住居」(「Rotunda」、「Gazebo」)から「hamlet」、「保田窪団地」団地、「緑園都市」への試みは貴重である。また、「NEXT21」は、問題点も含んでいるが、一般解への試みと言っていい*6。日本の集合住宅の抱える問題点は、集住の論理の欠如(集住形式が確立されていない・日当たり南面指向が配置を規制・町並み形成に寄与していない・都市型住宅になりえていない・共有空間の欠如)、歴史の論理の欠如(社会的ストックになりえない・仮住まい意識の問題・高齢化の問題・日本の住まいの伝統の問題)、多様性原理の欠如(画一的なプランニング・経済原理の優先・政策の貧困)、地域性の論理の欠如、直接性の原理の不在等、既に広く確認済みである*7。キーワードだけは用意されてもいる。停滞なく緩慢にでも多様で地道なな実践が積み重ねられていくことだけが指針である。
日本の住宅生産がどうなっていくのか、住宅産業はどう展開するのか、産業化の流れはどう帰着するのか、住宅生産供給主体はどう棲み分けていくのか等々は大きなテーマである。
フローからストックへ!、スクラップ・アンド・ビルドではなく社会基盤としての住環境を!とよくいうのであるが、果たしてそれは可能か。住宅着工戸数を加えてみると、この30年で日本の住宅はそっくり建て替えられたことになる。要するに、日本の住宅は現在30年を耐用年限としてリサイクルしつつあるのであるが、これを50年、100年の循環に切り替えることは実際如何に可能なのか。容易ではないだろう。住宅生産者社会の編成、ひいては日本の産業構造、国民総生産の動向にかかわるからである。建設産業の従事者が例えば半減するとすれば、自ずと建設戸数は減少するし、耐用年限は伸びる。建築家として、個別になしうることは、素材を素材としての生命を全うさせる、あるいは再生循環させるありかたを追求することかもしれない。住宅メーカーのセンチュリー・ハウジング(百年住宅)は信用できない。
日本の住宅地の景観は、日本の住宅生産構造のそのままの表現でもある。それが雑然としているとすれば、住宅生産システムが多様で混沌としているからでもある。この生産システムの雑然とした棲み分けの構造をどうすべきか。地域に固有な町並み景観の形成という観点からも再編成が考えられるべきであろう。景観形成のための材料や部品が安定的に供給されるシステムが地域毎に成立する可能性は果たしてあるのか。
例えば、住宅メーカーやディベロッパーの住宅供給戦略の中で、地域の住宅生産システムはどうなっていくのか。まず、地域という概念をどう捉えるか。前提となる地域とは具体的には何なのか。特に、地域の住宅生産システムという時の地域とは何か。何らかの閉じた系が想定されているのか。そのスケール、空間的広がりをどう考えるか。あるいは、地域を問題とする戦略的意味は何か。
地域の住宅生産システムのモデル、型にはどのようなものがあるか。生産者社会の組織体制、システムの内部と外部、およびその相互関連のネットワークはどのようにあるべきか。地域の住宅生産システムの担い手は誰か。その再生産の様式(後継者の養成)はどのように保証されるか。要するに、地域におけるこれからの住まい・まちづくりのあり方はどうあるべきか。
ひとりの建築家の営為を超えたテーマといっていい。そうした大きな制度的枠組みの中で、建築家は、住宅に対してどう取り組むのか。環境共生、ストック形成というけれど、個々の仕事で道筋をつけていく以外に方法はないのである。ただ、地域には多様な住宅ニーズがあり、それを満たすシステムが用意さるべきであるとすれば、建築家の仕事もその方向とは無縁ではありえないであろう。
10年前に建築家の新たな戦略目標について考えたことがある*8。バブルで見向きもされなかったけれど、もしかすると、バブルが弾けて、よりリアルな指針となりつつあるのかもしれない。住宅産業化の流れの中で、「アーキテクト・ビルダーの原理」を探る道はないか、「小さな回路」を自律的に構築することはできないか、「地域に固有なハウジング・システム」を持続的に担う方法はないか、「住宅=町づくり」の方法を展開できないか、・・・*9。
戦後まもなくのように建築家が特権的に住宅のモデルを提示するスタイルは無効であるにしても、「建築家」は、多様な住宅像を型として創り出していく役割は持ち続けることになろう。
2023年11月19日日曜日
2023年2月14日火曜日
80年代とは何だったのか、雑木林の世界77,199601
80年代とは何だったのか、雑木林の世界77,199601
雑木林の世界77
80年代とは何だったのか
布野修司
第3回かしも木匠塾が開かれた(一九九五年一一月二五日 岐阜県加子母村 雑木林の世界 参照)。今回は、エコ・ミュージアム構想、森林研修センターの全体計画、バンガローの設計案を持ち寄って、地域のまちづくりを考えるのがテーマであった。東洋大学、千葉大学、芝浦工業大学、京都造形大学、大阪芸術大学、京都大学の学生たちがそれぞれの案を模型やパネルにして参加し、村の人々の意見を求めた。「木匠塾」とは一体何か、何をやろうとしているのか、地域にとってどんなメリットがあるのか、どういう交流が考えられるのか等々、素朴かつ本質的な疑問も出され、議論は前二回以上に白熱したものとなった。村の事情も具体的に説明され、いくつかの困難な事情も明らかになった。相互の理解は深められたと思う。議論は積み重ねるものである。イヴェント的関係から、より粘り強い関係への一歩が踏み出されようとしている、そんな感想をもった。学生たちの大半は、村営のバンガローに泊まり込み、一晩、特にバンガローの設計についてお互いの案の相互批評を行い、実現への夢を膨らませることになった。学生主体にプロジェクトを運営できたらユニークなものができるのではないか、と思い始めている。
昨年暮れ、相次いで、インタージャンルにテーマをつなぐシンポジウムに出席する機会があった。ひとつは、BESETO(ベセト)演劇祭のシンポジウムで「リアルとは何か・・・同時代の表現をめぐって」と題されたシンポジウムである。もうひとつは、「一九八〇年代の表現領域ーーー八〇年代とはなんだったのか?」と題された武蔵野美術大学の「武蔵野美術」創刊一〇〇号記念シンポジウムと銘打たれたものである。ベセトとは北京( )、ソウル( )、東京( )の頭文字を連ねたもので、東アジアの三つの首都の演劇関係者が集う第二回目のお祭りが東京のグローブ座を中心に開かれたものである。日本側実行委員長は鈴木忠志氏で、僕が出席したシンポジウムのコーディネーターは菅隆行氏、パネラーは、佐伯隆幸(フランス近代演劇)、小森陽一(日本近代文学)、高橋康也(英文学)の諸氏であった。武蔵野美術大学の方は、司会が高島直之(美術評論)、パネラーは、柏木博(デザイン評論)、島田雅彦(作家)、上野俊也(政治思想)の諸氏であった。何故、筆者が演劇なのかというと、その昔、少しだけ、芝居のプロデュースをしたことがあるからである。これでも、シェイクスピア学会のシンポジウムに出たこともあるのである。
二つのシンポジウムに共通していたのが、「八〇年代の表現とは何か」というテーマである。建築表現における八〇年代とは何か、改めて考えさせられることになった。また、他のジャンルと比較しながら問いつめられることになった。
二つのシンポジウムを機会にいくつかの作品を思い起こしてみた。
1980 生闘学舎
1981 名護市庁舎
1982 新高輪プリンス
1983 つくばセンタービル ARK 国立能楽堂 土門拳記念館
1984 TIMES シルバーハット 伊豆の長八 釧路湿原展望資料館 眉山ホール 球磨洞森林館
1985 盈進学園 SPIRAL
1986 RISE ノマド 六甲の教会 ヤマトインターナショナル
1987 ROTUNDA 東京工大 龍神村 キリンPLAZA
1988 水の教会 下町唐座 ノアの箱船 飯田市美術博物館
1989 TEPIA 幕張メッセ 藤沢市湘南台文化センター 光の教会 ホテル・イル・パラッゾ スーパー・ドライホール 兵庫県立こども館
1990 青山製図専門学校 水戸芸術館 コイズミ・ライティング・シアター 国際花と緑の博物館 東京武道館 東京芸術劇場 熊本北警察署
1991 ネクサスワールド 再春館 センチュリー・タワー 八代市美術館 東京都新都庁舎 保田窪団地
1992 ハウステンボス
建築家の名がすらすら浮かべば相当の通というところであるが、いくつか気がつくことがあるであろうか。
ひとつは外国人建築家の作品が目立つということだ。日本建築もボーダレスの時代になった。日本人建築家の海外での仕事も一気に増えたのである。もうひとつは「建築の解体」(近代建築批判以降の)世代の活躍が目立つことだ。近代建築批判をスローガンに七〇年代にデビューした建築家たちは八〇年代を通じて次々にエスタブリッシュされていくことになる。要するに「ポストモダンの建築」の時代が八〇年代である。
建築の八〇年代は何であったのかという問いは、ポストモダンの建築とは一体何であったのか、という問いと同じである。
また、年表の裏面には、前川国男(一九八六年逝去)をはじめとする戦後建築を担ってきた建築家の相次ぐ死がある。そうした意味では、戦後建築が終わりを告げた時代が八〇年代である。
一言でいうと、「ポストモダンの建築が全面開花した時代」が八〇年代ということになるのであるが、別の言い方をすると、「近代建築批判の試みがコマーシャリズムに回収されていった時代」が八〇年代である。近代建築批判という課題は先延ばしにされ、宙吊りにされ続けたことになる。それどころか、建築そのものがバブル(泡)化する、そんな事態がクローズアップされたのが八〇年代である。建築は空間を包む包装紙であり、その包装紙のデザインの差異が競われた、そんな時代が八〇年代である。
建築表現の舞台としての都市のありかたそのものがバブルであった。スクラップ・アンド・ビルドの博覧会都市が日本の都市である。
そして、そうした日本の都市を舞台として展開された様々な表現ジャンルは、どうやら似たような展開をしてきたらしい。島田雅彦氏は、それを村上春樹的なものという。
八〇年代に露呈したものは、戦後建築の最も悪しき循環ではないか。そんなことを思いながら、阪神淡路大震災のショックもあって、『戦後建築の終焉』(れんが書房新社)を上梓したのであった。
2023年1月17日火曜日
北朝鮮都市建築紀行,雑木林の世界47,住宅と木材,(財)日本住宅・木材技術センター,199307
北朝鮮都市建築紀行,雑木林の世界47,住宅と木材,(財)日本住宅・木材技術センター,199307
雑木林の世界
北朝鮮都市建築紀行
布野修司
一九九三年四月二九日から五月四日まで、日本建築学会の朝鮮都市建築視察団の一員として、北朝鮮を訪問してきた。朝鮮建築家同盟との学術交流が主目的であったが、平壤、開城、板門店、妙香山などを訪れる機会があった。限られた見聞にすぎなかったのであるが、その印象を素朴に記してみたい。北朝鮮の都市、建築については極めて情報が限られている。誤解も多いかもしれないけれど、南北建築界の理解の一助になればと思う。
一時間遅れで名古屋空港を発った高麗航空のチャーター便は、日本列島を北上、新潟上空を通過してウラジオストックへ、一旦ロシア領へ入って平壤へというコースをとった。直線的に飛べば二時間足らずであろうが、三時間半かかる。まさに近くて遠い国である。
降り立った飛行場が閑散としてやけに寂しい。実は、着いたのは平壤の南、黄州の軍用飛行場であった。核査察の問題、チームスピリット(日韓合同軍事演習)の問題で、平壤空港が閉鎖されていたのである。帰国時には、平壤空港から飛べたのであるが、国際関係の緊張を否応なしに感じさせられる旅の始まりであった。
黄州から平壤へ向かうバスの車窓からうかがう農村の風景が珍しい。一ケ月前に見てきたばかりの韓国の農村風景と比べるとやけにすっきりしている。あたり一面赤い土の田圃が広がり、小高い丘の上に集落がつくられている。集落はいくつかのスタイルの住宅からなる。目につくのは、三層から五層の集合住宅である。もちろん、伝統的なスタイルと思われる平屋の農家もあるけれど、時代によってモデルを変えながら供給されてきたようだ。所々に小さな水力発電所がある。地域毎に電力をまかなっているという。
夜の平壤は暗かった。街灯が少なく、ネオンもほとんどない。雨のせいか人通りも少なかったのである。翌朝、早速、ホテルの回りを歩く。ホテルは、高麗ホテルという平壤でも最高級のホテルで、ツインのタワーが何となく東京新都庁舎を思わせる。未完成の柳京ホテルとともにまちのここそこから望める。平壤の新しいシンボルである。近くに、平壤駅があって、通勤、通学の人々でごったがえしていた。通勤の足は、バス、トロリーバス、地下鉄である。大人の間に子供の姿が多い。都心に職住近接で居住するからであろう。子供の手を引いた女性の姿も目立つ。何よりも気づくのはゴミが落ちていないことである。早朝に一勢に掃除をする人々を毎朝見かけたのであるが、通りは実にきれいである。
ゴミのないことが象徴するように平壤の街は実にきれいな街であった。市の中心にある主体(チュチェ)塔の上から俯瞰すると柳の緑が美しい。朝鮮戦争で壊滅的な打撃を受けた後、見事に復興したのである。電線の地中化が徹底して行われているのが都市の景観として大きい。日本の都市の猥雑さに見慣れていると随分すっきりした印象を受ける。看板や広告塔がほとんどないこともそうである。
ただ、洗濯物が全く見られないのはいささかとまどう。洗濯物はバルコニーや室内に干すことが決められているのであるが、それはそれとして、あまりにも生活の臭いが感じられないのである。たまたま、五月一日のメーデーの様子を見ることができた。特に行事があるわけでなく、休日なのである。遊園地でくつろぐ人々、輪になって歌い踊る女性達、泥酔する何人もの男性、いずこも変わらない風景であった。
今回のツアーの一つのハイライトは、開城(ケソン)であった。開城は、平壌の南西六〇キロに位置し、板門店へは一〇キロ弱のところにある。高麗(九一八年から一三九二年)の都が置かれた歴史都市である。実に驚いたことは、子男山の麓に歴史的な街区が相当分厚く残っていたことである。子男山から見おろすと、黒い瓦屋根の家並が一杯に広がる。韓国のソウルや慶州でもこんな街区は残されていない。歴史的な痕跡を一切破壊された高句麗の首都、平壌の様子からは想像できないことであった。
開城は実は三八度線の南にある。戦災を免れたのはあるいはそのことが関係するのであろうか。停戦協定の締結時点の戦力の配置によって国境が決定され、その結果、ある意味では偶然、開城は北朝鮮の領域に組み入れられたのである。開城は、最も離散家族の比率が高いという。南北分断を象徴する都市である。
開城の歴史的佇まいが残されていることはなんとも言えない感慨を呼び起こす。韓国の人々は、開城のこんな様子を知っているのであろうか。韓国の友人達にすぐさま知らせたい、とまず思った。これは世界歴史遺産とすべき都市ではないか、というのが続いての思いである。
『朝鮮と建築』(一九二一年創刊)に、野村孝文先生の「開城雑記」(一)~(五)(一九三二年~三三年)という連載記事がある。開城雑記といっても、後に『朝鮮の民家』(一九八一年)にまとめられることになる朝鮮全体についての記述を含んでいるのであるが、開城については、池町、北本町、東本町の八つの住宅を紹介した上で、「開城が朝鮮に於ける住宅建築に於いて、可成りの発達をなして居た事を知る事が出来る」と結んでいる。写真やスケッチからは、六〇年前の開城の様子を伺うことができる。今もその面影が残っているのである。
板門店からはソウルの北にある、風水説で言う祖山に当たる北漢山が見える。この近さはやはり不思議である。ベルリンの壁なき後、板門店は唯一特異な空間として存在し続けていくのであろうかと、ひとつの線を南北に跨ぎながら考えた。
妙高山へは観光客用の専用列車であった。国際親善展覧館で、各国の元首などから贈られた贈り物を厭というほど見せられたのはうんざりであったが、普堅寺は面白かった。スパン割の不均一な観音殿があって随分首をひねったものである。
白頭山建築研究所での朝鮮建築家同盟での交流会は短い時間ではあったが、北朝鮮の建築界を垣間見る貴重な機会であった。中心は、建築家の養成、教育であったのであるが、まず、さもありなんと思ったのが、設計教育の七割が実践教育だという点である。設計製図の優秀作品はそそまま建設される、なかなかいいシステムである。もちろん、実践家の教授、助手が指導にあたり、外部事務所がついてのことである。人民大学習堂もそうして建設されたという。
大学を出ると設計員の資格を受験する。六級から一級まであって、一級上がるのに三年の経験がいるという。かなり厳しい。二級以上になると、功勲設計家、さらには人民設計家となる資格ができるという。人民設計家というのが最高位である。
全体は限られた見聞でしかない。集合住宅の内部や農村住宅が見たいというわれわれのいくつかの希望も叶えられなかった。全体として、見せられているという感じは拭えない。しかし、それにしても貴重な経験をしたと思う。実に多くのことを考えさせられた。
2022年12月22日木曜日
2022年12月20日火曜日
-
traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...