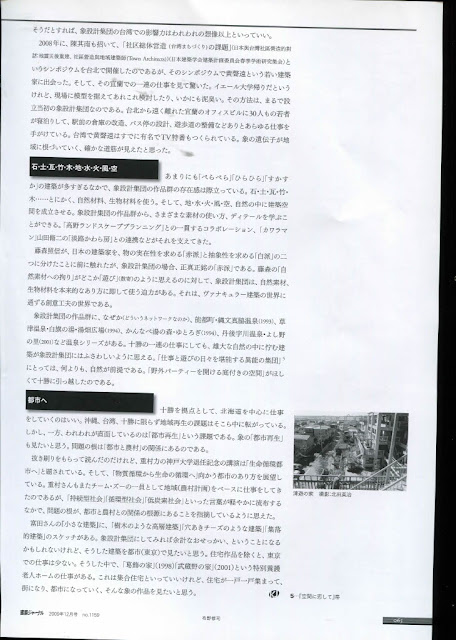現代建築家批評24 『建築ジャーナル』2009年12月号
現代建築家批評24 メディアの中の建築家たち
地球に根ざして・・・周縁から
象設計集団の作品
樋口裕康,富田玲子は既に古希を迎えた。「酒債は尋常行く処に有り
人生七十古来稀なり」(杜甫曲江詩)という。樋口さんなどとっくにこの心境であろうか。富田さんが『小さな建築』(2007年)をまとめたのもひとつの区切りが意識されている。ふたりとも,最近は講演で忙しそうである。十勝の拠点では,町山一郎さんが「象精神」溢れるブログを書き続けている。
象設計集団は,集大成の時期を迎え,世代交代というべきか,第二期象設計集団のスタートというべきか,さらに新たな展開が期待される段階に入っているといっていい。
『空間に恋して』が「いろはカルタ」に見立てて編集されているのは象らしい。「笠原小学校」の外廊下の柱一本一本には、「江戸いろは」の句が刻み込まれているし,ナントのワークショップ(2001)でも,「いろは」47文字を使って作品や考え方を掛け軸にしていた。『空間に恋して』には,長文も短文もある。視点も視野もばらばらである。体系を嫌うといってもいい。しかし,「決して気まぐれではない。どの言葉にも私たちの思いが込められている」のである。
「7つの原則」があるから,それ以上の整理はいらない,具体的作品[i]の多様性にゆだねるということであろう。
僕は,『戦後建築論ノート』(相模書房,1981年)の最後に,日本建築界の行方を論ずる中で(「閉じつつ開く」),次のように書いた。それから30年近く経つ。今もその期待は変わらない。しかし一方で,象設計集団のこの間の活動が一段落するのを振り返るとき,中心,すなわち,都市を果敢に攻めることこそいまや問題ではないか,と思い始めている。
「一つの指針は,その場を中心的なるものと周縁的なるものとの境界に設定することである。制度と空間とのヴィヴィッドな空間を見つめうる場所に設定することである。そして,さらに,そこでの具体的な活動を,少なくとも,時間軸としての昭和,空間軸としてのアジアによって張られる時空の広がりのなかで,繰り返し位置づけていくことである。
具体的な試みも,すでに多様に開始されているといっていい。たとえば,象グループの沖縄での仕事や内田雄造,大谷英二等の土佐・高知の被差別部落の計画は,もっとも先鋭にその方向性を示すものであったといっていい。市民社会から疎外された被差別部落,本土から疎外され続けた辺境の地,沖縄,いずれも,われわれにとって周縁の世界であった。」
コミュニティ・アーキテクトの可能性―地域と建築家―
地域と象設計集団というと,まずは「沖縄」である。そして,「宮代」であり,「宜蘭」であり,「十勝」である。70年代,80年代,90年代,そして2000年代とオーヴァー・ラップしながらも地域との関わりの密度は移行してきている。
地域と建築家の関わりといっても,いくつかのレヴェル,アプローチの位相がある。第一に,地域と建築家の持続的関わりの問題がある。また,建築家の居る場所,依拠する場所としての地域がある。タウンアーキテクト,コミュニティ・アーキテクトとして地域に関わるのと,「世界建築家」として地域に関わるのかは決定的に異なる。第二に,地域づくりと建築との関係の問題がある。たとえ,一個の「小さな建築」であれ,その設計を都市計画,地域計画の一環として捉えるか,自己表現の機会ととらえるか,あるいは新規の技術あるいは新奇な形態の実験ととらえるかは決定的に異なる。そして,第三に,地域性をどう表現するか,地域の中から,どのような建築言語を引き出すのか,という建築の方法のレヴェルがある。
コミュニティ・アーキテクトあるいはタウンアーキテクトのあり方を問題とする中で,コミュニティ・アーキテクトは「地」の人なのか,「風」の人なのか(あるいは「火」の人か)ということが問題となる。すなわち,コミュニティ・アーキテクトは,地域に住み地域の生活者であり続ける必要があるのか,「風」のように地域を吹き抜けながら,地域の価値を発見する役割を担うのか,という問題である。「火」の人というのは,マッチポンプのように火をつけるけれど,あとは地域を顧みない,あるいは,建築作品を建てるだけで地域を顧みない(「やり逃げ」)建築家のことである。
地域にとっては,「地」の人も,「風」の人も,場合によっては「火」の人も必要である。しかし,建築家としては,常にそのスタンスが問われる。象設計集団が十勝を拠点にして20年になる。その仕事の多くが十勝を中心とした北海道となるのは必然である。廃校を事務所に転用することを皮切りに,広々とした土地,厳しい冬を背景にしながら,「北海道ホテル」(1995-2001)「森の交流館」(1996)「十勝ビール」(1997)「高橋建設」(1998)・・・と場所の表現が追求されつつある。帯広には,五百もの建築を建てた五十嵐正[ii]のような建築家がいるけれど,象設計集団の場合,最終的にローカル・アーキテクト(地方建築家)になろうというわけではないであろう。
地球に根ざしているかどうか、それが問題なのである。
発見的方法
沖縄に先だって,吉阪研究室における大島計画がその原点と言われるが,象の方法の出発点はフィールドワークである。「一刻一刻が発見」であり,「こんな面白いことが他にあろうか」というフィールドワークが「建築そのもの」であるというのは,「発見のための視点と視野,実現のための手段と工夫,どれがいいのかそれをみんなで見つけよう」(吉阪隆正)という行為だからである。
沖縄でのその実践は鮮やかであった。今でも,象の沖縄の仕事を特集した『建築文化』[iii]のコピーを持っているほどだ。折に触れて学生たちに配るのである。
「山原(ヤンバル)」の土地利用,自然生態の分析,「環境構造線」と名づける景観分析,方言地名の分析,「ウタキ(御獄)」「アサギ」といった場所の意味を読み解く集落の空間構造の解析,水系の分析,「ヒンプン」「シーサー」といった建築的要素,街のディテールの発見といった地域の自然文化社会の生態空間を捉える手法が既に示されている。その地域空間へのアプローチは,ひたすらその古層へ向かい,歴史的空間の型をステレオタイプ化するのではない。コンクリート・ブロック(花ブロック)も発見されるのである。戦災を受けた沖縄に,米軍が戦後持ち込み一般的に用いられてきたコンクリート・ブロックが「今帰仁村中央公民館」「名護市庁舎」に積極的に用いられることになる。照明,時計塔,鐘つき塔,風見・方位塔,パーゴラなどがブロックでデザインされることになる。すなわち,建築生産体制もまたフィールドワークによって発見されるのである。
インドネシアを歩き始めた(1979年)頃のことを思い起こす。日本も戦後まもなくはこんな状況ではなかったかという住宅問題,都市問題を目の当たりにして,建築家はどうするのか,何をどう組み立てるのか,ということを随分考えた。直感的に自明であったのは,何か理念的なモデル(平面型)を呈示するだけでは何も動かない,ということである。すなわち,地域(場所)で調達可能な建築材料,職人集団が継承してきた技能,建築生産体制を前提とすることが出発点になると言うことである。
新しい村
沖縄での方法は,今日喧伝されるエコロジカル・プランニング,エコロジカル・デザインの手法をはるかに先取りするものであったと言っていい。沖縄という,本土から疎外され,その戦後復興,高度成長から取り残されてきたが故に,場所のポテンシャルを維持してきた地域だから成功したということではない。台湾という中国本土からみれば「化外の地」であった場所だから象流のアプローチが成功したということではない。その第一原則である「場所の表現」は,あらゆる場所で有効であるのが前提である。
そのアプローチが首都圏においても可能であることを示したのが宮代町である。宮代町は,富田玲子の疎開先でその後も夏休みを過ごした町であり,「世界のどこにもないものを」といった宮代町の町長,齋藤甲馬は富田玲子の叔父(父の兄)であるという縁があった。建築家を育てるのはこうした縁であり,自治体に一人のすぐれた人物―コミュニティ・アーキテクト―が居れば,公共建築については思い切った挑戦ができる。「進修館」(1980)は,「低層建築でいい」「議会を円卓でやる」「使わないときは町民ホールとして開放する」という町長の提案が大きかった。
設計については,「宮代の風景をつくる」「街の軸づくり」という方針が意識されている。環境構造線を意識的に創り出そうというのである。「進修館」を街中の屋敷林と見立て,世界の中心として,街の軸としての南北軸,筑波山―富士山をつなぐ軸に,同心円を重ねるプランは,コスモロジー派の方法を思わせる。「遠い宇宙,南極,北極,富士山,筑波山をこの場所に呼び寄せてしまおうと欲張ったのです」と富田はいう。
「進修館」とともに「笠原小学校」(1982)の設計も町から委託される。「教室は住まい」であり,「学校は街である」という象の一連の学校作品の最初の作品であり,代表作といっていい。象設計集団にとって宮代での仕事が大きいのは,その後も持続的な関わりを維持してきているからである。「笠原小学校」の南にあった老朽化した町役場の代わりに,「進修館」の南に地元の建築家たちによって木造新庁舎が建てられ,町役場の跡地に,「農のあるまちづくり」計画のシンボルとして「新しい村」が計画されつつある。地産地消の流通システム作り,「メイド・イン宮代」の商品開発,市場,工房,集落農園,育苗温室,機械化センターの整備など農家をサポートする施設が集中するのが「新しい村」である。
首都圏の町とは言え,江戸時代に新田開発(ほっつけ(堀上げ田))によって拓かれた場所である。市街地の近くに位置しながら未だかつての農村風景を残している。ほっつけの再生と森の拡充が「新しい村」の中心テーマである。
社区総体営造
前述のように,台湾での仕事も,郭中端という吉阪研究室のかつてのメンバーを通じての縁である。「冬山河親水公園」以降宜蘭で次々に懸の行政中心の建築を次々に設計してきたことも上述の通りである。1988年に設立された象設計集団の台湾事務所には今では,かなりのスタッフがいる。東京事務所とともに,南北から日本を挟撃する鮮やかなシフトを敷いていることも,既に触れた通りである。
台湾には,東南アジアに通い始めて(1979年)以降,その行き帰りに度々訪れる機会があった[iv]。李登揮が初代大統領に選ばれる時も,次の再選の時も,さらに民進党の陳水扁が大統領になった選挙の時も,1999年の921集集大地震の調査で台湾に居た。だから,台湾の街づくりについては,それなりによく知っているつもりである。もともと移民社会であり,しかも国民党の相互監視システムにおいて,1980年代末まではコミュニティーなど存在しないに等しい状況であった。
38年間続いていた戒厳令が解除された1987年に象設計集団の宜蘭行きも開始されるのであるが,翌年蒋経国が死去し,李登輝副が本省人として初めて総統に就任して以降,社会の基礎としての地域社会の構築(再建)を目標に掲げ,運動の先鞭をきったのは行政院文化建設委員会の陳其南である。彼の発案,主導の元に開始されたのが「社区総体営造」運動(1994)である。並行してノーベル化学賞受賞者の李遠哲中央研究院(SINICA)院長を会長に「社区営造学会」も立ち上げられた。その中心にいたのが,早稲田大学で重村力らと「生活集積としての都市研究」を展開してきた陳亮全(台湾大学)である。
陳其南とは何度か「社区総体営造」をめぐって話をしたことがある。彼が言うにはアメリカ流のCBD(Community
Based Development)ではなく日本の「まちづくり」に学んだのだという。もしそうだとすれば,象設計集団の台湾での影響力はわれわれの想像以上といっていい。
昨年(2008年),陳其南も招いて,「社区総体営造 (台湾まちづくり)の課題」(日本與台灣社區營造的對話:地震災後重建,社區營造與地域建築師(Town Architects))(日本建築学会建築計画委員会春季学術研究集会)というシンポジウムを台北で開催したのであるが,そのシンポジウムで黄聲遠という若い建築家に出会った。そして,その宜蘭での一連の仕事を見て驚いた。イエール帰りだというけれど,現場に模型を吸えてあれこれ検討したり,いかにも泥臭い。その方法は,まるで設立当初の象設計集団なのである。台北から遠く離れた宜蘭のオフィスビルに30人もの若者が寝泊りして,駅前の倉庫の改造,バス停の設計,遊歩道の整備などありとあらゆる仕事を手がけている。台湾で黄聲遠は既に有名でTV特番もつくられている。象の遺伝子が地域に根づいていく,確かな道筋が見えたと思った。
石・土・瓦・竹・木・・地・水・火・風・空
あまりにも「ぺらぺら」「ひらひら」「すかすか」の建築が多すぎるなかで,象設計集団の作品群の存在感は際立っている。石・土・瓦・竹・木・・・とにかく,自然材料,生物材料を使う。そして,地・水・火・風・空,自然の中に建築空間を成立させる。象設計集団の作品群から,様々な素材の使い方,ディテールを学ぶことが出来る。「高野ランドスケーププランニング」との一貫するコラボレーション,「カワラマン」山田脩二の「淡路かわら房」との連携などがそれを支えてきた。
藤森照信が,日本の建築家を,物の実在性を求める「赤派」と抽象性を求める「白派」の二つに分けたことに前に触れたが,象設計集団の場合,正真正銘の「赤派」である。藤森の「自然素材への拘り」がどこか「遊び」(数寄)のように思えるのに対して,象設計集団は,自然素材,生物材料を本来的なあり方に即して使う迫力がある。それは,ヴァナキュラー建築の世界に通ずる創意工夫の世界である。
象設計集団の作品群に,何故か(どういうネットワークなのか),能都町・縄文真脇温泉(1993),草津温泉・白旗の湯・湯畑広場(1994),かんなべ湯の森・ゆとろぎ(1994),丹後宇川温泉・よし野の里(2001)など温泉シリーズがある。十勝の一連の仕事にしても,雄大な自然の中に佇む建築が象設計集団にはふさわしいように思える。「仕事と遊びの日々を堪能する異能の集団」[v]にとっては,何よりも,自然が前提である。「野外パーティーを開ける庭付きの空間」が欲しくて十勝に引っ越したのである。
都市へ
十勝を拠点として,北海道を中心に仕事をしていくのはいい。沖縄,台湾,十勝に限らず地域再生の課題はそこら中に転がっている。しかし,一方,われわれが直面しているのは都市再生という課題である。象の都市再生も見たいと思う。問題の根は「都市と農村」の関係にあるのである。
抜き刷りをもらって読んだのだけれど、重村さんの神戸大学退任記念の講演は「生命循環都市へ」と題されている。そして、「物質循環から生命の循環へ」向かう都市のあり方を展望している。重村さんもまたチーム・ズーの一員として地域(農村計画)をベースに仕事をしてきたのであるが, 「持続型社会」「循環型社会」「低炭素社会」といった言葉が軽やかに流布するなかで,問題の根が,都市と農村との関係の根源にあることを指摘しているように思えた。
富田さんの『小さな建築』に,「樹木のような高層建築」「穴あきチーズのような建築」「集落的建築」のスケッチがある。象設計集団にしてみれば余計なおせっかい,ということになるかもしれないけれど,そうした建築を都市(東京)で見たいと思う。住宅作品を除くと,東京での仕事は少ない。そうした中で,「葛飾の家」(1998)「武蔵野の家」(2001)という特別養護老人ホームの仕事がある。これは集合住宅といっていいけれど,住宅が一戸一戸集まって,街になり,都市になっていく,そんな象の作品を見たいと思う。
[i] 象設計集団の主な受賞:1977・芸術選奨文部大臣新人賞(美術部門)今帰仁村中央公民館/都市計画学会石川賞 沖縄における一連の都市計画:1979・名護市庁舎公開設計競技
最優秀賞:1982・日本建築学会賞/甍賞 銀賞/労働福祉事業団山口保養所 錦グリーンパレス:1987・甍賞 金賞 /安佐町農協生活文化会館
1990・日本デザイン賞 大賞 ドーモ・チャンプルー/横浜市街並み景観賞 磯子アベニュー:1991・RACコンテスト
グランプリ/みちのく杜の湖畔公園インフォメーションセンター/・台湾 カマラン賞/冬山河風景区親水公園における価値観と仕事上の態度/たちかわ市デザイン賞 市長賞
/昭和記念公園こどもの国インフォメーションセンター:1994・石川県景観賞 大賞 能都町縄文真脇温泉/ドイツ
Frankfurter Zwilling 賞/北海道立釧路芸術館公開設計競技 最優秀賞
1996・フランス バール樹木園指名設計競技最優秀賞:1997・全税共地域文化賞 /地域における芸術文化の振興に資する活動:1998・多治見市立中学校指名設計競技
最優秀賞/広島街づくりデザイン賞大賞 矢野南小学校:2000・台湾「公共工程品質賞」金賞受賞 宜蘭縣議会:2001・台湾「公共工程品質賞」金賞受賞 土牛小学校
2002・文部科学大臣奨励賞賞受賞 多治見中学校/第8回公共建築賞優秀賞受賞 矢野南小学校:2003・北海道赤レンガ建築奨励賞
高橋建設/エコビルド賞受賞 高橋建設/台湾「優良緑建築設計賞」 宜蘭県庁舎:2004・第10回石川県景観賞 石川県九谷焼美術館
[ii] 『建築家五十嵐正―帯広で五百の建築をつくった』文:植田実,写真:藤塚光政,西田書店)
[iv] また,京都大学の布野研究室にもかなりの台湾からの留学生がいて,彼らとともに何度かフィールド調査をする機会があった。黄蘭翔(台湾大学)と若くして亡くなったが,闕銘宗が布野研究室の台湾研究の中心であった。闕銘宗,布野修司,田中禎彦:新店市広興里の集落構成と寺廟の祭祀圏,日本建築学会計画系論文集,第521号,p175~181,1999年7月/闕銘宗,布野修司,田中禎彦:台北市の寺廟,神壇の類型とその分布に関する考察,日本建築学会計画系論文集,第526号,p185-192,1999年12月/闕銘宗,布野修司:寺廟,神壇の組織形態と都市コミュニティー:台北市東門地区を事例として,日本建築学会計画系論文集,第537号, 219-225,2000年11月。