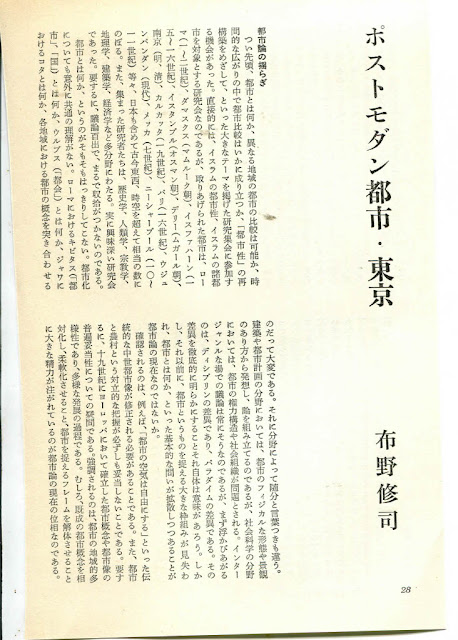布野修司建築論集Ⅱ
『都市と劇場』
★ポストモダン都市・東京[i]1
都市論の揺らぎ
都市とは何か、異なる地域の都市の比較は可能か、時間的な広がりの中で都市比較はいかに成り立つか、「「都市性」の再構築をめざして」、といった大きなテーマを掲げた研究集会に参加する機会があった。直接的には、イスラームの都市性、イスラームの諸都市を対象とする研究会[ii]2なのであるが、取り上げられた都市は、ローマ(一~二世紀)、ダマスクス[iii]3(マムルーク朝)、イスファハーン[iv]4(一五~一六世紀)、イスタンブル[v]5(オスマン朝)、デリー[vi]6(ムガール朝)、南京[vii]7(明、清)、カルカッタ[viii]8(一九世紀)、パリ(一六世紀)、ウジュンパンダン[ix]9(現代)、メッカ[x]10(七世紀)、ニーシャープール[xi]11(一〇~一一世紀)等々、日本も含めて古今東西、時空を超えて相当の数にのぼる。また、集まった研究者たちは、歴史学、人類学、宗教学、地理学、建築学、経済学など多分野にわたる。実に興味深い研究会であった。要するに、議論百出で、まるで収捨がつかないのである。
都市とは何か、というのがそもそもはっきりしてこない。都市化についても以外に共通の理解がない。ローマにおけるキビタス(「都市」、「国」)とは何か、ウルプス(「都会」)とは何か、ジャワにおけるコタとは何か[xii]12、各地域における都市の概念を突き合わせるのだって大変である。それに分野によって随分と言葉つきも違う。建築や都市計画の分野においては、都市のフィジカルな形態や景観のあり方から発想し、論を組み立てるのであるが、社会科学の分野においては、都市の権力構造や社会組織が問題とされる。インタージャンルな場での議論は常にそうなのであるが、まず浮かびあがるのは、ディシプリンの差異であり、パラダイムの差異である。その差異を徹底的に明らかにすることそれ自体は意味があろう。しかし、それ以前に、都市というものをとらえる大きな枠組みが見失われ、都市とは何か、といった基本的な問いが拡散しつつあることが都市論の現在なのではないか。
確認されるのは、例えば、「都市の空気は自由にする」といった伝統的な中世都市像が修正される必要があることである。また、都市と農村という対立的な把握が必ずしも妥当しないことである。要するに、一九世紀にヨーロッパにおいて確立した都市概念や都市像の普遍妥当性についての疑問である。強調されるのは、都市の地域的他犠牲であり、多様な発展の過程である。むしろ、既成の都市概念を相対化し、柔軟化させること、都市をとらえるフレームを解体させることに大きな精力が注がれているのが都市論の現在の位相なのである。
東京論の位相
実に不満なのは、世界史的な視野をもとにした大きな仮説や理論の提示、少なくとも、その必要性についての認識が欠如していることである。しかし、いまここで、都市をめぐって一般的に以上のような問題を論ずるのはもちろん手に余る。ひとつの具体的な都市についてたどたどしく考えてみようと思う。東京についてである。一九八〇年代半ばから九〇年代にかけての東京論の隆盛はすさまじいものがあった。そこで何が語られ、何が覆い隠されてきたのかがひとつのテーマである。
東京論[xiii]13と称されるものは、その時間的パースペクティブに関して大きく三つに分けることができる。すなわち、レトロスペクティブな東京論、ポストモダンの東京論、そして、東京改造論の三つである。路上観察の東京論、俯瞰する東京論、というように視線の置き方によって分けたり、イメージとしての東京論、景観としての東京論、形態としての都市論、というように対象やレヴェル、次元によって分けたりできようが、およそ以上の三つで全体の傾向を把握できる。
レトロスペクティブな東京論においては、ひたすら、東京の過去が掘り起こされる。東京の過去とは江戸であり、一九二〇年代の東京である。また、地形であり、水辺であり、緑であり、自然である。そして、そうしたものを失ってしまった東京がノスタルジックに回顧されるのである。また、現在の東京に、失われたものや価値が対置される。一方、ポストモダンの東京論は、ひたすら、現在の東京を愛であげる。いま、東京が面白い、世界でも最もエキサイティングな都市「東京」というわけだ。路上観察、タウンウォッチングに、パフォーマンスである。しかし、この二種類の東京論は、実は根が同じとみていい。ポストモダンの建築デザインを考えてみればわかりやすいだろう。都市の表層を覆うのは過去の建築様式の断片である。すなわち、すでに都市の表層を支配するのは、皮相な歴史主義のデザインである。近代建築に対して、それを批判すると称して(ポストモダンを標榜して)装飾や様式が実に安易に対置されたのであった。過去や自然はいとも容易に掘り起こされて、現在の都市は、そのまがいもので飾りたてられ始めたのである。
そして、この二種の東京論が結果として覆い隠し、覆い隠すことにおいて支持し、促すのが東京改造のさまざまな蠢きである。レトロスペクティブな東京論は東京が変わっていくことへのある意味では悲鳴であった。東京の変貌、その再開発や改造の動きと過去の東京へのノスタルジーが東京論という形でブームとなったことは、言うまでもなくストレートにつながっている。過去への郷愁は、それだけでは無力かもしれない。しかし、それは、すなわち、都市の過去や自然、水辺の再発見は巧妙にウォーターフロント開発や、都市の再開発へと接続されるのである。こうして仮に三つに分けてみた東京論はひとつの方向を指し示す。東京という空間はいままさに再編成されつつある。東京のフィジカルな構造はいまドラスティックに変わりつつある。そのいくつかの位相を見てみよう。
過飽和都市・・・フロンティアの消滅
一七世紀の初頭には小さな寒村にすぎなかった江戸が一九世紀半ば過ぎに東京と名を変えて一世紀あまりになる。明治に入って、産業革命を経、後進資本主義国として発展していく日本の首都として、東京の変貌にはすさまじいものがあった。江戸の人口はその末期には一〇〇万人にものぼり、既に世界最大級の都市であったのであるが、その膨張の速度と規模は比較にならない。行政区域としての東京の人口は一,二〇〇人を越え、東京大都市圏には三,〇〇〇万を越える人々が居住する。少なくともその規模においては世界有数の大都市となった。
東京は、その歴史的形成の過程において幾度かの転機をもつ。例えば、江戸から東京への転換における空間の再編成、関東大震災後の近代都市への編成、第二次世界大戦時における一瞬の白紙還元と戦後復興、東京オリンピックを契機とする高度成長期の大変貌などがそうである。そしていま、東京という都市はまた大きな転換期を迎えつつある。その転換期はこれまでとはいささか違うのではないか。ある究極の姿を東京は見せ始めたのである。
それを具体的に示すのが「東京問題」と総称される諸問題なのであるが、指摘すべきは、東京は都市として明らかに過飽和状態に達しつつあるということである。東京一極集中がますます加速されるなかで、都市のフロンティアが消滅しつつあるということである。
郊外への平面的な膨張が最早限界に達しつつあることを示すのが、この間の地上げ騒動であり、地価狂乱であり、東京再開発、東京改造のさまざまな動きである。民間活力の導入、内需拡大、経済摩擦の解消、国際化に伴うオフィス需要、などとさまざまな口実が掲げられるのであるが、要するに、金があり余っており、投資の対象が求められているのだけれど、投資すべき不動産は日本に限りがある。海外の不動産をあからさまに買い占めるわけにはいかないとすれば投資効果の高い空間を創り出す必要がある。そこで大きなテーマとなるのが東京再開発であり、東京大改造なのである。
まずターゲットとなったのは、都心にある未利用の公有地であり、下町地域の住宅地である。いずれも利便性は高く、再開発による高度利用が可能である。民活による公有地の払い下げ、地上げ屋による下町地域の買占めは、あっという間に地価を押し上げ、都心のみならず郊外へと波及していったのである。
東京再開発、東京改造の動きにおいて、はっきりしてきたのは、丸の内から新宿副都心への都心の移動である。その象徴が新都庁舎である。東京の重心は西へ移り、新宿に超高層ビルの林立する新都心が形成されつつあるのである。それに対して、丸の内の再開発をうたうマンハッタン計画が打ち上げられたりするのであるが、要するにフロンティアとして最初に問題とされるのは空中である。マンハッタンを見よ、東京の上空には、まだ広大な未開発地があるというわけだ。
続いて、開発のターゲットとなったのが、ウォーター・フロントである。郊外へスプロールしていくことがほぼ限界になったとすれば、平面的に延びていく可能性は海にしかない。水辺空間の再発見とか、親水空間の意義とかが強調されるのであるが、その実は、水運や造船業の衰退で陳腐化していて、それ故、地面が値上がりしなくて安かった土地に目がつけられたということである。また、埋め立てればいくらでも土地を生み出すことができるとばかりに、埋め立て地がターゲットになるのである。
さらに地下の空間にも目がつけられる。空中を利用するのであれば、地下も利用できるというわけだ。東京湾をほとんど埋め立てるというプロジェクトも壮大であるが、地下に五〇万人の居住都市をつくろうという構想も大変なスケールである。瀬戸大橋、青函トンネルと相次いで巨大プロジェクトが完工し、土木技術の最前線が、地下へ、海へと求められているのである。
先進諸国の大都市に比べれば、まだ東京には空間的余地があるといえるかもしれない。しかし、物理的な余地は無限にあるわけではない。過飽和状態、フロンティアの消滅という事態はいずれ訪れる。ロンドンのドッグランズ再開発やパリのさまざまな再開発を見ればわかりやすい。東京に比べれば、はるかに都市の骨格のしっかりしている、都心を歴史的建造物によって固められた西欧の大都市では、なんらかの再開発によらなければにっちもさっちもいかない。東京はすでにその兆候を見せ始めたといっていいのである。明らかに先進諸国の問題は連動し始めているのである。
世界都市・・・二十四時間都市
東京が明らかにこれまでの発展の過程とは位相を異にした展開を始めたというのは、フロンティアの消滅という決定的事実においてなのであるが、その質においてまず言えるのは国際化という新たな局面である。この国際化という局面に少なくとも二つのポイントがある。
ひとつは、東京が国際的な金融関係の中心都市となったということである。一般的に言われるのは、この意味での国際都市・東京の新たな相貌である。もちろん、この新たな局面は、外国の金融機関が東京に事務所を開設するからオフィス需要が足りなくなるといった次元の問題ではない。東京が世界都市として国際的な金融関係に同時的に巻き込まれるようになったということである。一刻一刻、二十四時間、瞬時に莫大な取引が行われる、国際的なネットワークの真っただ中に置かれるのである。二十四時間都市というのは、そうした国際関係に支配されながら、都市生活の全体が秒単位に組織されつつある都市をいうのである。
東京は、日本の都市であり、諸都市を結節する首都としての機能をもってきたのであるが、その次元を越え、世界都市になったといっていいのである。例えば、ロンドンのシティの歴史的建造物のいくつかは日本の証券会社や銀行によって占められている。ニューヨークの多くのビルやホテルが日本の資本によって買い占められる。東京の地上げ騒動は、国内のにならず、グローバルに波及しているのであり、国際都市といわれる諸都市は、はっきり具体的につながっているのである。
もうひとつのポイントは、外国人労働者の流入という、極めて具体的な国際化の新たな局面である。外国人労働者の流入という経験は、決して初めてのことではない。在日韓国人の存在とその歴史が既にわれわれにとっての厳しい経験になっているはずだ。しかし、東アジアからのみならず、より広範な地域から外国人が流入し始めたということ、すなわち、より文化的に多様な地域から労働者が流入してきたということにおいて、この国際化は新たな位相となる。より本質的には、日本の経済が世界資本主義において大きなウェイトを占めるに至り、国際的な労働力移動をよりダイナミックに惹起させ始めたことにおいて、東京という都市は世界性、国際性を具体的に獲得しつつあるといっていいのである。
発展途上国の大都市の多くは植民都市としての出自をもち、宗主国の植民地支配のメディアとして機能してきた。その結果、先進諸国にはみられない、奇形的な、過大な都市化が起こった。そうした都市はプライメイト・シティ[xiv]14(首座都市・単一支配型都市)と呼ばれる。首都圏に総人口の四分の一が集中する東京は、むしろ発展途上国のプライメイト・シティに近いというべきかもしれないのであるが、外国人労働者の流入という現象は、東京がアジアを中心とする発展途上国の大都市をサテライト都市とするメトロポリスであることを示す。
そうしたの諸都市のネットワークの中心としての東京は、イメージとして、大東亜共栄圏の首都としての東京に重なり合うと言えるだろう。経済支配の構造がそのネットワークをしっかり支えているのである。
電脳都市・・・人工都市化
具体的に都市の内部に目を向けてみよう。何が進行しつつあるのか。いくつかの方向性がはっきり指摘できる。例えば、インテリジェント化であり、人工都市化である。もちろん、そうした方向性は以前から一貫するものといえるのであるが、インテリジェントビルや東京ドームの出現は、ある究極的な都市のイメージを実感させる。すなわち、情報機器、コンピューター機器を搭載したインテリジェントビルの林立する都市のイメージ、あるいは、都市環境全体を完全に人工的にコントロールするドームで覆われた都市のイメージである。
建設にかかわるテクノロジーの水準によって物理的には規定されるのであるが、ありとあらゆる空間はこうして等しく利用可能なものとなる。そして、ありとあらゆる空間は、等しく投機の対象となる。空間の均質化徹底進行と言ってもいい。ただ、あらゆる場所が均質化していくイメージは、コンピュータ技術による情報メディアのネットワークの出現と人工的な環境コントロールの技術の出現によって具体的なものとなったのである。
人工都市化によって、都市の自然や歴史は抹殺される。意味をもつのは、いつでも自由に利用可能な空間、そのボリュームである。また、人工都市に意味をもつのは、現在という時間だけである。二十四時間の一刻一秒が等価となる。
時間や空間が均質化し、あらゆる差異が無差異化していく、そうした都市のイメージは、もう少し、具体的に、都市生活のあり方に即してみることができる。
すなわち都市は人々が生活していく場としての意味を希薄化させつつるのである。わかりやすいのは、いわゆるインナーシティ問題、都市の空洞化である。都心は最早人々が住めるような空間ではない。少なくとも、住宅が立地する条件はほとんど失われつつある。より投資効果の高いオフィス区間へと次々に置き換えられているのである。
住宅そのものもまた大きくそのイメージを変えつつある。電脳住宅などという、完全にコンピューターによって管理されるモデル住宅の出現もそうであるが、より大きいのは住宅に内包されていたさまざまな機能が外化し家事労働が完全にサーヴィス産業によって代替されつつあることである。ホテルをイメージすればいい。既にいくつかそうしたマンションが出現しているのであるが、そこでは住宅はインテリジェント・オフィス同様、諸装置のビルトインされた単なる容器に還元されつつあるのである。
映像都市・・・仮設部都市
完璧に人工的にコントロールされた都市のイメージに対しても、もちろん、多くの疑念が提出される。特に、都市の物質的基盤にかかわる、エコロジカルな観点からはそうである。完全に人工的にエコロジー・バランスをとった形で、東京湾をすべて埋め立てることなどが果たして可能なのか、また、同じように大規模な地下空間を開発して、地下水などのバランスを制御できるのか。テクノロジーに対する底抜けの楽天主義がなければ、人工都市化を究極的な都市のイメージとして思い描くことはできないのである。
そこでもうひとつの都市のイメージが生み出される。人工都市を人工の映像とみる都市のイメージである。映像メディアの発達は、これまでに考えられなかった視角をわれわれに与える。人工衛星からの視角や、電子顕微鏡による視角が、視覚をはるかに拡大すると同時に、日常的な身体の視角を相対化させた。また、フィクショナルなものとリアルなものとの境界が不鮮明となり、映像そのものの世界が優位となる。
具体的な都市の景観もひとつの映像としてとらえられるようになる。人工都市化によって、また、都市の高層化によって、思いもかけない視角がわれわれのものとなる。超高層の最上階に川が流れ、地下に野球場ができる。あらゆる場所が、どんな場所にでも人工的になりうるのであれば、その世界は限りなく映像の世界に近づく。スキー場の隣に海水浴場があっても、どんな空間が組み合わされようとおかしくはないのである。
具体的には、博覧会の会場のような空間をイメージすればいいかもしれない。今日の博覧会において、建造物は最早クリスタルパレスやエッフェル塔の時代のような主役ではない。主役は、映像メディアである。大型立体スクリーンとかマルチスクリーンとか、アストロラマとかいったスクリーンを装備したパビリオンにおける映像体験がメインである。建造物は仮設であり、映像的な体験のみが意味をもつ。現実の都市はますます博覧会の仮設の都市に似つつあるのである。
人工都市といっても、それが建造物によって、すなわちフィジカルな実態によって構成されるのだとすれば、あらゆる場所を均質なものとしてつくることは不可能である。また、フィジカルな実態が耐用年限といった物質的な限界をもつとすれば、時代の流れを無化することはできない。人工都市のイメージはあくまでイメージとしてのみ成立する。
そこで、具体的な建造物として最もふさわしのは仮設建築である。仮設建築のイメージのみが永続的な空間のイメージを表現し得るし、あらゆる場所を、どんな場所にでも転換するためには、実際には、すぐに壊せる、テンポラリーな建造物が最もふさわしいからである。また、スクラップ・アンド・ビルドによって、空間を次々と更新することが資本にとっても好都合なのである。
こうして、仮設都市の表層をポストモダンの建築デザインが覆い始めている理由を理解することができる。人工都市の究極イメージにおいて、ありとあらゆる空間は併置される。ありとあらゆる時代から、ありとあらゆる地域からさまざまなデザイン・エレメントが集められるのは、その映像による代替なのである。
都市の完成・・・都市の死
飽和の臨界に達する時点で都市は究極的に完成する。都市か一〇〇パーセント社会の実現である。そこでは地球全体が人工都市化する段階がイメージされるかもしれない。しかし、それ以前に、現実の都市は物理的に限界づけられており、東京が既にその兆候を示し始めたように、飽和状態の都市、都市の完成のイメージは極めて具体的なのである。
完全にフロンティアが消滅するとすれば、しかし、それは都市そのものの死を意味する。そこで問題となるのはその維持システムであり、循環システムである。都市のフィジカルな形態について、そのシステムはわかりやすい。すなわち、仮設建築によるスクラップ・アンド・ビルドの更新システムこそ究極の都市のイメージにふさわしいのである。
空間の生産・消費の循環は仮設建築・解体のシステムにおいてよりスムーズになしうる。モニュメンタルな建造物は不都合である。空間の生産・消費のシステムを支えるのがインベンストメント・テクノロジーである。空間そのものの生産のみならず、空間をみたものやサーヴィスについても同様である。その更新、循環のシステムが完成することにおいてのみ、究極の人工都市は完成し、維持されるはずである。
だがしかし、その究極の都市を支えるシステムが確立しうるかどうかは定かではない。その完成はひとつのフィクションといえるかもしれない。しかし、そのフィクションが既に現実の都市を支配しつつあるのである。
こうして東京に即して、究極の人工都市、都市の完成をイメージしてみるとき、都市論の役割はおのずと見えてこよう。レトロスペクティブな東京論にも、ポストモダンの都市論にも、東京改造論にも欠けているのは、都市の究極的イメージである。すなわち、都市の死を確認する視座がそれらにはない。その一歩手前で、ただ都市の現在が肯定されているのである。
[i]1 拙稿、『早稲田文学』、一九八九年七月。『イメージとしての帝国主義』(青弓社 一九九〇年)所収。
[ii]2 文部省科学研究費補助金重点領域研究「比較の手法によるイスラームの都市性の総合的研究」(一九八八年~一九九一年)における研究集会。
[iii]3 シリアの中心都市。キャラバン交易の中心となるオアシス都市。前一一世紀にはアラム人の首都として知られる。一一世紀末の十字軍時代以降に現在に至るイスラーム都市の基礎が築かれた。
[iv]4 イラン中央部の都市。起源は古く、バビロン捕囚(前六世紀)を逃れたユダヤ人によってつくられたという説がある。七世紀にアラブ人の支配下に入り、一〇世紀には現在の市街地の原型が出来上がった。一一世紀にセルジューク朝の中心都市として繁栄し、以後諸勢力の争奪の対象となった。一六世紀にサファヴィー朝の首都となり、オスマン帝国の首都首都イスタンブルと並ぶ西アジア・イスラーム世界の中心として栄華を極めた。一七世紀後半に人口五〇万人を数えたという。一九世紀になると首都機能をテヘランに、貿易中心としての機能をタブリーズに奪われることになる。
[v]5 トルコ共和国第一の都市。ボスフォラス海峡を挟んでアジアとヨーロッパの境界に位置する世界有数の歴史都市。三三〇年にローマ皇帝コンスタンティヌスが首都を置く。以後一〇〇〇年にわたってローマ、ビザンチンの都として地中海世界の中心であり続ける。一四五三年、コンスタンティノープルは陥落し、以後、オスマン帝国の首都となる。ギリシャ語で「町へ」を意味するイスティンポリを語源にすると言われる。トルコ語風に解釈され、イスラムボル(イスラームで充ちたという意)の形で用いられる。
[vi]6 ムガール帝国の帝都。現在の旧城(ラール・キラー)は、五代皇帝シャージャ・ハーンによって築かれた。荒松雄『多重都市デリー』(中公新書)がその歴史を重層的に明らかにしている。
[viii]8 インド、西ベンガル州の州都。ベンガル湾河口から一〇〇キロあまり遡ったフーグリー川東岸に位置する。前三世紀、アショーカ王の時代に港があり、プトレマイオスの地図にはタマリテスと記述されている。中国僧法顕や義浄も滞在した。一五世紀にイスラーム勢力の軍営地が築かれ、一六世紀にはヨーロッパ勢力が西河畔に位置した。一六九八年、イギリス東インド会社が町を設立した。カルカッタの名称はこの時の地名に由来する。ウイリアム要塞(一七〇二)が築かれ、英国人居住区が形成されるとともに、東インドの要衝として発展。一八五八年、イギリスのインド支配の中心都市となるが、一九三一年のデリー遷都で帝都から一地方都市となった。大都市圏は一〇〇〇万人を超えるインドでも有数の都市。
[ix]9 インドネシア、スラウェシ島南部の交易都市。かってのマッカサル。一七、一八世紀に島嶼部全体の奴隷交易の中心であった。
[x]10 イスラーム教の聖地。世界の中心であり、全世界のムスリムはそこへ向かって一日五回の礼拝が義務づけられている。アラビア半島の紅海に沿って走る山脈の西斜面の谷間に発達した町。起源は定かではないが、イスラーム以前からカーバ神殿があり、巡礼の目的地であった。コーランにはメッカという地名は一度も登場しない。後藤明、『メッカーイスラーム都市社会』、中央公論社、一九九一年。
[xi]11 イラン北東部、ホラーサーン州の都市。三世紀にササン朝のシャープール一世によって、東方への防衛拠点として建設された町。九世紀のターヒル朝の首都として発展。円形の城壁と市壁をもつ典型的なイラン都市の形態をもつ。
[xii]12 「都市計画のいくつかの起源とその終焉」Ⅱー① 参照
[xiii]13 松山巌『乱歩と東京』(パルコ出版)、陣内秀信『東京の空間人類学』(筑摩書房)、藤森照信の『明治の東京計画』(岩波書店)が建築、都市計画の分野からの火付け役となった。
[xiv]14 ある国、ある地域の諸都市の人口規模をみると、ひとつの大都市が突出した人口規模をもち第二位以下の都市との落差が極めて大きいケースが見られる。先進諸国の場合、都市の規模には一定の比例関係(順位規模配列 ランク・サイズ・ルール)が見られるのに対して、発展途上国にそうした都市が多い。タイのバンコク、ジャワのジャカルタ、ルソン島のマニラなどがそうである。