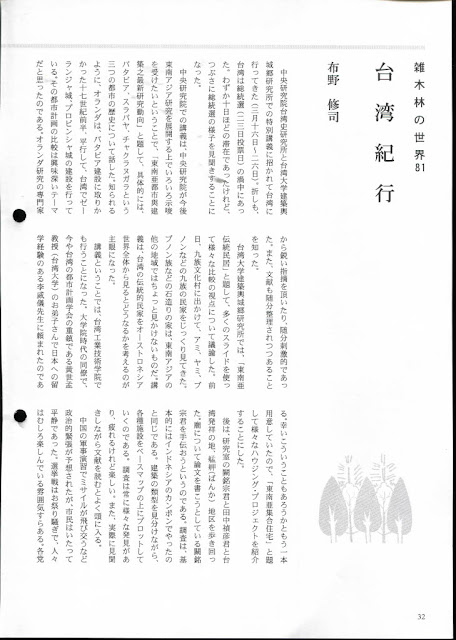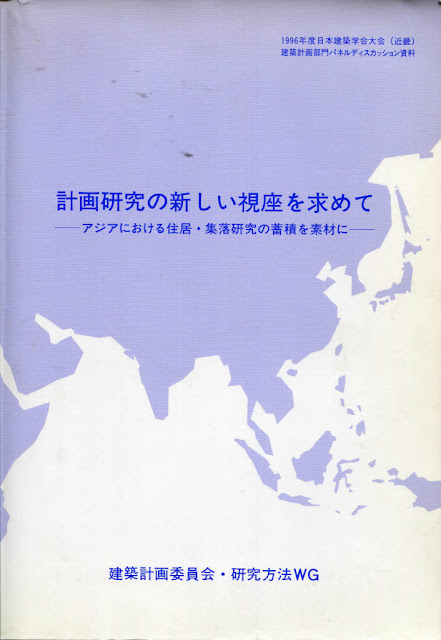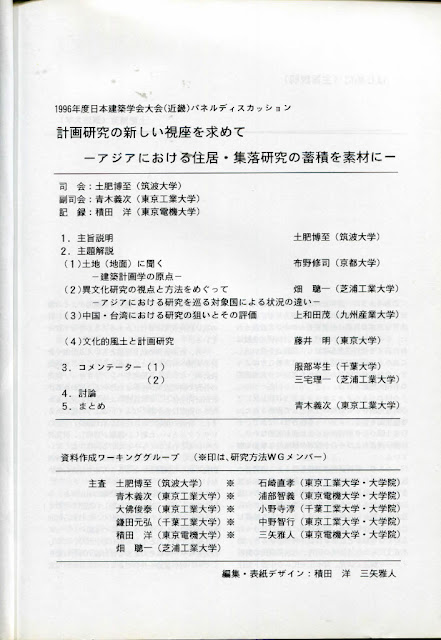阪神大震災研究の復旧・復興過程に関する研究(主査 室崎益輝 分担執筆),日本住宅総合研究所,1996年
復旧・復興計画手法の評価
Ⅰ章 2-2 復旧・復興計画手法の評価(布野修司)
阪神・淡路大震災は、多くの人々の命を奪った。かけがえのない命にとって全ては無である。残された家族の人生も取り返しのつかないものとなった。復旧・復興計画といっても、旧に復すべくない命にとっては空しい。残されたものに課せられているのは、阪神・淡路大震災の教訓を反芻し、続けることであろう。震災2ヶ月後に起こった「地下鉄サリン事件」(1995年3月20日)とそれに続く「オーム真理教」をめぐる衝撃的事件のせいもあって、阪神・淡路大震災に関する一般の関心は急速に薄れていったように見える。被災地は見捨て去られたかのようであった。直接に震災を体験したもの以外にとって、震災の経験は急速に風化していく。震災の経験は必ずしも蓄積されない。もしかすると、最大の教訓は震災の経験が容易に忘れ去られてしまうことである。
震災後3年を経て、被災地は落ち着きを取り戻したように見える。ライフライン(電力、都市ガス、上水道、下水道、情報・通信)に関わる都市インフラストラクチャーの復旧が最優先で行われるとともに、応急仮設住宅の建設から復興住宅の建設へ、住宅復興も順調に進んできたとされる。また、市街地復興に関しても、重点復興地域を中心に、各種復興事業が着々と進められている。
しかし、全て順調かというと、必ずしもそうは言えない。重点復興地域のなかにも、合意形成がならず、一向に復興計画事業が進展しない地区もある。また、「白地」地区と呼ばれる、重点復興地域から外され基本的に自力復興が強いられた8割もの広大な地区のなかに空地のみが目立つ閑散とした地区も少なくない。それどころか、復旧・復興計画の問題点も指摘される。例えば、復興住宅が供給過剰になり、民間の住宅賃貸市場をスポイルする一方、被災者の生活にとって相応しい立地に少ない、といったちぐはぐさが目立つのである。
復旧・復興計画の具体的な展開と問題点は、自治体毎に、また、地区毎に、さらに計画(事業)手法毎に以下の章でまとめられている。本稿ではいくつかの評価軸を提出することによって、共通の問題点を指摘し、復旧・復興計画手法の評価を試みたい。
2-2-1 復旧・復興計画の非体系性
復旧・復興計画の全体は、いくつかの軸によって立体的に捉える必要がある。まず、応急計画、復旧計画、復興計画という時間軸に沿った各段階における計画の局面がある。また、計画対象区域のスケールによって、国土計画、地域計画、都市計画、地区計画というそれぞれのレヴェルの問題がある。さらに、国、県、市町村といった公的計画主体としての自治体、民間、住民、プランナーあるいはヴォランティアといった様々な計画主体の絡まりがある。すなわち、少なくとも、どの段階の、どのレヴェルの計画手法を、どのような立場から評価するかが問題である。
また、それ以前に、復旧・復興計画の評価は、フィジカルプランニングとしての復旧・復興計画の手法に限定されるわけではない。震災のダメージは生活の全局面に及んだのであって、単に物的環境を復旧すれば全てが回復されるというわけではないのである。住宅を失うことにおいて、あるいは大きな被害を受けることにおいて、経済的な打撃は計り知れない。住宅・宅地の所有形態や経済基盤によってそのインパクトは様々であるが、多くの人々が同じ場所に住み続けることが困難になる。その結果、地域住民の構成が変わる。地域の経済構造も変わる。ダメージを受けた全ての住宅がすぐさま復旧され(ると公的、社会的に保証され)たとしたら、事態はいささか異なったかもしれない。しかし、それにしても、数多くの犠牲者を出すことにおいて家族関係や地域の社会関係に与えた打撃はとてつもなく大きい。避難生活、応急生活において問われたのはコミュニティの質でもあった。また、大きなストレスを受けた「こころ」の問題が、物理的な復旧・復興によって癒されるものではないことは予め言うまでもないことである。
復旧・復興計画の評価は、以上のように、まず、その体系性、全体性が問題にされるべきである。すなわち、地域住民の生活の全体性との関わりにおいて復旧・復興計画は評価されるべきである。そうした視点から、予め、阪神・淡路大震災後の復旧・復興計画の問題点を指摘できる。その全体は必ずしも体系的なものとは言えないのである。まず指摘すべきは、復旧・復興計画の全体よりも、個別の事業、個別の地区計画の問題のみが優先されたことである。例えば、仮設住宅の建設場所、復興住宅の供給等、地域全体を視野に入れた計画的対応がなされたとは言い難いのである。また、合意形成を含んだ時間的なパースペクティブのもとに将来計画が立てられなかった。既存の制度手法がいち早く(予め)前提されることによって、全体ヴィジョンを組み立てる土俵も余裕もなかったことが決定的であった。
2-2-2 復旧・復興計画の諸段階とフレキシビリティの欠如
震災復興は時間との戦いであり、時間的な区切りが大きな枠を与えてきた。
被災直後は、人々の生命維持が第一であり、衣食住の確保が最優先の課題である。ガス、水道、電気、電話、交通機関といったライフラインの一刻も早い復旧がまず目指された(ガスの復旧が完了したのが4月11日、水道復旧が完了したのが4月17日である)。そして、避難所の設置、避難生活の維持が全面的な目標となる。多くの救援物資が送られ、多くのヴォランティアが救援に参加した。未曾有の都市型地震ということで、また、高速道路が倒壊し、新幹線の橋脚が落下するといった信じられない事態の発生によって多くの混乱が起こった。リスクマネージメントの問題等、その未曾有の経験は今後の課題として生かされるべきものといえるであろう。むしろ、この段階の評価は、震災以前の防災対策、防災計画、さらに震災以前の都市計画の問題として、議論される必要がある。また、この大震災の教訓をどう復旧。復興計画に活かすかが問われていたといっていい。
最初に大きな閾になったのが3月17日(震災後2ヶ月)である。建築基準法第84条の地区指定により当面の建築活動を抑制する措置が相次いで取られたのである。この地区指定の問題は復旧・復興計画において大きな決定的枠組みを与えることになった。阪神間の自治体(神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、伊丹市)では、「震災復興緊急整備条例」が3月末までに相次いで制定されている。
続いて、仮設住宅の建設と避難所の解消が次の区切りとなる。仮設住宅入居申し込みは1月27日に開始されている。また、「がれきの処理」無償の期限が復旧の目標とされた。がれき処理の方針は震災10日後に出される。倒壊家屋の処理受け付けは早くも1月29日に開始されている。このがれき処理は結果的に多くの問題を含んでいた。補修、修繕によって再生可能な建造物も処理されることになったからである。ストックの活用という視点からは拙速に過ぎた。資源の有効再生という観点から、貴重な経験を蓄積する機会を逃したと言えるのである。さらに、まちの歴史的記憶としての景観の連続性について考慮する機会を失したのである。災害救助法に基づく避難所が廃止されたのは8月20日である。兵庫県が「救護対策現地本部」を完全撤収したのが8月10日、震災後ほぼ半年で復旧・復興計画は次の段階を迎えることになる。
その半年間に様々なレヴェルで復旧・復興計画が建てられる。国のレヴェルでは、「阪神・淡路大震災復興の基本方針および組織に関する法律」(2月24日公布 施行日から5年)に基づいて「阪神・淡路復興対策本部」が設置され、「阪神・淡路地域の復旧・復興に向けての考え方と当面講ずべき施策」(4月28日)「阪神・淡路地域の復興に向けての取り組指針」(7月28日)などが決定される。また、「阪神・淡路復興委員会」(下河辺委員会)が設けられ、2月16日の第1回委員会から10月30日まで14回の委員会が開催され、11の提言および意見がまとめられている。タイムスパンとしては「復興10ヶ年計画の基本的考え方」が提言に取りまとめられている。県レヴェルでは「阪神・淡路震災復興計画策定調査委員会」(三木信一委員長 5月11日発足)によって、都市、産業・雇用、保健・医療・福祉、生活・教育・文化の4部会の審議をもとにした3回の全体会議を経て6月29日に提言がなされている(「阪神・淡路震災復興計画(ひょうごフェニックス計画)」。
こうした基本理念や指針の提案の一方、具体的な指針となったのが県の「緊急3ヶ年計画」である。「産業復興3ヶ年計画」「緊急インフラ整備3ヶ年計画」「ひょうご住宅復興3ヶ年計画」が3本の柱になっている。住宅復興に関する助成の施策は、ほとんど3年の時限で立案され、ひとつの目標とされることになった。また、応急仮設住宅の在住期限が2年というのも3年がひとつの区切りとなった理由である。
緊急対応期、短期、中期、長期の時間的パースペクティブがそれぞれ必要とされるのは当然である。個々の復興計画理念、計画指針の評価は上に論じられるところである。
ひとつの大きな問題は、それぞれの間に整合性があるかどうかである。しかし、それ以前に、住民の日々の生活が優先されなければならない。そのためには、柔軟でダイナミックな現実対応が必要であった。しかし、復旧・復興計画を大きく規定したのは既存の法的枠組みである。従って、復旧・復興計画の体系性を問うことは基本的には日本の都市計画のあり方を問うことにもなる。
2-2-3 復旧・復興計画の事業手法と地域分断
復旧・復興計画を主導したのは土地区画整理事業である。あるいは市街地再開発事業である。震災4日後、建設省の区画整理課の主導でその方針が決定されたとされる。モデルとされたのは酒田火災(1976年)の復興計画である。あるいは戦災復興であり、関東大震災後の震災復興である。復興計画の策定が遅れれば遅れるほど、復興への障害要因が増えてくる、復興計画には迅速性が要求される、という「思い込み」が、日本の都市計画思想の流れにひとつの大きな軸として存在している。関東大震災の復興も、戦災復興も結局はうまくいかなかった、酒田の場合は、迅速な対応によって成功した、という評価が建設省当局にあったことは明らかである。区画整理事業は、権利関係の調整に長い時間を要する。逆に、震災は土地区画整理事業を一気に進めるチャンスと考えられたといっていいだろう。
2月1日、神戸市、西宮市で建築基準法第84条による建築制限区域が告示され、2月9日、芦屋市、宝塚市、北淡町が続いた。第84条の第2項は1ヶ月をこえない範囲で建築制限の延長を認める。すなわち2ヶ月がタイムリミットとされ、都市計画法第53条による建築制限に移行するために、3月17日までに都市計画決定を行うスケジュールが組まれた。この土地区画整理事業の突出は復旧・復興計画の性格を決定づける重みをもったといっていい。少なくとも以下の点が指摘される。
①復旧・復興計画は、基本的に既存の都市計画関連制度に基づいて行われた。また、その方針は極めて早い段階で決定された。復旧・復興計画の全体ヴィジョンを構想する構えはみられない。関東大震災後、あるいは戦災復興時のように「特別都市計画法」の立法が試みられなかったことは、復旧復興計画を予め限定づけた。
②2月26日に「被災市街地復興特別措置法」が施行されるが、既存の制度的枠組みを変えるものではなく、震災特例を認める構えをとったものであった。土地区画整理事業および市街地再開発事業を都市計画決定するために後追い的に構想制定されたものである。
③復旧復興計画は、法的根拠をもつ土地区画整理事業および市街地再開発事業を中心として展開された。また、その都市計画決定の手続きが復旧・復興計画のスケジュールを決定づけた。「被災市街地復興特別措置法」によって復興促進地域に指定すれば2年間の建築制限が可能となったが、全ての地区で既往のプロセスが優先された。
④土地区画整理事業、市街地再開発事業の決定は、基本的にトップ・ダウンの形で行われ、住民参加のプロセスを前提としなかった。あるいは形式的な手続きを優先する形で決定された。決定の迅速性(拙速性)の反映として、都市計画審議会は「今後、住民と十分意見交換すること」という付帯条件がつけられる。また、骨格の決定のみで、細部の具体的な計画案は追加決定するという異例の「2段階方式」が取られた。
こうして被災地区は、土地区画整理事業、市街地再開発事業の実施地域とそれ以外の大きく二分化されることになった。いわゆる「重点復興地域」とそれ以外の「震災復興促進区域」の区別(差別)である。注目すべきは、震災以前からの継続事業、予定事業が総じて優先され、重点的に実施されることになったことである。震災復興計画と震災以前の都市計画は一貫して連続的に捉えられているひとつの証左である。決定的なのは、再開発事業の具体的イメージが画一的かつ貧困で、都市拡張主義の延長に描かれていることである。
事業手法としては、もちろん、土地区画整理事業、市街地再開発事業に限られるわけではない。住宅復興あるいは住環境整備については、「住宅市街地総合整備事業」と「密集住宅市街地整備促進事業」を中心とする法的根拠をもたない任意事業としての住環境整備事業および住宅供給事業、あるいは住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業(法的根拠をもつ)が復旧復興計画として想定されている。
すなわち、被災地は復旧復興計画の事業(制度)手法によって以下のように3分割されることになった。俗に「黒地地域」「灰色地域」「白地地域」と呼ばれる。
A地域(黒地地域)
土地区画整理事業10地区
市街地再開発事業6地区
B地域(灰色地域)
住宅市街地総合整備事業11地区
密集住宅市街地整備促進事業6地区
住宅地区改良事業5地区
C地域(白地地区)
具体的には建築基準法84条(「建築制限」)による指定地区、被災市街地復興都市計画(「被災市街地復興推進地域」)による指定地区、震災復興緊急整備条例(「震災復興促進区域」「重点復興区域」)による指定地区、あるいは被災地における街並み・まちづくり総合支援事業による指定地区が区別されるが、ABの各地区にはダブりがある。各事業手法が組み合わせて適応される場合が少なくない。
復旧復興計画の問題は、この線引きによって、A(B)地域の問題のみに焦点が当てられることになる。大半の地域はいわば見捨てられ、その復旧復興は公的支援のない自力復興あるいはなんのインセンティヴも設定されない通常の都市計画の問題とされた。また、それ以前に、復興計画の全体がそれぞれの地域の、しかも住環境整備の問題にされたことが大きい。都市計画全体のパラダイムを考える契機は予め封じられたと言っていい。具体的には、個別事業のみが問題とされ、全体的連関は予め問題にされなかったのである。
2-2-4 コミュニティ計画の可能性
以上のように、阪神淡路大震災によって、日本の都市計画を支えてきた制度的枠組みが大きく変わったわけではない。大震災があったからといって、そう簡単にものごとの仕組みが変わるわけはない。関東大震災後も、戦災復興の時にも、そして、今度の大震災の後も、日本の都市計画は同じようなことを繰り返すだけではないのか。要するに、何も変わらないのではないか、と思えてくる。
各地区の復旧復興計画は必ずしもうまくいっているわけではない。合意形成がならず袋小路に入り込んでいるケースも少なくない。震災が来ようと来まいと、基本的な都市計画の問題点が露呈しただけであるという評価もある。確かに、どこにも遍在する日本の都市計画の問題を地震の一揺れが一瞬のうちに露呈させたという指摘はできるだろう。
一方、阪神淡路大震災のインパクトが現れてくるまでには時間がかかるであろうことも確かである。その経験に最大限学ぶことが極めて重要である。特に地区計画レヴェルにおいてはプラスマイナスを含めた大きな経験の蓄積がなされたとみるべきであろう。
建築家、都市計画プランナーたちは、それぞれ復旧、震災復興の課題に取り組んできた。コンテナ住宅の提案、紙の教会の建設、ユニークで想像力豊かな試みもなされてきた。この新しいまちづくりへの模索は実に貴重な蓄積となるはずである。
今回の震災によって、一般的にヴォランティアの役割が大きくクローズアップされた。まちづくりにおけるヴォランティアの意味の確認は重要である。もちろん、ヴォランティアの問題点も既に意識される。行政との間で、また、被災者との間で様々な軋轢も生まれたのである。多くは、システムとしてヴォランティア活動が位置づけられていないことに起因する。
被災度調査から始まって復興計画に至る過程で、建築家、都市計画プランナーが、ヴォランティアとして果たした役割は少なくない。しかし、その持続的なシステムについては必ずしも十分とは言えない。ある地区のみ関心が集中し、建築、都市計画の専門家の支援が必要とされる大半の地区が見捨てられたままである。また、行政当局も、専門家、ヴォランティアの派遣について、必ずしも積極的ではない。粘り強い取り組のなかで、日常的なまちづくりにおける専門ヴォランティアの役割を実質化しながら状況を変えていくことになるであろう。
復旧復興計画は行政と住民の間に様々な葛藤を生んだが、とにかくその過程で新しい街づくりの仕組みの必要性が認識されたことは大きい。また、実際に、コンサルタント派遣や街づくり協議会の仕組みがつくられ試されてきた。この住民参加型のまちづくりの仕組みは大きく育てていく必要があるだろう。個別のプロジェクト・レヴェルでも、マンション再建のユニークな事例やコレクティブ・ハウスの試行など注目すべき取り組がある。
復旧復興の多様な経験から、あらたなまちづくりの仕組みをつくりだすことができるかどうかがコミュニティ計画レヴェルの評価に関わる。無数の種が芽生えつつあると考えたい。
2-2-5 阪神淡路大震災の教訓
a 人工環境化・・・自然の力・・・地域の生態バランス
阪神・淡路大震災に関してまず確認すべきは自然の力である。いくつものビルが横転し、高速道路が捻り倒された。地震の力は強大であった。また、避難所生活を通じての不自由さは自然に依拠した生活基盤の大事さを思い知らせてくれた。水道の蛇口をひねればすぐ水が出る。スイッチをひねれば明かりが灯る。エアコンディショニングで室内気候は自由に制御できる。人工的に全ての環境をコントロールできる、というのは不遜な考えである。災害が起こる度に思い知らされるのは、自然の力を読みそこなっていることである。山を削って土地をつくり、湿地に土を盛って宅地にする。そして、海を埋め立てるという形で都市開発を行ってきたのであるが、そうしてできた居住地は本来人が住まなかった場所だ。災害を恐れるから人々はそういう場所には住んでこなかった。その歴史の智恵を忘れて、開発が進められてきたのである。
まず第一に自然の力に対する認識の問題がある。関西には地震がない、というのは全くの無根拠であった。軟弱地盤や活断層、液状化の問題についていかに無知であったかは大いに反省されなければならない。一方、自然のもつ力のすばらしさも再認識させられた。例えば、家の前の樹木が火を止めた例がある。緑の役割は大きい。自然の河川や井戸の意味も大きくクローズアップされた。
人工環境化、あるいは人工都市化が戦後一貫した都市計画の趨勢である。自然は都市から追放されてきた。果たして、その行き着く先がどうなるのか、阪神・淡路大震災は示したといえるのではないか。「地球環境」という大きな枠組みが明らかになるなかで、また、日本列島から開発フロンティアが失われるなかで、自然の生態バランスに基礎を置いた都市、建築のあり方が模索されるべきことが大きく示唆される。
b フロンティア拡大の論理・・・開発の社会経済バランス
阪神・淡路大震災の発生、避難所生活、応急仮設住宅居住、そして復旧・復興へという過程において明らかになったのは、日本社会の階層性である。すぐさまホテル住まいに移行した層がいる一方で、避難所が閉鎖されて猶、避難生活を続けざるを得ない人たちが存在した。間もなく出入りの業者や関連企業の社員に倒壊建物を片づけさせる邸宅がある一方で、長い間手つかずの建物がある。びくともしなかった高級住宅街のすぐ隣で数多くの死者を出した地区がある。
最もダメージを受けたのは、高齢者であり、障害者であり、住宅困窮者であり、外国人であり、要するに社会的弱者であった。結果として、浮き彫りになったのは、都市計画の論理や都市開発戦略がそうした社会的弱者を切り捨てる階層性の上に組み立てられてきたことである。
ひたすらフロンティアを求める都市拡大政策の影で、都心地区が見捨てられてきた。開発の投資効果のみが求められ、居住環境整備や防災対策など都心への投資は常に後回しにされてきた。
例えば、最も大きな打撃を受けたのが「文化」である。関西で「ブンカ」というと「文化住宅」というひとつの住居形式を意味する。その「文化住宅」が大きな被害にあった。木造だったからということではない。木造住宅であっても、震災に耐えた住宅は数しれない。木造住宅が潰れて亡くなった方もいるけれど家具が倒れて(飛んで)亡くなった方が数多い。大震災の教訓は数多いけれど、しっかり設計した建物は総じて問題はなかった。「文化住宅」は、築後年数が長く、白蟻や腐食で老朽化したものが多かったため大きな被害を受けたのである。戦後の住宅政策や都市政策の貧困の裏で、「文化住宅」は、日本の社会を支えてきた。それが最もダメージを受けたのである。それにしても「文化住宅」とは皮肉な命名である。阪神・淡路大震災によって、「文化住宅」の存在という日本の住宅文化の一断面が浮き彫りになったといえる。
都市計画の問題として、まず、指摘されるのは、戦後に一貫する開発戦略の問題点である。拡大成長政策、新規開発政策が常に優先されてきた。都心に投資するのは効率が悪い。時間がかかる。また、防災にはコストがかかる。経済論理が全てを支配するなかで、都市生活者の論理、都市の論理が見失われてきた。都市経営のポリシー、都市計画の基本論理が根底的に問われたといっていい。
c 一極集中システム・・・重層的な都市構造・・・地区の自律性
日本の大都市は、移動時間を短縮させるメディアを発達させひたすら集積度を高めてきた。郊外へのスプロールが限界に達するや、空へ、地下へ、海へ、さらにフロンティアを求め、巨大化してきた。その一方で都市や街区の適正な規模について、われわれはあまりに無頓着であったことが反省される。
都市構造の問題として露呈したのが、一極集中型のネットワークの問題点である。大震災が首都圏で起きていたら、東京一極集中の日本の国土構造の弱点がより致命的に問われたのは確実である。阪神間の都市構造が大きな問題をもっていることは、インフラストラクチャーの多くが機能停止に陥ったことによって、すぐさま明らかになった。それぞれに代替システム、重層システムがなかったのである。交通機関について、鉄道が幅一キロメートルに四つの路線が平行に走るけれど迂回する線がない。道路にしてもそうである。多重性のあるネットワークは、交通インフラに限らず、上下水道などライフラインのシステム全体に必要である。
エネルギー供給の単位、システムについても、多核・分散型のネットワーク・システム、地区の自律性が必要である。ガス・ディーゼル・電気の併用、井戸の分散配置など、多様な系がつくられる必要がある。また、情報システムとしても地区の間に多重のネットワークが必要であった。
d 公的空間の貧困
また、公共空間の貧困が大きな問題となった。公共建築の建築としての弱さは、致命的である。特に、病院がダメージを受けたのは大きかった。危機管理の問題ともつながるけれど、消防署など防災のネットワークが十分に機能しなかったことも大きい。想像をこえた震災だったということもあるが、システム上の問題も指摘される。避難生活、応急生活を支えたのは、小中学校とコンビニエンスストアであった。地域施設としての公共施設のあり方は、非日常時を想定した性能が要求されるのである。
また、クローズアップされたのは、オープンスペースの少なさである。公園空地が少なくて、火災が止まらなかったケースがある。また、仮設住宅を建てるスペースがない。地区における公共空間の、他に代え難い意味を教えてくれたのが今回の大震災である。
e 地域コミュニティのネットワーク・・・ヴォランティアの役割
目の前で自宅が燃えているのを呆然とみているだけでなす術がないというのは、どうみてもおかしい。同時多発型の火災の場合にどういうシステムが必要なのか。防火にしろ、人命救助にしろ、うまく機能したのはコミュニティがしっかりしている地区であった。救急車や消防車が来るのをただ待つだけという地区は結果として被害を拡大することにつながった。
阪神淡路大震災において最大の教訓は、行政が役に立たないことが明らかになったことだ、という自虐的な声がある。一理はある。自治体職員もまた被災者である。行政のみに依存する体質が有効に機能しないのは明らかである。問題は、自治の仕組みであり、地区の自律性である。行政システムにしろ、産業的な諸システムにしろ、他への依存度が高いほど問題は大きかった。教訓として、その高度化、もしくは多重化が追求されることになろう。ひとつの焦点になるのがヴォランティア活動である。あるいはNPO(非営利組織)の役割である。
f 技術の社会的基盤の認識・・・ストック再生の技術の必要
何故、多くのビルや橋、高速道路が倒壊したのか。何故、多くの人命が失われることになったのか。問題なのは、社会システムの欠陥のせいにして、自らのよって立つ基盤を問わない態度である。問題は基準法なのか、施工技術なのか、検査システムなのか、重層下請構造なのか、という個別的な問いの立て方ではなくて、建築を支える思想(設計思想)の全体、建築界を支える全構造(社会的基盤)がまずは問われるべきである。建造物の倒壊によって人命が失われるという事態はあってはならないことである。しかし、それが起こった。だからこそ、建築界の構造の致命的な欠陥によるのではないかと第一に疑ってみる必要がある。
要するに、安全率の見方が甘かった。予想をこえる地震力だった。といった次元の問題ではないのではないか、ということである。経済的合理性とは何か。技術的合理性とは何か。経済性と安全性の考え方、最適設計という平面がどこで成立するのかがもっと深く問われるべきである。
建築技術の問題として、被災した建造物を無償ということで廃棄したのは決定的なことであった。都市を再生する手がかりを失うことにつながったからである。特に、木造住宅の場合、再生可能であるという、その最大の特性を生かす機会を奪われてしまった。廃材を使ってでも住み続ける意欲のなかに再生の最初のきっかけもあったといっていい。
何故、鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物の再生利用が試みられなかったのも問題である。技術的には様々な復旧方法が可能ではないか。そして、関東大震災以降、新潟地震の場合など、かなりの復旧事例もある。阪神・淡路大震災の場合、少なくとも、再生技術の様々な方法が蓄積されるべきであった。
j 都市の記憶と再生
阪神・淡路大震災は、人々の生活構造を根底から揺るがし、都市そのものを廃棄物と化した。建てては壊し、壊しては建てる、阪神・淡路大震災は、スクラップ・アンド・ビルドの日本の都市の体質を浮かび上がらせたともいえる。復旧復興計画は、当然、これまでにない都市(建築)のあり方へと結びついていかねばならない。
そこで、都市の歴史、都市の記憶をどう考えるのかは、復興計画の大きなテーマである。何を復旧すべきか、何を復興すべきか、何を再生すべきか、必然的には都市の固有性、歴史性をどう考えるかが問われるのである。
建造物の再生、復旧が、まず大きな問題となる。同じものを復元すればいいのか、という問いを前にして、基本的な解答を求められる。それはもちろん、震災があろうとなかろうと常に問われている問題である。都市の歴史的、文化的コンテクストをどう読むか、それをどう表現するかは、日常的テーマである。
戦災復興でヨーロッパの都市がそう試みたように、全く元通りに復旧すればいいというのであれば簡単である。しかし、そうした復旧の理念は、日本においてどう考えても共有されそうにない。都市が復旧に値する価値をもっているかどうか、ということに関して疑問は多いのである。すなわち、日本の都市は社会的なストックとして意識されてきていないのである。スクラップ・アンド・ビルド型の都市でいいということであれば、震災による都市の破壊もスクラップのひとつの形態ということでいい。必ずしも、まちづくりについてのパラダイムの変更は必要ないだろう。しかし、バブル崩壊後、スクラップ・ビルドの体制は必然的に変わっていかざるを得ないのではないか。
都市が本来人々の生活の歴史を刻み、しかも、共有化されたイメージや記憶をもつものだとすれば、物理的にもその手がかりをもつのでなければならない。都市のシンボル的建造物のみならず、ここそこの場所に記憶の種が埋め込まれている必要がある。極めて具体的に、ストック型の都市が目指されるとしたら、復興の理念に再生の理念、建造物の再生利用の概念が含まれていなければならない。また、それ以前に建築の理念そのものに再生の理念が含まれていなければならないだろう。
日本の都市がストックー再生型の都市に転換していくことができるかどうかが大きな問題である。都市の骨格、すなわち、アイデンティティーをどうつくりだすことができるか。単に、建造物を凍結的に復元保存すればいいのか、歴史的、地域的な建築様式のステレオタイプをただ用いればいいのか、地域で産する建築材料をただ使えばいいのか、・・・・議論は大震災以前からのものである。
阪神・淡路大震災は、こうして、日本の建築界の抱えている基本的問題を抉り出した。しかし、その解答への何らかの方向性をみい出しえたどうかはわからない。半世紀後の被災地の姿にその答えは明確となるであろう。しかし、それ以前に、半世紀前から同じ問いの答えが求められているとも言える。
*1 拙稿、「阪神大震災とまちづくり……地区に自律のシステムを」共同通信配信、一九九五年一月二九日『神戸新聞』、「阪神・淡路大震災と戦後建築の五〇年」、『建築思潮』4号、1996年、「日本の都市の死と再生」、『THIS IS 読売』、1996年2月号など 拙著、『戦後建築の終焉』、れんが書房新社、1995年、『戦後建築の来た道 行く道』、東京建築設計厚生年金基金、1995年