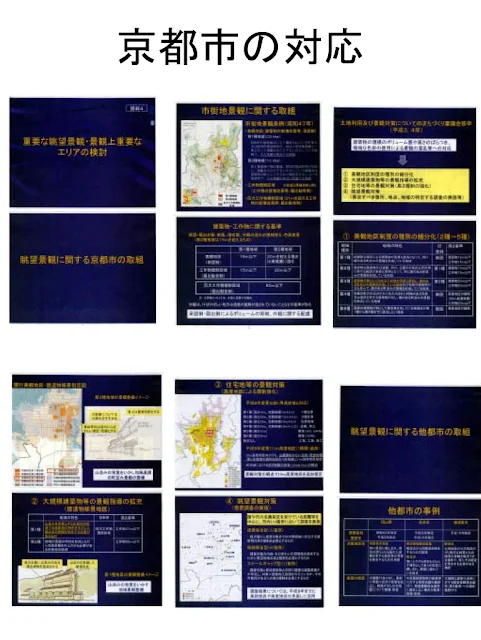基調講演,「環境への参画ー景観とまちづくりーコミュニティ・アーキテクトの可能性」,日本感性工学会感性哲学部会研究発表会,2007年3月30日
日本感性工学会感性哲学部会研究発表会
日時:平成19年3月30日(金)、31日(土)
場所:広島大学東千田キャンパス 共用講義室2
http://www.hiroshima-u.ac.jp/category_view.php?folder_name=access&lang=ja
プログラム
テーマ:「環境」を壊してみる
「環境」の概念がさまざまな領域で議論されるなか、その意味の細分化、硬直化も進みつつあります。今回のパネルディスカッションでは、環境と景観、環境と文化など、環境と関連する多様な領域を視野におき、その意味を総合的に捉えるための視点を再構築します。
3月30日(金)
13:00-16:00 一般研究発表
16:00-18:00 基調講演およびパネルディスカッション
基調講演:布野修司氏(滋賀県立大学教授)
パネラー:石丸紀興(広島国際大学教授)、大井健次(広島市立大学芸術学部長、クリエイティブ・ディレクター)
18:00~18:30 感性哲学部会総会
19:00-21:00 懇親会
3月31日(土)10:00~14:00
感性ツアー:広島市の平和環境を横断する(予定):比治山芸術公園〜平和大通り〜お好み村〜頼山陽記念館〜平和記念公園。
感性哲学部会長 桑子敏雄 実行委員長 千代章一郎
一般発表プログラム(発表7分、質疑3分)
13:00-13:10 柏崎尚也(東京電機大学)
『感性と感情の情報処理についての一考察』
13:10-13:20 和崎 宏(兵庫県立大学)
『地域SNSの効果と展望~WEB2.0環境によるネットコミュニケーションの変化』
13:20-13:30 浜田利満(筑波学院大学)・大久保寛基・大成尚
『認知症高齢者向けレクレーションにおける効果的ロボット・セラピー』
13:30-13:40 原田暢善(産業技術総合研究所関西センター)
『形式的環境および象徴的環境の破壊の大脳皮質脳活動への影響の検討』
13:40-13:50 豊田光世(東京工業大学)
『思考力の育成と環境倫理教育』
13:50-14:00 榊眸(三重大学)・安部剛・馬淵晶子・根津知佳子・松本金矢
『子どもの日常の音楽体験における形式をこわす~人と人・モノ・音とのかかわりを重視した活動の構築~』
14:00-14:10 北村真衣央(三重大学)・倉田真由美・根津知佳子
『音楽会の枠をこわしてみる~さわさわの匂い~』
14:10-14:20 根津知佳子・松本金矢(三重大学)
『子どもの感性を可視化する -沈黙から掬う-』
14:20-14:30 清水裕子、佐々木和也(宇都宮大学)
『万葉集にあらわされた染めと織り』
休憩(10分)
14:40-14:50 神頭成禎(兵庫県立大学)
『インドネシア慣習法的共同体社会における土地観念‐「所有者」か「使用者」か‐』
14:50-15:00 古賀弘一(兵庫県立大学)
『入会地をめぐる長尾契約講員の地域感性』
15:00-15:10 桑子敏雄(東京工業大学)
『日本の空間文化と環境・景観管理の課題』
15:10-15:20 千田智子(東京芸術大学)
『英国式風景庭園の現在』
15:20-15:30 千代章一郎(広島大学)
『広島市における小学生児童の平和環境表現』
15:30-15:40 清水義雄(信州大学)
『人工科学から自然科学への転換-景観から読み取れる科学の現状-』
基調講演およびパネルディスカッション『環境を壊してみる』
16:00-18:00
基調講演:布野修司氏(滋賀県立大学教授)
パネラー:石丸紀興氏(広島国際大学教授)、大井健次氏(広島市立大学芸術学部長、クリエイティブ・ディレクター)
コーディネータ:桑子敏雄氏(東京工業大学教授)
16:00-16:45 布野修司:「環境への参画」
日本・アジア・アフリカなど多様な「環境」の徹底したフィールドワークを通じて長年にわたり、植民都市やアジア諸都市の都市組織あるいは都市住宅のあり方を研究されてきた布野氏は地域の景観問題にも積極的に関与されている。どうして景観問題に取り組むようになったのか、また、景観を論じるための哲学についてご講演していただく。
略歴:1949年島根県生まれ。専門は都市生態環境史。著書に、『曼荼羅都市 ヒンドゥー都市の空間理念とその変容』(京都大学学術出版会,2006年)など多数。
16:45-18:00 パネルディスカッション
16:45-17:00 石丸紀興:「破壊された環境」
「環境」といえば自然環境を意味することが多いが、人間的な環境の一つの極である「戦争」についても議論を広げるべきであろう。戦争遺跡や廃墟の保全・再生に関する我々の認識は、イデオロギー的にも概ね定着しているように思われる。しかし、そのような場所の痕跡の扱いによっては、記憶の継承・教訓の場の意味を喪失していき、観光地化の問題も浮上する。長年、広島市の都市史、とりわけ復興期初期に提起された復興構想・理念やさらには世界の戦争廃墟について研究してきた石丸先生より、現代の戦争遺産の諸問題についてご講演いただき、壊された環境を持続することについて、今後の多様な保全的デザインの方策について話題提供をしてもらう。
略歴:1940年中国東北地方(旧満州)生まれ。広島大学大学院工学研究科教授を経て現職。専門は、都市計画史、特に戦災復興計画の研究、広島の戦後復興史研究、広島における建築家の活動と役割に関する研究、被爆建物の歴史と保存、日本の近代都市計画史研究。広島被爆40年史都市の復興(共編・共著、1985年、広島市)被爆50周年未来への記録—ヒロシマの被爆建造物は語る(共著、1996年、広島市)など論文・著書多数。
17:00-17:15 大井健次:「環境と芸術」
都市環境における廃棄物の問題は、その重要性にもかかわらず常に隠匿されてきた。それは負の環境であると同時に、今日では循環型社会の価値において積極的な意義を持つようになってきている。リサイクル・リユース・リデュースの機能論を越えて芸術に仕立てることの意義は何か。ゴミ処理施設が立地する吉島地区のアートプロジェクトを手がけている大井氏から、ゴミ環境を芸術にする戦略について、話題提供をしてもらう。
略歴:1945年広島県生まれ。主なプロジェクトとして、1996年広島市交通科学館企画展「カーデザイナー小林平治の夢とロマン」展監修、1996年宇品橋 デザイン実施計画・デザイン総合監修、1997年鷹野橋交差点 横断歩道橋デザイン基本計画・デザイン監修、1999年紙屋町地下街 環境・空間デザイン総合監修など多数。
17:15-18:00 討議
18:00-18:30 感性哲学部会総会
19:00-21:00 懇親会
瀬戸内の料理で歓談していただきます。
隠戸(一人5000円の飲み放題コース。学生3000円で残りを調整します)
広島電鉄袋町電停より徒歩5分 広島県広島市中区中町3−21 tel:082-249-2010
http://www.hotpepper.jp/A_20100/strJ000027320.html