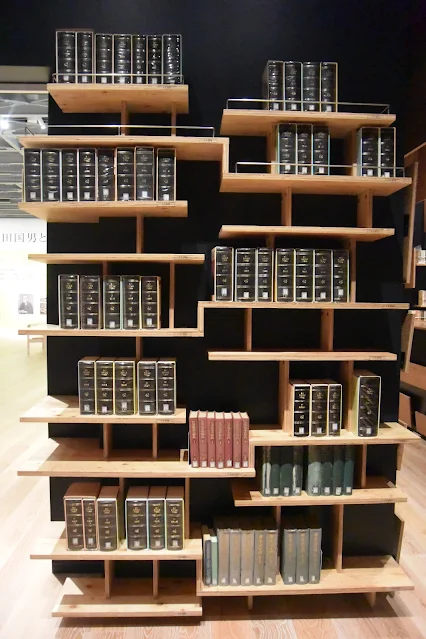京はこんな町になったらエエナ
―広原盛明の<はんなり・まちづくり>へのつぶやき―
1.「ひと・くらし・いのち」ありき、がエエナ。 (ひと・まち・くらしづくり)
わけあって今までは
「もの・かね・せいど」中心。
そやからまちのかたちも
ひとのこころもかとうなってきてるんとちがう?
京都はほっこりしたぬくもりある
しなやかなひと・まち・くらしづくりへ。
2.論も大切やけど実行もっと大切にしたいナ。 (スポーツ人間)
中学の頃から陸上競技やってきました。
走り高跳びでは、関西学生一部で優勝しました。
スポーツでは、からだを動かしながら
からだがいちばんはずむ理屈がわかっていくように、
京のまち、ようしていくのに
現場でいろんな人々と話し合いを重ね
実行のうねりを細く太く育くんでいきたい。
3.はっきりいうて京の町がいちばん好きや。 (京都との出会い)
人間だれでも青春時代の出会いが人生決めるもんや。
京都大学の西山研究室との出会い。
京都市内の田中、楽只、竹田、崇仁地区の調査やりながら
住み手にとってくらしやすい住まい・まちづくり
を問い、実践することに人生をかけてみよう
という志が心の片隅に広がっていったんや。
私の生きる方向を示し、いろんなことを教えてもろた
京のひと・まちに心からお返しすることに
いま再びの青春してみたい。
4.「嵐電」みたいに「市電」が走るまちにしたいナ。 (公共交通)
1970年代の8年間
京都の市電守る運動に青春かけました。
自動車交通の限界をこえて
ひとにも環境にもやさしい
移動しながら京の町の風情・風景をながめられる
「新型市電」の実験路線をつくってみたいナ。
今走っているバスもひとにやさしい心配りをしたい。
5.もりもりと緑ひろがり、そよそよと風はらむまちがエエナ。 (歴史都市)
盆地と鴨川に象徴される
山紫水明の生命みちる京の都。
軒先の草花から山の端にかかる月に至るまで
自然美も工芸美も構築美も
慈しみあい照らしあいもてなしあう
環境共生の歴史都市を守り育くんでいきたい。
6.りんとした「勇気」「公開」「参画」の姿勢を基本にしたい。 (基本姿勢)
複雑でやっかいな対立の状況や
硬直した事態をゆるやかに開くためには
烈け目や葛藤をのりこえていく勇気をふるいたたせたい。
勇気とは次の瞬間への意図、いさぎよいふるまい。
そのためには
何事もつつみかくさない公開のしくみと
市民の多様な参画の場づくりをすすめていきたい。
7.あがないつつ、伝統的アートの価値を継承したいナ。 (伝統工芸)
1960年代、清水焼の団地を山科につくった時
伝統的な登り窯をうかつにもないがしろにした。
均質なものができないことを理由に。
それは近代的な効率性をものさしにした考え方。
しかし、登り窯が生むかけがえのない個性と、
出来損いをワリ、破片にひそむワザを
アーチストたちがわかちあう「競争的共存」。
これは新しい時代の芸術家や事業者の生きる価値。
8.記憶を呼びさまし、記憶をふりつもらせたいナ。 (まちなみ景観)
1本の電柱をなくすことは、まちなみの記憶をよびさます。
1本の電柱を地中に埋めると、1軒の家をきれいにしたくなる。
1軒の家がきれいになると、まわりの家々は連鎖的にきれいになる。
京の人々のまちなみへの記憶を呼びさます動きは
次世代の子どもたちの記憶をふりつもらせていく。
電線ない町は町への愛が伝染していく。
電線のない町は町への愛が伝染していく。
電柱と家々と青空のすき間に降りしきる記憶
それは京の町の内なる力を育くむ。
9.反芻する住民の知恵が子どもの楽しい学びを高めるとエエナ。 (学区コミュニティ)
京都は日本ではじめて住民が町組ごとに小学校をつくった。
小学校をコミュニティのセンターとして
地域の多世代のチエとワザとココロを生かして
子どもとまちの生き生きとした出会いの機会を高めたい。
「タンケン・ハッケン・ホットケン」は
子どものココロの感動をよびさます。
感動を絵地図や紙芝居などに表現・発表・交流すると
子どもも住民も双方が高まりあう
学校と地域が相互に呼吸しあう学区の育くみへ。
10.難儀な空店舗にまちの力をまぜあわせてみよう。 (商店街)
まち中でもはずれでも商店街にアキが生まれたら、
お年よりたちの安心居場所のデイサービスを営んでみよう。
散髪屋や美容院が髪をすき、歯医者が歯をみて
和菓子屋が季節の香りを届け、花屋が四季の彩りを飾り…
ひととまちの力をまぜあわせて
「おでん」のようなおいしいコミュニティの拠点を創りたい。
11.理性も感性も豊かな市民力を育くむまちにしたいナ。 (市民力)
千年の都の歴史に蓄えられた人間の知恵の深さのある市民力。
「もう一度考えときます」ということは
京では時には否定を意味するけれど
「ことわります」と言い切ってしまわない
お互いに閉ざさない、孤立しないという
京ならではの裏表の微妙なバランス感覚。
個人の役割をきちんとこなしつつ
ゆるやかに周りと協働していく連帯感覚。
伝統の市民力に期待をよせたい。
12.なんと観光客が伝統産業にかかわる、そんな場をひろげたいナ。 (観光と伝統産業)
京の多様なタカラの外面を見にくる観光をこえて
織物紡いだり陶器をこねたり扇子をつくったり
立花を生けたりと伝統の文化・産業にジカにかかわる
観光客がふえてくると、まちなみに勢いが発露するし
伝統産業の元気がよびさまされていく。
究極の観光は創り制作することへの参加と体験
そのことで京の町の内なる力はきたえられていく。
13.これからは多世代交流のコミュニティづくりをしたい。 (多世代交流)
子育て支援と高齢者福祉をたてわりにせんと
横につなぐゆるやかな世代間の結びあう場づくりは
決して見なれた風景とはちがうけれど
静けさを尊ぶ存在と
動きの中に生を育くむ存在の
せめぎあいのエネルギーがほとばしる時
思いがけない偶発的な関係の中で老若共に育ちあう。
14.交番、路地、地蔵さんは京の町の安全安心の象徴。 (安全安心)
六地蔵は平安時代のおわり頃に
京に至る街道に安置された道祖神。
のちに家内安全、無病息災などを祈願して
地蔵尊を巡り拝むようになった。
古い時代の安全・安心のコミュニティ・シンボルとともに
現代のそれを育くむことを目指したい。
地域の人間関係を日頃から育くむことが
震災や犯罪などの危機管理とのりこえの基本の基。
15.ろくでもないゴミに生命をよびさましたい。 (ゴミ問題)
資源をムダ使いして大量のゴミを出す
建てては壊すやり方はやめて
古材を新しい柔らかい場所づくりに生かしたい。
日常の生活ゴミも丁寧に分別すると
資源がめぐりめぐって生きつづけられ
うらうらとした朝日の中で
人のくらしの営みの叡知の種子は発芽し
人もまちも健やかに育くまれていく。
16.ところで、これまでの各頁の第1行を束ねてみよう。
「ひと・くらし・いのち」ありき、がエエナ。
論も大切やけど実行もっと大切にしたいナ。
はっきりいうて京の町がいちばん好きや。
「嵐電」みたいに「市電」が走るまちにしたいナ。
もりもりと緑ひろがり、そよそよと風はらむまちがエエナ。
りんとした「勇気」「公開」「参画」の姿勢を基本にしたい。
あがないつつ、伝統的アートの価値を継承したいナ。
記憶を呼びさまし、記憶をふりつもらせたいナ。
反芻する住民の知恵が子どもの楽しい学びを高めるとエエナ。
難儀な空店舗にまちの力をまぜあわせたいナ。
理性も感性も豊かな市民力を育くむまちにしたいナ。
なんと観光客が伝統産業にかかわる、そんな場をひろげたいナ。
これからは多世代交流のコミュニティづくりをしたい。
交番、路地、地蔵さんは京の町の安全安心の象徴。
ろくでもないゴミに生命をよびさましたいナ。
各行の頭文字を束ねてみたら
<ひろはらもりあき はんなりなこころ!>
広原盛明は京都らしいはんなりとした
品格の高い陽気ではなやかな志と
明瞭な政策としての「はんなり・まちづくり」を
市民とともに紡ぎだすために
ささやかな力を尽くしたい。
広原盛明はひたすらそう念じています。
ここ一番のジャンプに誠意と渾身の力をこめて…。
建築・すまい・まちづくり関係者の集い」
のよびかけ
今年も残り少なくなりました。皆様いかがおすごしでしょうか。話題の総選挙も終わり、政治の季節もひとまず過ぎ去ったように感じられますが、来年2月8日には京都市長選挙が行われます。そしてこの京都市長選に広原盛明さん(京都府立大学前学長、京都大学建築学科1961年卒業)が立候補されることになりました。
日本人の心の故郷といわれる京都は、世界的にも貴重な社寺城郭を有し世界遺産にも登録され、また地球温暖化防止国際会議が開催されて「京都議定書」が採択されるなど、世界の歴史文化都市としてその環境保全に重大な責任と役割を課せられた都市です。にもかかわらず、京都南部においては巨大な高架高速道路が市内に向かって建設が進められ、俵屋、柊屋など老舗旅館が立地する中心市街地では高層マンションの乱立に歯止めがかからない状況です。また世界遺産の背景地においても宅地開発が進行しています。京都はいま歴史都市として存亡の岐路に立っているといっても過言ではありません。
広原盛明さんは、はやくも1960年代から住民参加のまちづくりに取り組んだ先覚的なまちづくり研究者です。また8年間にわたる京都の市電存続市民運動(1970~78年)を通して、環境保全の視点から都市交通とまちづくりのあるべき姿を追求した実践家でもあります。阪神・淡路大震災ではいち早く救援活動に駆けつけ、建築士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などの職能団体によって組織された「阪神・淡路まちづくり支援機構」の代表委員として活躍されてきました。
私たちは、京都の現状を憂い、京都の明日を切り開く見識をもった広原盛明さんがこのたび京都市長選に立候補表明されたことを、勇気ある行動として心から歓迎し、支持したいと思います。
つきましては、建築・すまい・まちづくりの分野でご活躍の皆様方に広原盛明さんへの支援をお願いしますとともに、「広原盛明さんの京都市長選立候補表明を支援する建築・すまい・まちづくり関係者の集い」(12月20日、京大会館)へのご案内を申し上げます。ご多忙中とは存じますが、ご参加をお待ちしております。
2003年11月
よびかけ人(予定)
陣内秀信(法政大学教授)、鈴木成文(東京大学名誉教授、前神戸芸術工科大学学長)、林泰義、山岡義典、内田雄造(東洋大学教授)、藤本昌也(建築家)、峰政克義氏、曽田忠広(愛知工業大学教授)
白砂剛二・湯川聡子・高口恭行・延藤安弘・安藤元夫(近畿大学教授)・森本信明(近畿大学教授)・海道清信(名城大学教授 、横尾義貫(京大名誉教授)・田中喬(京大名誉教授)・中村泰人(京大名誉教授)、小島攻(近畿大学教授)、千葉桂司(都市公団OB
)、渡辺豊和(建築家・京都造形大教授)、若林広行(建築家)、安原秀(建築家)
青木志郎(東京工業大学名誉教授・元日本建築学会副会長)、石田頼房(東京都立大学名誉教授・元自治体問題研究所副理事長)、牛見 章(東洋大学名誉教授・元埼玉県都市計画審議会会長)
大谷幸夫(東京大学名誉教授・建築家)、岡田光正(大阪大学名誉教授)、小川信子(日本女子大学名誉教授・元生活学会会長)、片寄俊秀(関西学院大学教授)、柴田徳衛(東京都立大学教授・元東京都理事)、住田昌二(大阪市立大学名誉教授・元福山女子大学学長)、吉田あこ(筑波技術短期大学名誉教授・元国際女性建築家協会副会長)
記
広原盛明さんの京都市長選立候補表明を支援する
建築・すまい・まちづくり関係者の集い
1.日時:2003年12月20日(土)午後3時~5時
2.会場:京大会館
3.次第(1)よびかけ人挨拶、(2)広原盛明さん挨拶、(3)参加者スピーチ、(4)事務局からの
支援活動についての訴え、(5)今後のスケジュールなど
4.会費:3千円
5.出欠:同封の葉書あるいはFAX用紙で12月15日(月)までにお返事下さい。
なお欠席の場合も趣旨にご賛同の場合はカンパ(1口5千円)をお願いいたします。
宛先:〒612-0846
京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町455 広原盛明宛
tel/fax 075-643-8524 E-mail: hirohara@skyblue.ocn.ne.jp
郵便振替:京都市伏見区万帖敷郵便局 口座番号(申請中)
銀行振込:京都銀行墨染支店 普通口座(開設中)