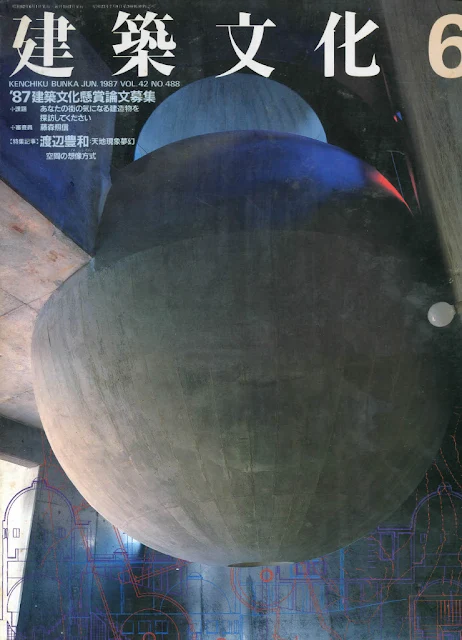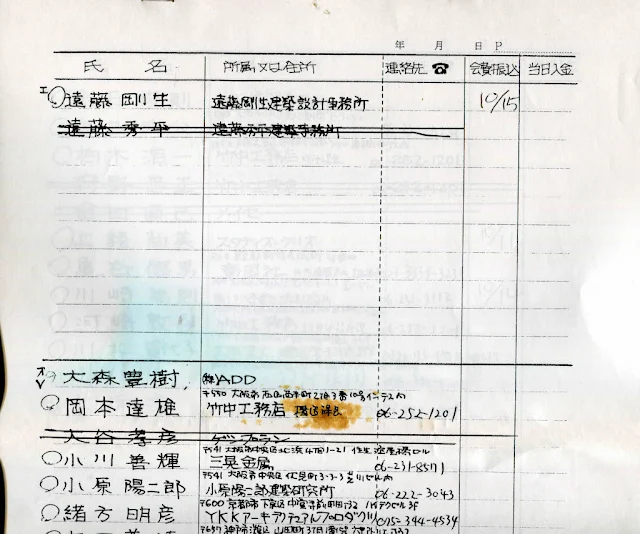このブログを検索
2022年6月11日土曜日
講義:インドネシアの集合住宅について,APEX,関西APEXセミナー,19961109
講義:インドネシアの集合住宅について,APEX,関西APEXセミナー,19961109
第五回関西APEXセミナー
インドネシアの集合住宅について
1996年11月9日
18:00~20:30
布野修司(ふのしゅうじ)
京都大学工学部助教授/工学博士
経歴
1949年 島根県生まれ
1972年 東京大学工学部建築学科卒業
1976年 同大学院博士課程中途退学 同助手
1978年 東洋大学講師
1984年 東洋大学助教授
1991年 京都大学助教授~至現在
「インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究」(学位請求論文)で、日本建築学会賞(論文賞)受賞(1991年)。現在、建築フォーラム(AF)、サイト・スペシャルズ・フォーラム(SSF)などで活動。建築同人誌『群居』編集長。
著書
『戦後建築の終焉・・・世紀末建築論ノート』 れんが書房新社 1995年
『戦後建築論ノート』 相模書房 1981年
『スラムとウサギ小屋』
青土社 1985年
『住宅戦争』 彰国社 1989年
『カンポンの世界』 パルコ出版 1991年
『これからの中高層ハウジング』 丸善 1992年
『建築・町並み景観の創造』 技報堂 1993年
『十町十色』 丸善 1994年
『戦後建築の来た道行く道』 東京都設計者厚生年金 1995年
『見知らぬ町の見知らぬ住まい』(布野修司編) 彰国社 1990年
『現代建築ーーーポスト・モダニズムを超えて』 新曜社 1993年
『見える家と見えない家』 岩波書店 1981年
『建築作家の時代』(布野修司 藤森照信 柏木博 松山巌) リブロポート 1987年
『悲喜劇・1930年代の建築と文化』 (同時代研究会編) 現代企画室 1981年
『作法と建築空間』(日本建築学会編) 彰国社 1990年
『新建築学体系1 建築概論』(大江宏編) 彰国社 1982年
『建築計画教科書』(建築計画教科書研究会編) 彰国社 1989年他
専門
地域生活空間計画(建築計画 都市・地域計画)
第五回関西APEXセミナー
インドネシアの集合住宅について
1996年11月9日
18:00~20:30
Ⅰ インドネシアのカンポン
Ⅱ 東南アジアの集合住宅
Ⅲ カンポン・ススン
2022年6月10日金曜日
2022年6月8日水曜日
日本都市計画学会論文賞:2006年 『近代世界システムと植民都市』(京都大学学術出版会,2005年)
日本都市計画学会論文賞:2006年 『近代世界システムと植民都市』(京都大学学術出版会,2005年)
平成17年度 日本都市計画学会賞論文賞 受賞にあたって
植民都市計画研究のための基礎作業
布野修司
研究経緯
赴任したばかりの東洋大学で磯村英一先生(当時学長)から、いきなり「東洋における居住問題に関する理論的、実証的研究」という課題を与えられて、アジアの地を歩き始めたのは1979年初頭のことである。振り返れば、最初に向かったのがインドネシアであったことが運命であった。インドネシア、殊に、スラバヤという東部ジャワの州都には以降度々通うようになった。経緯は省かざるを得ないが、10年の研究成果を『インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究---ハウジング計画論に関する方法論的考察』という論文にまとめて、学位(東京大学)を得た(1987年)。そのエッセンスを一般向けにまとめたのが『カンポンの世界』(パルコ出版,1991年)で、光栄なことに日本建築学会賞論文賞を受賞することができた(1991年)。
このカンポンkampungというのが曲者であった。OED(オクスフォード英語辞典)によると、コンパウンドcompoundの語源だという。バタヴィアやマラッカの都市内居住地がカンポンと呼ばれていたことから、インドでも用いられだし、アフリカなどひろく大英帝国の植民地で使われるようになったという。大英帝国は、最大時(1930年代)、世界の陸地の1/4を支配した。英国の近代都市計画制度が世界中で多大な影響力をもった理由の大きな部分をこの事実が占める。
インドネシアの宗主国はオランダである。オランダは、出島を通じて日本とも関係が深い。オランダ植民都市研究を思い立ったのは、インドネシア、カンポン、出島という縁に導かれてのことである。
受賞論文:「近代世界システムと植民都市」(京都大学学術出版会、2005年2月刊行)
受賞論文が対象とするのは、17世紀から18世紀にかけてオランダが世界中で建設した植民都市である。オランダ東インド会社(VOC)、西インド会社(WIC)による植民都市の中で、出島は、長崎の有力商人によって建設されたことといい、オランダ人たちの生活が、江戸参府の機会を除いて、監獄のような小さな空間に封じ込められていたことといい、唯一の例外といっていい。論文は、オランダ植民都市の空間編成を復元しながら、17世紀から18世紀にかけての、世界の都市、交易拠点のつながりと、それぞれの都市が現代の都市へ至る、その変容、転生の過程を活き活きと想起する試みである。
まず、アフリカ、アジア、南北アメリカの各地につくられたオランダの商館、要塞など植民拠点の全てをリスト・アップした。そして、主として都市形態について類型化を試みた。さらに、臨地調査(フィールド・サーヴェイ)を行った都市を中心にいくつかの都市をとりあげ比較した。比較の視点としているのは、都市建設理念の起源と原型(モデル)、地域空間の固有性によるモデルの変容、近代化過程による転生、<支配―被支配>関係の転移による土着化過程(保全)植民都市空間の現代都市計画上の位置づけ、などである。
オランダ植民都市を起源とする諸都市はインドネシアなどを除いて、イギリス支配下に入ることによって変容する。そして同様に19世紀末以降、産業化の波を受けてきた。また、独立以降(ポスト・コロニアル)の変容も大きい。論文は、英国植民都市計画そして近代都市計画の系譜以前に、オランダ植民都市の系譜を措定して、その原型、系譜、変容、転生の全過程を明らかにしている。
まず広く、西欧列強の海外進出を概観(第Ⅰ章)した上で、オランダ植民地拠点の全容を明らかにした(第Ⅱ章)。続いて、植民地建設の技術的基礎となったオランダにおける都市計画および建築のあり方をまとめた上で、オランダ植民都市計画理念と手法を考察し(第Ⅲ章)、オランダ植民都市誌として各都市のモノグラフをもとに、植民都市の変容、転生、保全の様相について考察する(第Ⅳ章)構成をとっている。巻末には、詳細な植民都市関連年表、オランダ植民都市分布図をまとめている。
アジアからの視点
近代植民都市研究は、基本的には<支配←→被支配><ヨーロッパ文明←→土着文化>の二つを拮抗軸とする都市の文化変容の研究である。近代植民都市は、非土着の少数者であるヨーロッパ人による土着社会の支配を本質としており、西欧化、近代化を推し進めるメディアとして機能してきた。植民都市の計画は、基本的にヨーロッパの理念、手法に基づいて行われた。西欧的な理念がどのような役割を果たしたのか、どのような摩擦軋轢を起こし、どのように受け入れられていったのか、計画理念の土着化の過程はどのようなものであったのか、さらに計画者と支配者と現地住民の関係はどのようなものであったか等々を明らかにする作業は、これまでほとんど手つかずの状況であった。本論文は、飯塚キヨ氏の『植民都市の空間形成』(1985年)以降の空白を一挙に埋め、ロバート・ホームの『植えつけられた都市 英国植民都市の形成』(布野修司+安藤正雄監訳,アジア都市建築研究会訳,Robert Home: Of Planting and Planning The making of British
colonial cities、京都大学学術出版会、2001年7月)に呼応するアジア(日本)からの作業として位置づけることができる。
植民都市の問題は、現代都市を考えるためにも避けては通れない。発展途上地域の大都市は様々な都市問題、住宅問題を抱えているが、その大きな要因は、植民都市としての歴史的形成にあるからである。また、西欧列強によってつくられた植民都市空間、植民都市の中核域をどうするのか、解体するのか、既に自らの伝統として継承するのか、これは、植民都市と地域社会の関係が、在地的な都市=地域関係へと発展・変容していく過程の中で現出する共通の問題でもある。具体的に、歴史的な都市核としての旧植民都市の現況記録と保全は、現下の急激な都市化、再開発が進行するなかで緊急を要する問題である。本論文は、現代都市の問題を大きな問題意識として出発しており、それぞれの都市の現況を記録することにおいて大きな意義を有している。都市問題、住宅問題の解決の方向に向かって歴史的パースペクティブを与える役割を果たし、さらに加えて、世界遺産としての植民都市の位置づけに関しても多大な貢献をなすと確信するところである。
アジア都市建築研究
17世紀をオランダ植民都市という切口で輪切りにしてみて、残された作業は少なくない。スペイン、ポルトガルと植民都市計画の歴史を遡行する作業ももちろんであるが、アジアからの作業として、前近代の都市計画の伝統を明らかにする必要がある。大きく、インド、イスラーム、中国の都市計画の伝統が想起されるが、ヒンドゥー都市についてその理念と変容を篤かったのが、『曼荼羅都市』(京都大学学術出版会、2006年)である。また、カトゥマンズ盆地の都市について“Stupa &
Swastika”をまとめつつある(2007年出版予定)。
この度の受賞は、さらなる作業のために大きな励みとなるものである。心より感謝したい。
アジア都市建築研究会は、布野修司を中心として1995年に発足したゆるやかな研究組織体で、2005年5月までで69回の研究を積み重ねて来た(研究会の内容は、http://agken.com/index.htm)。その主要な成果として、*『生きている住まいー東南アジア建築人類学』(ロクサーナ・ウオータソン著 ,布野修司(監訳)+アジア都市建築研究会、学芸出版社,1997年3月、*『日本当代百名建築師作品選』(布野修司+京都大学亜州都市建築研究会,中国建築工業出版社,北京,1997年 中国国家出版局優秀科技図書賞受賞 1998年)、*『植えつけられた都市 英国植民都市の形成』(ロバート・ホーム著:布野修司+安藤正雄監訳,アジア都市建築研究会訳,京都大学学術出版会、2001年)、*『アジア都市建築史』(布野修司+アジア都市建築研究会,昭和堂,2003年)*『世界住居誌』(布野修司編著、昭和堂、2005年)などがある。
受賞論文の元になっているのは、「植民都市の起源・変容・転成・保全に関する研究」と題した共同研究(文部科学省・科学研究費助成・基盤研究(A)(2)(1999~2001年度)・課題番号(11691078)・研究代表者(布野修司))である。布野が、報告書をもとに全体を通じて筆を加えて受賞論文の原型となる予稿をつくった。それを各執筆者に回覧し、確認を受けたものを再度布野がまとめたのが受賞論文である。共著者は、魚谷繁礼、青井哲人、R.Van Oers、松本玲子、山根周、応地利明、宇高雄志、山田協太、佐藤圭一、山本直彦である。また、共同研究参加者は、以上に加えて、安藤正雄、杉浦和子、脇田祥尚、黄蘭翔、高橋俊也、高松健一郎、佃真輔、Bambang Farid Feriant、池尻隆史他である。
2022年6月6日月曜日
新井葵+新藤恒樹+中島柚季+吉田奈由+小野美史+北原啓司+砂土原聡+布野修司+濱本卓司:聞き手:佐藤淳,座談:東日本大震災について「理系高校生」が知りたいことを「専門家」に聞いてみる,「特集:災害対策研究の新しい起点」,『建築雑誌』2016年3月
新井葵+新藤恒樹+中島柚季+吉田奈由+小野美史+北原啓司+砂土原聡+布野修司+濱本卓司:聞き手:佐藤淳,座談:東日本大震災について「理系高校生」が知りたいことを「専門家」に聞いてみる,「特集:災害対策研究の新しい起点」,『建築雑誌』2016年3月
『建築雑誌』2016年3月号 都立戸山高校SSH生座談会 2部 校正原稿
話者:新井葵×新藤恒樹×中島柚季×吉田菜由×小野美史(戸山高校1年)、北原啓司(弘前大学大学院地域社会研究科研究科長・教授)、佐土原聡(横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授)、布野修司(日本大学特任教授)、濱本卓司(東京都市大学教授)
聞き手:佐藤淳(佐藤淳構造設計事務所)
録音時間:2時間37分28秒(実質:2時間28分00秒)
収録日 2015年12月8日(火)
第二部については頁割は特に意識しません.6頁そのままデザイナーさんの思うレイアウトで写真と組み合わせて割り付けてください
2部全体タイトル案:質問リストを携えて,理系高校生が専門家と議論してみました
避難と建築物の性能のあり方について
――今日は、戸山高校の学生さんたち5名の皆さんと座談会をし、その中で議論したことを先生方への「質問リスト」として作製していただきました。この後半の座談会では各分野の先生方に参加していただき、質問についてより深く考えていきたいと思います。まずは簡単に自己紹介からお願いします。(佐藤)
佐土原 横浜国立大学の佐土原と申します。私は建築や都市の環境が専門で、エネルギーについても研究しています。震災の日は、ちょうど建築会館にいて、そのまま一泊しました。
濱本 東京都市大学の濱本と申します。私は構造の分野に所属しています。震災の日は大学の研究室にいました。非常に長く揺れていましたが、私は結構鈍感な方で、ずっと研究室内に留まっていました。その後、大学から学生たちに早く家に帰るよう連絡がありましたが、実際は交通機関がみんなストップして帰れませんでした。結局、大学の体育館が開放され、学生たちはそこで寝泊りしました。大学からおにぎりがふたつずつ支給されたと思います。私は自由が丘まで歩き、親戚の家に泊めてもらいました。東京でも帰宅困難者がたくさん出ました。やはり東日本大震災は、「想定外」「未曾有」などの言葉が使われましたが、津波による被害が大きく、建築分野ではそれほど対策が考えられてこなかったことでした。
布野 東大助手、東洋大学講師、京都大学助教授、2015年3月までは滋賀県立大学で、今は日本大学生産工学部で特任教授をしています布野です。国公私立全て経験したのは珍しいかもしれません。分野は建築計画で、まちづくりを専門としています。僕は第二次提言には関係していないのですが、学会の復旧・復興支援部会の部会長を務めました。震災当日は滋賀にいましたが、たまたま仙台の宮城大学に京大布野研究室出身の竹内泰(現東北工業大学助教授)先生がいて、南三陸町出身の学生の実家の支援のために番屋を建てるというので、支援しました。毎夏、インターユニヴァーシティで木について学ぶ「木床塾」でお世話になっている加子母村(岐阜県中津川市)の支援を受けて、全国大学の学生が参加して、連休には完成させました。復興のための拠点になったと思います。「みんなの家」とか「竹の会所」とか、建築家の多くが拠点づくりに参加しました。
北原 弘前大学の北原と申します。専門は都市計画やまちづくりです。生まれは三重県伊勢市ですが、親の関係で仙台にいたことがあり、大学も東北大学でした。当日は弘前にいて揺れを感じ、インターネットを見ると東北の地震だということがわかりました。親も仙台に住んでいて、息子が東北大の3年生でしたが、電話がつながらず安否が心配でした。息子はTwitterで無事を知りました。今は岩手県北上市に拠点をつくり、いろいろな街の復興の仕事をしています。
小野 私は小学生の頃から建築に興味を持っていて、今も建築家を目指して大学に進学したいと思っているので、このような機会はとても嬉しいです。
吉田 私は数学をやっていて、建築についてはあまりわからないのですが、よろしくお願いします。
新藤 僕もあまり建築に関してあまりよくわからないのですが、身の回りに関係する話題が多いなと思っています。
中島 震災後に疑問に思ったことなどを直接専門家の方に聞けるので嬉しく思います。
新井 これまで建築の分野がこれほど震災に関係しているとは思っていませんでしたが、よろしくお願いします。
――それでは、高校生の質問リストから,先生方の気になるものから順に話ができればいいかなと思います。いかがでしょうか。(佐藤)
佐土原 ここは都心ですが、質問リストの「高層階で被災した時の避難方法」というのはどういう意味の質問ですか。
新藤 当時小学5年生だった頃に、友だちが住んでいた高層マンションが大きく揺れていました。災害時にエレベーターが止まったり、階段に人が集中したりした場合、どう避難するか,また、避難方法があっても本当に安全かどうか証明されているのか疑問に思っています。
濱本 まず構造分野からの意見です。建物を設計する時には、どんな地震が来るのかをあらかじめ考えています。たとえば新宿に建っている建物は、今回の震災を経験する前に設計されていて、その当時の知識によって建てられています。ですが、東日本大震災は想定と違っていて、すごく遠くからやってきて、非常にゆっくりとした揺れでした。地面の振動数と構造物の振動数が一致する「共振」によって、すごく揺れたのです。そのような長周期の揺れだと、高層階では身動きが取れませんから、避難できない状況でした。その時その時の最先端の知識で設計されているはずですが、新しいタイプの地震が起きる度に、その経験をフィードバックしてより安全なものをつくっていこうとしています。かつて建てられたビルも、長周期の地震に耐えられるよう、レトロフィットという改修をしています。
東日本大震災は1000年に一度とか、500年に一度と言われていますが、自然現象としては同じような地震は過去にも繰り返し起きているのです。社会の記憶からは消えてしまっているだけで、やはり、今回の最も大きな教訓は、自分たちはちゃんと自然のことを考えながら新しいものをつくってきたのかもう一度見直すべきだということです。
布野 高層マンションだけでなく,高層の業務商業複合のビルで劇場のような多数の人を集客する施設を高層階につくっているのは,問題です。避難のシミュレーションをしてみると結構大変だと思います。建築計画としてまずおかしいですね。
北原 落ち着いて逃げれば本当は大丈夫でも、全員が整然と階段を降りるはずがないですし,余震も来ますから、やはりパニックになると思います。大人数が高層階にいる建物からの避難ということで,人間の心理的な側面が集団行動にどう結びつくか予測不可能な面もあります。
佐土原 建築会館でも、揺れが収まると一斉に人が降りてきたので,混雑して動きが取れないような状態になりました。実は超高層の中にいる人たちがみんな外に出てきてしまうと、足元のスペースは足りないのです。ですから、一斉に降りなくても大丈夫という情報をちゃんと出し、ビル内に留まってもらうようにするにはどうするかを考えているところです。そのあたりは今回の震災で考え方が変わった点のひとつです。
また、ビル内に留まるとすると水道、電気、ガス、そして情報というライフラインが問題になります。当時は,超高層マンションで、本来はより価格の高い高層階が売れなくなっていました。
小野 私は震災当時、小学校の校庭に避難したのですが、上からガラスが落ちてきたりすることもあるし、避難経路に割れたガラスが落ちていたら避難しない方が安全なのかなと思いました。
佐土原 高層ビルは柔構造といって揺れやすくつくられていますが、窓枠とかは固くできていますね。
北原 僕の学生時代に宮城県沖地震があったのですが、建物の玄関のガラスが落ちました。また、ブロック塀が倒れて、僕のすぐ側にいた小学生が亡くなりました。それ以前は、倒れないということが重視されていましたが、以来、ガラスの固定などを含め、新耐震基準ができました。でもやはり自然はそれを超えてきますから、安心はできません。小学校の避難訓練なんかでは、座布団みたいなものを頭に被って守りますよね。
――非構造部材、つまり柱や梁などのメインの構造ではない、窓ガラスなどが壊れるということをもっと検証しようということですよね。(佐藤)
布野 今回はあまりなかったのですが、阪神淡路大震災の時は、家具が倒れたり、飛んだりして、相当の人が亡くなっています。
――続いて,避難に関連する項目がいくつか質問リストに挙がっていたので,順に高校生の方から質問の内容を教えて下さい。(佐藤)
新井 携帯電話を持っていない小学生の登下校時に地震が起きたら安否確認をどうするのか気になりました。
小野 私も,震災以後、家族で避難場所を話し合うようになりました。
吉田 私も小野さんと同じで、家族で避難場所を決めています。
中島 家の近くにはちゃんとした避難所があるのですが、学校にいるときは、耐震がしっかりしているので学校にいなさいと言われています。
――こんなふうに,高校生の皆さんは家族で避難するときに「災害があったらどこに集まろう」みたいな話をされていて,とりあえずの集合場所として地域の広域避難場所をあまり目標にはしていないということがよくわかりました.もちろん地震をイメージしているか津波をイメージしているかで違うと思うのですが,都市計画的な観点からいかがでしょうか。(佐藤)
北原 いわゆる避難と聞くと公共的な建築物とか大きな空間にみんな逃げるイメージがありますが、東日本大震災では津波によって体育館などに集まった人が全員亡くなっています。一方、大船渡のある地域では、高台にある神社に避難して全員が助かりました。明治の津波の時以来、地震が来たら神社に逃げろと言われていたそうで、長く歴史が残っているところは比較的安全なのです。
布野 関東大震災の時も、避難のためにみんなが集まった場所に、火災が及んで、たくさんの方が亡くなっていますね。
北原 まず逃げる場所として津波がない場合は学校などに避難するのは正しいと思います。安全が確保されてから、水の支給などがある広域避難場所に家族で行くという二段階になりますね。集合場所を家族で決めておくのも良いと思います。神社は最初に避難する場所ですね。
佐土原 広域避難場所とは安全確保のための大きな空き地などで、避難生活をするところはまた別ですね。直後に避難する一時避難場所と、広域避難場所、防災拠点の3種類があります。
吉田 学校など避難所となる建物の安全性は確かなのでしょうか。
――特に学校などの公共的な建物は国の予算が付いていて、耐震診断と対策が進んでいます。耐震補強がされた建物とまだされていない建物を区別する表記・表示があるべきかもしれません。(佐藤)
減災か防災か,その前に生活できる経済基盤か
佐藤 そういえば高校生からも火災の話は出ていましたね。
中島 自宅が住宅密集地にあり、古い建物とか木造の建築が多いので、震災が起こったときの木造住宅密集地の火災対策をお聞きしたいです
佐土原 一例ですが公的な補助をしながら、建て替えの時に不燃化を進めています。面で広がってしまう火災を断ち切っていくものです。
北原 東京の墨田区とか足立区のあるエリアでは、木造の雰囲気を残すために、自主組織をつくり、防火用水を用意して訓練もし、初期の消火を自分たちでやろうとしているところもあります。そうしたコミュニティの力によって乗り切ろうという地域もあります。
佐土原 1923年の関東大震災の時は火災旋風が起きてしまいました。当時の報告書を読むと、本当に竜巻のように火が走っていたようです。ですから、その後の東京の対策は、基本的に火災対策として、安全な場所の確保をやってきました。たとえば、大きな団地を開発するときに、広域避難場所をつくるなどです。
濱本 1995年の阪神淡路大震災でも、やはり木造密集地帯が火事になってしまいました。初期消化のための道が、崩れた建物で塞がれてしまっていたことも大きな問題でした。火災対策だけではなく、倒れないようにちゃんと建築をつくっておくことも大切です。
新藤 いままで逃げ方の話だったのですが、それに関連して「防災と減災の具体的な違い」についてはどうでしょうか。これまでは「防災」が意識されてきたと思うのですが、最近学校で「減災」という考え方が出てきていると聞いたのですね。でも、どのように変わってきているのかということがよくわからなくて。具体的に身の回りでどのように変わってきているのか教えていただければと思います。
濱本 構造分野からお話します。防災は英語で「prevention」で減災は「mitigation」と言われていますが、イメージしやすいのは、風に耐える松と、受け流す柳です。今回の津波については、やはり受け流すような建物の方が良かったのかなという話が出ています。構造的には,自然に対してひたすら真正面から立ち向かい対抗するより、ある程度自然の力を受け入れながら、それを弱めて被害を最小化し安全を確保することを設計に取り込むような考え方であると思います。巨大な防潮堤は防災を前提にしたものですが、陸と海がつながった豊かな生活や日常的な暮らしにとってはマイナスになります。嵩上げも、そのためには山が削られ緑や生態系が失われています。震災直後は特に「とにかく守る」という短絡的なところがありましたが、減災はもう少し引いた視点で全体像を見ながら災害に対応しようというものです。
北原 都市計画では、災害が起きることを想定し、それを技術や訓練も含めてさまざまな方法でできるだけ小さくしようという考え方です。たとえば、今、青森県で歴史的な町並みを残す仕事をしていますが、木造の雁木による積雪時の道、いわゆる「こみせ」は木造だから良いのであって、同じ形をコンクリートでつくっても興冷めしてしまいます。文化財としてではなく、使いながら残すために消火栓などを埋め込んだりしています。災害はゼロにはできないので、そこで生きたいという人たちのための減災を考えています。
佐土原 阪神淡路大震災や東日本大震災でわかったのは、防災技術を求めても、それを乗り越えて物事は起こるということを前提に考えておかないと対応が後手後手に回ってたくさんの人の命が失われてしまう。想像を超えた状況であっても被害を減らす対応を検討しておくという意味で、減災は大きな転換だと思います。
北原 あとは、防災か減災かという話以前に,これからその土地でどうやって食べていくか。堤防や嵩上げだけではまちづくりになりませんし、農業や商業にしても、産業が成り立たなければ復興になりませんので、災害対策とあわせての復興にはまだまだ時間がかかると思います。
布野 東北地方は少子高齢化が進んでいて、日本の将来の縮図と言われていたんですが、今回2万人もの人が亡くなり、一気に2050年の人口規模になりました。被災地の問題は、日本のあらゆる地方は同じ問題を抱えているわけです。少子高齢社会、人口縮小社会で、どうサステイナブルな社会をつくっていくか、わかりやすく言えば、それぞれの地域がどうやって食べていくのかが大問題です。
北原 岩手の大槌町で、ワークショップに地元の高校生に参加してもらっています。おそらくみんな大学や就職で仙台とか東京に行ってしまいますが、自分たちが関わってつくった公園に戻ってきたいという気持ちを持ってもらおうとしています。20年後に効いてくるのかもしれません。
――私は防災の嵩上げや防潮堤に反対なのですが、皆さんは率直にどう思いますか。(佐藤)
中島 街自体がなくなってしまったので、わざわざお金をかけて防波堤をつくるよりは、安全なところでまちづくりをしていく方がいいと思います。
新藤 嵩上げしても津波の被害は絶対あると思います。減災という考え方は、単にものを築くことだけではなく、教育やワークショップによって人から変えていくことの重要性ともつながっていると思いました。
北原 1000年に一度の災害に耐えられるようなものをつくっていますが、われわれの人智を超えた5000年に一度の災害だって起こり得るわけです。最近になってようやくみんながあのスーパー堤防で誰を守るのだろうかと考え始めましたが、震災直後は誰もそんなことを言えませんでした。国の復興予算が付いていて、既に発注まで終えてしまっています。石巻では、今復興庁のお金で再開発がいくつか動いていますが、それらはなかなか完成が見えません。一方で、たった4人で発起した「COMICHI石巻」という小さなプロジェクトは復興交付金をもらわずに完成し、イタリアンレストランやお寿司屋さんが入っています。大きな計画よりも、やりたいという意思を持った人たちが自力でやっていったほうが動くということがわかってきています。
佐土原 減災にとっては日常と災害時の連動が大切ですね。1000年に一度を想定して防潮堤で防災をしても、それが本当に機能するかどうかが問題です。
――少しトピックを変えて、「仮設建築の必要形態」という質問を書いた人は。(佐藤)
小野 建築学科に通う大学生の知人が、ゼミが陸前高田の方で、仮設住宅に住む人たちに話を聞いたそうです。その時に一番多く耳にしたのが、地域の人たちとコミュニケーションできる公的な建物がほしいということでした。誰も利用できるような図書館のような建物が必要なのかなと思いました。
北原 阪神淡路大震災や中越地震の経験もあったので、ボランティアのNPOの人たちもかなり入り、仮設団地の集会室が機能しているところもあります。一方で今問題なのは空き家の戸建住宅に被災者が入った「みなし仮設」です。仮設団地であればイベントもできますが、バラバラの戸建住宅に突然入った人たちはコミュニティがありません。潜在的にどれくらいいるかも把握できていませんし、大きな問題ですね。
あと、仮設団地でも財力のある人は出ていきますから、だんだん歯抜けになっていって、焦燥感や諦めが生まれてきます。そうするとコミュニティが崩壊していきます。
布野 阪神淡路大震災の時にはくじ引きで仮設住宅の入居者を決めたんですね。あまり、入居者のコミュニティを考慮しなかった。店屋や集会施設なども考慮しなかった。その経験を踏まえて、東日本大震災の時には、様々な工夫もなされ、集会所もつくられています。
北原 集会施設はあっても、図書館みたいな空間はないですね。公的な動きとしては、まず住宅が優先になるので難しいかもしれません。また、仮設住宅を規定する災害救助法は、厚生労働省関連なので、「まず収容しよう」という発想からつくられたものなのですが、本来ならば、ひとりひとりが自立した生活を営めるようなまちづくりの考え方が必要です。
マスメディアの切り口について
――今まだ「震災後(最中)のメディア」「省エネによる節電」などがまだ話題に出てきていませんがこれを書いてくれた高校生は?(佐藤)
新藤 テレビなどでは「省エネ」がかなり言われていると思います。たとえば蛍光灯がLEDになったり、技術によって実現できているところもあると思いますが、学校などのエアコンの設定温度など、人びとの意識には根付いていない気がします。何か策はあるのでしょうか。
佐土原 計画停電を経験すると、電気の大切さはよくわかると思います。建築学会の大きな取り組みとしては、照明の電力使用量についての研究があります。近年、企業による宣伝などによって、どんどん照明が明るくなってきていますが、いろいろ調査すると約半分までは落としても問題ないという結果が出ましたので、そうした提言をしています。東日本大震災後、電力の消費量を落とし、さらにLEDになってきたことで、冷房の負荷も下がっています。照明についての認識は大きく変わっていきています。
また、HEMS(Home Energy Management System)やBEMS(Building and Energy Management System)といったマネジメントや、スマートエネルギーシステムが出てきていますが、現状ではまだメーカーによる押し付け的なところがあり、本当に生活に馴染ませるにはどうするかが大きなテーマになっています。たとえば、健康や高齢化の問題と一緒に断熱のことを考えるとか、人が自発的に関われるような節電になればと思っています。
新藤 今、多くの原発が止まっていて、火力に頼り続けている状態ですが、どうやって再稼動させていくのか、もしくはもう使わないという方向なのか、どちらなのでしょうか。
佐土原 あれほど巨大で複雑な設備をこの災害多発国の日本で将来にわたって使っていくのかはやはり考えるべきです。今どうするかという一時的な問題と長期的な問題を分けて考えなければいけません。
新井 「震災後(最中)のメディア」についてなのですが、震災後、どのテレビ局も似たような情報が流れ、同じ会社の同じCMが何度も流れていました。情報発信という意味では無駄が多いようにも思えたので、例えば、地域やチャンネルを限定して、必要な情報を選べるようにしたり、見たくない人が避けられるような改善はできないかと思いました。災害時のメディアのあり方について新しい知見があれば教えていただきたいです。
濱本 東日本大震災後、SNSが注目されました。やはりある種マスメディアの限界が見えたのだと思います。
布野 米軍がものすごく活躍しても、CNNなんかでは流しているけど、日本では流さない。地元の工務店や建設会社が死体処理をしているとか、そうした活躍のことはほとんど放送されませんでしたね。
北原 沢山のテレビ局で同じようなニュースを繰り返されてもあまり意味がなくて、たとえばフジテレビは岩手、日テレは福島などを徹底的にやってもらった方がありがたいです。情報番組であることをもっと意識してもらいたかったという話をお聞きしました。また、FMラジオでは他の番組を止めて徹夜で安否や状況を放送していて、役に立ちました。阪神淡路大震災の時も長田区あたりでは、コミュニティFMができて海外から来ている人たちにも安心感を与えるような放送をやっていました。ラジオは今また見直されてきていますね。
佐野原 阪神淡路大震災と東日本大震災を比べると、YouTubeにアップされた映像など、視覚的な情報がすごく沢山あり、多くの人の災害に対する理解を助けています。たとえば、液状化については一般の人でもかなり理解が深まったと思います。
――東日本大震災の当時に,メディアについて私が感じたのは、例えば体育館の中に間仕切りをつくったり、簡易に組み立てられる仮設建築物を供給したり、建築分野の関係者がさまざまな活動をしたのですが、メディアには、一部の成功した事例が取り上げられるわけです。だけど、うまくいかない例もあったわけです。「こんなみっともないものをもってきてくれるな」と言う人もいたらしいのです。でも、あのときは本当に何がうまくいくか誰もわからないから、失敗して責められてもしょうがない、という覚悟でみんな取り組んだのであり、それも含めて伝えてくれないと真実を伝えたことにはならない。先に自分たちでおきまりのストーリーを描いておき,そこにはめ込んで報道しようとしたメディアにも問題があるように思いました。(佐藤)
座談会を終えて(高校生の感想)
――最後に高校生の皆さんに感想や考えていることなどを一言ずつ述べていただけますか。(佐藤)
新井 建築の専門家の方々が沢山震災に関わっているということを知ることができてよかったです。ありがとうございました。
中島 震災だけを考えるのではなく、普段の生活から防災を考えていくということが心に残りました。とても勉強になりました。
新藤 減災という考え方がとても響きました。人の気持ちや行動なども重要だということがわかって、これからそういった視点を広げていけたらいいなと思いました。
吉田 震災復興は今もうメディアにあまり出てこなくなってきていて、もう終わったかのように感じていましたが、今日お話を聞いて、長期的なスパンで見なくてはいけないものだと知りました。これから私が大人になっていく上で何かしら貢献できたらいいなと思いました。
小野 建築は、いろいろな専門分野が総合されている学問だと深く感じました。いろいろな分野を学ぶことで、震災復興などの社会的な貢献にもつながるのだと思いました。
[2015年12月8日、ハロー貸会議室田町にて]
2022年6月5日日曜日
布野修司、西山良平、高取愛子 町家de春の京大トーク 京都「歴史」に住まう 『読売新聞』 2015年4月30日

▼西山先生講演
今回の町家トークでは「住まう」ということがテーマになっていますが、「住人」という言葉が初めて史料に出てくるのは985年です。つまり、人が「どこに住んでいるか」ということに重きを置くようになるのが西暦1000年頃ですが、実は平安京の町家も大体、同じ頃に成立したのではないか、と私は考えています。その頃、それまでの平安京とは断絶した、現在の京都の原型を生む非常に大きな転換があった。一言で言えば古代都城が衰滅して、道路と住人の結びつきが強くなったことが、町家が成立した要因なのではないか、ということです。
その前の時代、平安京では、1町すなわち120㍍四方の大きな空間(町)が細かく分けられ一般庶民に分け与えられました。そこに小屋あるいは小家と言われた町家(当時は町家という言葉は無く、町家の語が使われるようになるのは鎌倉時代)が作られるわけですが、それらは基本的には道路に沿って並ぶわけですし、それぞれの奥行きは小さいですから、必然的に奥に空閑地ができます。これはいわば多目的共用空間というべきもので、井戸やトイレ、洗濯物の干し物といったような空間になる。つまり四面が道に面した区画の内側に共用空間がある、今日私たちが「四面町」と呼ぶものが誕生する。その四面それぞれが自立して「片側町」として地縁を結び、さらに向かいの片側町と合体していわゆる両側町が誕生する。両側町の誕生はずっと後、応仁の乱の頃と言われますが、いずれにしても、西暦1000年頃に、町家の成立とともに「随近」「近辺」と呼ばれた地縁集団が誕生するわけです。
これが現在の町内会などと違うのは、刑事事件に対応して自分達で制裁を加えることもある、つまりは現在と比べて広範な権限をもった集団だったということです。時代が下るにつれ、裁判権などは国家の側に移っていきますが、それでも江戸の中頃までは、町家を売買するときには町の了解が要りました。つまり家屋敷の保全が両側町の役割だったわけですね。空間としての町家の特性やその今日的な意味については、高取先生、布野先生にお任せするとして、そうした暮らしをどう保全し、改善し、継承していくかということを考えるとき、町家の成立とともに誕生した地縁、今日の言葉で言えば町内会の持つ役割について、平安時代、中世、近世とは自ずと違った形にはなりますが、しっかり考えて行く必要があるのではないでしょうか。
▼高取先生講演
私は大学で研究活動をする傍ら、京都はもとより全国で実際の住宅設計をしています。言うまでもなく、生活や文化は地域によって異なるわけですが、そうした差異を個別性や特異性として強調しつつ、それらを包み込むことのできる器としての住まいには、日本中あるいは世界中、不思議なほど共通点があります。中でも京都の町家には、人が心地よく住まうための普遍的な技術が数多く見られます。
一般に京都の町家では、いわゆる「ウナギの寝床」と言われるような間口に対して、深い奥行きが目立っています。これは間口にかけられた税制度によるものと言われますが、こうした敷地形状の制約が、空間を豊かに見せるための様々な工夫や知恵を生み出しています。例えば、複数の庭を用いた伝統的平面計画は、都市化した街中集合居住への最適解を示しています。また、京町家に入るときは、少し頭を下げるような形で木戸をくぐった瞬間、一気に吹き抜けの垂直空間に投げ出されますが、京町家では、水平、垂直といった対比的な空間を並置することで、空間に抑揚がもたらされているのです。こうしたことは、現代的な課題のひとつでもある極小住宅の設計にも展開可能な事柄と言えます。
さらに言えば、そもそも時代時代の厳しい要請に応じる形で発展してきたこと、その発展が、住まい手と作り手双方を主体にして行なわれてきたという町家の発展過程そのものにも、今日私たちが質的に豊かな人間生活に立ち返るための、一つの大きな解が示されているように思います。売り手から一方的に供給されるマンションや建て売り住宅のそれとは対局にある、住む事に実直に向き合うことの重要性が示されているのです。
このような「暮らすための技術」は、空間や関係性に濃度というか、質的な湿り気(あるいはグラデーション)を与えるものであり、このような間(あわい)もまた、様式や形式をこえて、時代を超えた力強さを持っていると考えています。これからも残していくべき「京都らしさ」として、私はこうした点を強調したいと思います。
▼布野先生コメント
碁盤目状の都市、すなわちグリッド都市というのは、古今東西に見られます。アジア全体を見ますと、伝統的な都市は、大きく中国とインドの二つの都市形式に分かれますが、中国の形式は、日本、韓国、ベトナム、台湾に影響を与えました。京都は、その中でも大変精密な寸法体系を持っています。世界中を見渡しても、1000年以上の長きにわたってこの規模と繁栄を維持した都市は、京都の他にはほとんどありません。その秘密の一つは、この強いグリッドにあることは間違いありません。もう一つ、世界の住居をおおざっぱに2種類に分類すると、中庭型と外庭型というようなものに分かれます。西山先生のお話しにもありましたが、都市に住むためにはどうしても道路に面して並ばなければならない。そうすると、どうしても風と光をとる空間が必要になる。そこを作業スペースにする。そういうことで必ず中庭が出来ます。大きくいうと京町家もその系列ですが、高取先生が指摘されたように、京都の町家は、都市における狭小な住宅のあり方としては最適な解と言えます。
私は2004年まで京都大学にいて、京町家再生の活動にも取り組みましたが、そのときびっくりしたのは、巨大な合筆が起こったことです。土地というのは細分化されていくのが歴史だと思うのですが、小学校校区をまたがるような巨大なマンションが建つというような現象が起こった。もう一つ、京町家を今のまま建て替えようと思うとできない。消防法とかもろもろの問題があってそのまま再現するのは相当な壁がある。つまり、グリッドにしても町家に住まう技術しても、京都を今日まで持続させてきた普遍的な力というものが失われかねない。持続的な都市、持続的な都市生活というものを考えるとき、このことは、京都だけの問題ではありません。お二人がおっしゃるように、私たちが、都市に住まうと言うことに主体的に実直に向き合うことが大切になっているのではないでしょうか。
実は今日の会場になっているこの建物(西村家住宅)は、戦後日本における近世町家建築研究の嚆矢となった、故野口徹先生の研究対象となった建物です。偶然とはいえ、こうした場所で、私たちの住まいと暮らしの未来を考えることが出来たことは、まさしく京都ならではの、貴重な機会だったと思います。
プロフィール
西山良平(にしやま・りょうへい)
1951年、大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。著書に『都市平安京』など。
高取愛子(たかとり・あいこ)
1975年、岡山県生まれ。京都大学工学研究科付属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センター講師。1級建築士。
布野修司(ふの・しゅうじ)
1949年、島根県生まれ。前滋賀県立大学副学長・理事。『韓国近代都市景観の形成』『グリッド都市』で二度の日本建築学会著作賞を受賞するなど、多数の受賞歴を持つ。
2022年6月4日土曜日
2022年6月3日金曜日
布野修司 履歴 2025年1月1日
布野修司 20241101 履歴 住所 東京都小平市上水本町 6 ー 5 - 7 ー 103 本籍 島根県松江市東朝日町 236 ー 14 1949 年 8 月 10 日 島根県出雲市知井宮生まれ 学歴 196...
-
traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...
-
進撃の建築家 開拓者たち 第 11 回 開拓者 13 藤村龍至 建築まちづくりの最前線ー運動としての建築 「 OM TERRACE 」『建築ジャーナル』 2017 年7月(『進撃の建築家たち』所収) 開拓者たち第 12 回 開拓者 14 藤村龍至 ...