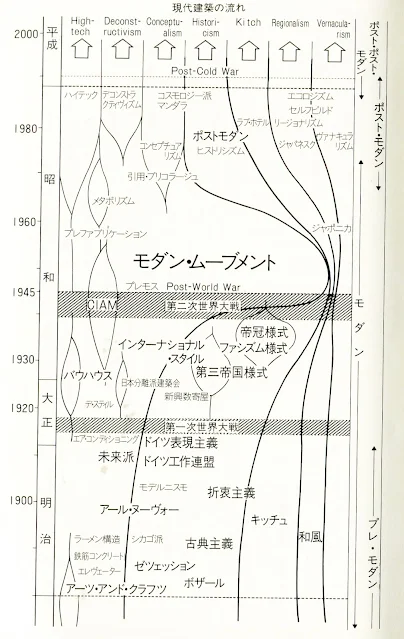布野修司監修:待てしばしはないー東畑謙三の光跡,日刊建設通信新聞社,1999年5月
布野修司監修:待てしばしはないー東畑謙三の光跡,日刊建設通信新聞社,1999年5月
組織事務所の原点・・・産業社会と建築家
東畑謙三の「工場建築」
布野修司
はじめに
一九九八年四月二九日、東畑謙三は逝った。享年九六歳。大往生である。
五月一三日、西宮市山手会館で東畑建築事務所による社葬が執り行われた。その業績は、親しく師事した、後輩の横尾義貫、佐野正一両先生の心のこもった弔辞に的確に表現されている*[1]。横尾先生が思い出として述べられたのは、京大建築会の草創の頃の『建築学研究』*[2]の発刊、東畑建築事務所の開設、京都大学での教育*[3]、そして日本建築総合試験所の創設*[4]である。加えて、佐野先生が挙げられるのが、大阪大学での教育、日本建築協会での活動*[5]、大阪万国博(一九七〇年)の会場設計についての組織化などである。二人とも口を揃えて、趣味人、愛書家、蔵書家としての東畑謙三にも触れられている。
本書は、東畑謙三と東畑建築事務所の軌跡をその著作、作品、発言をもとに構成しようとしたものである。本書の企画に当たって新たにインタビューを試みることになっていたのであるが、既に体調を崩されていて、不可能であった。やむを得ず、本書に収録するインタビュー構成(これまでのインタビュー、対談等を再構成したもの)に眼を通して頂くことにしたのであるが、それも叶わなかった。直接お会いすることのないままお別れの時を迎える、それを予感しながらの編集作業であった。
編集の過程で、多くの資料を収集した。また、多くの人々にインタビューも試みた。さらに、新たに東畑謙三論の執筆を求めた。本稿は、そうした編集作業を通じて得られた資料をもとに、東畑謙三という「建築家」のひとつの像を描き出そうとする試みである。
建築家・東畑謙三
東畑謙三は一九〇二年に三重県に生まれた。四兄弟の三男で、長兄は著名な農政学者で東京大学教授を務めた東畑精一(一八九九~一九八三年)。次兄、速見敬二も学者である。一橋大学から京都大学に移って学を修め、國學院大学教授を務めた。弟、東畑四郎は、東大法学部を出て、農林事務次官を務めている。学者一家、エリート一家である。東畑謙三に学者の素質があったことは疑いないところである。
三高に通う頃、京都ではじめての鉄筋コンクリート造の建物、京都大学建築学科本館が建設中であった。仮囲いがとれ、チョコレート色の本館が現れるのをみて面白いと思ったのが、建築を志すあるきっかけになったという。父親に、建築をやりたい、と言ったときのエピソードが面白い。「大学まで行って大工になるのか」と言われたのである。昭和初頭の大学の建築学科への一般の認識がよくわかる。
三高を出て京都帝国大学の建築学科に入学、一九二六年に卒業する。京都帝国大学に建築学科が設置されたのは一九二〇年のことであり、草創期の京都帝国大学建築学科の昂揚のなかで建築を学んだことになる。東畑は建築学科卒業第四期生である。建築を志すきっかけになったというチョコレート色の本館で学んだ最初の学生のひとりである。
日比忠彦(構造学)は既に亡かった(一八七三~一九二一年)けれど、武田五一(建築意匠学、建築家 一八七二~一九三八)以下、天沼俊一(建築史学)、藤井厚二(建築環境工学、建築家 一八八八~一九三八)、坂静雄(建築構造学)、森田慶一(建築論、建築家 一八九五~一九八三年)といったそうそうたる教授陣に薫陶を受けた。下宿の前の家の二階でよく勉強していたのが坂助教授だったとか、天沼先生の熱心な授業が面白くてクラス全員が歴史家になろうと思ったとか、分離派のプリンス、森田助教授が建築材料を教えていたのだとか、分離派の集会に行ったら、十人ちょっとしか参会者がなかったとか、様々なエピソードが後年語られている。
卒業後、大学院に進学。東京の建築学会の『建築雑誌』に対抗する形で発刊された『建築学研究』の編集に携わる。原稿が集まらず、新雑誌紹介欄を設けて、L.コルビュジェ(一八八七~一九六五年)やT.v.ドゥースブルグ(一八八三~一九三一年)を紹介する記事を一人で書いていたという(文献参照)。二年の給費生期間が過ぎると、師である武田五一の命で「東方文化研究所」京都事務所(現京都大学人文研究所)の設計に携わることになる。一九二九年の三月から外務省の嘱託になっている。武田五一の代表作と言われるけれども、実質上は東畑謙三の処女作である。一心不乱に仕事に取り組んだ様は、後年生き生きと振り返られている。
その後続いて新大阪ホテルの設計で一九三一年から一年大阪市の嘱託を務めた後、独立、事務所開設に至る。一九三二年暮れのことであった。
以後、事務所の歴史は六〇年の還暦を超えた。現在は三五〇名にのぼる事務所員の数の推移がその発展の歴史を物語っている。東畑謙三建築事務所といえば、戦前にルーツをもつ、代表的な組織事務所のひとつである。
東畑謙三が事務所を開設した頃、大阪の主な設計事務所としては、安井建築事務所、渡辺節建築事務所、横河建築事務所、松井(喜太郎 一八八三~一九六一年)建築事務所、置塩(章 一八八一~一九六五年)建築事務所などがあった。安井武雄(一八八四~ ● )が片岡事務所から独立したのが一九二四年、村野藤吾(一八九一~一九八四)が渡辺節建築事務所から独立したのが一九二九年である。安井、村野が四〇歳近くでの独立であるのに対して、弱冠三〇歳の独立であった。
日本を代表する近代建築家と目される前川國男(一九〇五~一九八六)の独立は一九三五年のことである。同じ三〇歳であるが、東畑は三つほど年長であり、一足早いスタートであった。
「工場建築」と「美術建築」
前川國男の軌跡*[6]と比べると、日本の近代建築の歴史における東畑謙三の位置がくっきり見えてくる。時代と社会に対するスタンスが陰と陽と思えるほど対極的なのである。
同じようにL.コルビュジェに心酔したといっても直接そのアトリエで学んだ前川とC.R.マッキントッシュ(一八六八~一九二八年)流のアール・ヌーヴォーの作法を身につけた武田五一のもとで学んだ東畑では出発点が違う。前川國男の場合、近代建築の実現という課題が常に意識されており、日本の建築界をリードしていくのだという使命感が鮮明なのであるが、東畑の場合、他をリードし、啓蒙するといった構えはない。書かれた文章から容易にそのスタンスの違いをみることができる。東畑の文章はそう多くないし、限定されたテーマに関するものがほとんどである。
何よりも二人の建築家を区別するのは「工場建築」である。東畑は「美術建築」という言葉を使う。「芸術としての建築」というより、いわゆる公共建築のことと考えていい。前川が敢然と闘争を挑んだ数々の設計競技(コンペティション)の世界、モニュメンタルな建築の世界が全体として「美術建築」と呼ばれている。それに対して、東畑が選びとったのが「工場建築」の世界である。
独立のため洋行し、アルバート・カーン(一八六九~一九四二年)の「工場建築」に深く感動して「工場建築」を始めることになったというのが有名なエピソードである。アルバート・カーンは、シカゴやデトロイトでフォードやゼネラル・モーターズの自動車工場を手掛けていた建築家である。もちろん、アルバート・カーンの作品を見た後、初めて「工場建築」を志したということではない。既に決断はなされつつあった。事務所開設の後援者であり、外遊のスポンサーであった義父、岩井勝次郎から「産業的な建築、すなわち工場建築を勉強してこい」と言われているのである。カーンの作品を予めリストして出発したのであった。
しかし、最初に赴いたのはヨーロッパである。ローマのパラッツォ・ファルネーゼのスケールに感動した話など後年振り返られるところだ。「イタリアルネッサンス建築」*[7]といった記事も書かれている。ヴィトルヴィウスの『建築十書』のイタリア語初版本など、青林文庫のコレクションを思うとき、「西欧建築」への思いは後々まで断ち切り難かったようにも思えるのである。
彼にはある自負があった。ヨーロッパの新興建築の動向に通じているのは自分だ。身近に接した分離派の先生方も、ペルツィッヒやメンデルゾーンに言及するだけだ。コルビュジェを日本に最初に活字にして紹介したのは自分だ。だから、コルビュジェからアルバート・カーンへの転向には多少のためらいがあったのではないか。しかし、実際に作品を見て、その徹底した合理主義の表現に心底感嘆したのであった。
考えてみれば、近代建築の理念を具現する上で最も相応しい対象である。P.ベーレンスのAEGタービン工場など近代建築の傑作も多い。しかし、日本の「新興建築家」たちは、「工場建築」を主たる議論の対象とはして来なかった。そうした中で、紡績工場、製鉄工場をはじめとして「工場建築」を数多く手がけた日本の建築家の代表が東畑謙三なのである。
「工場建築ははっきり答えが出る」
「工場建築は、それぞれの産業に合った固有のスケールがある」
書かれた文章は少ない中で、工場建築についての原稿がいくつか残されている*[8]。日本の近代建築の歴史において、「工場建築」を正面きって主題化し、実践した建築家は東畑謙三以外にはいないのではないか。
「建築技師」と「建築家」
東畑謙三は、自らを「建築技師」あるいは「建築技術者」と呼び、決して「建築家」とは言わなかったのだという。「市井の一介の技術者に過ぎません」というのが口癖だった。前川國男が終生追い求めた「建築家(アーキテクト)」像とその建築家像は対比的である。その建築を学んだ出発点において果たしてどうであったかは別として、フリーランスの建築家、芸術家としての建築家という意識は東畑には少ないのである。もちろん、日本建築家協会*[9]という職能団体との関係はある。建築士事務所協会*[10]が設立された時(一九七六年)は、むしろ日本建築家協会を引き継ぐ立場であったという。しかし、公取問題s*[11]などには関心は薄かったようだ。関西に拠点を置く日本建築協会、そして日本建築総合試験所といった組織がより身近な組織であった。
いわゆる「建築家」とは違うという、その自己規定は、特にその初期において専ら「工場建築」を選びとって設計してきたことと無縁ではないだろう。 「構成技師」という言葉も使われるが、「建築技術者」という言葉には、エンジニアに徹するというより、産業社会の要求する建築をつくり続けてきたという自負が込められていると言うべきではないかと思う。
そして、一五年戦争期(一九三一~四五年)における経験が決定的であった。東畑建築事務所は徹底した合理主義システムによって、仕事(体制)の要求に答えたのである。
戦前から戦中にかけて、軍関係や工場の仕事で忙しい日々を東畑建築事務所は送っている。海軍の仕事は、竹腰健三事務所が横須賀、山下寿郎事務所が横須賀、東畑謙三が舞鶴と佐世保を分担したのである。
ここでも前川國男をはじめとする一線の近代建築家と東畑は違う。というより、決定的な違いがあるというべきか。軍の仕事をすることは、ファシズム体制に協力することであり、日本の「近代建築家」にとって許すべからざることであった。しかし、専ら「帝冠様式」をめぐって論じられる一五年戦争期の建築のプロブレマティーク(問題構制)の土俵とは違う世界がそこにはある。すなわち、屋根のシンボリズムをめぐって日本精神や大東亜共栄圏の理想が論じられる基底で、戦時体制を建築技術者としてどう生きていくかこそが問われていたのである。
書かれた近代建築の歴史においては、ほとんどの建築家が仕事がなかったということになっている。確かに、東畑のいう「美術建築」の世界ではそうかもしれない。しかし、戦時体制を支える軍需施設の仕事は体制挙げての課題であった。東畑謙三建築事務所はその課題に忙殺されたのである。
軍関係の仕事をするのはタブーということで、日本の近代建築の歴史においてほとんど触れられていない。しかし、多くの「建築技師」が戦時体制を支えたのは言うまでもないことであった。基本的には、全ての建築家が戦時体制に巻き込まれたのであって、前川國男も例外でない。東畑謙三の場合、「工場建築」に生きる覚悟の上で懸命に一五年戦争期を生き抜いたのである。
ある野心
東畑謙三は、もしかすると、人生を間違えたのかもしれない。「清林文庫」の膨大なコレクションを眼にするとついそんな感慨に囚われる。
建築家としての東畑の出発点には、処女作「東洋文化研究所」(現京都大学人文研究所)がある。北京で起こった団匪事件の賠償として中国から古文書二〇万冊を譲り受けるに当たって、東京と京都の帝国大学のそれぞれに一〇万冊づつ分け、外務省の所轄のもとに研究所を建てて保管することになった。それが「東洋文化研究所」である。そもそも一〇万冊の本を収める研究所がその原点なのである。
立体書架のアイディアで、京都大学の文学部の諸先生とわたりあったエピソードが残っている。浜田耕作(考古学 一八八一~一九三八)、羽田亨(西域研究)といった碩学との交流は余程刺激的だったようである。中国の陶磁器や彫刻、絵画への傾倒はこの時に始まっているのである。浜田耕作先生には中国の建築の研究をやれと言われたというのであるが、「清林文庫」の貴重本の中には、アジアの建築についての本が目立つ。
そもそも学者になりたかったのだ。だから、武田五一先生にお願いして大学院に入ったのだ。兄弟も、長兄の東畑精一をはじめ学者を志している。しかし、給費生が二年で切れるという現実があった。そして、「東洋文化研究所」の設計という仕事があった。しかし、建築学者になる夢は消えなかったのではないか。建築学者になる夢が戦後「精林文庫」のコレクションに結実したのではなかったか。
転機はいくつか考えられる。
「東洋文化研究所」の設計が実務への興味を呼び起こしたと、東畑はいう。「建築というものは実際やらんとおもしろくない」というのは、全くその通りだろう。しかし、実務ということであれば武田五一のもとでも続けられたであろうし、プロフェッサー・アーキテクトの道もあり得た。
野心がわいてきたのだと、東畑はいう。
「崇拝する先生というのは自分らの専門の先生だけではないということです。仕事をやっているうちに見解が広くなったわけです。だから必ずしも武田先生にばかりついて勉強していても、自分の道は開けてこない。なんと申しますか、野心的な思想がわいてきたわけです」。
しかし、単純に野心ということでもないと思う。大学院にいても、先の展望が見えなかったのである。武田五一の退官は三二年の一二月三日である。そして、結果として、事務所開設は一二月一三日なのである。三〇歳前にして京都帝国大学に居ても、学者としての展望がないとすればどうするか。洋行(三三年五月)を決める以前に、決断の時期は迫っていた。
独立への決断の理由は身近にもあった。結婚は誰しも人生の画期となるが、義父となった岩井勝次郎との関係は大きかったと思う。岩井産業株式会社(日商岩井)の創設者であった義父は、東畑の独立を促し、支持するのである。義父無くして「建築技師」東畑謙三はなかった筈だ。
構成の基礎概念
決断には、さらに設計思想の問題があった。東畑の決断は、大袈裟に言えば、近代建築の理念の日本への受容の過程における、最も正統的な決断だったかもしれない。合理主義の思想を最もよく表現すると考えられたのが「工場建築」だからである。そしてそれは、武田五一のもとを離れることを意味した。
「東洋文化研究所」は、武田五一の名において設計されたけれど、全ては東畑謙三のものである。処女作であり、代表作ともされる。しかし、東畑の回顧談には誇らしさはなく、むしろ、ほろ苦さが滲む。一方、T.v.ドゥースブルグの「新構成芸術の基礎概念」の翻訳やL.コルビュジェの紹介は誇らしげに語られる。
東畑には、近代建築の基本的方向が自分なりに見えていた。東畑は海外の雑誌で学んだ合理主義の建築をやりたかったのである。だから、「東洋文化研究所」の仕事を勝手に中国風の建築の設計と考え、とまどい、断ろうともしたのである。文学部の諸先生との協同作業によって、貴重な仕事をやりとげることになるのであるが、結果的に主観的には敗北感の残る仕事となった。「妥協することを学んだ」というのであるが、徹底さを欠いたことを悔いるのである。徹底さとは何か。T.v.ドゥースブルグの「新構成芸術の基礎概念」の実現ではなかったか。
既に「工場建築」をやるという覚悟の上での洋行ではあったけれど、上述したように、アルバート・カーンのフォードやゼネラル・モータースの大自動車工場工場を直に見たことが決定的であった。
「合理主義に徹したシカゴの大工場群を見たときは非常に感嘆しました。当時としては斬新な溶接によるラーメン構造、非常に明るい工場の計画、整然と配置された運搬装置等を見て、なるほど義父が言ったとうり、これが建築家として行くべき道だと思い、眼が洗われたような気がしました。」
日本人建築家が、L.コルビュジェ、W.グロピウス(一八九六~一九五九)、F.L.ライト(一八八三~一九六九)など近代建築の巨匠たちに師事する中で、東畑はアルバート・カーンに帰依したのである。テーラー・システムの工場とともにアメリカの資本主義社会がモデルとして、はっきり意識されたのだと思う。
合理主義と個の表現
戦後間もなくの混乱期の苦労はともかく戦後もビルブームが起こる頃から順調に仕事があったように思える。日本の戦後社会は急速にアメリカ化していく。東畑が戦前に目指した合理主義の建築の時代がやってきた。工場から事務所ビルへ、作品のウエイトは移って行くけれど、日本の戦後社会を支える仕事が一貫して続けられることになる。
六〇年代以降、都市再開発の仕事へと業務が拡大していくのも、その基本姿勢から極自然に理解できる。振り返って見ると、東畑謙三の「建築家」としての軌跡には、事務所設立以降全く屈折はないのではないか。彼は、事務所をベースに一貫して合理主義の建築を目指し、実現してきたのである。
もちろん、その合理主義は与えられた条件のもとでの合理主義である。与えられた枠組みにおいて、目的、手段、過程を明確にすることによって最適の解を求めるのが合理主義であるとすれば、与えられた条件のもとで、というのは当然のことである。ひとつ指摘できるとすれば、東畑は、その与えられた枠組みを問うことはなかったように見えることである。産業合理主義の世界をそのまま受け入れ、「建築技師」としてそれを建築化することを出発点とすることにおいて、屈折することはなかったのである。
東畑が個の表現にこだわらなかったのもそれ故にである。こうして処女作「東方文化研究所」における当人の屈折を理解できる。われわれは逆にそこに個の表現を見て、東畑謙三という個の臭いをかぎつける。そうした臭いのする作品は、他に、自邸と辰馬考古資料館(一九七六年)、奈良・依水圓寧楽美術館(一九六九年)ぐらいであろうか。
中国陶器をはじめとする美術への造詣も、もしかすると、個のアイデンティティの表現であったかもしれない。「美術建築」と「工場建築」との間の内なる葛藤が美術品に眼を向けさせたのかもしれないとも思える。もともと美術が好きで建築を選んだのである。
産業社会と組織事務所
仕事があって組織がありうる、これは組織事務所の基本原理と言うべきであろう。東畑の口癖であったという「チャンスは前髪でつかめ」あるいは「待てしばしはない」という処世訓は、産業社会で生きていく厳しさを指摘するものであろう。
東畑建築事務所の歴史を見ていて興味深いのは、平行していくつかの組織がつくられていることである。戦後間もなく不二建設が設立され、パネル式の組立住宅の供給が試みられたりしている。また、時代は下るが清林社という不動産部門がつくられている。
設計施工の分離を前提とする建築家の理念に照らすとき、施工会社の設立は普通発想し得ないことである。しかし、実業界において設計施工の連携ということは自然の発想である。もっとも、東畑の場合、施工会社の経営はなじめず、建築事務所に専念することになる。やはり、美術好きの学者肌なのである。
清林社は、古今東西の貴重な建築書のコレクションで知られ、東畑謙三の人となりの一側面を物語るのであるが、実質的な機能としては事務所の財産の担保が目的である。事務所員の生活を第一に考える姿勢がそこにある。主宰者の責任は事務所の経営を安定させることにまずあるのである。
こうして、日本の建築士事務所のふたつの類型が見えてくる。いわゆるアトリエ派と呼ばれる個人事務所の場合、表現が先であって組織はそのためにある。組織事務所の場合、組織を支える社会システムがあって仕事がある。もちろん、二つの類型の間に截然と線が引かれるわけではない。個人事務所から出発して、一定のクライアントを獲得することによって組織事務所に成っていくというのがむしろ一般的である。個人名を冠した組織事務所の大半がそうであった。
しかし、東畑の場合、最初から時代と社会に身を委ねる基本方針ははっきりしていたようにみえる。といっても、専ら、利潤を追求するということではない。彼に営業という概念はないのである。建築事務所は、技術を持った人を集め、その技術の知恵を提供して報酬を得る。それが経営の基本理念である。
七〇年大阪万国博におけるまとめ役としての働き、日本建築協会の会長としての仕事、日本総合建築試験所の設立への努力など、その社会への貢献はもちろん事務所を越えて拡がっている。
おわりに
こうして見ると、今日の組織事務所は随分とその姿を変えてきたと言えるかもしれない。東畑謙三がくっきりとつくってきた組織事務所のあり方に照らせば、その変貌の姿が見えて来るのである。
戦前期に設立された、個人名を関した建築設計事務所は時代の要求に答え、社会的役割を果たすことにおいて成長してきた。六〇年代の「設計施工一貫か、分離か」という大議論が示すように、ゼネコン(設計部)と肩を並べる一大勢力となったのが一群の大手組織事務所である。
しかし、そうした建築設計事務所は、既に二代、三代と世代を変えつつある。九六歳という長寿を全うすることにおいて、東畑健三は、その最後の世代代わりを象徴する存在となった。
組織事務所は、次第に、その創業者の個性、初心を忘れさる。組織が巨大化するとともに別の組織原理が働いてくる。組織の中に個が埋没する、それが一般的な傾向である。
建築表現にける個と組織の問題は古くて新しい問題である。一般にアトリエ派と組織事務所という対立構図において、その差異が論じられるけれども、組織と個の関係はアトリエ派においても同じように問われる。今日の大手組織事務所の多くもかってはアトリエ事務所だったのである。
東畑健三の「工場建築」の世界は、単純に個の表現を否定的媒介にして選び取られたものではないだろう。彼には産業社会の行方を読みとる力があった。前髪で時代を掴んだのである。
組織事務所は何処へ行くのか。はっきりしているのは、建築界が大きな改革を経験しなければならないことである。「待てしばしはない」。時代を一歩先んじてつかんでいるもののみが生き残りうるのである
*1 「東畑謙三先生天寿を全うされる」、『建築と社会』、一九九八年七月号
*2 一九二一年四月、教官と在学生の親睦を図るために京大建築会が発足、また、若手の教官と大学院生を中心に建築学研究会がつくられた。一九二七年五月に機関誌「建築学研究」が創刊された。一九三三年二月まで着実に月一回出され、一一輯六八号まで号を重ねた。
*3 科目「建築計画各説」で、一九四七年~一九六二年、京都大学建築学科で非常勤講師を務めた。。
*4 佐野インタビュー註より
*5 佐野インタビュー註より
*6 拙稿「Mr.建築家ー前川國男というラディカリズム」、『建築の前夜 前川國男文集』所収、而立書房、一九九六年。
*7 ●文献リストより 『新建築』
*8 「工場建築の二つの行き方」、『建築と社会』、一九四〇年八月。「工場建築の諸問題」、『建築と社会』、一九六二年九月。
*9 佐野インタビュー註より
*10 佐野インタビュー註より
*11 佐野インタビュー註より
*[1] 「東畑謙三先生天寿を全うされる」、『建築と社会』、一九九八年七月号
*[2] 一九二一年四月、教官と在学生の親睦を図るために京大建築会が発足、また、若手の教官と大学院生を中心に建築学研究会がつくられた。一九二七年五月に機関誌「建築学研究」が創刊された。一九三三年二月まで着実に月一回出され、一一輯六八号まで号を重ねた。
*[3] 科目「建築計画各説」で、一九四七年~一九六二年、京都大学建築学科で非常勤講師を務めた。。
*[6] 拙稿「Mr.建築家ー前川國男というラディカリズム」、『建築の前夜 前川國男文集』所収、而立書房、一九九六年。
*[8] 「工場建築の二つの行き方」、『建築と社会』、一九四〇年八月。「工場建築の諸問題」、『建築と社会』、一九六二年九月。