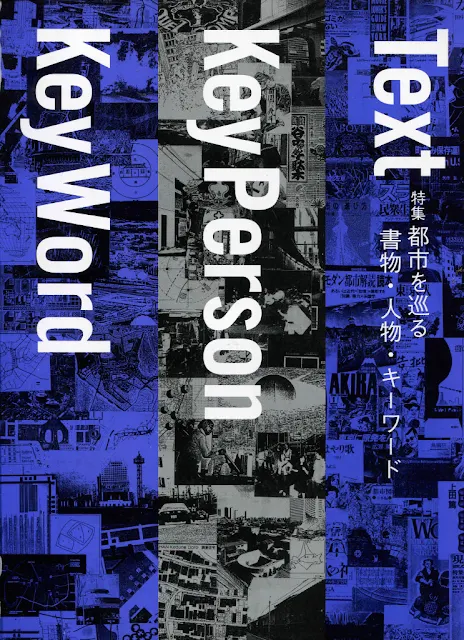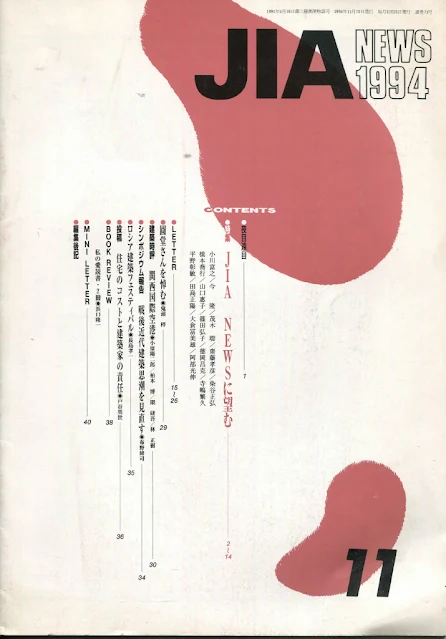建都1200年の京都,布野修司+アジア都市建築研究会編,建築文化,彰国社,1994年2月号
京都というプロブレマティーク
布野修司
京都:歩く、見る、聞く
京都に移り住んで2年が経過した。移り住んだといっても、バタバタしているだけでその実感は薄い。2年など、建都1200年を迎えた古都の歴史にとって、瞬きの間にもならないだろう。それに、取りあえず居を構えたところが洛外も洛外、宇治の黄檗だから、京都に住んだとはとても言えない。京都のことはわからない、というのが全くもって正直のところだ。
しかし、京都に住み続ければ京都のことが果たしてわかるようになるのであろうか。「京都は奥深い。京都を理解しようとするのならば、徹底的に京都を研究する必要がある。中途半端に理解しようとするのであれば、観光客でいる方がまだましだ。」と京都の友人はいう。そうであるとすれば、まあ観光客でいるしかなさそうではないか。ただ、観光客にとっての京都も、京都の半面とはいえなくても1割ぐらいの(観光収入がGNPの1割というから)京都ではありうるのではないか、そんな気分である。
観光客といっても、清水、金閣、銀閣、二条城、三三間堂といった有名観光社寺をめぐるのとは違う視点の可能性はある。「路上観察学会」の面々が京都を襲って一冊の本をものしている。『京都面白ウオッチング』( )である。「大人の修学旅行」、「路上観察の旅」ということで、京都の珍建築や珍木・名木、小鳥居、犬矢来、石亭、縁石、角石、狛犬、猛獣のレリーフ、壷庭、鬼門、ステンドグラス、金物、消火栓、銭湯、西洋館、マンホールの蓋、張り紙等々、ありとあらゆるディテールが発見され、観察されている。京都人にとっては全く理解できない「宇宙人」の視点かもしれない。しかし、京都人でも、「ええっ」と思うような発見があるのではないか。路上観察学会は、「純粋観察」を標榜する。「純粋」観察がいかに成立するかは不明であるが、「路上」の観察は、あるいは「路上」からの観察は、大きな京都への接近方法である。路上からの接近といってもいろいろある。ディテールはディテールでも、『仕組まれた意匠ーーー京都空間の研究』( )の方が「京の意匠」についてのはるかにオーソドックスなアプローチとなっている。要は視点であり、視角なのである。
「見知らぬ町を見慣れた町のように見る。見慣れた町を見知らぬ町のように見る。」といったのはW.ベンヤミンであるが、この眼の往復運動は基本的なアプローチとしてどこでも通ずる筈だ。と格好をつけて、とにかく、京都の町を歩きだした。今までに5回ほどになろうか。
まずは、新町通り、西洞院通りを南北に歩いた。京都の都心、山鉾町の中心である。町家の落ち着いた佇まいよりも、駐車場やマンションでがたがたの町並みに驚いた( )。続いて、二度目は伏見へ飛び出してみた。伏見の大手筋は買い物などで日常的にも親しくなりつつあるのであるが、秀吉の城下町の骨格を感じることができる。近世の洛中と洛外、南と北の断層が見えた。松ノ木町40番地の印象は強烈であった。高瀬川の姿も木屋町あたりとは同じ川かと思う程違う( )。三度目は、上七軒、下之森、四・五番町、島原、六条柳町、五条橋下、祇園とかっての花街をめぐった。洛中の周縁をぐるりとめぐったことになる。角屋の見学が主目的であったのだが、洛中のスケールを身体で実感できた( )。四度目は、太秦から三条通りを河原町まで歩いた。京都横断である。都心の三条通りには近代京都の厚みが残る( )。五度目は、鴨川を出町柳から七条まで歩いた。鴨川からの眺望は無惨。東山は見えかくれもしないほど。橋の下のスコッターたちの住まいが印象的であった( )。
歩きながらの学習である。もちろん、ただ歩いても仕方がない。しかし、歩きながら京都の歴史をひもとけばよく頭に入る。京都はそうした意味では日本史の書物のような都市だ。一般的な歴史の学習ばかりではない。研究室には、特に、歴史的環境、地域文化財に関する膨大な調査研究の蓄積があった。また、「保存修景計画研究会」といったオープンな研究会が続けられている。おかげで、わずかな時間にしては、随分と勉強できたような気がしないでもない。
京都に移って、すぐさま調べたのは祇園である。バブル経済に翻弄される実態を所有関係の変化から探ろうとしたのである。また、いきなり「町家再生研究会」(望月秀祐会長)に加えて頂いた。相続税についての具体的検討などを通じて町家をめぐる厳しい状況が理解される。研究会は、例えば橋弁慶町の町会所の改築問題など実践的課題を眼の前につきつけられている。さらに、横尾義貫先生の御下命でより一般的に「町家再生のための手法」について考える作業もある。
以下は、以上のようなささやかな京都体験に基づく京都論のためのノートである。
世界の中心としての京都
「京のいけず」とか「京のぶぶづけ」とかステレオタイプ化された一連の京都論、京都人論があるのであるが、そうした中に「東京は日本の中心かもしれないけれど、京都は世界の中心であると、京都人は思っている」というのがある。京都府建設業協会の出している雑誌「建設きょうと オープン・フォーラム」で読んだ。京都府建設業協会は、全国に先駆けて「現場作業服のファッション・ショー」(SAYプロジェクト)を開いたり、今また「年収1000万円プロジェクト」などを展開するなど極めて活動的である。京都は他に先駆けて新しいことをやるべきだという意気込みがその先進的プロジェクトの数々に現れているように見える。なるほどと思う。
京都は日本の都市のなかで唯一特権的な都市である。「京都はただの地方都市になってしまった」という言い方がよくなされるのであるが、それも京都を特権的なものと考える裏返しの表現だろう。
第一、千年を超える歴史をもった都市は世界にもそうはない。ローマ、北京、イスタンブール、・・・ぐらいであろうか。新たな都市が生まれてやがて衰退する。都市にも栄枯盛衰があり、生死があるのはむしろ自然である。17世紀の初頭、東国の寒村であった江戸、東京を考えてもいい。今、その東京はほぼ平面的広がりの限界に近づき、このまま行けば「死」を迎えるしかないであろう。過飽和状態に至って、新たなフロンティア(ウオーターフロント、ジオフロント・・・)を求める動きが顕在化したのがこの間の様々な東京改造の動きであった。少なくともさらに数百年の首都であり続けるかどうかは大いに疑問である。千年の都であり続けた京都は希有の存在なのである。
第二、京都には千年の都としての世界的な遺産がある。千年の都といっても、建設された都市がそのまま生き延びるということではない。江戸は火事で頻繁に焼けたし、東京にしても、震災、戦災で、繰り返し白紙に還元されてきた。京都だってそうである。むしろ、ドラスティックな変転を経験してきたのが京都である。大火も何度も起こっている。今、世界遺産条約に登録申請を行なうほどの遺産が残されたのはある意味では偶然かも知れない。京都は有力な原爆投下目標地として、通常爆撃禁止という措置により温存されており、小規模な空襲しか受けなかったのである。また、陸軍長官スティムソンの反対で、たまたま原爆投下の候補地から外れただけだからである( )。しかし、残された歴史遺産、文化遺産の厚みはその特権性の大きな根拠である。
第三、京都は日本的なるものの源泉である。そうした意味で「日本」の中心である。日本文化の原型、日本的美意識といったものは全て京都で生み出されてきたものである。京都は宿命的に「日本」を背負った都市である。「日本」というアイデンティティーが問われ続ける限り、「京都」も問われ続ける可能性がある。
東京遷都により、京都は千年に及ぶ首都としての地位を失った。京都の最終的「危機」はこの時に始まったとみていい。首都機能という意味では、既に江戸にその役割を譲ってきた。そして、天皇の居住地という天皇制のシンボルとしての京都はそのアイデンティティを失ったのである。「天皇は遷都宣言をされていない」、「天皇は京都にお戻り下さい」といった主張は今でも京都で根強い。京都が京都である第一の根拠だからである。
京都が京都である根拠を失い、衰微していくが故に、京都「府」は京都を活性化するために積極的な近代化策をとる。学区制に基づく小学校の創設、病院や各種文化施設など全国に先駆けてつくられたものは数多い。職制や戸籍の導入なども同様である。近代技術の導入も実に積極的であった。琵琶湖疎水しかり、蹴上の発電所しかり、市電しかりである。明治28年(1895年)の平安遷都1100年記念の年の京都は大いに元気であった。具体的な記念事業は平安京を模した大極殿(平安神宮)の建設、『平安通志』の編纂、第4回内国勧業博覧会である。博覧会には、京都市の人口の3.3倍の113万人が入場したのだという。この年、時代祭がつくられ、疎水の発電所の電気で市電が走った。街厠(公衆便所)がつくられたのもこの年だ( )。
それから100年、建都1200年を迎えた京都はどうか。いささか盛り上がりに欠ける。建都1200年記念事業の規模といい、意欲といい、建都1100年の時には及ぶべくもない。何故か。少なくとも、首都機能の喪失は決定的な形で明らかになりつつある。政治的、経済的、社会的中心ははっきりと東京へと移動したのである。それに対して、首都(あるいはその機能)の復権は果たして如何に可能なのか。
文化や学問に特化する方向がある。「京都学派」や「アカデミー賞」が強調される。文化的中心、首都としての京都の地位の保持である。一方、徹底して「アンチ東京」、革新の政治的立場を貫く主張がある。いずれも中心(反中心を含めた)志向の発想である。首都機能が一方的衰退していく中で、国賓のための「和風」迎賓館が今テーマとなるのはよく理解できる筈だ。また、大学の洛外移転による都心の衰退が大問題とされるのも、単に経済的理由からだけではないのである。
第二、第三の京都の存在根拠はどうか。世界的遺産としての京都が危機に瀕していることを示すのがこの間の景観問題である。また、「日本」=「京都」というのも果たして絶対的であり続けるかどうか。「京都」を特権的な都市であらしめてきた根拠が失われるとすれば、「京都」は滅びるしかないであろう。坂口安吾の「京都」滅亡論( )は、京都再生論の対極に位置し続けているように見える。
日本の都市の鏡としての京都
京都もまた生活者の都市である。生活している人々によって生きられてこそ生きた都市でありうる。実際どんな都市であれ、それを支えてきたのは生活者の論理である。「京都の博物館化」、「京都のテーマパーク化」( )が一方で極論されるのであるが、京都の場合、むしろ特に、生活者の論理を強調してきたように見える。「町衆」の論理である。京都「市民」への道を「京戸→京童→町衆→町人」とたどった林屋理論がそのベースである( )。
東京から京都へ移り住んで色々気づくことがあるのであるが、否応無く感じるのは地域共同体、隣保組織の根強さである。例えば、祇園祭がある。祇園祭に山鉾を出す山鉾町のコミュニティー組織の結束は根強いのである。例えば、地蔵盆がある。これまた大きく変容しつつあるのであるが、今猶、随分盛んなように見える。少なくとも、町を歩くと、ここそこに地蔵堂がある。余所者には実に印象的である( )。
いま、山鉾町のコミュニティー組織や屋台保存会は大きな変容を迫られている。都心のブライト化によって、人口がどんどん減りつつあるのである( )。地価高騰、相続税等の問題で再開発圧力が強まり、町家の町並みも変わる。山鉾町を歩いてみると、ところどころに虫食いのように空き地や駐車場がある。セットバックして建てられるビルと町家の町並みはガタガタである。象徴的なのは町会所である。四条通りなどの大きな通りに面した町会所は、間口の狭いビルに建て替えられつつあるのである。
東京の下町でもいい、あるいは、地方都市でもいい、都市化の進展とともに地域の共同体は一様に解体のプロセスを辿ってきた。京都もまた同じである。都心の小学校の統廃合問題がその象徴だろう。町衆の伝統をベースに全国に先駆けて住民の発意で小学校をつくったのが京都の各町である。祇園祭を支える山鉾町に代表される京都の地域共同体がどうなっていくかは京都の行方に大きく関わっているといっていいだろう。
京都のそうした地域共同体のあり方に決定的なインパクトを与えてきたのは経済の論理である。あるいは産業化の論理である。その趨勢の及ぶところ、如何に特権的な都市「京都」といえども免れることはできない。否、特権的であるが故に、開発のターゲットが京都に向けられるそんな構造があるのである。
例えば、祇園がいい例だ。四条大橋から八坂神社へ向かう四条通りの両側には駐車場が目立つ。また、空き家も少なくない。いわゆる「東京の地上げ屋」の仕業だという。一極集中の核としての首都東京にまず顕在化し、やがて、地方に波及して行ったバブル経済の猛威は、日本の諸都市をすっかり翻弄してしまったのであるが京都も例外ではないのである。というより、最も翻弄されたのが京都であり、祇園のような町であった。京都を代表する「町」のひとつである祇園。京都の「応接間」といわれるように、接待文化の中心である。芸やマナーの伝統を支えてきた。そうした町で、路線価格がわずか三年で十倍以上に跳ね上がった。例えば、四〇坪の借地の評価額が十億円で相続税は約一億円になる。住民は住めなくなる。それだけではない。舞子さんや芸妓さんのなり手がいなくなる。仕出し屋さんの後継者の問題もある。町家を修理したり、改築したりする大工さんだって危うい。「町」を支える構造が大きく揺らいでいるのである。西陣のような伝統産業の町の衰退は産業構造の転換そのものに関わり、そこでも町の構造そのものが問われているのは同じである。
1991年秋、「祇園地域の歴史的まちづくりを考える」シンポジウムが開かれたのであるが、大袈裟に言うと、その会場には「東京資本」に対する怨嗟の声が満ちていた。しかし、祇園で起こりつつあることを「東京の地上げ屋」のみのせいにすることは誤りである。また、相続税や地価税など税制のみのせいにするのも誤りである。売るものがいるから買われるのであって、問題の根は地域の中に存在している。言うまでもなく、その根底にあるのは日本の各都市に共通の問題だ。地上げ屋の論理、経済の一元的論理が支配するとすれば、京都は確かにただの「地方都市」になりつつあるといっていいのである。
何故、京都がターゲットとなるのか。いうまでもなく、それだけの環境資源、歴史資源、地域資源を持っているからである。全国の各都市の問題を象徴するからこそ京都の問題が象徴的に取りあげられるのである。モヒカン刈りの一条山、大文字の裏山などスキャンダラスな問題が頻発するのも、裏返して見れば京都のもつポテンシャルを示すものであろう。
「京都ホテル」、「JR京都駅」の問題にしてもそうである。高さが象徴的に問題とされるであるが、そこで問われているのは単に高さではない。その根底において問われているのは町づくりの論理であって、経済性という一元的な尺度によって、自然や文化や歴史や景観が切り捨てられていくその論理が激しく問われているのである。
京都について大谷幸夫は次のようにいう( )。
「ごく一般論として言えば、日本の中でまあ一応、最も古い都市でしょ、歴史を持った。だから歴史的文脈とか論理とか、歴史的成果を蓄積されて、あるわけでしょ?・・・都市は事実に基づいて考えろっていう主張から言って最も根拠を持ってる、事実が意味と根拠を持ってるわけよね。その京都でまともな都市計画ができなかったら、日本の都市でどこでできるんだって言いたいわけね。」
確かにその通りである。
京都オールタナティブ
具体的な都市、京都について今何が問題なのか。
京都ホテル、JR京都駅、京都市コンサートホール、京都市勧業会館、和風迎賓館、市庁舎建替、・・・いくつか具体的な建築物の建設をめぐる問題がある。また、高速道路、地下鉄、幹線道路などインフラストラクチャー整備の問題は都市計画の基本問題としてある。また、関西文化学術研究都市の建設、梅小路公園の建設、二条城駅周辺整備事業、京都リサーチパークの建設など開発、再開発の地区整備の課題がある。より構造的な問題としては、経済活性化の問題があり、産業構造のリストラクチャリングの問題がある。「新京都市基本計画」には様々な課題が網羅的に、また、地区毎の課題とともに挙げられているところである( )。
こうした様々な都市計画的課題は日本のどの都市においてもそれぞれに問われることではある。しかし、京都には京都故に特権的に課題とし得るテーマがあり、議論がある。新京都市基本計画は、「平成の京づくりー文化首都の中核をめざして」とうたうのであるが、「世界性」、「中心性」のテーマをどう展開するかがまずキーとなる。京都への遷都論、和風迎賓館など首都機能の建設、国際日本文化研究センターの建設、「国際歴史都市研究センター」構想、「国際木の文化研究センター」構想などがそれに関わる。日本の文化の固有性に関わるセンター機能の特権をどう展開するかである。このレヴェルの主張は、京都の新しい経済センターを建設するとか、洛南に新たな都心を造るといった主張とははるかに次元を異にする。京都をめぐる議論がすぐさま錯綜し始めるのは理念としての京都と現実の京都が同一レヴェルで語られるのが常だからである。
とはいえ、現実の京都をどうするのか、というのは大きな問題である。景観問題がこの間大きくクローズアップされたことが示すように、一方で、大変な危機感があるように見える。しかし、一方で、意外にクールな眼もある。「何も困っていない。何があっても、1200年の京都はびくともしない。」という層も少なくないのである。「京都はこれまでも新しいものを取り入れながら、古いものとの調和を計りながら生きてきた。これからもそうであろう。」という底抜けの京都肯定論である。京都の景観が破壊されることに、より危機感があるのは観光客であったり、観光客に依存する層である。あるいは傍観者としての京都以外の居住者なような気がしないでもない。
京都肯定論の裏には、かなりニヒリスティックな京都論、京都滅亡論もある。もう手遅れだ、なるようになるしかない、という。しかし、通常、京都の経済的地盤沈下を問題として活性化を訴える京都開発論がそれに対して対置される。というより、現実の京都をつき動かしているのは、開発の波であり、再開発への蠢きである。それに対して、古都の自然や町並みの景観を守ろうという京都保存論がある。もちろん、論議の順序は逆である。京都を開発の波が襲うことによって、京都の景観が失われる。そこで京都の景観を守れ!と声が上がり、それに対して、「景観で飯が食えるか」という活性化論が切り返すというのが構図である。
そこで問題なのは議論が極めて単純化されることである。京都開発論に対して、京都凍結論が出される。木造都市復元再生論が出される。地下都市論が出される。京都博物館化が訴えられる。いずれも極論である。京都の完全な木造都市としての復興、完全地中化の主張など「保存」という名の大変な開発論である。一方、京都を更地にしてしまおうという活性化論などないのである。保存と開発という二分法が決して有効ではないことは明白であるにも関わらず、極論の提示によって議論が閉鎖される。思考の怠慢である。
南部開発、北部保存という緩やかな了解も同じ様な単純化がある。南北一体化が一方で大声で主張される( )のは京都がそれ自身、南北問題、洛中ー洛外問題を抱えているからである。北部は保存、南部は開発と決めつけるにはいかないし、また、単純な一体化もそう簡単ではないのである。
建築物の高さだけが問題とされるのであるが、これまた議論の単純化である。何がどこからどのように見えないといけないのか、そんな議論が少しも深まらない。京都ホテルやJR京都駅以前に既に問題は顕在化していた筈であるにも関わらず、何故、より一般的な問題として突き詰められないのか。例えば、町家再生の問題がある。町家を何故再生しなければならないのか。再生すべき町家とは何か。基本的な議論が一般化されていない。また、それ以前に、町家の町並みがガタガタに崩れていくメカニズム(経済原理、税制、消防法など法・制度)は誰もが指摘するけど一向にメスが入らない。単純化した主張は確かにわかりやすくセンセーショナルではあるけれど、一方で、現実の様々な矛盾を覆い隠してしまうのである。
そこで何が必要とされるのか。ひとつには強力なリーダーシップである。歴史的にみても、あるいは近い例としてミッテランのグラン・プロジェをみても、思い切った都市計画の実現には巨大な権力が必要とされる( )。しかし、おそらく、それは京都には、あるいは日本には馴染まないだろう。可能性があるとすれば、京都のこれからの壮大なヴィジョンとして、可能な限り英知を集めたコミッティーによって立案されたプログラムをしかるべきプロセスにおいてオーソライズし、建都1300年に向けて着実に実行していくというシナリオである。
しかし、何よりも必要なのは個別の具体的な実践である。日本の都市計画が最悪なのは決定のプロセスが不透明で曖昧なことである( )。オープンな議論の上でしかるべき機関とプロセスにおいて決定し、実践する、そうした回路が不可欠である。個々のモニュメンタルな建築物の建設についても開かれた場における徹底した議論が必要である。議論が曖昧なまま中途半端な形で残されたまま事態が進行していくのは実に不健康なことである。
数々の提案は以上にみたように既にある。また、様々なまちづくりのグループも多い。そうだとすれば何が必要か。都市計画のためのユニークな仕組みを創り出しうるかどうかこそが京都に今問われていると言えはしないか。同じ制度同じ手法を前提にする限り、これまでの遺産という特権が残されるだけである。遺産を食いつぶしていくのもいい。ただ、新たな遺産を創り出していく仕組みの再構築がなされないとすれば建都1300年にはもしかすると京都は京都でなくなっているかもしれない。わずか2年の観光客の眼にはそんな根拠の無い不安も沸きつつある。
註1 赤瀬川原平 藤森照信他 新潮社 年
註2 川崎清 小林正美 大森正夫 鹿島出版会 年
註3 脇田祥尚 「祇園山鉾町周辺の伝統と変容」(「京都 歩く・見る・聞く①」 『群居』30号 年
月)
註4 青井哲人 「伏見へ出る?」(「京都 歩く・見る・聞く②」 『群居』31号 年 月)
註5 堀 喜幸 「遊里めぐり」(「京都 歩く・見る・聞く③」 『群居』32号 年
月)
註6 荒 仁 「「京の横断面」ー三条通りを歩く」(「京都 歩く・見る・聞く④」 『群居』33号 年
月)
註7 鎌田啓介 「鴨川を行く」(「京都 歩く・見る・聞く⑤」 『群居』34号 年 月)
註8 吉田守男 「奈良・京都はどうして空襲をまぬかれたか」『世界』 号、 年
註9 井ケ田良治、原田久美子編 『京都府の百年』、山川出版社、
年
註10 坂口安吾 「日本文化史観」、坂口安吾著作集、ちくま文庫
註11 堀 貞一郎 「完全なテーマ・パーク=京都を」、『京都2001年ー私の京都論』所収、かもがわ出版、 年
註12 林屋辰三郎 『町衆』、中公新書、 年
註13 地蔵盆とコミュニティー組織についてはいくつか研究があるが、地蔵信仰と地蔵の配置をめぐっては、竹内泰君が「聖祠論」として研究中である。
*14 中村淳 「歴史的都市における地域コミュニティーに関する研究」( 年度 京都大学修士論文)
*15 大谷幸夫 「時日に基づかない都市計画」、『建築思潮』02号、学芸出版社、 年
*16 京都市企画調整局、 年
月。本特集の内田俊一京都市助役(前企画調整局長)論文参照。
*17 京都南北一体化研究会、『京都が蘇るー南北一体化への提言』、学芸出版社、 年
*18 磯崎新・原広司、「消滅する都市」、『建築思潮』02、 年。および本特集巻頭対談参照。
*19 拙稿 「都市計画という妖怪」、『建築思潮』02、 年