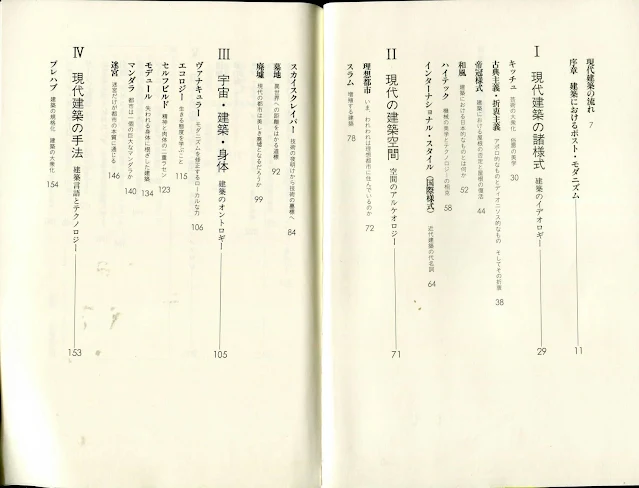京都大学東南アジア研究センター編:事典 東南アジア 風土・生態・環境,布野修司:住,弘文堂,1997年

集落の形式
集落を構成する諸要素がどのように配列されるかについては様々なパターンがある。一般には、地域毎に、民族毎に、ある共通の配列規則が認められるが、集落が立地する地形や気候など自然環境の条件によって多くのヴァリエーションがある。東南アジアに見られる集落の形式を分類するのは必ずしも容易ではないのであるが、いくつかわかりやすい構成原理を見ることができる。住居や集落の構成にヒンドゥーのコスモロジーが密接に関わっているバリ島のように、コスモロジーと集落の構成原理との対応関係が見て取れる地域が少なくないのである。
リニア・パターン(平行配置)
集落形式について東南アジア全体を見るとき、各地に見られ、その原初的形態と思われるパターンがある。住居と倉が、あるいは倉、家畜小屋、作業小屋など他の施設が平行に向き合って直線的に並べられるパターンである。リニア(線状)パターンとか、クラスター(房状)・タイプと呼ばれる。直線状の広場を中心に諸要素が配列されるパターンである。
極めて明解なのが、バタック・トバ族の集落形式である。土塁で囲われた矩形の敷地に、一方に住居が一方に倉が、妻を向き合わせて平行に並べられている。中央の広場は様々な用途に使われる。住居はワンルーム(一室空間)であるが、中二階のブリッジをもち、広場側には簡単なベランダが設けられ太鼓などの楽器が置かれる。広場での儀礼時に使われる。米倉の下部は高床になっており、これもまた多様に使われる。住居の構造と広場など公共的空間の配置には密接に関連があるのである。
バタック・トバ族の集落形式とよく似ているのがサダン・トラジャ族の集落形式である。住居と倉が妻を向き合わせて並ぶパターンは全く同じと言っていい。ただ、中央の広場空間が地形に合わせて緩やかにカーブする場合がある。もちろん、その場合もトポロジカルな関係は同じである。
さらに、極めて素朴にこのリニア・パターンを残しているのが、マドゥラ島の住居集落である*[1]。北側に住居棟が南側に作業小屋、家畜小屋等が平行に並べられる。この場合は、平側を対面させる形で、ニアス島の集落の場合と同じである。西側にランガールと呼ばれるイスラームの礼拝棟が置かれるが、イスラーム化以前の原型を残すのがマドゥラ島のパターンである。
ロンボク島の集落
住居棟と他の施設群が平行に配される集落形式は、ロンボク島のササック族の間にも見られる*[2]。ただ、ロンボク島全体を見ると三つの地域類型がある。1)住居とブルガ(露台)が平行に配列されるパターン 2)住居と穀倉が平行に配列されるパターン 3)住居が丘陵の等高線に従って配置されるパターン。北部山間部のワクトゥー・テル(ササック族のうちイスラーム化ののちも土着の信仰を保持する種族。敬虔なムスリムであるワクトゥ・リマに対比される)が居住するバヤン、スゲンタール、スナル、ロロアンは1)のパターンをとる。住居がブルガを両側から挟み込むかたちで、それぞれ平行に並べられる。一つのブルガは、一世帯ないしは二世帯によって所有される。穀倉の配置には、それぞれ特徴が見られる。バヤンの場合、穀倉はまとめて集落の周縁部に配置されるのが一般的である。スナル、ロロアンの場合は、住居・ブルガと同様平行に配置される。スナルの場合、集落の内部にも穀倉が配置されるのに対し、ロロアンは集落の端部にのみ配置される。スゲンタールには独立した穀倉は見られない。住居内に貯蔵するのが一般的である。
2)のパターンが見られるのは、サジャン、スンバルン、サピット、レネックなど北東部から東部にかけての諸集落である。ほとんどの穀倉は、その床下部分が居住部分にあてられている。穀倉の周囲を壁で囲い、内部に炉をきり、床下に露台を設置しそこで寝起きする。
それに対し、3)のパターンの南部に位置するサデ、ルンビタン、スンコールでは丘陵地に集落が築かれている。乾燥地帯であるロンボク島南部において耕作の可能な平地は貴重であり、耕作の不可能な丘陵に居住するのが望ましいと考えられているのである。形態は非常に特徴的で、丘陵の等高線に沿って住居が配置されるのが極めて特徴的である。
この1)2)3)の分類は単なる形態的な分類にとどまらず、それぞれ地域的な分類になっていることがわかる。そしてそれぞれの地域は、それぞれ特徴をもった建築形式をもつ。すなわち、ロンボク島北部では、イナン・バレ(6本柱)を持つ住居の存在やカンプ(祭祀集団の居住する区画)の存在が、その特徴となる。それに対し、ロンボク島南部では、独特の形をした穀倉アランの存在が、その特徴となる。
バリ島の住居とコスモロジー
バリ島の集落形式とバリ・ヒンドゥーのコスモロジーの関係については、諸文献が明らかにするところである*[3]。天上界、地上界、地下界という宇宙の三層構造は、バリ島全体→集落→屋敷地→住棟→柱へ、大きな空間構成からディテールに至るまで貫かれている。バリ島は山ー平野ー海という三つの部分からなる。住棟は、屋根ー柱・壁ー基壇に分かれる。柱も柱頭ー柱身ー柱脚の三つに分けて認識され装飾が施されている。それぞれミクロコスモスとしての身体の頭部ー胴体ー足部の三つの分割に擬せられるのである。
集落のレヴェルでも、頭ー胴ー足という三分割が意識される。その象徴がカヤンガン・ティガである。集落は、プラ・プセ(起源の寺)、プラ・バレ・アグン(集会の寺)、プラ・ダレム(死の寺)という三点セットの寺(プラ)を必ずもち、北から南へ(バリ島の南部の場合)順に配置されて三つの部分に分けられるのが基本である。
また、ナワ・サンガと呼ばれる方位観(オリエンテーション)が住居、集落の構成を大きく規定している。山の方(カジャ)が聖、海の方(クロッド)が邪、日の昇る方向(東 カンギン)が聖、日の沈む方向(西 カウ)が邪、という方位に対する価値付けがなされ、住居や他の施設の位置が決められるのである。バリの南部では、北東の角が最もヒエラルキーの高い場所で、屋敷地には屋敷神が置かれる場所(サンガ)である。
しかし、以上のような集落形式は、ヒンドゥー化以降のもので、バリには他の形式も見られる。その形式が、また、住居と倉などその他の施設が平行に配置されるパターンである。バリ・アガ(バリ原住民)の集落といって、バリ・マジャパイトの集落とは区別されるのである。具体的には、風葬で知られるバトゥール湖のトゥルーニャンや東部のトゥガナンがそうである。極めて単純なリニア・パターンが東南アジアで見られる原初的な集落形式であると考えられるのは、バリ・アガの集落やササック族の集落の存在からである。
環状パターン
リニア・パターンに対して、広場を環状に取り囲む形式もある。アフリカや南アメリカののコンパウンド型の集落には綺麗な円形のパターンが見られる。東南アジアの場合、自然の地形に従って配置されるパターンが多く、環状パターン少ないが無くはない。スンバの集落がそうである。スンバではリニアな集合形式も見られるが、多くが求心的パターンである。また、スンバにはジャワのジョグロに似た住居形式が見られるのは興味深い。スンバが高床であるのに対してジャワのジョグロは地床式なのである*[4]。
集落形式について注目すべきは、中央の広場を囲んで環状に住居などが配置される形式が三つ連なって一つの集落となるパターンである。この形式はヌサ・トゥンガラの他の島々にも見られた。フローレスの集落は、前方部、中央部、後方部の三つに分かれていた。例えば、マンガライでは三つの部分に対する特別な呼び方が残っていて、それぞれアバン、ベオ、ンガウンと呼び、三つの部分それぞれに「聖なる場所」があったという*[5]。
オリエンテーション
明確な集合形式を持たない場合も、個々の住居や施設の配置についてその向き(オリエンテーション)が意識されることが多い。建物の棟の方向、妻・平の方向が何らかの基準に合わせられるのである。その場合、東西南北の絶対方位が特に日の出・日の入りの方向として意識されることも少なくないが、多くの場合参照されるのは、山や川(上流下流)である。アチェやバタック・カロの場合のように、多くの建物の棟は平行に並べられる。伝統的な集落が調和ある景観をつくってきたのはこのオリエンテーションの感覚に依るところが大きい。